
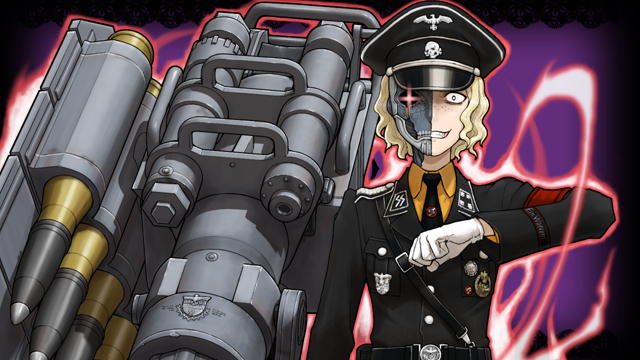

<亡霊の哭く夜に>水たまりのStreiten

|
●振動する水たまり 蜂の巣を突いたようなとは恐らくこの事を言うのだろう。 静寂に包まれている筈の――深夜帯。厳重な防御の張り巡らされた日本の『要塞』には平時らしからぬ戦争の音色が踊っていた。 「状況を報告したまえ、フランツ軍曹」 『殊の外』冷静な司令官――リヒャルト・ユルゲン・アウフシュナイターが傍らの下士官に言葉を投げる。檄した調子では無く、狼狽したそれでも無く。 「――は。どうやらこの工場に攻め入った敵がおるようです。 『あの』アークの強襲であると推測されます」 精々が二十代前半程度にしか見えないリヒャルトに対して浅黒い肌で白髪の混ざる下士官は親程の年齢にも見える。革醒者の外見の年齢はあてにならないが或る意味で『同じ目的の為に同じような連中が集まった親衛隊』においては『そうでもない』。『親衛隊』の全てがそうではないが、屈辱に塗れた前世紀の戦争を越えた者同士の話ならば、至上最年少とも言われるスピードで出世を果たしたリヒャルトは『バロックナイツには殆ど存在しない外見通りの年齢序列』を持つ人物である。 されど、誰よりもと言って過言では無い『祖国』への鉄の忠誠と、その強大な能力は部下の誰にも軽んじられているものでは無い。多くが元々軍属にあった『親衛隊』はリヒャルトの下で完全な結束を見せている。 「先の攻撃は――これを見越してのものかと思われます」 「日和やがったな、マフィア共」 「同じ猿ならば無謀にしても勇気のある猿の方が見れるものだ」とリヒャルトは失笑混じりのドイツ語で呟いた。欧州最悪にも名が挙がる武装革醒者集団――『親衛隊』。聞く者が聞けば震え上がり、戦意さえ喪失しかねないそんな彼等は何時でも畏怖の象徴であった。成る程、口汚く罵りはしているものの戦略行動に一定の評価を下すべきアークが無謀な『カミカゼ』に出るとは思えない。彼等が動き出したという事は『国内主流七派による見えない牽制』が破られたと考えるのが妥当である。 問題は『破られた理由』が方法も理屈も読めない点だ。 「思い切ったものです」 「だが、悪いやり方では無いぞ。少なくとも僕達の戦力の一部は三ツ池公園側に吸収された。『親衛隊』に敗北は無いが、本拠の戦力を減じたのは確かだ」 臨戦態勢を整え厳重なる警備を行う自分達に易く挑もうと考える者等多くは無いが――今回の敵はその数少ない例外だったという事なのだろう。七十年、待ち続けた『親衛隊』に訪れた最良の機会は簡単に逃せるものではない。この事態とて全く想像していなかったリヒャルトではないが、そのリスクさえ『地下に潜った時間』の鬱屈に比べれば些少である。 何よりアーリア人に決定的敗北は無いのだからこの程度―― 「少佐、敵の攻撃の全容が掴めましたよ」 「劣等共も――どうやらかなりの覚悟を決めてきたみたいですね」 自身の軍装の確認をしながらフランツ軍曹と会話を続けるリヒャルトの下にオットマー曹長とヤム曹長のコンビが駆けてきた。「さもありなん」と驚きも無くこれを受け止めたリヒャルトは腹の底からこみ上げてくる言葉に出来ない感覚をもう押し殺す事は出来なくなっていた。 戦いが来る。 戦争の足音が近付いて来る。 魂を賭け、肉体を削り合い、運命を捧げ、唯世界に屍を積み上げる―― 総ゆる悪徳を飲み干して、躊躇う必要は何処にも無い。 心を折れ、命を刈れ、無人の野に偉大な祖国の歌を点せ。 敵対する者は完膚無きまでに殲滅せよ。それが戦争の唯一である筈だ! 「ヤム曹長、クリスティナ中尉に各隊のバックアップの命令を」 「Ja!」 「フランツ軍曹、ブレーメ曹長に『本気の遊撃』を認可したまえ」 「Ja!」 誇りと栄光に満ちたアハト・アハトを自らに手渡したオットマー曹長に小さく頷いたリヒャルトから魔人のオーラが立ち昇る。 歯茎を剥き出し、崩壊した顔の奥に禍々しい光を点した彼は宣言する。 「さあ、鉄十字猟犬達。水たまりのアマチュア共に本当の親衛隊(Schrecken)を教えてやれ!」 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:YAMIDEITEI | ||||
| ■難易度:VERY HARD | ■ イベントシナリオ | |||
| ■参加人数制限: なし | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2013年08月11日(日)00:53 |
||
|
||||
|
||||
| ||||
|
●1945I しとしとと雨が降っていた。 そこかしこから上がる黒煙と、赤い残り火が瓦礫の街に破滅のコントラストを描いている。 「……ょう……」 胡乱とした意識の中で、別人のような自分自身の声を聞いた。 「……くしょう……」 全身には何ら力が入らない。 顔の半分にへばりついた『べっとり』とした感触がどんなものだかを彼は知っていた。生暖かく、鉄分の香りがするそれは戦場に似合いのものだった。身体に断続的に降りかかる冷たさと、見上げた灰色の半ばまでを真っ赤に染めるその視界はどうしようもない程に彼の辿るべき運命を彼自身に痛感させている。 (畜生、畜生……!) 声は上手く出せないから――代わりに心の中で『敵』を呪った。 遠雷のような怪物の唸り声を上げる空の獣達(B-24)は愛すべき祖国の空を我が物顔で闊歩している。 ベルリンの街並みは悪逆非道の『敵』の無慈悲に打ち壊されている。 命を賭けて戦った。 祖国、『この街、守らなければならない人達』は神が創り給うた『最も美しいもの』である。 何故、こんな結末が許されようか。 人生の黄昏、今際の際にありながら――彼の自問自答は止む事は無かった。 命を賭けて戦った。 この世で最も偉大な閣下の為に、この世で最も精強な軍団の一員として。 何故、こんな悲劇が認められようか―― (……殺す、絶対に殺してやる! 一人残らず、塵芥さえも残さずに! 必ずこの世から消去してやる!) ――馴染みの仕立て屋が跡形も無くなったのを思い出した時、必死で避難させようとした少女が爆風で『バラバラ』になった時の事を考えた時、彼の腹の底からは並々ならぬ憎しみがこみ上げてきた。 アーリア人種に敗北は無い。 従って、この苦境も、困難も、きっと閣下が挽回する筈だ。そうに決まっている。 道半ばで一人の男が死んだとしても、その結末だけはきっと変わらない――そうに決まっている。 理想の溺死の中で藁に縋るかのような想いは、それでも褪せる事さえ無い。 身体の半分近くを失い、間もなく死亡する彼がこの一時を生き永らえたのはその憎しみのなせる業だった。一瞬一秒でも敵に呪いを浴びせかけたいと願った彼に神が施した最後の慈悲であった筈だ。 遠のく意識。重い瞼が落ちれば世界は闇に包まれた。 この時、永遠に包まれる筈だったのだ。『本来』は! ●序 パンドラの箱の底には必ず希望が残されている―― 現代に蘇った『亡霊』とそれを阻む者達の戦いは果たして激烈なものになっていた。 バロックナイツ第八位『鉄十字猟犬』リヒャルト・ユルゲン・アウフシュナイター率いる『親衛隊』は謀略と世界平和への危険な企みをもって出現した強力な敵であった。 自身等の制圧と第三次世界大戦の誘発を企図する彼等に対抗を図ったアークはキース・ソロモンによる宣戦布告という状況を逆手に取る事で『親衛隊』と国内フィクサード達が作り出した『包囲網』を突破するに到り、早い段階での決戦に踏み切ったという訳である。 「チッ、思ったよりやりやがる……!」 事務・管理棟から手勢を率いて出撃したリヒャルトは戦況に思わず舌打ちをしていた。 『親衛隊』本拠地・大田重工埼玉工場での戦いは、制圧された三ツ池公園奪還を陽動(ブラフ)に本拠地を強襲するという乾坤一擲の攻撃によりアーク側優位に進んでいた。要塞めいた工場は容易く落ちるような防御力をしていないが、相当数の戦力が本拠を離れたのはかなり痛い。無論、『親衛隊』側とてやられるばかりではないのだが、一敗地に塗れたアークの戦意は高さは何とも言えずに厄介だった。 「こっちの言葉で言うなら――『窮鼠猫を噛む』ってヤツですかね」 「それもここまでになりますけど」 通信機越しに不敵に笑ったのはオットマー、ヤムの両曹長。 「……ゆめ、油断はなさりませぬように」 軽い調子の『上官』を嗜める重厚な声はフランツ軍曹のものだ。 リヒャルト以下、三人の指揮官が率いるのは『親衛隊』の大戦力。都合四十名の四小隊である。 緊密な連携と制圧能力でアーク側の攻撃戦力を沈黙させんとする彼等はまさに『親衛隊』の切り札である。各隊のバックアップに努めるクリスティナ中尉、正門裏門から『本気の遊撃』を見せるブレーメ曹長と合わせて状況を塗り替える(リバーシする)為の――今度は此方の番、と言わんばかりのそれであった。 「――諸君の健闘を祈る!」 全く衰えず精強である自軍に誇りを感じたリヒャルトは短いその言葉で一旦通信を閉じていた。 彼の視線のその先には―― 「よぅ大将、また会ったな――今度はこっちが全力で潰させてもらうぜ」 ――常識外れの長さと刃幅を誇る震動破砕刀を肩に担ぐようにした御龍が居る。 「まさか本物の軍人と戦う羽目になるとは。こんな事は今回だけで済ませたいものです」 飄々と何処まで本気か。白い仮面の向こうの表情は悟らせず嘯いた九十九が居る。 「さて、そんじゃまぁ……派手な喧嘩を始めるとしますかねえ。邪魔ァする奴は、容赦なくブッ潰す!」 「第三次世界大戦? 劣等種の駆逐? ふざけるな。 今宵この場こそが戦場――日本来訪を必ず後悔させてくれる!」 「亡国の軍隊と言えば聞こえは良いが、貴方がたの実態はもはや単なるテロリストです。 交戦によって撃破されるのではなく、制圧や鎮圧による駆除がお似合いですね――」 気合を入れた猛、傲慢なる敵の相容れぬ主張に怒りを隠せない優希、守の姿がある。 つまり――そこにはまさに会敵せんとするリベリスタ達の集団が存在していた。 「思ったより……数だけは集めやがって」 唾を吐き、悪態を吐くリヒャルトは瞬時に敵の数が自身等の倍はあろうかという事を察知していた。 然程離れている訳では無いが、それぞれ出撃した他三隊の対戦相手がどうなっているかまでは分からなかった。しかし少なくとも五分程度以上の戦力は振り分けられていると考えるのが妥当と思われた。 少数精鋭の『親衛隊』は個々の武力でアークを上回るケースが多い。されど、アークの一部の戦力はその親衛隊を個々の戦いでも圧倒した事もあると聞いていた。本拠地たるこの現場に、首魁たる自身との決戦を挑まんとする敵の『能力値』を決してリヒャルトは過小に侮る事は無い。 「だが――相手が悪かったな、劣等共!」 それでも彼は苦境の戦場に微塵も揺らぐ事は無い。 記憶の底に揺らめく『何時か』に比べればこの程度、と鼻で笑う。 「劣等に猿。トコトン、連中は見下す事が好きみたいね。 いいわ、其処まで見下してくるなら私達の意地を魅せてあげようじゃない」 目を細める焔。 ほんの僅かの猶予は早急に終わりを告げ、いよいよ戦いが始まろうとしていた。 両軍は騒乱に満ちた鉄の工場のアスファルトを猛然と蹴り上げた。 (バロックナイツの強さは知ってるし、死ぬかも知れないって恐怖もあるよ。 けれど……戦わないって選択肢は無いんだ。 だって、私はリベリスタだから。姉さんの愛したこの世界を守るんだ――) 白い大きな翼を広げ、低く滑り――闇を縫うかのようにセラフィーナの小さな身体が舞い踊る。 戦いに先鞭をつけるのはソードミラージュの役割。敢えて乱戦さえ望むのは少女の勇気。手にした刃は受け継がれた想い、鬼の王さえ見事穿った夜明けの霊刀―― 親衛隊の出鼻を挫かんと繰り出された氷刃の霧が夜霧のように辺りを包む。 戦いの号砲にグラス・フォッグは余りに冷たく。同時に亡霊の哭く夜にこれ以上の似合いは無いとも思わせた。 「しゃらくせぇ――!」 「肌を突き刺すような鬼気は有象無象とはまるで別。嗚呼、まさにこの時を待っていた! 魔神王の我侭も分からないでも無いが……性分には合わん! もうお預けは御免被る!」 吠えたリヒャルトを歓喜極まる朔の声が塗り潰した。 低い獣の姿勢で飛び込んだ彼女に遅れて縛った黒髪が闇に流れる―― ●vsオットマー 「サジタリー同士だ、仲良くやろうかオットマーとやら」 「長い付き合いにする気は無ぇんだけど、な」 「相手がバロックナイツだろうが関係ない。立ち塞がるなら捻じ伏せて押し通る、それが俺のやり方だ」 「分かっております。アークに所属して大きな戦いをどれだけ経験したでしょうか。 何度だって構わないですわ……私が成すべき事は何一つ変わりませんから」 敵と対峙する櫻霞が口元を歪めた理由は常必ずその傍らにある櫻子の言葉を受けてのものである。 「櫻霞様を本当の意味で支えられるのは私だけですわ」そう自認する彼女の戦いは彼を全力で生かす為のもの。それは愛情による献身であり、その為に培った能力での補給(サポート)でもある。 「屍積みの悪食か。遠回しな自殺志願者共は面倒だな。 生憎満足させる気はないが――自慰に耽って無意味に果てろ」 それぞれに戦いの準備を整えた戦士達は当初より激しい削り合いを見せていた。 「……やれやれ、とんだ色男にお嬢ちゃんだ。こりゃかなり『ガチ』な戦いになるかねぇ」 得物を構えた櫻霞と淡々と表情さえ変えぬまま罵倒とフラッシュバンを投げ込んだユーヌに眉を顰め、肩を竦めたオットマーがそんな風に呟いた。 (皆、無茶するんじゃねぇぞっ……て、言ってもかなりの相手ではあるが) この工場のあちこちに散ったMGKの仲間達の事をちらりと考え、翔太が激しく切り込んでいる。 「!?」 瞬時にその場から姿を掻き消し、間合いを『初めから無いもの』のように奪い去った彼の動きに敵兵の対応が遅れていた。敵を唖然の内に切り裂いた一閃は威力以上に敵を乱す意味で効果を発揮した。 ――果たしてリヒャルトの読みは概ね正解であると言えた。本作戦に参加する精鋭リベリスタの数は合計で八十七名。八十八人目(アハト・アハト)のアシュレイを除いてもその数はリヒャルト側に約二倍する。 「攻撃力の高い部隊を相手取る皆の体力の下支えが僕の仕事だ。こ、怖くない。怖くない。怖くりゃい……」 「死なないように頑張る! どんどんハードな仕事になってる気がしてアイドル泣きそう! でも、部長は絶対守るから安心しろよな!」 中には涙目で鼻水を垂らして恐怖に耐える支援役の美月や、言葉は勇ましくは無く、それでも彼女等を守らんと胸を張る明奈も居るが、彼女等とて異能者としての能力が低い訳では無い。温存された戦力も含め三倍以上を相手取る事になるリヒャルト及び彼の隊に比べれば比較的少数と言えなくも無いが、純粋にオットマー隊対応に動いたリベリスタも精鋭ばかりで十六人の部隊を組んでいたのだから彼の反応も頷ける所であろう。 「過去の亡霊に、今を渡したりしません――ミュゼーヌさん!」 「ええ、分かってるわ! 三千さん!」 断固とした決意を秘めた三千の声(クロス・ジハード)に誰よりも見事に応えてみせたのは威風凛然たるその姿で戦場に華を添えるミュゼーヌだった。 「時代錯誤のキャベツ野郎(クラウト)さん達、ご機嫌よう!」 熱を帯びた夜風にはためく青いコートは彼女の矜持。敵を踏みつけ、叩きのめす鉄の脚は『鋼脚のマスケティア』のその異名の源だ。 「前大戦が遺した負の遺産、裏の歴史からも駆逐してあげましょう!」 マグナムリボルバーマスケットが次々と轟音を吐き出した。 突き刺さる暴力的な弾丸の嵐は敵なる大波を押し返す強烈な意志の発露だった。 「……」 「……………はい!」 目と目で分かり合う決して互いの位置を離れないミュゼーヌと三千の二人は一組で一人の戦士になる。 時代が離れれば騎士と銃士とはなるまいが―― 「必ず、勝ちます!」 「ええ、そうだわ」 ――三千の強い言葉を聞けば乙女の唇が緊迫の中でも僅かに綻ぶ。 「三ツ池公園は大事な場所だ。色んな思いが募った、大切な場所。 それを好き勝手使わせるわけにはいかない――全て返してもらう!」 「生憎とそうもいかねぇのよ、お宅は劣等の味方をしてぇのかも分からんけどよ」 「ならば、決着をつけるまで!」 鼻で笑うオットマー。レンは強く言い切って宙空に不吉な月の輝きを解き放つ。 呪いめいた魔力の照射は極めて精強な親衛隊の一部を赤く灼く。 「行くぜ親衛隊! 第三次世界大戦なんて起こさせるかよ!」 更に攻めるラヴィアンが瞬時に葬操の術式を組み上げた。 「攻撃は最大の防御だぜ! ブラックチェイン・ストリーム!」 少女の裂帛の気合が夜を切り裂く。優れた敵技量は容易く攻撃を決定的打撃に届かせる事は無いが、弾幕的に作用したレンとラヴィアンの攻勢は敵陣を牽制するに十分なものである。 「死体の後に亡霊が相手とはな。結構皮肉は効いていたとは思うよ」 反撃の構えを取った敵兵をすかさず小烏が迎撃した。 案の定と言うべきか味方陣の弱い部分、要の部分――つまりは後衛を狙い撃ちにしようとする彼等の考えは小烏にとって先刻承知のものだった。敵兵が前衛を構うならば式符・鴉で引き付け、後衛を狙うならば即座にそれを邪魔しにかかる。展開した守護結界と共に全くインヤンマスターらしい術士は笑みさえ浮かべて言う。 「ま、お前さん方が優秀なのは否定せんがね。 何せ大概の人間は自分よりも優秀だ。だが、周りが見えん馬鹿に好き勝手されるのは御免だよ」 惚けた台詞は、されど『親衛隊』への強烈な毒(アンチテーゼ)を含んでいた。 強烈な銃撃は容易く凌げるものではない。しかして傷付けられても小烏の仕事は成っている。 「連携を重視して――状況を崩さずに戦いましょう!」 全員が生還出来るように――それを強く願う京一の指揮に応えてリベリスタ達が更に動く。 味方のバランスを取りながら支援役としても動く京一にオットマーが口笛を吹いた。 「劣等の分際でやりやがる!」 見た所、互いの指揮の精度はかなり高い次元で拮抗している。 戦闘指揮により上積みを得た戦闘は非常に技巧的に、連携で敵の隙を伺うものとなっていた。 「他人の苦しむ顔や悲鳴って心地いいですよねー。 ああ、我慢してる顔も素敵ですよ。こんなの何てことないって顔してる相手を叩き潰すの何て格別です! そんな楽しみを味あわせてくれる親衛隊の皆さんが――私は大好きですよ?」 食い込んだ珍粘のスケフィントンの娘が執拗に『親衛隊』を狙う。 「もっと、もっと聞かせて下さい?」 「言ってろ、劣等!」 自身にまで届かんとしたその『悪意めいた愛情表現』に彼は唾を吐き捨てた。 自身等の盟主と並んで『邪悪』とも称されたリベリスタは笑顔のまま、戦場の線上に踊っている。 「――掃射!」 オットマーの号令を受けた敵陣が一斉に猟犬の牙を剥く。 強力なスターサジタリーであるオットマーのガトリングガンが強烈な弾幕を吐き出し、強かにリベリスタ達を傷付けた。やや寡兵ながら数の差を感じさせぬ戦い振りは歴戦のリベリスタ達にとっても脅威そのもの。 「助かったのだわ」 「これも任務故な。気にする事は無い」 『ガトリング』と言えばウラジミールの堅牢なる巨体の影から姿を現したエナーシアも黙っていない。 「生憎と頑丈さには自信があってな。この程度ならまだまだいける。 フランツに遅れをとれば閣下になんと言われることか!」 小さくない衝撃をその全身に浴びまくりながらも意気軒昂なるウラジミールは怯む様子は無い。 「戦争は外交の一手段に過ぎないわ」 いよいよ饒舌なエナーシアと合わせ、二人は己が得手を担当するそれぞれが盾と矛の関係だ。 「三割損耗で全滅扱いの戦争で殲滅で解決だなんて――大隊指揮官殿は星でも見てるのかしらね?」 猛烈な攻撃には猛烈な反撃が付き物である。 大いに博打めいたエナーシアの小火器は口径以上に暴れに暴れた。 「とんでもねぇ女だ!」 オットマーがむしろ愉快気に喝采を上げたのは彼女が黄色にあらぬ白人だったからであろうか。 「成る程、露助が相手ならいよいよ燃えるぜ!」 或いは――眉をピクリと動かしたウラジミールが『親衛隊』とも東部戦線で因縁浅からぬロシア人だったからであろうか。 「御託は十分だ」 「あん?」 「如何な相手であれ、どれほどの犠牲を出そうとも」 風が鳴る―― 「悪を討つ機を逃す理由はない――亡霊はここで潰えなさい」 「っぶねーな!」 やや前のめりになったオットマーは首を竦めて閃いた死の風を辛うじて避ける事に成功していた。 慌てた彼が視線を移したその先にはConvictioを月に冴え冴えと煌かせたノエルが居る。 この局面に有罪以外を認めない『審判』は彼ならずとも首が寒くなる冷たさを抱いていた。 「次から次へと……劣等から同郷から他所の連中まで……『極東の空白地帯』が呆れるぜ! こんなもん、どっちかって言や混沌のスープにお似合いだろうが!」 今まさに、強烈な消耗戦が始まろうとしていた。 ●vsフランツ 「時間を稼げ。粘り強く守り、そして跳ね返してやれ!」 質実剛健たる軍人の低い声が敵兵達に格別の規律をもたらしていた。 『親衛隊』の矛であるオットマー隊とリベリスタ達が削り合いを繰り広げる一方で『親衛隊』の盾に当たるフランツ隊は対応するリベリスタ達と泥沼めいた持久戦を展開していた。 「これが、軍隊……これがその戦場……」 「戦いは非情だ辜月。この戦場の空気に飲まれれば死ぬことになる」 「う、はい……」 自然に肌を伝った不快な汗に辜月は思わず小さな呟きを漏らしていた。 気圧されそうになる気持ちをぐっと耐え、敵を強く見据える。 「成る程、少しは骨がありそうなじゃな。タフな男は嫌いではないぞ」 「勿論、負けませんよ!」 傍らのシェリーが漏らした一言に辜月は気合を入れて胸を張った。 情けない所は見せられない。相手がどれ程に『厄介』だったとしても―― 「無論。妾も闘志で負けるわけにはゆかぬよ。 これが戦争ならば散っていった仲間の痛みも――胸の内に秘めても良い」 シェリーは気張る少年を目を細めて見つめてから、敵の指揮官たるフランツに声を掛けた。 「おぬしらの仕掛けた戦いに何の意味がある?」 「意味は、上官が考える事だ。軍人は己の職場を投げ出す事は無い」 「誇りが命よりも重いのはわかる。それでもおぬしたちは手段を誤ったのだ。 本当の誇りとは心に灯す篝火だ。誰からも何からも得られるものではない。故に――覚悟せよ」 フランツの鉄面皮はシェリーの言葉にもまるで揺らぐ事は無い。 『戦いの意味は上官が考える事』とした彼が本気でそれを言っているかどうかは定かでは無い。されど、彼が与えられたこの戦場に全力を尽くさんとしているのは何処までも明白な結論に過ぎなかった。 「決戦だ、進撃あるのみ。はっはっはぁ! 滾ってきたぜぇぇぇええ!」 高笑いと共に猛烈に突進した隆明が強暴な大蛇の如く敵陣で荒れ狂う。 「蛆虫以下のタンカス共が! テメェら残らず潰すまでは――この戦いは終わらねぇぞ!」 わざとらしい程に見得を切り、挑発する隆明に対してもフランツ隊は冷静さを失っていない。 「おっとぉ……!?」 隆明は強い。 猛然と敵兵を薙ぎ倒し、フランツに肉薄するまでを狙いとしていたが……突出すれば危険は増した。 集中攻撃で痛んだ彼が辛うじてフェイトに縋り、危急からエスケイプする。 「リヒャルトの援護はさせんっ! ハートブレイクッ!」 優れた直観を全力で働かせ、敵の動きと狙いを読まんとした麗香が隆明を追いすがる敵に激しく打ち込んだ。されど、その麗香もまた新たに前に出た猟犬にナイフで組みつかれ、苦戦は余儀ない格好である。十六vs十一の数的優位を持ったオットマー隊との戦闘に比較すれば、十二vs十一の状況を作り出したフランツ隊との戦闘はリベリスタ達にとって困難なものになっていた。 「流石に手強いな! だが! でるたさんと共に敵の撃破である! この場に居る仲間の為に敵を弾き飛ばして道を作るぞ!」 「うん。やる事は、何時もと同じだ。英傑や英雄はともかく、俺の様な一兵卒ならね――」 爆砕戦気を纏い、敵陣に仕掛けた『隊長』ことブリリアントを追い、『でるたさん』こと出田与作がコレに続く。 「では、状況を開始します」 ブリリアントが繰り出した渾身の一撃が猟犬のライフルを跳ね上げた。 強烈な威力にやや後退しかけた彼を含め――複数の敵を与作の多重幻影が追撃する。 されど、頑健なるからこそ『親衛隊』。敵は、総じて鉄壁であるからこそのフランツ隊である。 それ相応の威力を誇る二人のコンビネーションも極めて高い防御能力を誇る敵陣の前には有効打とは言い難い。 体力と防御力を武器にプレッシャーを強める彼等に冥真が密かに臍を噛む。 (戦禍交えて戦果を掻っ攫う。それがアークのやり方だ。だが、コイツ等はなかなかどうして……) パーティの支援を担う冥真だからこそ、状況に粘り強い戦いが必要なのは知れていた。 『絶対者』たる能力を持つ冥真が止められる時は、完全に倒された時のみである。それまでは決して止まらぬバックアッパーとして機能せんと考えた彼は一秒でも長く一人でも多く戦場に送り出して一人残らず生かして勝つ事を、それに必要な立ち回りを至上の命題に据えていた。 「逝ねよ劣等。戦場から現れたお前達が戦場から放逐されればそれで終いだ」 押されまくる戦況を何とか食い止めんとするのは、 「自分の仕事は、生きて帰ることです。仲間を、生かして帰すことです」 戦いを知らぬ過去に別れを告げて――今戦士として亡霊に対峙するシィンも、 「私達の目的はあなた達じゃないの。邪魔しないで」 そんな彼女を守るように肉薄する猟犬を阻んだウーニャも同じであった。 「イージス軍団と正面切ってはさすがに厳しいけどね。でも――」 かたくてかたくて壊せないモノなら――くすぐってあげる―― 戦場に響く勝利の凱歌、ラグナロクの栄光を笑う道化の一枚が打ち砕いた。 「――私の武器はちっぽけなカード一枚。ごつい人達と殴り合うのは向かないんだけどなあ」 くすくすと笑うウーニャは敢えて苦境にも冗句めいた。 額の端から血を流す彼女には言葉程の余裕は無い。彼女だけに非ず、ハッキリと断言してしまうならば戦力的に『抑え』の役割を果たさざるを得ないフランツ迎撃部隊には余裕らしい余裕は存在していなかった。 「少しでも傷が少なくなるように……皆、頑張って下さい……!」 『指揮官』たる辜月は翼の加護で、或いは聖神の息吹で仲間達を支援する。 リベリスタ達の余力を減じながら戦いは続く。 運命は次々と瞬き、その被害は専らリベリスタ側に集中していた。 「ヘイヘイ、お次はこっちだぜフラちゃあん!」 それでもノアノアは敢えて鉄の眼光を向ける叩き上げの軍人を挑発した。 「規律仕込みのブロッカーと自由仕込みのブロッカー、面白いカードだと思わないかい?」 「全くだ。妹の為の露払いも楽じゃないけど――」 ノアノアの放った光の砲撃が闇を引き裂く。 ほぼ同時に目前の敵を抱くように両手を広げたロアンが口元に凄絶な笑みを浮かび上がらせた。 「さて、親衛隊諸君。初めましてだよ、そして永遠にさようならだ。 懺悔でもしてみる? 許さないけど。負けっぱなしって嫌いなんだ――」 『殺す』事に特化した麗しき死――三日月を思わせる銀の軌跡が複数の猟犬を鮮血に染める。 「死神となって影と踊ろう、鮮血の輪舞曲。 血を撒け、中身をブチ撒けろ――まだだよ、まだ全然『浴び足りない』!」 哄笑めいたロアンに複数の弾丸が突き刺さる。 『浴び足りない』といった彼の法衣は既に赤く濡れている。濡らした赤が返り血なのか、己のものなのか――外から見ればその判別は不可能にも等しかったのだが。 ともあれ、麗香が、ウーニャが、或いは時にシィンが火弾の嵐で――辛うじて引き剥がした『ラグナロク』は彼に刃(ブラッドエンドデッド)を振るう機会を確かに作り出していた。 フランツ迎撃隊には数少ない火力らしい火力は敵陣を傷ませ僅かにその勢いを減じさせた。 「反撃と行くか」 「ああ、本当に――お前等も強くて気分がいいぜ!」 漸く訪れた好機らしい好機に快哉を上げたのは『火力らしい火力』ならぬ『完全火力』。 この場を承ったアーク戦力の中でも究極の破壊力を持つシェリーと影継の二人であった。 魔陣より放たれた銀の弾丸は敵を薙ぎ、防御姿勢を取ったフランツさえも飲み込んだ。 これで倒れた者は居ないが、効いたかどうかと言えばこれまでよりは格別である。 「ケイオスの執事どもより強いかどうか、試してやるぜ古強者!」 何者にも阻めぬ破壊神の如き鬼気をその身に纏い、吠えた影継が真紅の大剣斧を砲撃に傷んだ間合いの敵兵に叩きつけた。生死を占う上段からの打ち下ろしは構えた盾の鋼を散らす。 肩口から切り裂かれた猟犬の一人が血を噴いて倒れれば、流石のフランツ隊も殺気を増した。 「望む所だ。その守り、撃ち抜かせて貰う――」 不利は元より承知の上。だが、それでもリベリスタ達は諦めない! ●vsヤム 「あたしがきたからにはポーンとまかせるといいですぅ! なのにどうしてポーンとされているのですかぁ!」 マリルの台詞を聞くまでもなく――攻防の二隊が激戦を繰り広げているのと同じように、遊撃のヤム隊もリベリスタ達との交戦を激化させていた。 「バロックナイトと直接戦える戦場は~、実は初めてです~。実は~、とっても緊張してますよ~」 「あら、それなら少佐の所に行けば良かったのに」 言葉とは裏腹に間延びした調子で言うユーフォリアにヤムが刺激的な言葉を添えた。 「逃がさないけど」 唇を三日月に歪めたヤムからは自信と持ち前の嗜虐性が伝わってくる。 敵を翻弄し、弄ぶ――猫のような女は実に上手く戦力を繰る曲者だ。 (ヤム曹長、厄介な相手ね。オールマイティーな格上。嫌がらせ担当。ある意味で狙撃手ね……) イーゼリットが認識したヤム曹長なる敵は『弱い者にはとても強い』。ある意味で自分に似た気質を持っていた。英雄願望等持ち合わせぬ彼女は専らその配下を狙う役目に自らを置く。そんな女軍人と積極的に矛を交える心算は毛頭無かったが、『親衛隊』の有力者たる彼女は恐らくはこの場の誰よりも強いのだからその面倒は言うまでも無かった。 「……いやがらせが得意、とまで言えるのはうらやましい。だけど、だから負けていいわけじゃない」 半ば呆れるように呟いた涼子がギリ、と歯を鳴らした。 素晴らしいスピードで踏み込み、敵陣を暴れ大蛇で制圧しにかかった彼女だが――成る程。敵への『嫌がらせ』に余念が無いヤム隊は敵の行動力を奪うに長け、一方で己が行動力を減じる事を嫌う集団なのだろう。涼子の武技は確かに猟犬にダメージを与えたが『麻痺』というスタンダードな行動の束縛は不発のままに終わっていた。 「もう、眠ってもいいんだよ? 世界大戦の亡霊さん」 夜の闇に暗黒を迸らせたシャルロッテのその言葉はその実、『同郷』を気遣ってのものだったが――『親衛隊』たるヤムがそれを受け入れる事等、元より何処までも有り得ないか。 「無理ね。アマチュアさん達。それじゃ私達は倒せないわよ」 からかうようなその言葉は嫌という程鼻につく。 (他に、目を向けさせたりは、しない――!) 高い指揮能力に裏打ちされたヤム隊の連携は他二隊のそれをも上回っていた。 極めてバランスの良い戦力の作り出す戦いは搦め手と持久、攻撃を全て兼ね備える確かな脅威である。 「アマチュアとは言ってくれるわね。 アンタ達がどれだけ優秀が知らないけど、うちらだって命掛けの戦いを繰り返してきたわけなのよ。 見せてあげるわ! 全力全身全霊!」 されど、今日ばかりはストイックに――吠えた瞑は「楽しみにしているわ」と嘯いたヤムを睨み付けた。 アーク攻撃部隊とヤム隊の戦力比は十六対十一。オットマー隊と同数を数えるリベリスタ達は抑えのみに寄らず、可能ならばこれを撃破せしめる期待を背負っているのは間違い無い。 「驚かせてあげるわよ、きっと」 驚異的とも言えるスピードで――ヤム目掛けて踏み込んだ瞑が両手の刃を閃かせた。 彼女がイメージするのは一撃で敵の首を刈る自分。二度を数えた驚異的な行動力は、アークトップレベルを自認するスピードはその為の武器であった。 されど。 「速いだけって――誰かも言われて無かったかしら?」 渾身の二撃もひらりと身をかわすヤムを捉えるには至らない。 鋭く舌を打った瞑が切り返せば、靴が摩擦に音を立てる。 「木漏れ日浴びて育つ清らかな新緑――魔法少女マジカル☆ふたば! 魔を以って法と成し、描く陣にて敵を打ち倒さん……本気でいくよっ! 我が血よ、黒き流れとなり疾く走れ……いけっ、戒めの鎖!」 行動不能が何処まで通用するかは別にして――葬操の魔術は双葉が持ち得る最大の攻撃の一つであった。惜しみなく繰り出される黒鎖の奔流は驚くべきか連なって敵陣に襲い掛かる。ある者はこれを避け、ある者はこれを凌ぎ。やはり行動を奪うには足らないが、押し切る他無い戦場において彼女の攻勢は強力だ。 「噂に違わぬ美しさ……どうです、今晩私とディナーでも」 「私に勝てたら考えてあげるわよ」 「それは漲る。仕事にも張り合いが出るというものですよ」 嘯いた恭弥が猟犬達が繰り出したフラッシュバンの投擲、或いは葬操の調べから――ニニギアを庇う。 ヤム隊の猛攻は止まらず弾幕のように繰り出された妨害の嵐を不吉の月の輝きが撃ち抜いてくる。 「貴女の強さは良く知っているけれど……今度は思い通りにはさせないわ!」 個人の雪辱よりも、今為せる事を為す。 力の差を知っていようとも――敵う部分で敵を上回れればそれでいい。 その美貌に必死な表情を乗せたニニギアは庇われるばかりの存在ではない。庇われる意味を持つ存在は強力な賦活の力をもって仲間達の態勢を一気に立て直さんとしていた。 同程度の能力の持ち主が居たとした場合、総合力に優れるという事は一点特化の優秀さを持たない事とも同義である。ヤム隊が同じ『親衛隊』である以上、力量の程は多少の差でしかあるまい。 (しぶとく、少しでも――彼女の意図を食い止める――) なればこそ、極めて優秀な回復手であるニニギアは自らの強味を『火力』と考えたのだ。 そして、もう一人。 「言っとくけどな――俺がこの場いる限り、そう簡単に皆の自由は奪わせねぇよ」 ヤム隊にとっては或る意味で天敵とも言える男がこの戦場には存在していたのである。 「いっちばん嫌いだわ、貴方みたいなの」 「褒め言葉と受け取っておくぜ」 エルヴィン・ガーネットの能力は遂行力そのものである。何時如何なる戦いでも彼は行動し、生存し、戦線を維持させる事に特化していると呼べる。ヤム隊お得意の小細工も彼には根本的に通じず、生半可な火力では彼を簡単に沈める事は不可能だ。パーティ全体を支援し続け、行動不能を許さないその存在感は確かにこの場に楔として機能するものになる。 「正直、猟犬がどうだとか歪夜が何だとかどうだって良い。 でもよ、俺様の縄張りで好き勝手されんのは気にいらねェ訳よ。 分かるだろ、てめえらが売った喧嘩だ。誰が買おうが文句は無えよなあ――落し前きっちり果たして貰おうか!」 アッシュが吠える。 「オラオラ雷帝様のお通りだァ――!」 考えるよりずっと本能に近い『喧嘩慣れ』を武器に『舐めた連中』に渾身の一撃をお見舞いした。 戦いは続く。次々と繰り出す猛攻がヤム隊を削り、その反撃がリベリスタ達を削る。 「伊達や酔狂で騎士を名乗っている訳ではない、この身を倒したければその十倍は持ってくるが良い!」 凛然と声を上げたアラストールの素晴らしい防御力が殆ど跳ね返すと言っても過言では無い程にヤム隊の前に立ちはだかった。無論、鉄壁たる彼女ばかりを構うような敵では無いが…… 「――はっ!」 聖骸闘衣を纏うアラストールは防御ばかりの存在ではない。 煌く剣で苛烈に攻めかかる彼女を『放置』する事はヤム隊も出来はしない。 「面倒ね、ちょっと抑えて!」 「Ja!」 されど、盾には盾。矛には矛。 ヤムの号令に応え守りに長けた猟犬がアラストールを相手取らんと動き出した。 総合的に穴の無いヤム隊は状況に応じて耐久・攻撃を自在に可変させる術を持っていた。数ではリベリスタが上回るが、個々の能力では劣るといった所。予断を許さぬ展開は未だ終わりの気配を見せない。 攻防に運命は瞬き、より濃密になる死の足音が近付いてくる。 敵味方共に傷付き、戦いが続けば徐々に展開は加速する。 殆どの戦場がそうであるのと同じように――きっとこの戦場にも慈悲は無い。 「……怖いっスか?」 「ううん」 並んで戦場に立つ【黒猫】の二人――フラウの問い掛けに五月(メイ)は静かに首を振った。 「大丈夫。フラウが居れば強くなれるよ」 「うちだって一緒だ。メイが居るから強くなれる」 だから。 共に踏み込み、共に敵に立ち向かう。 フラウの剣が氷刃の霧を作り出す。 怯んだ敵陣にメイの振るう残影の剣が突き刺さった。 (オレは攻めるしか脳が無いから只管にこの剣を振るうと決めている。 オレは護る事に貪欲だから理不尽な世界でも剣を振るう事しか出来ないんだ) (こんなちっぽけな手でも共に手を取ってくれる者が居るから。 だからうちは戦える。きっと、最後まで。さぁ、行こう。うち等の明日を掴み取る為に!) 想いは交差し、力になる。 (涼はやっぱり最前線なんだよね。どうか無茶だけはしないで……) 祈る気持ちの少女(アリステア)の呼び声に応え、幾度も奇跡は舞い降りた。 アメジストの双眸が見つめる背中は決して敵を彼女に近付けんと奮闘する涼のものだ。 「――まァ、これだけいるのに喰らうとは運が悪かったな」 不敵に笑った彼の賽が『不運な』猟犬の一人を爆花に包む。 素晴らしい行動力で次々と攻撃を繰り出す彼は漸く倒した一人の向こう――ムッとしたヤムに視線を送る。 「ダンスってワケじゃあないが――ま、一曲付き合ってくれよな?」 ●1945II 「……佐」 「……?」 「リヒャルト少佐。ご無事ですか……は愚問ですが。まだ存命のようで安心しました」 掛けられた声に彼はゆっくりと目を開けた。 殆ど最後の力を振り絞っての行為である。滲んだ視界の中には黒髪の女が立っていた。 アーネンエルベ特務機関付き中尉、クリスティナ―― 『鉄の星』で鳴らす同僚の顔は知らない訳では無かった。だが、彼女は彼の直接の部下では無い。 「少佐。貴方は復讐をお望みの筈だ」 言うまでも無い。 「貴方はまだその方法があると知ったなら――最高のアーリア人である筈だ」 言うまでも無い。 「貴方には、戦う意志がある筈だ」 言うまでも無い! 声にならない叫びを目を見開いて睨み付ける事で代替する。 「成る程、『貴方』は最良を見誤らない。 『貴方』の残る力を振り絞るその先として、これ以上の機会はありますまいね」 クリスティナの携える魔術書はまるで歓喜するかのように怪しい輝きを強くしていた。 全身を蝕む激痛が、今にも消えそうな意識が徐々にクリアになっていくのを彼は実感した。 有り得ざる奇跡は神の望んだものか、悪魔の望んだものか――そんな事は彼にはどうでも良かった。 ――この地球上から消し去ってやる、劣等共め―― 打ち立てられた誓いは死んでいない。 彼の抱いた決意は燃え上がる炎のように、満ちる活力に応じてその熱意を上げていた。 リヒャルト・ユルゲン・アウフシュナイターはあの日の屈辱を決して、決して忘れない―― ●vsリヒャルト 「プライドなんてチンケなもんじゃねぇ……」 燃えるような赤毛が怒りと闘気にまるで逆立つようだった。 「あんな穴何ぞに頼って世界を取ろうなんて奴に――負けてやるかって話なんだよ!」 暗中の戦闘に激烈なまでの存在感を放ったのはランディが全身全霊で放った最大出力の気砲である。 間合いを鮮烈に駆け抜けた破壊の光は真っ直ぐに――彼が望んだ敵を目指して夜を食らう。 (俺の敵は世界だ、世界を壊す為に俺は世界を守る、負けて良い戦いなど無ぇ!) 当然と言うべきか敢えてリヒャルト・ユルゲン・アウフシュナイターの足止めを望んだ男はここが死地である事を知っていた。されど、ここで死ぬ心算は毛頭無かった。 覚悟が無いではない。覚悟をする気が無い。傲慢であり、プライドであり、結論である。 「は! 効かぬ程でも無いが、この程度。所詮劣等の技に過ぎんな!」 そう――あのモーゼス・マカライネンさえも屠った光弾さえ目の前の将校が右手で弾き飛ばしたとしても。ランディの結論に変わりは無い。獰猛に――本音で嘯くばかりなのだ。 「……イライラすんだよ、俺より強ぇって面してんのがな!」 三隊三様に戦いを展開する『親衛隊』各隊とアークの部隊。 「うーん、盛り上がってるね!」 翔護の目が見通した周囲の戦況は一進一退、有利不利こそあれ個々の動きでは比較的拮抗した戦いを展開しているのに対して、やはりと言うべきかリヒャルト隊と対決するアーク主力攻撃部隊の戦いは毛色の違うものとなっていた。 「みんなっ! ふぁいとっ!」 キャラクターには似合わない程に的確な戦術で全体を支援するのがミーノである。 高い支援能力をも持ち合わせる彼女は、五感を研ぎ澄まし、翼の加護で仲間達を底上げし。 「ミーノがいつでもうしろにいるのっ! ぜーんぶおまかせなのっ!」 更にはブレイクイービルとインスタントチャージまでをも備えるサポートの十得ナイフといった所。 ミーノの支援能力、快のラグナロク…… 温存戦力も加え、他隊に比べて質も量も申し分ない。 実に数にして三倍近くの戦力を用意したアーク側ではあったが、流石にバロックナイツ――『親衛隊』首魁のリヒャルトは簡単に勝利を望める相手では無かったという事である。 「力の差は歴然。だが、それが良いぞ! 『閃刃斬魔』、推して参る――」 「雑種如きが、僕に挑めると思うなよ?」 「挑むだけなら自由さ。私は万に一つの勝利も、億に一つの勝利も必須とは思わない。唯――」 繰り出された葬刀魔喰がアハト・アハトと噛み合った。身を乗り出すようにぐ、と体重を掛けた朔とリヒャルトの距離は至近。しようと思えば接吻さえ出来そうな距離で彼女は囁くように声を漏らした。 「――私は単純に、お前と出会えた事を最高の幸運だと考えている」 彼女が吐き出した人を食ったような言葉はリヒャルトの痛撃にそこまでとなった。 成る程、朔の歓喜は大抵の場合、リベリスタには余り有り難い情報では無いか。 リヒャルトの猛烈な存在感にリベリスタ側はかなりのプレッシャーを禁じ得ない。 戦いが続く程に必殺性を帯びるその攻撃は危険さを増す。多くのリベリスタがそう考えていた通り、彼の攻撃が多くのリベリスタ達に対して『一撃一倒』ならば手厚い支援があろうとも余力を削られるのは不可避であった。 されど『それは分かっていた事』なのである。 (相手が誰でも関係無い、アークの、沙織さんの敵になるのならアーリア人でも私が劣等って言われようとなんでもいい。劣等でも今立ちふさがっているのは私達なのですから誰であろうと戦うしかない!) 分かっていれば対策も或る程度は立つ。敢えて戦場の前線から離れた京子が作り出した影人は彼女の能力を模す特別性だ。一瞬の閃き(クリティカル)に優れるそれは時に強敵の攻撃さえ避けるデコイになる。 「敗れ、遥か時を経て尚色褪せないその鉄十字の意思…… その魂には敬服しますが――戦争など、起こさせない。 例え『現在』の始まりが誤っていようとも。積み重ねた時を、貴方達の憎悪だけで否定などさせない!」 先のランディ、このユーディス等、優れた前衛は次々とリヒャルトの抑えに出るが、彼の配下は彼をサポートする為の存在なのだからいよいよこれは厄介である。リヒャルト隊は部隊に矛としての機能を求めるよりも、部隊に盾としての機能を求めていた。それは屈強なるフランツ隊をも上回る意味で、である。 ヤムの柳眉を顰めさせたエルヴィンのような猟犬が居る。 絶対的な防御力を誇るアラストールのような猟犬が居る。 有無を言わせぬ弾幕で邪魔な障害物を叩き潰すエナーシアのような猟犬が居る。 圧倒的な支援能力で陣営を立て直すニニギアのような猟犬が居る。 『戦奏者』たるミリィのように陣営を強化するレイザータクトも無論、居る。 そして彼等は何れもかなり堅牢である。 平均値において確実にリベリスタ側より精強である彼等は能力、装備の両面から『リヒャルト少佐をより長く支援する事』を第一の目標として企図していると言えた。リヒャルトという絶対のジョーカーは作戦に彼の存在以外が必要無い事を決定付けている。丁度『神の子』を擁したサッカーチームがそれだけで『最強』だったのと同じように。連携がありながら、ワントップが絶対という構築は非常に面倒な敵になる。 「……っ、あ……!」 ユーディスの輝く穂先がリヒャルトの軍服を浅く切り裂く。 怒りの表情を見せた彼の重い主砲での鉄槌に彼女の身体はアスファルトにめり込んだ。 盾の上からの一撃であっても凌ぎ切れないその威力は攻防の中で確実にリベリスタ達を追い詰める。 「どうした劣等? 跪き、許しを請うても貴様等に神は居ないがな!」 血を流し、片膝を突き。それでも運命を燃やして立ち上がるユーディスを見下ろすリヒャルトが嘲笑う。 その言葉に劇的な反応を見せたのは当の彼女自身ではなく―― 「さて! 我が主・鳩目が、親衛隊の首領に申し上げたき儀がございますそうで」 「そうだ。アーリア人の優性? 笑わせるな。人に仇成すことしかできないエリューション風情が!」 ――供にロウを伴った 鳩目・ラプラース・あばたの方であった。 「主のご所望とあれば、道を斬り拓いてご覧に入れる!」 猟犬の一人がロウと斬り結ぶ一方であばたのピストル(げてもの)は見事な連射を見せていた。 「お前は最早欠片もアーリア人では無い。人間辞めた奴が人間語るな、殺すぞ」 「貴様――」 全く自身にも跳ね返る――言葉はまるで革醒者全てが帯びる呪いのようである。 さりとて、彼女のこの言葉はリヒャルトのみならず『親衛隊』全体を熱くしたのは間違いない。 『それ』に至上の価値を置く彼等にその言葉は余りにも劇薬過ぎた。七十年の時を『そんな事』に拘り続けてきた彼等にとって、それは確実かつ危険な挑発に違いない。 露骨な集中攻撃を受けたあばたが血の海に沈んだ。 しかして、やや冷静さを欠いた『親衛隊』が隙を見せたのをリベリスタ達も見逃していない。 「閣下に尻捧げて賜った階級でふんぞり返って楽しそうだな。『島国の黄色い猿』以下の優良種じゃ、第三帝国の滅亡も必然だ。ご大層なモノぶら下げて、担いで逃げるの一苦労だったろ」 更に挑発めいた快に意識が集まれば―― 「少しでも多く屠らせて貰うわよ――」 ――バランスを崩した敵方はエーデルワイスが狙うには格好の獲物だった。 ノアールカルトが複数闇に閃けば、親衛隊の一人が片目を抑えて声を上げた。 「お嬢様!」 「恥ずかしい呼び名ですわね、それ」 呼びかけた時、既に亘は戦場の宙を舞っていた。 「行きます!」 「さあ、囀りなさいな!」 青い六枚の羽がはばたき、戦場に散る。何処か余裕めいて応えた黒い翼がそれに続いた。 亘とクラリスは敵陣の僅かな綻びを突き、宙より降下する格好でリヒャルト隊の後方に切り込んだ。 (心配何て微塵もなく――自分の心と命は貴方と共に!) 華麗流麗な二翼の戦いに続き、 「一気に行くぜェ! 舞台上から退場したい奴だけ掛かって来なァ!」 「この戦を――この夜に終わらせる!」 猛が優希が暴れに暴れる。 「何としても――食い止めます!」 守は手にした盾で敵の弾丸を食い止め、 「パニッシュ☆」 翔護の弾幕が制圧的に敵陣に襲い掛かる。 「優良と言うのも大した事がないみたいね?」 更には惚けた笑みさえ見せた焔の火焔が強烈に敵陣を炎に包んだ。 リベリスタの戦いは極めて戦意の高いものだった。リヒャルトと『親衛隊』の攻勢は彼等の体力・余力を確実に奪い続けてはいたが……それは自力に勝るものの、数に劣る『親衛隊』側も同じであった。 「……チッ……」 舌を打つリヒャルトは部隊からの支援もあり殆ど傷んでいない。 しかして、彼の配下はフェイトを燃やした者もあれば、倒された者もある。互いにとって良くも悪くも状況が動き出そうとしているのは余りに明白であると言えた。 「鬱陶しいハエ共が――」 リヒャルトが虎の子たる主砲(アハト・アハト)の使用を躊躇したのは激しい消耗と砲撃の隙を嫌った事もあるが、言うまでも無くそこに『親衛隊』が居たからだ。彼の主砲に巻き込まれれば彼ならぬ何者も只で済むようなものではない。非常に傲慢で、非常に神経質で、非常に悪辣なリヒャルトはしかし――同胞においてのみはその気質を喪失する。 彼は守るべき存在(もの)を持っていた。 彼は仲間に悪態を吐いた事は無い。失敗した者も含めて――自身の部下を軽んじ、罵倒した事等無い。 アーリア人種は、神が愛した――彼が愛した『美しいもの』だから。 「リヒャルト少佐……」 吹き抜けた温い風にその髪を靡かせながら、敵と対峙するリセリアが『ドイツ語で』呼びかけた。 「かつてベルリンは焼け落ち、けれど――全てが失われた訳ではない筈です。 ……僅かでも護り通せた筈のもの。それらには、貴方達の憎悪を拭う事はもう出来ないのですか」 「お前に何が分かる?」 鼻で笑うリヒャルトの声が幾分か彼が敵に向けるものにしては和らいでいた理由は言うまでもあるまい。 「月並みな台詞だがね。お前に一体何が分かる。 戦争の常とは言え、だ。大切なものを根こそぎ奪われ、この顔の傷を受けた僕の気持ちが分かるのか? 愛する者を目の前でミンチにされた経験は? そのバーベキューの臭いを知っているか? ええ? 愛する祖国の為に戦い――命を賭けて。その祖国から『間違った歴史』と呼ばれる気持ちが分かるか? ベルリンを土足で踏み荒らした連中は、祖国の何を引き裂いた。 あの壁が倒れた時、此の世に有りもしなかったお前に――『親衛隊』の憎悪の何が分かる!」 「――――」 息を呑んだリセリアは若年故にそれに返す言葉を持たなかった。 少なくとも人間と人間の大きな戦争を経験した世代では無い。 少なくともリヒャルトが口にした痛烈なまでの衝撃を『戦争で』知る人間では無かったからだ。 リヒャルトが奪わなかった訳は無い。 誤りに満ちた戦争が、誤った『祖国』が奪ったものは数限りなく、何処までも痛烈だ。 全ての犠牲は『戦争の世紀』に当たり前とされてしまっただけだ。単純善悪で割り切る事が出来ない、事情は誰にでも存在する。リヒャルトは悪だが、盗人に三分の理を唱えさせれば容易く論破出来ようものか。 答え等――最初から何処にもありはしないのだから。 「だから、戦争は終わっていないのさ」 リヒャルトの、傷付いた『親衛隊』の背後に黒い何かが見えた気がした。 「戦争は終わっていない。僕はこの世界が終わりとするまやかしを認めていない。 僕達は一握り残された戦争の残滓だ。栄光ある祖国の夢を最後に叶える開拓者だ。 それを劣等に――邪魔される訳等には行かぬのだよッ!」 決して交わる事無く、決して分かり合う事無く、決して溶けない氷の壁は絶叫で最早明らかだ。 リヒャルト・ユルゲン・アウフシュナイターは結局、唯の人間でしかないのだ。或いはあのジャック・ザ・リッパーより尚青く。九十二歳(としそうおう)でしかない。否、若い肉体と強大な力とを兼ね備えてしまったが故に『その程度の成熟すら許されなかった』。 研ぎ澄ましたリセリアの一突きがリヒャルトの胸を突き刺した。 仰け反ったリヒャルトの唇が僅かに血を吐き出した。 お返しに繰り出された銃撃が『もう一度』受け切れなかったリセリアをアスファルトの上に叩きつけた。 幾度目か猛烈な攻撃がリベリスタ達に降り注ぐ。 「知った事じゃない」 鬼気迫る『親衛隊』の攻撃を一言の下に斬り捨てたのはレナーテだった。 「取り返すものは取り返す。何より、誰も死なせやしない――その為にここにいるのよ!」 神ならぬ人の世の造形に完全な正義も完全な悪も数少ない。されど、彼女には自身が信じた道があった。支援役ながら傷付いたリセリアを何とか起こし、その身を庇うように敵に向く。 「同感だ」 そんな彼女の――更に前に立ったのは両手に大型のシールドを備えた快だった。唯、仲間の盾になる事を望む恋人の背中には敵主砲(アハト・アハト)さえ食い止めてやる、と言わんばかりの強烈な矜持と信念が迸っていた。 「ところでニッキ、帰ったら先週見せびらかしてた大吟醸開けようぜ☆ 死亡フラグ? ならオレ達毎月死んでる事になるってさ!」 冗句めいた翔護に一方の快は清々しいまでに言い切った。 「――ああ。俺は、一歩も退がらない!」 ●1942 偉大なあの方から勲章を賜る。 この胸に鉄十字を宿したその瞬間に――僕は思ったのだ。 命も誇りも全て祖国に捧げんと。どんな困難も僕の心を惑わす事は出来ないと。 ●vsリヒャルトII 「おや、案外簡単に誇りが地に落ちましたな」 「貴様ああああああああああッ!」 リヒャルトを激昂させたのは九十九が放った実に精密な狙撃だった。 彼の軍服を飾っていた鉄十字勲章がアスファルトの上に転がっている。慌ててそれを拾おうとしたリヒャルトが大きな隙を晒し、リベリスタ達の猛攻を受けたのは――彼が彼であるが故。 数に勝るリベリスタ達はリヒャルト隊を次々と撃破し始めていた。 確かにリベリスタ側も同程度、或いはそれ以上戦力を喪失していたのだが――彼等には対リヒャルトの為の切り札と言うべき温存戦力が存在していた。確実に彼を仕留める為の『魔弾』は終局に向かい始めた戦場で解き放たれるその時を待っていた。 他三隊の動向と言えば、それぞれである。 「此方は片付いた。今度が、本番か――」 櫻子を伴い、駆けつけた櫻霞の様子が示す通りオットマー曹長は最後はノエルの一撃に半身を吹き飛ばされ、ミュゼーヌの黒銀円舞曲に踏み潰された。 「――少佐、ご無事ですか!」 残る戦力を引き連れてリヒャルト支援に急行してきたフランツ軍曹を見れば分かる通り、対フランツ隊に当たっていたリベリスタ達は自力の差に押し切られ、敗退した。 残るヤム曹長の部隊、対応したリベリスタ共々が現れないのは彼等が依然拮抗しているという事を示している。 「既に終わった亡霊なんかより、今を生きるワタシのドラマが勝つ所を見せたるぜ!」 「う、うん。逃げない。逃げない。ぼ、僕だけが怖いだなんちぇ言ってられないんだ!」 何度転がされてもむくりと起き上がる明奈は敵を変えても萎える事は無い。 必死の形相でそれでもここから去る事は無い――美月もそれは同じ事。 凄絶な消耗を見せる彼我の戦いはいよいよクライマックスを迎えようとしていた。 「いよいよ本番じゃな」 「――で、ございます!」 瑠琵と愛音はまさにこの終盤にリヒャルトに届かせん為の一手を用意する為にここに居た。 アーク側が温存戦力を投入する瞬間は、彼女等が準備を整えた瞬間である。 「さあ、いよいよですね」 「ねーさまのお手伝いも十分ね」 「同胞の命を一つでも多く救えるのであれば――全ては」 ラグナロクを張り直す要も含め、【楔石】は五人。万葉、灯璃のチャージによる支援を受けながら愛音、瑠琵がこの戦いの間に量産した式符・影人は吶喊するリベリスタ達の数を十分フォローするだけの物量を持っていた。無論、要のラグナロクが影人達に更なる力を与えるのは言うまでも無い。 木偶と侮る無かれ。反射による不可避のダメージは因果応報に敵陣の体力を削り取る。それも、確実に。 (灯璃はあの副官が黒幕だと思うんだけどねー) 視線の先にあるリヒャルトよりも――唯の乙女の勘である。 「鉄の猟犬とは大層な。愛音たちは子犬でございましょうか? 侮った子犬に喉元食い破られることなかれ。しかし、この牙、必ず届かせるのでございます!」 「流石にこれを即座にどうにかするには手が足りまい?」 リヒャルトの馬鹿げたまでの攻撃力も――主砲の殲滅力も。 主の命に従い、只の一瞬を稼ぐ命無き式神共は邪魔にしよう。 ――私は戦奏者。―戦場を奏で勝利へと導く者。任務開始。さぁ、戦場を奏でましょう―― ミリィ・トムソンの号令は今夜も全てを動かす鍵となる。 彼女の指揮と教導(ドクトリン)は戦場に奏でられる凱歌のよう。 主砲(アハト・アハト)こそ温存されたままだが、最早敵戦力は半減。 「お嬢様、参りましょう……!」 全身に気力と力を漲らせ、聖骸闘衣を纏うリコルは見得を切る―― 「貴方方の誇りは埃(ダスト)の間違いでは? 時代遅れのポンコツ頭様?」 嗚呼、この瞬間ならば――攻撃を束ねるには十分過ぎる。 「さぁ、悪意に鉄槌を叩きつける時だ!」 晃の一声が仲間達を奮い立たせる。クロスイージスの勇猛はジハードの時を告げていた。 「出し惜しみ無しだ――覚悟しろ!」 「さあ、『お祈り』を始めましょう」 静謐と呟いたリリが両目を開ける。 少女の双眸が見据えたその先を風斗が走る。 「この千載一遇のタイミング、絶対に逃すわけにはいかない。リヒャルト!」 「私の蒼が穿ち、楠神さんの紅が断ち斬る。怒りの日は来たれり。 リヒャルト・ユルゲン・アウフシュナイター、聖なる十字の下、貴方を断罪します――Amen」 リリの呪弾を従えて、繰り出した赤い斬撃を刹那に重ねて。 「――この場で必ず――お前を仕留めるっ!」 遂に、リベリスタ側の総攻撃が始まった。 無論、敵は強大無比なる『鉄十字猟犬』。全ての力を重ねても打倒に足るとは言い切れまい。 だが、それでも彼等はこの瞬間に勝利を賭けたのだ。 猛烈な攻撃には猛烈な反撃が待っている。 次々とリベリスタが深手を負う、『親衛隊』も同じく。 そあらが叫んだ。 「リヒャルトとの戦いは危険とわかっていても決着をつけなければいけないのです――!」 あの公園で彼に敗れた人間だから。 (あたしの力及ばず――満足に成功出来なかったから。 大丈夫、あたしにはいつでもさおりんがついてるです。さおりん――) そあらはその力を振り絞り癒しの息吹で戦線を支えるのだ。 「思い出せ、この赤き恐怖を! そして教育してやる! この真紅こそ、今を生きる我々の血潮だ! 貴様ら亡霊の纏う鋼鉄など、赤錆に過ぎんと知れ!」 因縁は巡り、極東の地で時代を変えて――再びベルカとリヒャルトは対峙した。 零下の視線と狂熱の視線は絡み合い、何れも――殆どの戦士が執念の如く運命に縋り、敵の運命を消し去らんと喰らい合う。それはまるで――あの、逆凪黒覇が喜びそうなウロボロス。 「あんたに直接の因縁はねーけどな」 飛び込んだクロトが減じつつある手勢とリヒャルトに多重残幻剣を繰り出した。 「種の云々とかこまけー事に拘ってるのに目を瞑れば、あんたは確かに立派な軍人さんで、なかなかの強敵だよ。まぁ歯牙にもかけねぇとは思うが、雑種の全力ってのを味わってみてくれよな!」 「大将首だろ、狙うなら」 「アシュレイちゃんの動向も気になるが」とは口に出さず。 『まだ塔は崩れない』とあくまで今は彼女をも『信じて』ここを自分の働き所と考えた竜一が踏み込んだ。 「おいしい役回りなんざいらないさ、俺はただの一矢だ。 リヒャルトの生死を問う一矢だ。ただの一の文字を刻めばいい。竜一の、一の文字を――!」 凄まじい程の加速はリュミエール以外の認識を例外なく『過去』にする。 (痛いほどオマエの力は知ッテイル。 ダガこの戦場ニハアイツガイルだから私は死ネナイ。ダッテ死んだらアイツが悲しむカラ――) 超高速による斬撃の連続がリヒャルトの得物と絡み合い、硬質の音を響かせた。 猛烈な攻撃の数々を浴びればリヒャルトとて消耗を否めない。 あのジャックと戦った頃のリベリスタならばそうはいかなかっただろう。しかし、今の彼等は『親衛隊』と十分渡り合える高い実力を持っているのだから―― 集中打がリヒャルトを追い詰める。 圧倒的な防御力を、技量を物量が上回る。 丁度、あの大戦の空の戦いのように――リヒャルトの奮戦さえ、勢いが上回りかけていた。 「劣等共が――!」 「少佐、主砲を!」 歯を剥き出したリヒャルトに鋭い声で制したのはフランツだった。 「何?」 上官を庇うようにリベリスタの攻勢の前に仁王立ちした彼は言う。 「主砲を。何、自分は防御力には自信がありますからな。お前達――文句は無いな?」 「――Ja!」 亡霊は最初から一つの未来しか見ていない。認めない。 遠い『あの日』にリヒャルトがそうであったのと同じように―― 言葉の意味を明敏に察したリヒャルトはそれ以上の問答をしなかった。 「今一度、身の程を知らしめてやる。劣等共め――!」 魔人の全身に力が漲る。この夜に最も危険な存在がリベリスタと同じく『勝負』に出たのだ。 「死力を尽くせ! 邪魔な木偶を掃除しろ!」 フランツの声に応えた残る少数の猟犬達が命も捨てるとばかりに猛烈に攻める。 リベリスタを傷付け、同時に庇いに入った影人達を破壊する。 「止まって――!」 鋭く身を翻した陽菜が弾幕から阻害に――その行動を切り替えた。 彼女の放った輝く気糸がリヒャルトの主砲(アハト・アハト)に絡み付く。 されど届かない。化け物染みた膂力はその糸を一瞬で引き千切り、陽菜は即座に態勢を立て直した。 リベリスタ側に構えられたアハト・アハトが危険な気配を集中させる。 (アシュレイさん、何の為にいるですか! 今貴方の力が必要なのです!) 胸が潰れそうな緊迫感にそあらが唇を噛み締めた。 (どうして全力を尽くしてくれないの? 貴方はただアークを利用するだけなの? 貴方の言葉を信じる者がいないと決めているのは貴方自身でしょう。 アタシ達を信じられないのに利用するのは、虫が良過ぎるとは思わないの――?) 恵梨香が周囲を思わず探した。だが、彼女等が頼む魔女は、無い。 「魔女殿は成る程、中々徹底しておられる。 今回の神秘は曰くの深度がこれまでと比較にならない程“浅い”が――ふむ」 イスカリオテが口にした通り、彼女は自らの『予定』を変える心算は無いのだろう―― 『神頼み』にも等しい『魔女頼み』を良しとしなかった者が居た。 「だって、神様――嫌いなんですもの」 嘯いた海依音が構えを取るリヒャルトに楔の聖矢を突き刺した。 「女は誰でも魔女になれるわ。ねぇ、そうは思わない?」 アシュレイ君。 呼びかけはそっと仕舞って海依音は笑む。 乾坤一擲、切り札は最後まで残しておくものだ。 先に『切った』リヒャルトは――もう止まるまい。 「皆、『通して』欲しいんだよぅ!」 声を張ったアナスタシアが焔腕で目前を薙ぐ。 彼女の意図――後方に全精力をこの瞬間に注ぎ続けた鷲祐の存在――を知った時、リベリスタは真に勝負を掛けるべきが『この瞬間』である事を完全に理解した。 「もはや貴方達の時代は終わったのだ!」 「させん!」 「いや、今日ここで終わらせよう。それが時計が止まったままの貴方達への手向けだ!」 「ぬ、ぬあああああ――!」 咆哮を上げたフランツをゲルトが強引に押し退けた。 焦りにミスを犯した彼を肩で息をした焔の蹴撃が撃ち抜いた。 次々と突き刺さる攻撃に血を吐いた『壁』が今、崩れ落ちた! 「感謝する――」 頼みにするのは唯一のみ 彼は脆弱で、彼は拙く、彼は言ってしまえば二流以下だ。 しかし――彼は、今夜を打開する最高の武器を有していた。 炸裂音も、怒号も、悲鳴も。 痛みも、恐怖も。全て、切り捨てて。 集中は十二分。駆ける鷲祐には声を上げるリヒャルトも、今更現れたアシュレイも関係ない。 「いっけぇ鷲祐、派手にやっちゃえ―――!!!」 「フッ、分かっている」 コマ送りの世界を泳ぎ切るに――司馬鷲祐は『速過ぎた』。 「弾指六十五刹那。奏でよ竜鱗ッ!」 常識を超えた挙動が音速の壁をぶち抜いた。 二流のリベリスタが有する超一流のスピードは更に倍加し、威力となり、 「――神速斬断『竜鱗細工』――ッ!」 構えたリヒャルトの腕ごと、アハト・アハトを貫き、破壊し、駆逐する。 砕けたのは祖国の誇り。最も素晴らしい兵器の一つ。衝撃は最早無限大。 「馬鹿な、馬鹿な、馬鹿な、馬鹿な――ッ!」 血に咽ぶリヒャルトが凄絶に叫び、空を仰ぐ。 「アーリア人は負けない。僕は、『親衛隊』は、この間違った――」 無慈悲な戦場を黙らせるのは何時だって苛烈な暴力だった。 慟哭する亡霊に最後の攻撃が降りかかる。 リヒャルト・ユルゲン・アウフシュナイターが終焉する風景をアシュレイは静かに見つめ……『壊れた神器級アーティファクト』にその柳眉を顰めていた。 「……成る程、これはなかなかどうして……話は簡単には済まないかも知れませんねぇ……」 そんな風に呟いた。 果たして――リヒャルトだったものが挙げた慟哭で『それ』は満腹した。 世界に充満した怪しい気配の存在を、リベリスタが感知し損ねる事は無い。 「これは――?」 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||






























































































