
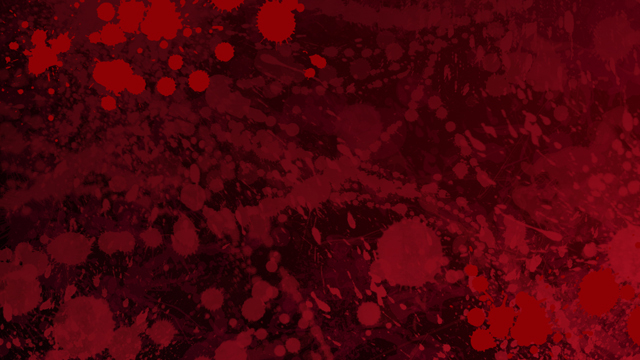

罪なき者と、罪ある者、最後に笑うのは誰か?

|
● まるで夏の雪の様に。溶けて消え逝く、この運命なら。 ●破界器ヴァリアントとその周辺。 特殊破界器『ヴァリアント』により一般市民の多数殺害を行った駁儀による神秘的殺人事案を、 『アーク』は、万華鏡を用いたフォーチュナらによる予知観測により把握。それを受けて作戦部は、 あるフィクサードの捕縛又は殺害作戦を実行し、その後リベリスタにより目標は捕縛されていた。 その捕えたフィクサードの名を、『駁儀』と云う。 ヴァリアントとは、有機化合物型の破界器であり、服用した人間の生死条件を結合させるものである。 定刻までに服用者の何れかが死ななければ、両者が死ぬ。 言うなれば絆と鋏。一蓮托生で、唯一生存という性質の悪い部類の破界器である。 この駁儀というフィクサードは自ら投降した為、『アーク』は更生プログラム実施していた。 保護監視官三名付きのちょっとした特例は、駁儀への不信感の残滓でもある。 だがその後しばらくすると、保護監視官三名らにより、駁儀の予後観察経過は”極めて良好”である、 との報告を受け、作戦部は駁儀の実戦投入を進言、司令部はこれを受諾、決定したのだった。 現在、”元フィクサード”駁儀は数十対処神秘事案に派遣され、良好なリベリスタ適性を発現している。 そして、『アーク』が駁儀を飲み込んだ本当の理由。 悪辣な破界器ヴァリアントを根絶するための作戦が、始まりを告げようとしていた。 “例に倣って”、多くの人の命と引き換えに。 極秘裏に動き始める作戦部に対し、司令部は一つだけ注文を付けた。 『駁儀の投入を許可する。但し―――』 ●ブリーフィング ヴァリアントという破界器は、多数の一般市民を殺害してきた唾棄すべき歪な存在である。 その存在に繋がる革醒者、駁儀を捕えた事実は事の進展を大きく加速させた。 “ヴァリアント壊滅作戦”。 調査の結果、裏に居たのは『四月朔日』と云う革醒者であることが判明し、裏が取れた。 彼女との会敵は事実上これが初めてである。 知性。其れが彼女の武器であることを作戦部は強く主張している。 『アーク』はこれ以上の被害を抑えるために、元同僚である駁儀を投入して、四月朔日を処理する事にした。 しかしながら、敵本拠地には捕えられた一般市民が居る。第一優先は彼らの救出になる。 従って今回の作戦は、敵本拠地の陽動と四月朔日捕縛・一般市民救出の二本立てで実施される。 此処に集められているのは、『後者』に専属するリベリスタである。 正面からの敵本拠地強行突破はリスクが高いと判断し、研究所の屋上にヘリボーンさせ、 内部を強襲する形になる。その時には既に、先行組が陽動を行っている筈だ。 君達には四月朔日の下へと急行し、ヴァリアントを投与された一般市民を救出してきて欲しい。 ……今回の作戦で憂慮すべき点は、二つある。 一つ目は、『ヴァリアントの効果』である。 残念ながら、今回も其の使用を事前に食い止めるには至らなかった。 現在、四月朔日研究所には二十名の一般市民が捕えられ、投与された様子である。 四月朔日が製作し、主に駁儀が使用していた液体型破界器。その”改良型”だ。 共鳴型効果を有しており、服用した人間を生死条件設定の下に有機連結的に殺害する。 今回、改良されたヴァリアントのリミットは深夜零時丁度ではなく、規定時間により時限的に、 殺害条件が満たされてしまう様だ。持って数時間と見積もられる。 最終的に“最大でも半数”しか最終的に生存出来ないのだとしても見過ごす訳には行かない。 半数超過の一般市民を、迅速に救出する必要がある、ということだ。 二つ目は、『駁儀明日香という革醒者の存在』である。 今回四月朔日の件が明るみに出たのは、駁儀の協力に依るところも大きい。 加えて、研究所施設の地下一階――その構造も明確になっているとは言い難いが――に存在する、 と云う四つの”神秘材料生体認証セキュリティ扉”を通過するには、その駁儀が必要と云う事だ。 この生体認証の前では健康な駁儀の存在が必要である。残念ながら、駁儀を拘束して連行しても、 セキュリティはパス出来ない。 ……残念ながら、というのは、駁儀と云う革醒者はリベリスタとしての活躍が認められるものの、 未だに”完全に信用できない事情がある”、と上層部は判断している。 今回の件では―――君達は”抑止力”という役目も背負っている。 詰まり。 ヴァリアントによる凄惨な事案を、この夜に叩き潰す、と同時に。 “もしもの場合”は……、”駁儀の処分”も必要となるであろう、という事だ。 四月朔日の生死は問わない。 負の連鎖を此処で断って欲しい。 ●駁儀。 「駁儀。君も元々はフィクサードと呼ばれた革醒者ではあったが、やはり私の見込み通りだったね。 最近の活躍は聞いているよ。 リベリスタとしての特性に於いても、やはり優れている」 三名居る駁儀の保護監視官の中で、最も若い一人の男が言った。 「だーかーらボクはフィクサードやないってずっと言ってるにゃ。 考え方はあんたらと変わらんにゃ。”人助け”大好きやし」 駁儀と呼ばれた革醒者は不満げに反論した。そして「お前ら見てるのも楽しいしにゃ」と加えた。 『自称男性』を頑なに主張する駁儀だが、その容姿は極めて妖艶だ。 腰にまで届く優しく流れた黒い髪、雪の様に白い肌、細い四肢、長い睫毛、濡れた唇、 ―――全てが女性の様に美しい。 本質的な問題ではない、という判断から未だ駁儀の客観的な性別判定は行われていない。 或いはリベリスタの性別が常に明示されている訳では無いのと、同様の事情である。 「まあ、その辺りは君の云う通り”定義の問題”だろう。 僕は犯罪心理専門だから、実を云うとそっちにはあまり興味は無いんだ。 ……しかし、駁儀。 実は今、作戦部の方からあまり表沙汰になっていない話が君に来ているんだ」 「ふーん。どんにゃ?」 「君が使っていた破界器―――ヴァリアントを覚えているね」 保護監視官の男の言葉は常に穏やかだった。しかしその眼光は、確かに鋭利さを備えていた。 「勿論にゃ。なつかしー」 「どうやら君を使って『アーク』はヴァリアントの壊滅させると決意したようだ。 その内作戦部から君に、公式な通達が出るだろう」 「にゃんと。さすが”清濁併せ呑む”、”日本最強”リベリスタ集団。 使えるもん全て使ってでも神秘的諸悪を追放する気やにゃ」 「―――引き受けてくれるね?」 眼鏡越しの瞳は、駁儀の挙動を捉えていた。 「無問題にゃ。ボクは”適任”に間違いないしにゃ」 ●四月朔日。 代行実験者、あるいは再現性立証者として『ヴァリアント』を提供していた駁儀が『アーク』に寝返ったという話は、遅からずその提供者である四月朔日の耳に届いていた。 ただ白に彩られた居室の中で、四月朔日は伸びをした。 その無機質な部屋の片隅に無造作に置かれた異質な”太刀”。 其れを見遣って、四月朔日はデスクに肘をついた。 「"もう要らない”か」 そう言った彼のことを、自分はどんな感情で見送ったのか、既に忘却している。 微睡む様な幸せな罰を噛みしめて、突然、彼女の部屋に電話が鳴り響いた。 胡乱な瞳はその元を辿る。 ……その電話は、埃まみれで特別回線に繋がっていた。 「わたし、この電話に出るの初めてね」 「四月朔日さん、悠長な事云ってる場合じゃ無いっすよ、あの」 「わかったわ」 「……え? わかったって―――」 かちゃ、と受話器が置かれた。 話を聞く必要は無い。 その傭兵からの電話が鳴り響いた瞬間に、四月朔日は全ての結論を導き出していたからだ。 電話に出たのは、”ちょっとした好奇心”に他ならない。 「最後の”試行”を始めましょう」 “大体の事”は既に理解していたのだ。 だが理性で割り切れない理屈もある。 「きっとあなたも、来るのでしょう?」 その玻璃の様に美しい唇を、蠱惑的に歪めて。 四月朔日は今宵、自らの手でヴァリアントを投与する。 彼らはどんな表情をするのだろう。 そしてどんな解が得られるのだろう。 そう思うと、普段は無感情な彼女も、笑わずにはいられなかった。 其処では、人の死も生も、等しくない重みを抱いていた。 ●明日香と明日香の昔話。 「やけど、ボクら、”求めるもん”は大体一緒だったやろ?」 駁儀の独特のイントネーションに、四月朔日は口の端を吊り上げた。 「ええ。『死』こそがヒトの本質。ヒトの生は、その一点に凝縮される。 わたしはね、この観点ではあなたをとても評価しているの。 あなた達と―――大学で出会った時からね」 ヴァリアントは見せてくれるのだ。 人の本質というものを。 何故、人は生きるのかを。 駁儀が共感欠落者なら―――、四月朔日は自己認識欠落者に他ならないのだから。 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:いかるが | ||||
| ■難易度:NORMAL | ■ ノーマルシナリオ EXタイプ | |||
| ■参加人数制限: 10人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2015年02月11日(水)22:03 |
||
|
||||
|
||||
| ■メイン参加者 7人■ | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
●I 轟音ひしめくヘリの中では、異様な雰囲気が展開されていた。 無理も無い。その革醒者とは面識のある者も、無い者も居る。 だが誰しもが、少なくとも報告書に目を通し、その悪事を知っている。 「ひゃー、高所恐怖症のボクにはこれちょっと厳しいにゃ!」 駁儀明日香。 年齢不詳。性別不詳。 艶やかな黒髪長髪に玻璃の様な瞳、細い四肢は女性の様。けれど、自称男性。 「にゃんこ先生おいっす。おじさんですよと」 駁儀を除くリベリスタ達には、”その命令”が下されている。 その辺りの配慮もあってか、ヘリに搭乗するまで彼らの接触は禁じられていた。 不安そうに肩を抱いていた駁儀が声の元に視線を移すと、『足らずの』晦 烏(BNE002858)の姿が目に映る。 「お、博識で怪しげなおじさんじゃにゃいか」 「久しぶりだな。 しかし、にゃんこ先生の友達の雨水君、覚えてるかい」 「もちろん。クサレエンって奴よにゃ」 「あれが今度、『京極』の当主やるんだってさ。驚いたねぇ。人ってのは”変わる”もんだなと」 「んん? それ、ほんまかにゃ?」 駁儀が怪訝そうな表情で烏に問い返す。そしてその様子を、『レーテイア』彩歌・D・ヴェイル(BNE000877)は気づかれぬように観察していた。 雨水という名はフィクサードとして『アーク』の報告書に上がっていた人物であり、駁儀が捕縛された作戦では、敵勢力として会敵していたこともある。 彩歌は今回の制圧対象である四月朔日、そして味方である駁儀、動きに不確定性を含む雨水の三者に通ずる糸を見て取っていた。 (ここがラインの終端だと助かるんだけど) 駁儀と云う人物は何処か掴み処が無い。故に彩歌は其処に不審な点が無いかを十分に警戒していた。 「所で、一つ質問があるんだけど」 けれど警戒と云う点では更に一段階高いレベルで、駁儀を監視しているリベリスタもいる。『覇界闘士<アンブレイカブル>』御厨・夏栖斗(BNE000004)である。 夏栖斗は今回の作戦概要を確認した時から、その破界器に着目していた。 「『観測者はかく語りき』って、四月朔日が雨水にあげたものなの?」 ……いや、しかしその存在そのものに対する興味と云う点では『黒と白』真読・流雨(BNE005126)を上回る者は居なかっただろう。彼女の紅瞳も駁儀を映した。 「四月朔日があげたってことはないやろにゃ。あの人、そーゆー武器とかって興味なさげにゃ」 「じゃあ、なんで四月朔日が持っているんだろ」 「そりゃ、逆なんやろ。雨水が四月朔日にあげたんじゃにゃいの?」 「目的は?」 流雨が口を挟んだ。駁儀は夏栖斗から視線を外すと、やれやれと手を振った。 「そんにゃん、ボクが知ったこっちゃないにゃ」 「そろそろ時間だ」 扉を開ければ凄まじい勢いで風が吹き荒ぶ。『デイアフタートゥモロー』新田・快(BNE000439)も目を細めながら髪を揺らし、降下地点を覗きこんだ。 漏れ出ていた閃光がより鮮明になるが、音はヘリの轟音に掻き消された。 平坦な屋上では、ヘリボーンのスペースを確保する味方リベリスタの姿が一人見える。 「そなたの言った経路が最短で、間違いないのだな?」 飛び降りる準備を始めた『殺人鬼』熾喜多 葬識(BNE003492)の隣で、『無銘』熾竜 ”Seraph” 伊吹(BNE004197)が駁儀に向かって念を押した。サングラス越しの瞳は、思いのほか鋭く、駁儀を射抜いた。 葬識の異能の目が完全に無効化されることはないが状況が状況であり、無生物以外のモノが多すぎた。これから始まる合法的な戦いを前に喜楽を宿した葬識の瞳にも、ノイズが走る。 (味方とは言え、何処まで信用するに足る存在か) 伊吹は”最悪の可能性”を頭の隅に留めている。それは飽くまで予想に過ぎないが、完全に否定する材料も揃っていない。 駁儀は一瞬だけ快が開けた外を覗きこむと、途端にびくっと体を引っ込め、眉を顰めながら伊吹を見た。 「もうちょっとボクのことも信じて欲しいにゃ。こう見えても”リベリスタ”として一杯頑張って来たにゃ」 「まあまあ、俺様ちゃん達も別に猫ちゃんを信じて無い訳じゃないよ」 いよいよ降下体勢に入った葬識が面白そうに駁儀を宥めた。「猫ちゃんっていうにゃ!」と頬を膨らます駁儀を横目に、葬識は眼下の混凝土を眺めた。 ●w 悪性破界器を生み出した四月朔日の箱庭。 防戦である彼女に、けれど攻性であるが故にリベリスタ達が抱えるリスクも決して低くは無かった。 彩歌は熱を求めて視界を移ろわせる。 快は記憶上の配置と駁儀の語った経路を照合させていく。 と、同時に与えられた殲滅の加護を身に纏わらせて、その純白ときどき深紅の廊下を抜けていけば、 「……来るわ」 「来るね」 立ち止まって彩歌と葬識が呟く。伊吹が構えた。 金属の冷たさと人の血の暖かさを含んだ扉が突然開くと、一人の男が魔術書を抱えながら詠唱を始めた。 「討ち漏らしですか。雑な仕事ぶりですね」 流雨の囁きの直後、険しい顔つきの傭兵―――フィクサードの身体から、黒鎖となった血液が濁流と成りリベリスタ達へと放たれた。 「どうせこのアークの、というか”猫ちゃん”の介入くらい予測してるでしょ」 そう言って瞳を妖しく輝かせた葬識が自らの禍々しき鋏を構えるよりも早く、後衛陣への射線を防ぐように伊吹の乾坤圏が空間を裂く。 「貴様らに恨みは無いが、此処は通さんぞ!」 既に事前投入戦力が制圧を始めている事を考えれば、此処に潜んでいたその男の手腕は評価出来る。魔術展開も悪くない。決して雑魚ではない。 だが惜しむらくは、リベリスタ達が、其れを遥かに凌駕してしまっていた事だろう。 伊吹が撃ち放った白輪が男を貫き、その顔を醜悪に歪めさせた。 「―――鋏?」 が、と突如息が止まる。足が地について居なかった。 「ホントは君を相手してる時間も勿体ないんだけどさ。 説得力っていうの? やっぱり、ひつよーだと思って!」 「やめろ……!」 「その美味しそうな悲鳴と一緒に、俺様ちゃんのメッセージも、伝えてくれない? ―――『命はお金で買えないんだよ☆』」 「やめ……」 男の言葉尻は糸が切れるように唐突に途絶えた。力の抜けた人形の様なシルエットが、葬識の赤く染まった左頬に重なった。 しかし、先行戦力も万全とは行っていないようだ。駁儀の情報と快の情報を合せて、更に現状についての流動的な戦況は、伊吹がアクセス・ファンタズムを介して先行隊との照合を始めていた。 「良い殺しっぷりやにゃあ。三つ編みくんに比べたらボクなんか可愛いもんやよ」 「冗談にしては、少しきついわね」 「むむ。そんにゃこと……」 彩歌の指摘に駁儀が口籠る。その横では、夏栖斗が伊吹を通じて先遣リベリスタ達に指示を飛ばしている。 「それじゃあ、急ぐかね」 烏の言葉に、流雨も静かに頷く。 其処が研究施設であるということのメリットが、今回ばかりは効いた。余剰な天井スペースは通常の建築物の倍ほどは高い空間を有しているから、屋内でありながら翼の加護の異能を十分に発揮できるだろう。 そのまま階下へと繋がる階段を降りたリベリスタ達は、一階へと進んだ。 ●i 「しかし、例の破界器の感染源は不明ですが、にゃんこまん様はどのように使用されていたのでしょうね」 一応露出を控えた服装で今回の作戦に臨んでいる流雨が通路を進みながら訊ねた。 「あれは液体やからにゃ。ボクは専ら注射やったにゃ」 「四月朔日様がその他の投与手法を習得している可能性は、ありますね?」 「開発者やからにゃ。普通の皮下注射でも勿論できるやろし。色々あるとは思うにゃ」 会話しながら進む所内は、兎に角、扉が多かった。多くは所謂両開きの押戸であり、そして、構造も複雑で、迷路の様であった。純白の一様性が、何処か感覚を狂わせている様にも感じる。 「……っと!」 快は逐次現時点の座標と記憶とを参照し、マッピングを繰り返す。先導する彼はその扉を抜けた瞬間に、交戦している四名の人間を視界に入れた。 「前方交戦中だ!」 後続に指示した快は、そのまま突っ込む。幸い、リベリスタ達は飛行可能だから多少の強引さを発揮すれば頭上を抜くのも無理ではない。 だが交戦中の現場をそのまま通り抜けるのが、簡単な訳は無い。其処に敵も味方も居るとなればなおさらだ。 「伏せろ!」 烏が言うと、一対三の不利な状況でジリ貧になっていたリベリスタは咄嗟に体勢を低くした。それを見届けて、烏は引き金をひいて掃射を始める。 「気前よくいくかにゃ!」 同時に駁儀も駆けながら拳銃を握り、薬莢が散る。それを踏まない様に注意しながら走りつつ、彩歌はその銃撃を浴びる傭兵の脚を精確に的確に気糸で撃ち抜いた。 突然の鉛雨に怯んだ傭兵フィクサード達は、其の内の一人が彩歌の攻撃を受けて膝を曲げた。一人だけ一歩後ろに位置する女が回復手であることを見抜いた伊吹は、突っ込むようにしてその女に乾坤圏を狙い撃った。 「やあ、雇われ君たち。しかし熾喜多君の言う通り、命は金じゃ買えないもんでね。 金にくらみ“薬”を恐れて今死ぬか、挽肉にされずに済むか。どちらがマシかな」 彩歌に撃たれ蹲る男と回復手の女に若干の敵意の減少が見られたのに対して、大剣を握ったもう一人の傭兵はあろうことかリベリスタ達に背を見せて逃走を試みた。 「―――そうかい」 烏は真改の照準をそのデュランダルの四肢に合せた。 銃声が鳴り響いた後、純白の通路がその男を中心にして放射状に紅く彩られた。苦痛に歪む声が響いて、傭兵達は完全に戦意を失った。 「まあ、おじさんも似たようなもんだから、完全に否定はしないがね」 その後も順調……ではないが、概ね問題無く一階を制圧していくリベリスタ達。 敵のブレイクなどを牽制しながら前衛として射線を塞ぐ伊吹や、出し惜しみ無く究極幻想で切り結んでいく快らの性能は、統率立ててリベリスタへと襲い掛かる傭兵たちを大きく上回っていた。 異形の二刀流を実現させている流雨も例外ではない。烏同様、金で動くこと自体をとやかく言う心算は彼女には無い。 だがその仕事振りは何処か無感情だ。そして恐らくそれは、四月朔日が所持していると伝えられている例の太刀に起因していた。 (私の目的は『観測者はかく語りき』の回収。それのみ―――) 流雨の中の誰かが疼いていた。 流雨の誰かが呻いていた。 其れを、“あの男”以外が持っているのは何処か気に入らない……。 先遣リベリスタ勢力も次第に減っていく。どうやら一階の中盤で手こずっている様だった。 「此処までに処理した人数を考えると、やはり四月朔日が地下一階に配置した傭兵数も一人や二人ではなさそうだな」 <恐らく……> 「了解だ……っと!」 通路が曲がり角に入った瞬間、一人の男が大きく権を横一線に振り、 「危ない―――!」 「にゃ?」 丁度その刀身の軌道上に居た駁儀は一瞬出遅れた。待ち伏せに警戒していた様に、咄嗟に伊吹が駁儀の腕を引き、変わるように体を入れ込んでその攻撃をカバーする。 直後、通路を恐ろしい冷気が襲った。次の瞬間には、冷撃に体の自由を奪われた男と、夏栖斗の姿が在った。 「だいじょうぶ?」 夏栖斗は伊吹と、そして駁儀を確認した。駁儀の方は無傷だが、伊吹は多少肉を抉られていた。 「グラサンのお兄さん、ごめんなさいにゃ。でも、もしソッチ側が斬られても、ボクは義手やから大丈夫にゃ。替えは効くにゃ」 「グラサンと呼ぶな。彩歌だってサングラスだぞ。 ……そうか、それは義手だったな。しかし、命に替えは効かないだろう」 彩歌が至極簡単な手当てを伊吹に施す。伊吹の言葉に、駁儀は淋しそうに笑った。 「それはグラサンのお兄さんも一緒にゃ。 まあ、ボクは利用価値もあることやろうしにゃ」 「利害も無論あるが、同時に今、そなたは俺達の仲間だろう?」 「まあ、そうやけど……」 駁儀が無意識にお腹を擦った。 「猫ちゃんは、お腹でも減ったのかな?」 葬識が面白そうにそう突っ込むと、駁儀は手を腹部から離した。 「にゃ、いや、そういうわけじゃないにゃ。癖みたいなもんにゃ」 「ふーん。俺様ちゃんのお腹は、まだまだ満たされてない感じなんだよね。 ってことだから、熾竜ちゃんに問題が無かったら、先を急ごうかな?」 ●l リベリスタ達の役割分担は功を奏していたと云える。一階を幾らかの傭兵たちを残したまま遣り過ごした烏達は、その処理を残るリベリスタらに任せ、地下一階へと降りる階段へと辿りついた。 エレベーターもある事にはあったが、此処で電子制御された箱の中に入るのはリスクが高い、と彩歌は分析していた。何より、先程から彼女が電子の妖精に依るシステム掌握を試みているのに、それが丸で上手くっていないことが、実際的なその根拠だった。 幸いと云うべきか、それが意図された結果なのかは分からないが、少なくとも一つ目の生体認証扉の所には敵戦力は見受けられない。 夏栖斗達は警戒を緩めず、早速駁儀を直ぐ傍の認証地点に向かわせた。 (生体認証時に不審点が無いか見ておきたいけど) セキュリティパスを始める駁儀を彩歌はじいと眺める。この状況で出来るのはそのやりとりを監視するぐらいだろう。電子の妖精だけでなく、熱感知すら精度が下がってきている。 「構造上の問題かしら」 「その可能性は、高いだろうね」 快が周囲を見渡しながら頷いた。彩歌の視線の先では、駁儀が指から血を滴らせていた。 (血液認証か……DNA判別までするなんて手が込んでるわね) 「おっけーにゃ~」 傍目から見れば、その巨大な扉の横に搭載されているデバイスコンソールの前で立っていただけだった駁儀は、そう言うとリベリスタ達へと振り返った。 すぐさま、モーターの稼働音と共にこれまで突破してきた扉などとは比較にもならない分厚く特殊な素材で出来た扉が上下左右に幾重にも開かれていく。革醒者達が本気でやろうと思えば破壊できなくはないだろうが、相当の時間はかかるだろう。 その時、駁儀がいち早く次の防壁に進もうと一目散に駆け始めたのが、夏栖斗には気になった。 あと三つの扉を抜けるまでは逃げようも無い。背信行為ではないだろう。しかし、開いた扉を再度『閉じる事』は可能だ。その場合は……、かなりややこしい事態になる。 「ちょっとまって!」 夏栖斗は駁儀の細い背を追うようにして、声を掛けた。一瞬立ち止まった駁儀が不思議そうに振り返ると、夏栖斗はその左手を握った。少し冷たく、小さな手だが、それは義手じゃない方の手だった。 「にゃ……」 何事かと硬直した駁儀を気にも留めず、夏栖斗は何時になく真剣な眼で口を開く。 「独断専行は止めよう。今回、それが止められてるのは、知ってるよね?」 ……だが、司令部から流雨らリベリスタ達に下された“もう一つの命令”を、駁儀は知らないのだろう。 「もし君が怪しい動きを取ったら、僕たちは“然るべき対応”を取らなきゃいけないかもしれない。 でも僕は、そんなことしたくないって、思ってる。疑ってるわけじゃないんだ。 だけど、一緒に行こう」 「わ、わかったにゃ。やから、手、離してくれにゃ」 駁儀が顔を何処か朱に染めながら眉を顰めて言った。 「……嫌だった?」 「嫌というかなんとゆーか……、その、そういうの、あんまり慣れてないにゃ」 「男同士で恥ずかしがることもないだろ」 烏がそう駁儀に突っ込む。夏栖斗が手を離すと、すぐさま引っ込めるようにして駁儀はその左手でお腹を擦った。 「そ、それもそうにゃんやけど、ちょっと、変な感じにゃ」 そう言った駁儀は夏栖斗の言う通り立ち位置を下げた。丁度駁儀の前を進む形になった快には、その人間臭さと、これまでの悪行が何処かちぐはぐに見えた。 だが、だからと言って駁儀が完全に信用できたわけでは、ない。少なくとも快にはそうは思えない。だがそのリスクを承知して此処に立っている事も知っているから、彼は、自身にできる事はリスクの最小化であること理解していた。 ●l 静謐な空間だった。最後の生体認証扉を抜けてからは清潔で清廉な純白が病的にただ真直ぐに続いていた。 最奥部に居室や実験室があるのは分かっているとは云え、此処からは、本来は見取り図にすらその構造が示されていない区域になる。 ……先程は引き下がった駁儀だったが、烏は、駁儀が改心したなどとは微塵も考えていなかった。あれが更生などするタイプの人間ではない、と烏は半ば確信の様に感じている。 (見す見す殺しちまうのは、ちと勿体ない気もするがな……) ならば出来る事は、快と同じ。リスクを受容した上で、その最小化を如何に行うか、である。 無論、駁儀自身が再度敵に寝返るかなどは確定事項ではない。少なくともアークは賭けに出た。賭けに出た以上は勝ち目がゼロではないということだ。 ●k 「救助に来ました。出来るだけ扉から離れて、動かないで!」 その声に、集められていた被験者達は不思議そうに振り返った。 「え? なに?」 分厚いガラスを隔てた向こう側では、四月朔日と伊吹らリベリスタが対峙している。突然の事態に彼らは、状況が良く飲み込めないと云った感じだった。 それも仕様が無いだろう。彼らは真実を知らない。割のいいバイトぐらいの感覚で参加しているに違いなかった。 「その実験は碌でもないものの可能性が高い、ということです。 取り敢えず、此処にいると危ないですから―――」 丁寧に諭そうとする快だったが、咄嗟にその気配に気づく。 被験者に紛れるようにしていたようだが、忍ばせていたナイフを握り間合いを詰めてきたその男の一振りを快も難なく受け止める。 誰かが悲鳴を上げた。ただならぬ状況にあることを、漸く理解し始めたのだろう。 「早く外へ!」 自分一人をどうにかするのは容易な事だ。しかし二十名全てを護りきるのは簡単ではない。 襲い掛かってきた男を弾き返す快だったが、傍らからのもう一つの影を視界の端に収めた。身体を回転させるようにしてそのもう一人の傭兵からの攻撃を受ける。 「邪魔を……」 ナイフを握る快の手に力が籠る。 「……するなっ!」 ●i 快が被験者達の保護に回ったのと同時に、烏らは四月朔日と対峙していた。 葬識の視線の先に居たその女は、人形の様だった。 背は高い。肩より少し下まで伸びた黒髪に、絶望的に白い肌。 造形としての完成度が高いが故に、その存在は違和感の塊だった。 「もう少し時間がかかると思っていたわ。何処かの“野良猫”の悪知恵が働いたかしら?」 首を傾げるが、そこに表情の動きは無い。 言葉と同じだけの感情の質量が無い。 人形劇に、恐ろしく美しい声だが棒読みの声優を付けたみたいだった。 「ねぇ、四月朔日のほうの明日香ちゃん。僕達がここに来た意味くらいはわかるでしょ? 合理的に物事をすすめるなら、君を倒して、半分の被験者を殺したらいい。でも僕はそうしたくはない。 実験結果が必要であれば、僕が被験対象になっても構わない。 だから、関係ない彼らは開放してよ」 ただ知りたいだけなら、自分の身を使えばいい。夏栖斗が言ったのは、そういう事だった。 今回のオーダーは十一名以上の被験者の救出だ。このままでは全員死亡するか憎しみと恐怖に任せて互いに殺し合うかの未来しか残っていない。そして其処から更に十名を間引けば、残った人間は生き延びる事が出来る。 だからリベリスタ達は、最大十人、最終一人の命を救うことが、出来る。ヴァリアントの代償となる十名は、もう如何こう出来る範囲を既に超えていた。 ちらりと伊吹は視線を四月朔日から外す。リベリスタ達から二メートル程先で回転椅子に腰かける彼女の傍には数名の傭兵たちが立っていたからだ。 「大丈夫。わたしが命令しなければ、動かないわ」 四月朔日は夏栖斗を見たまま不意に言った。伊吹はそれが、自身に言った言葉であることを理解したのと同時に、内心で感嘆した。 (瞳孔の動きだけで読んだのではないな。 むしろ、もっと深層的な推論か……) ならば彼女が伊吹を視界にすら入れずそう言い放ったのも理解できる。詰まり其れは、極めて高度な理論展開という訳である。最早、未来予知の域に達しそうである程の。 ガラス壁の向こうでは快が被験者の対処に入っている。それは四月朔日にも、彩歌達にも良く見えていた。 「貴方では意味が無いのよ。貴方の手は、汚れすぎている。貴方の手は、美しくない」 「人を殺し過ぎている、ということ?」 「偽善の下に殺し過ぎている、ということ」 夏栖斗は思わず拳を握った。 「貴方達が此処に来た意味も、提案の意図する所もわたしは理解している。 その上で、貴方の命では釣り合わない、とわたしは言っているの」 そのタイミングで、流雨が口を開いた。 「極限状態でこそ、人間の本質は現れる。なるほど。道理ですし、効率的です。 尤も。どれだけ他人の死に触れた処で、己の本質など見えてくるはずもありませんが」 「それは、経験則?」 「ええ。“本質”などという物は、結局のところ、どうしようもなく。己の中にしか無いのです」 未だ椅子に深く腰掛けている四月朔日は、足を組み替えた。 「その論には再現性がない。仮にそれは置いておくとして、それは自己を保持している人間が出来る事。 けれど、その拠り所であるべき自己が無い者はどうするべきかしら?」 「嘲りも問答も時間があれば構わないが、今は時間が無い」 切り替えるように伊吹が言った。 「俺達はそなたの投降を受け入れる準備がある。これまでの悪行を、水に流す準備がある」 「ああ。ヴァリアントの製造の中止、解除の手立ての申請、アークへの協力を条件に出来るのなら、 アーク側で観測を行えるよう話は通すさな」 補足する様に烏が続けると、伊吹も頷く。四月朔日は駁儀を見た。 「貴方、其処に居て、楽しくないわね?」 「それは……」 駁儀も四月朔日を見た。何時になく真剣そうなその表情で、 「“立場上”、同意しかねるにゃ」 ―――次の瞬間、駁儀はその拳銃を構えていた。 そしてその銃口は、真横に居た彩歌の頭を向いていた。 「ちょ―――」 夏栖斗が手を伸ばすよりも早く、乾いた発砲音が部屋に響いた。 「―――」 状況をスローモーションの様に捉えていた彩歌自身は、その至近距離では何をどうする事も出来ない、と早々に結論付けていた。彼女に出来るのは、迫りくる弾丸を見つめる事だけだった。 そして、その弾道は、彩歌の『眼の前』を通過していった。 計算と違う。減速感が失せて加速度的に現実が回帰し始めると、彩歌は駁儀を見遣る。 其処には間合いを詰めた烏にデコピンされて仰け反る駁儀の姿と、 「そっちが狙い―――か」 四月朔日に視線を移し、彩歌が独りごちた。“同様の結論”に至った葬識は、四月朔日の傍らに居た傭兵に既に斬り込んでいた。 「これ、『京極』の子のモノだよね? 第一神刀が生まれるから、もう要らないってことなのかな?」 「いえ、その太刀は“私の物”ですので、あしからず。『どちら』かは知りませんが」 葬識と挟撃する様に流雨が得物を振り、無造作に隅に置かれている『観測者はかく語りき』の回収に乗りだしていた。 何時の間にか立ち上がっていた四月朔日の頬は、直線上に朱色に彩られていた。 「おじさん! 早とちりにゃ!」 「いや、すまんすまん」 駁儀と烏がぽこすか殴りあってるのを眺めて四月朔日が頬を指で拭う。彼女が立っていたのは、“立たされた”からだ。 「―――跳弾か」 彩歌が言うと、夏栖斗が「でもそれじゃ、交渉は……」と続けるが、 「正義くんはまだそんなこといってんのかにゃ!」 四月朔日配下の傭兵も動き始める。リベリスタに斬り込み始め、その場は乱戦と成った。 「あっちはボクらと取引する気なんか最初っからないのにゃ。 フェアな天秤をこっちに傾けさせられる程、簡単な相手やにゃいってこと!」 「でも……」 「でもじゃないのにゃ。“全員”、助けるんやろ?」 駁儀は夏栖斗を見て、次に伊吹を見た。 「……ああ!」 「しかし、にゃんこ先生らしくないさな」 「あんたら見てて、気が変わったのにゃ」 引き金をひきながら駁儀の横へとつけた烏がからかう様に言うと、駁儀はお腹を擦った。 「殺す人間を選ぶのも、生かす人間を選ぶのも、大差ないってにゃ!」 ●l 彩歌はすぐに向こうにある実験室への連絡方法を思い浮かべる。最初に考え付くのは、マイクのようなものだ。 「……」 四月朔日の身にそのような物が、見当たるかどうか。 (……無いか。じゃあ連絡はコンソール周りで、あちらへと通じるスピーカーがあるとか) 同じプロアデプト。同じ頭脳戦闘者。快に依る被験者退避は進んでいる様だが、まだ少し時間を稼ぐ必要がある。 ここで被験者達にヴァリアントについて告げられては厄介だ。 四月朔日にそうさせないために彩歌は彼女へ気糸を手繰らせる。意識を、こちらへと向かわせる。 彩歌の攻撃が寸での所で躱される。或いはそれは、最小限の動作だけで避けられたのかもしれない。 「“自己認識欠落者”が造った絆のアーティファクト。 最終的に貴方自身に投与する心算、或いは既にしているんじゃないの? ……丁度いい事に同じものを求めている人がそこにいる事だし」 「あら、それは悪くないアイデアね」 逆に四月朔日が軽く腕を振るった。直後、彩歌を精緻な気糸が襲う。 「残念ながら、『私』が何者かなんて、私は自分で定義した覚えは無いのよね」 穿ち迫るその攻撃を受けながら表情を若干歪め、それでも彩歌は言葉を紡ぎ続けた。四月朔日も相当の異能者であることが、彼女には良く分かった。 「その通り。やっぱり、あなたは少し違うわね。なら、わたしと一緒。 わたしにも、土台が無い。わたしはわたしを定義し得ない。 ならやっぱり、その定義を外界に求めるしかないのね」 「他者に求める事は否定しないけれど。その為に命を奪う権利は、『私達』にはないのよ」 彩歌が弾かれる。代わるように夏栖斗が四月朔日の前に立った。 「君の言う解釈でなら、僕も罪人だ。この手は確かに汚れてる。 けれどそれが偽善だったとしても、僕はきっと立ち止まっちゃいけないんだ」 それがこの手にこびり付いた血の代償だ。 「一人を救う為に他者を殺す覚悟は、見ていて残酷ね。貴方は只の功利主義者よ。 其処に道徳なんてないわ」 「それでも」 夏栖斗がトンファーを振るう。至近距離で打っている筈なのに当たらない。 目の前の彼女の顔は、自分を嘲笑っているかのようだった。 「―――それでも僕は、そのたった一人を救うんだ」 ●l 「それじゃあ、引き継ぎはお願いします」 そう言って被験者達を残っていた先遣リベリスタに引き継ぐと、快は四月朔日の居室へと合流すべく向った。 ……幸か不幸か。ヴァリアントの効能により神秘異能を使役する者は、終ぞ現れなかった。 (しかし) だが快には一抹の不可解さが残っていた。 (上手く行き過ぎている) 被験者達を確保してしまえば、こちらの目標は殆ど達成されたと言って良い。快の手際の良さもあっただろう。快の強さもあっただろう。 だがそれでは、知っていながら此処で自分達を待ち受けた理由は何だ? 「ああ―――やっぱり『お前ら』は似ているよ。 何処まで行っても其処が見えないところが、特に―――」 そのまま直ぐに伊吹ら味方勢力が四月朔日らと交戦しているところまで引き返すと、『観測者はかく語りき』の回収に成功した流雨と葬識が四月朔日に肉薄していた。 四月朔日の動きは妙だった。彼女がそこそこの神秘異能者であることは間違いない。だが戦闘に特化している訳でもない。けれど、致命打を与えられない。まるで柳を斬っている様だった。 「さてさて、≪ヴァリアント≫(勇気)とはよくいったものだ。 効果も知らずに勇気を試す。こっちの猫ちゃんは、『葛藤ある殺し』を命題にすることで、人間観測をしてたみたい。 だけど。それは四月朔日ちゃんが求めている観測結果ではないよね」 葬識の振るった鋏は四月朔日の髪を梳いたが、やはり紙一重に躱された。 「そう。わたしは其処に介在する懊悩には、興味がなかった」 「俺様ちゃんも君とおなじ求道者だよ。 『他人の命を奪う事』が存在の意味で、価値で、生き様だ。 君の『生き様』はなに?」 「生き様―――」 「君には大切なものがある? あるとしたらそれが君の“存在の意味”だ」 「生きる目的なんてないわ。わたしは、空っぽだもの。 だから、貴方とわたしは全く違う。貴方は自分の生存の為に他者を殺すけれど―――。 わたしはきっと、死に場所を見つけるために観測を続けるのね」 「四月馬鹿にはまだ早いぞ、四月朔日」 迫る巨体の傭兵の攻撃を避けた伊吹が狙い澄まして四月朔日を穿たんと白輪を撃つ。 「駁儀とそなたは二重人格の同一自己かとも危惧していたが、どうやらそうではなかったようだ。 しかし、死に場所を見つけるために他者を殺めるなど、本末転倒ではないか」 「本質的に違いは無いわ」 その白輪の軌道が気糸に捻じ曲げられる。 「ヒトは死ぬために生きる存在だから」 「それ自体は否定しませんが」 その伊吹の攻撃は謂わば、フェイクだった。彼の攻撃を捌くために失った四月朔日の視界から、流雨が迫っていた。 「どれだけ『死』に触れようと。己が生まれてきた意味も。これから死んで逝く理由も、其処にはありませんよ。 『私達』が言うのです。間違いありません」 「『私達』?」 四月朔日の顔に、初めて感情が宿った。 下段からの流雨の斬撃に、四月朔日は振り返りながら右腕を抉られた。 「まさか」 その完成された眉間が、醜く歪んだ。 それは痛み故か。 流雨に巣食う意識の異常さ故か。 「―――『何人』居るというの」 さあ。とはぐらかせた流雨は続けざまに快の斬撃を避けた四月朔日を見据えて、話を続ける。 「そも貴方達は、答えなんて最初から分かっているのに、解らないフリをしているだけでしょう? 違うのですか? 私には貴方達が、わざわざ遠回りをして無い物ねだりをしている子供の様にしか見えませんが。 ―――生きる事が恐ろしいなら。それを認めてしまえばいいだけでしょうに」 気づけば四月朔日配下の傭兵は数名しか残っていなかった。そしてその一人も、 「四月朔日の方の明日香ちゃん」 崩れ落ちた女から、夏栖斗が快らに囲まれた四月朔日へと視線を移すと、静かに言った。 「皆の言う通り、君の道は間違ってる。これじゃ君は、ますます孤独になるだけだ。 だから……、僕はやっぱり君を傷つけたくないし、被験者達を救いたいんだ」 明らかに劣勢だった。此処を戦場に選んだ四月朔日に、誤算があったというのか……。 「俺もそなた達に生きて欲しい。その理由では駄目か?」 伊吹が零したのは、最終通告でもあった。今回の作戦で、最初から一般人を『全員』救うことを目標に掲げていたのは伊吹だっただろう。 従うなら殺さず済む。 烏の、彩歌の視線の先で、四月朔日は疲れた様に息を吐いた。 「……そういうことね。貴方がアークに行った理由、わたしには分かる気がする。 求める最終地点は一緒でも、現在地点でわたし達は異(ちが)っていた」 分かったわ、と四月朔日は続ける。 「此処で終わりにしましょうか」 「……投降する、ということかい?」 烏が確認する様に言うと、四月朔日は首を傾げた。 「その可能性は否定しないけれど」 「まさか、猫ちゃんの目の前で君自身にヴァリアントを投与して、その反応が見たい、だとか。 そんな詰まらない構ってちゃんなんて、しないよね?」 まだヴァリアントが残っていた。葬識の指摘に彩歌と快の視線が厳しく四月朔日を捉えた。 当の四月朔日は汚れた白衣を気にも留めず、再度椅子に深く腰掛けた。 「それはそこの彼女も言ってたわね。私はね、駁儀の着眼点を評価しているの」 烏が駁儀を見た。当の本人は「にゃ?」と首を傾げた。 「貴方と雨水がアークとやったとき、貴方は最初からヴァリアントの効果には興味が無かったのよね。 その右腕が吹き飛ばされた時から、興味の対象をリベリスタに移していた。違う?」 「……否定はせんけどにゃ」 「そう。リベリスタという存在は特異だから。 最後に貴方達の意見が訊きたい」 「意見?」 快が訊き返す。被験者達を確保した時から渦巻く不信感が、姿を表そうとしていることに、彼は薄々気が付いていた。 ……その時、実は駁儀は、心底驚いていた。 何故なら、四月朔日が、 「被験者達を全員生かしたまま生命有機連結を解除する条件が、あるの。 そう……そこの駁儀を殺す事でね」 笑っていたからだ。 ●y 「……何だって?」 夏栖斗が思わず口を開いた。 「今、駁儀の生死条件は、あの被験者達とヴァリアントで結ばれている。しかも、特殊条件でね。 革醒者の生は、体が頑丈な分、天秤を大きく傾けさせるの。 だから、駁儀を一人殺せば、二十人の被験者は助かる」 「しかし、その証拠はあるのかい」 不穏な空気が漂い始めた中、烏が問いただす。 「再現性は取れているけれど、貴方達にそれを示す時間は無いわね。 早くしないと、タイムリミットで皆死んじゃうでしょう?」 その場合、駁儀だけは助かる可能性はあるけれどね。そう続けた四月朔日の口元に湛えられた微笑みが、伊吹には悍ましいものに思えた。 「本当はね、貴方達に告げる心算は無かった。でも、そう、駁儀と一緒で、気が変わったの。 貴方達に、興味が湧いた。だから、貴方達の選択が見たいの」 「……ふざけるな」 「新田……!」 伊吹の制止も構わず、快が四月朔日の襟を掴んだ。これまでの抵抗とは全く異なり、四月朔日はそれを避けようともしなかった。 「お前は、人の命を何だと思っているんだ―――」 「だから、言ったでしょう?」 快が持ち上げた四月朔日の身体は驚くほど軽かった。間近で見る彼女の顔は美麗だが、快はそれを好ましいとは思えなかった。そこに人間性は残っていなかった。 「新田」 伊吹が快の肩に触れた。彼が手の力を緩めると、四月朔日はすとんと椅子に戻った。 「わたしは空っぽだから。そこに何を詰めても……やっぱりわたしは居ないの」 流雨は駁儀を見た。太刀も回収できている。彼女には駁儀の殺害にそこまで抵抗感は無いだろう。だが、この状況で駁儀がどう出るかについては若干の興味が在った。 「これは一杯くわされたにゃ」 困った様にお腹を擦った駁儀は、気の抜けた声でそう言った。 「しかし、猫ちゃんにヴァリアントを投与する暇は四月朔日ちゃんには無かったと思うけどね?」 「―――血液認証」 葬識の疑問にぽつりと彩歌が呟くと、駁儀と四月朔日が頷いた。 「あそこで仕込むとは中々やにゃあ。確実にボクだけ決め打ちできるしにゃ」 「改良型、だから。友人の馴染で教えてあげるけど、あまり時間は無いわ。 それで。貴方達は、どうするの?」 「決まってるにゃ」 駁儀は即答した。 「こうするにゃ」 「待って―――」 「待たないにゃ。こっちくるにゃ」 夏栖斗の伸びかけた手の先では、銃口を自らの蟀谷に捧げた駁儀の、何故か嬉しそうな笑顔が在った。 「先延ばしにしたところで意味はにゃい。四月朔日の策に嵌るにゃよ、正義くん。 これは、最初から一つしか選択肢のにゃい命題やでにゃ」 「まあ、そう早まるなや」 「おじさん、これは早まってる訳じゃにゃいにゃ。 ボクは、納得してるにゃ。だってあんたら、優しすぎるから」 「……貴方」 四月朔日が怪訝そうな表情で駁儀を見た。 「何を笑ってるの?」 「選択する立場になって、初めて分かることもある、ってことにゃ」 「何が分かったの?」 「こいつらはボクを殺さなかったにゃ」 最後の生体認証扉を抜ければ駁儀は用済みだった。危険因子と目される駁儀を、そこで殺害ないしは捕縛してしまっても良かった。そういう命令が出ていた。駁儀は、そんなことは見抜いていた。だが彼らはしなかった。その選択肢を胸に秘めていても、実行はしなかった。 「四月朔日。ボクもキミも死を過大評価していたにゃ。死なんて大したことにゃい。 キミは最初からそう言っていたじゃにゃいか。ああ、でも」 駁儀は伊吹を見た。 「……でも、痛いのは、ちょっと怖いにゃ」 「駁儀―――」 「たぶんボクは死にきれないにゃ。やから、三つ編みくん達には、介錯をお願いしたいにゃ。 引き受けてくれるかにゃ?」 葬識、流雨、彩歌を順に見た駁儀は、申し訳なさそうに微笑んだ。 「あと、出来たら。 ―――こっちの手、握っててくれたら嬉しいにゃ」 駁儀は右腕を差し出した。生身の方の手だ。 差し出された夏栖斗は、すぐにその手を取れるほど割りきれていなかった。その背を、快が無言で押した。 駁儀の冷たくて小さな掌を夏栖斗が握る。 駁儀は恥ずかしそうに笑った。 「ほら、これで全然怖くにゃいにゃ」 「ちょっと、待ちなさい。わたしは、貴方の選択なんて興味ないの。貴方が選択しても、意味は無いの」 「やからボクが選択してやるにゃ。これが“ボク達”の答えにゃ」 凛とした瞳で、駁儀は四月朔日を見返した。トリガーにかかる指に徐々に圧力がかかる。 そして夏栖斗の左手は。ぎゅうと握られる駁儀の右手の圧力を痛いほど感じていた。 「―――やめなさい!」 と言って四月朔日が立ち上がった瞬間、風船が破裂する様な音が残響し、彼女の白衣は紅い斑点で彩られた。夏栖斗の身体の左半分も、朱が塗りたくられていた。 ●o 倒れた駁儀には、まだ微かに息があった。 葬識達は完全に息の根を止めるために腕を振り上げる。 「待ちなさい」 それを、四月朔日が制止した。流雨が別段表情も変えず視線をそちらへとやった。 「何か?」 「これは、誤算だった」 吐き棄てるように言った四月朔日に、先程までの余裕などなかった。何故なら、駁儀が自ら頭を撃ち抜くまでの『全て』は、四月朔日の描いた道筋だったからだ。 「だから、殺める事になったのは仕方ないという事ですか?」 「違う」 信じられない。そう呟いた四月朔日は、力なく椅子に座り込んだ。 「『だから言ったでしょう』」 流雨は敢えて四月朔日の言葉を借りた。 「貴方達は、ただ無い物ねだりをしているだけの子供だと」 細く細く残る駁儀の息は、酷く残酷だった。 「猫ちゃんの遺言だからさ、ちゃんと殺してあげたいんだけど」 待ちくたびれた様に葬識が言うと、四月朔日は首を振った。 「殺さなくて、いいわ」 「どうして?」 「―――貴方達の言う通り。 私は結局、ただの“構ってちゃん”だったということ」 葬識が目を細めた。状況は極めて複雑だった。 「駁儀がヴァリアントの効果を受けている、というのは、虚偽よ。 本当に条件連結しているのは、わたし。……ね、構ってちゃんだったでしょ?」 「なら、にゃんこ先生の行為は―――」 言い掛けた烏に四月朔日は頷く。 「無駄ではなかった。 本当なら貴方達が駁儀を殺し、それで効果が解除されたと誤解した貴方達の眼の前で、被験者達も死ぬ筈だった。 わたしも瀕死の傷を負う筈だった。わたしはその時の貴方達が、見たかった。 ……結果としての状況は一緒でも、過程が大きく変わってしまった。 こんな結末は、わたしの欲している観測では無かった」 だからやっぱり駁儀の行為は無駄ではなかった。 流雨は、ガラクタの様に何の力も持たなくなってしまっている“太刀”を握り、かつかつと四月朔日の前まで進んだ。夏栖斗と快は、すぐさま他の階に居るリベリスタ戦力と連絡を取り、駁儀の移送を始めていた。 「詰まる所―――おじさんたちは今すぐにでもたぬき君の息の根を断たないといけなくなっちまった訳だが」 「ええ」 「その前に、一つ訊きたいことがあります」 「……なにかしら」 「『此れ』は“どちら”のです?」 すっとその切先が四月朔日の首に突きつけられた。 「雨水君のよ。三つ編みの彼が言う様に、雨水君はもうそれが必要ないのね。 けれど、今では“ただの古い太刀”よ」 「何故、貴女が?」 彩歌の問いに「知らないわ」と四月朔日が応えた。 「わたしにもわからないことはあるのよ」 「……そう。何か、言い残すことはあるかしら」 「そうね。貴方達とは沢山お話しできたし、あんまり思い浮かばないわ。 ……あ、だったら」 「何かある?」 「『その刀』で殺して欲しいわね」 四月朔日が流雨の構える太刀を見ながら言った。 ……知らないだなんて、やっぱり嘘だ。彩歌はそれを直感的に理解したが、追及するのは止めた。 彩歌にしては珍しい。それが余計なお節介であろうと、判断したからだった。 「承知しました」 流雨がそのまま刃先を四月朔日の細く白い首元に当てる。 四月朔日の瞼は、閉じられていた。 「これが報いなのね」 「いや」 小さな小さな呟きを、葬識は否定した。 「それが、君の“生き様”だ」 くす、と四月朔日は瞼を閉じたまま笑った。 それは葬識が見た彼女の中で、一番人間らしい笑い方だった。 流雨は、腕に力を籠めた。 ●u. 罪あるものと罪なきものを結びつける絆と鋏。 それが罪人だらけの場合は何を結びつける絆なんだろう―――。 四月朔日の死亡後、被験者達の監視が暫く行われた。神秘異能活性の疑義が残る事からやや厳重に行われた監視だったが、結局、被験者らには異常が見られないまま、ヴァリアントは消滅した。烏の考えていた通り、四月朔日は真実を述べていた。 絆の破界器は今回、罪人だけを結びつけた。そんな風に夏栖斗には見えていたが。 「誰しも罪人なのだろう。誰しもが裁かれるべき罪を抱えている。 つまりヴァリアントは、それを平均化あるいは平等化するというコンセプトだったのだろうな」 伊吹の分析に彩歌も静かに頷いた。 「善を見出すか悪を見出すかは判断の仕方だけに任されている、か。 “罪なき者と罪ある者、結局は二人とも区別なく、罰として殺される”。 ―――まるでカフカの一節ね」 貯蓄してあるヴァリアント等について、四月朔日が語ることは無かった。しかし、その後監査に入ったアーク職員らにより押収された膨大な資料からその方面での捜査は飛躍的に進展するだろう。 「これで良かったのかな」 「これで良かったのさ」 快が夏栖斗に応えた。 「一般人の死者は零。俺達はオーダーを完璧にやり遂げたんだ」 「それは、そうだけど」 四月朔日はどうしようもない革醒者だった。 けれどその姿は迷っている様にも映った。 本当は、彼女だって救えたのではないか。 「―――俺達は、十分よくやったんだ」 夏栖斗の肩を、快は優しく叩いた。 ●エピローグ 「仮に全ての事象は人為的結論だとしよう。 だが、人為をもって他者を観測したとして、バイアスが掛かった状態で得られた結果では“理”は得られないとおじさん思うがねぇ」 そう烏が話しかけた相手は、勿論。 「そりゃーおじさん、量子論の話にゃ」 包帯でぐるぐる巻きにされ拘束された駁儀だった。 ……その後、研究所内に残存していたホーリーメイガス二人を急遽呼びつけて、駁儀は九死に一生を得た。無論、癒えぬ後遺症が残る可能性は多分に大きい。現に今も、視界は殆ど無い。 「そんな大層な話じゃないさね。 生きる限りは真の観測者足り得ぬ。他者へのバイアスは常にかかるもんだ。 なれば、梵我一如。己が身で得た経験を元に、己が内に“理”を問うべきかと、ね。 ……早い話が巻き込まれる側に立てって事な訳だが、面倒は勘弁しろやってのがおじさんの心境だな。 にゃんこ先生もたぬき君も探求者としての意欲は買うがね」 「万物は我の内に在り、かにゃ。って、にゃんこ先生ってゆーにゃ! ……ま、そこらへんは身に染みたから今後考えなおすにゃ。たぬき君の二の舞は嫌やし」 「で、猫ちゃんはこれで“立派”にリベリスタの仲間入りなのかな?」 「ふーんだ。三つ編み殺人鬼くんが出来てボクが出来ない道理はねーにゃ!」 「どうでもいいことですが」 既に夜は明けている。朝日が眩しく、帰還の途に就くヘリの中を照らし始めていた。 「結局、にゃんこまん様は男性なのですか、女性なのですか?」 貴方の三人称は常に中性なので全く分かりません。と言った流雨に「三人称ってにゃに?」「いえ、此方の話です」と返して、 「……剥いでみる?」 と、しおらしく胸元を指先で広げる素振りをした駁儀は、同乗していた夏栖斗が居るだろう方角をちらりと見た。見た目は間違いなく美女の類だが、胸囲は薄く一見して分からない。重傷を負った直後、包帯で巻かれ、少し汗ばんで見えるその白肌に動揺するが、彼にも心に決めた人が居る。その“神秘”を覗く事はその後も無く、こうして長い夜の戦いは漸く終焉を迎えた。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||














