
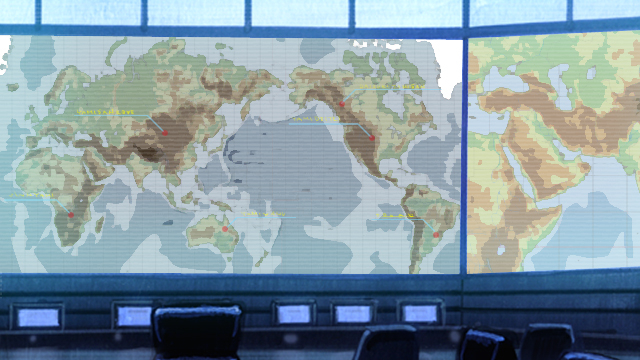

<アーク傭兵隊>惨饗事件

|
●第一楽章 ――――ならば例え、世界が許さずとも。 ●黒屍片(ゾンビパウダー) アーク本部、ブリーフィングルーム。 集められた面々を一瞥し、『リンク・カレイド』真白 イヴがまず示したのが、 テーブルの上に積まれた上質紙の包みを指差す事だった。 「……皆、こんな物が送られて来た」 白い紙から毀れる黒い粉。それは鋼の様な艶やかさを持ちながら、けれど何所か異質だ。 そう、例えばW.P.の造った破界器を見た事が有る人間ならば。 それの持つ禍々しさを稀釈し薄く伸ばした様な気配だと、評する事が出来たろうか。 「状況を説明する前に、確認事項」 一拍、呼吸する程度の間が空く。 「先のウィルモフ・ペリーシュの”大量神隠し”の所為で、 日本だけでなく世界各国に、神秘に対する疑惑と波紋が広がってる。 『ヴァチカン』が全力で抑え込んでるけど、正直これ以上の隠蔽工作は厳しい」 神秘は秘匿されるべし。それは、リベリスタである以上の共通認識だ。 その帳が破られ様としている。これは確たる事実として、まず受け入れなければならない。 「その上で……この数ヶ月、西欧は愚か米国まで含めて水面下で異常流行してる新種の麻薬が有る」 小さな指が、その黒い粉末をなぞる。淡く眉を寄せ、言葉だけが淡々と続く。 「吸うと気分が高揚して痛覚が鈍り身体能力まで大幅に向上。依存性以外の副作用は無し」 それだけ聞くと随分盛り過ぎではあるが、良くあるアッパードラッグの類に聞こえる。 神秘界隈とは余り関係の無い代物の筈だが、こうして呼ばれている以上それだけでは有り得ない。 視線を返せば案の定。イヴがこくりと首肯する。 「これ、飲んで死ぬと動く屍として蘇る。飲ませた人間の言う事を聞く死なない兵隊」 屍である以上それ以上死に様が無い。理屈は酷く単純だ。 けれど、その薬効。そしてある人間の指示通りに動く屍と言う形態。 それはアークが以前遭遇した、”楽団”による暗躍を髣髴とさせる。 「……実は飲まなくても、新しめの死体に振りかけただけでも効果を発揮するって分かって、 西欧の方でちょっとした騒ぎ」 続いたイヴの言葉に、リベリスタ達が明確に引き攣る。 大凡想定され得る碌でも無い展開である。流石にどんなに全能感を堪能出来るとしても、 自分から将来生ける屍になる契約書にサインする様な狂人はそこまで多くない。 しかし、ただの死者にも使えるなら別だ。死して物言う屍無し。 例えばテロリスト。例えば抗争中のマフィア。例えば内紛中の国家であればどうだろう。 組織の末端よりむしろ上層部の人間が好んで仕入れる様は想像に難く無い。 新種の生物兵器だとでも言えば誰もそれを疑いはするまい。 「再利用された屍は、大体1夜で死滅するんだけど……」 何所か言葉にしたく無さそうなイヴの様、次の言葉も凡そ想像出来る物。 「……死滅した死体は、自分の質量の凡そ10%程の“黒い粉”を残す」 増えてるじゃん。と言うツッコミすらこの場合意味を持たない。 摂取量と産出量が比例して増加するなら、それは流通量も増える訳だ。 生産が容易く、効果が十分であり、おまけに素材は死体である。 今、この地球上でこの瞬間どれだけの人間が死んでいるかと考えれば、 使い道など吐いて捨てる程有る。初期投資に一定負担が掛かろうと回収は容易だ。 「まるでネズミ講」 そう。実の所幾ら用途が沢山有っても使う度増える何て状況では、 あっと言う間に価格は暴落していく。と言って腐っても破界器である。 一般の兵器で“生ける屍”に対処するのは非常に困難だ。売り切る等出来る訳が無い。 「結果、短期間に凄い安価で膨大な数があちこちにばら撒かれてる」 何故、そんな事態に気付かなかったのか。 要約してしまえばそれが何故か“日本を含むアジア圏にだけは一切入ってこなかった”からだ。 情報すら9割方カットされていた。これはまるで“倫敦の蜘蛛の巣”の手口だ。 「幸い、スコットランド・ヤード傘下の組織から情報が流れて来た。 この粉……黒屍片(ゾンビパウダー)の生産工場が有るみたい」 放置しておく事は出来ない。けれど、既に流通している方の回収からも手は抜けない。 結果、世界中のリベリスタ組織の傭兵として各地を転々としているアークであれば、 然程問題にもならないだろうとお鉢が回ってきたと言う次第だ。 「流通分はオルクス・パラストと米軍が全力で回収してるみたい。 だから……生産拠点を潰すのが私達の仕事。スコットランド・ヤードが協力してくれる予定」 そう言って、漸く点いたモニターの一点。イヴが指し示した場所。 そこはスコットランド、エジンバラ市郊外――タンタロン城。 ロンドンに次ぐイングランド第二の首都。文字通りの、スコットランドの中枢である。 ●残響組曲 「ったく、何でこうなっちまうかなあ……」 何故か、と言う問い掛けがこれ程虚しい事も無い。 髪を掻き上げながら背凭れに身を預ける美丈夫は、それでも何所か軽薄な溜息を吐いた。 「何でも何も、分かってた事じゃないの?」 対面するのは少年か、少女か。見た目からは判別が付かない。 以前彼、ないし彼女にそれを問い掛けた時は、けらけらと笑ってかくの如く答えた。 “僕は天使(エンゼル)だよ。天使に性別が有ったらおかしいじゃない” その名乗りの通り。良く目を細めて見れば、その頭部には光輪が浮かんでいる。 神秘界隈に通じた人間なら先ず、彼を上位世界の異界人(アザーバイド)と判断するだろう。 けれどそうではない。説明されなければ先ず勘付かない事だが、彼は“エリューション”だ。 “フェイトを得たE・フォース”理屈としては、そういう存在が成立し得る事は理解出来る。 が、実感としては未だに有り得ないと言う感想しか浮かばない。 E・フォースとは言うなれば想念の結晶だ。特定単一の目的を果たす為に存在しており、 自由意志等その大半が持ち合わせない。そんな神秘世界の常識を、相手は真っ向から否定する。 「そりゃそうだけどよ、幾ら何でもこりゃ負け戦だろ。割りに合わねぇにも程があんだって」 出来るだけ手を抜いて、楽をして、傷付かず勝利と金を掴みたい。 傭兵として生きる以上は誰しもそう考える物だろう。勿論、答えた男も同様だ。 いや、傭兵として生きる前から彼はそうだった。性分だ、そういう風にしか生きられなかった。 「それを何とか持ち応えさせるのが僕らの仕事。そうでしょ――『極緻猟犬』」 そう告げられた男。ヘルムート・フォン・ヴィルヘルムの眼がすっと細まる。 「餓鬼が軽々しく“猟犬”の名を呼ぶんじゃねえ」 鉄の様に、鋼の様に、洩れた声は冷え切って響く。 件の組織が崩壊し、極東を逃げる様に脱出してより丸一年が経とうとしていた。 その間、彼の射撃の才能は遺憾無く発揮され、傭兵として一定の知名度と功績を得た。 楽隠居するに十分な金も稼いだ。女も好きなだけ抱ける。傭兵仲間からも一目置かれ始めている。 それなのに、何故こんな場所に自分は居るのか。自分でも良く、分からない。 けれど。 けれど、理由はあった気がするのだ。 “貴方に力を貸して欲しいのです” 依頼主の、栗色の髪の少女はそう言った。幾らで何をしろではなく、力を貸してくれと。 “私達は、聖櫃(アーク)の……英雄の敵” その名を聞いた時、背筋が凍る様な忌避感と共に確かに感じた。言い様の無い高揚感を。 『あんた、俺が何で、誰だか分かって誘ってんのか』 敗残兵。敗北者。選ばれしアーリア人の面汚し。そう蔑まされた記憶は決して消えない。 それを実力で覆し、それなのにどうしても満たされない。どうしようも無い程渇くのだ。 “ええ。貴方は鉄十字を掲げる猟犬。私達の祖国が恐れた、彼の第三帝国の末裔でしょう” それを――まさか恐怖と共に語る人間が未だ居る何て思いもしなかった。 そうだ。褒められたかった訳じゃない。賞賛されたかった訳じゃない。 恐怖と共に、畏敬と共に、彼らの歴史が無価値なモノでは無かったのだと認められたかった。 癇癪を起こせない餓鬼の様に、そんなわだかまりを抱いたまま逃げ延びて。 今更になって気付くのだ。彼は決して、あの“同胞達”を嫌ってなどいなかったのだと。 そんな、酷く下らない理由が。 つまりは、それで。悔しくとも、誰にとってもきっとどうしようもない一言で。 けれど男は身動きが出来なくなっていた。 『……奥に一人で来い。話、聞いてやんよ』 それは、勝ち目の無い戦いの誘いだった。時間稼ぎの、捨て石として雇われる。 傭兵として、こんなハズレ籤はまず有りえない。素気無く袖にされて当たり前だ。 撤退戦のキツさは、既に嫌と言う程味わったのだから。 それなのに。 「いいかクソ餓鬼。“猟犬”は、恐怖の名だ。しっかりその軽い頭に刻み込んどけ」 説教じみたヘルムートの言葉に、天使はへにゃりと焼き立てのパンの様に柔らかく笑う。 なるほど、これだけ切り取ったならあながち天使と言う肩書きも伊達じゃないかもしれないと。 そんな風に思える位には。無邪気なまでに素直に微笑む。 「うん。君達は本当に、どうしようも無く、不器用だねえ」 「お前本っ当嫌味な奴だな」 据わった目で愛用の銃を肩に掛ける。気の抜ける様な、緩い空気はここまでだ。 敵はあの“箱舟(アーク)”。指先一つの油断すら出来ない。 けれど、何所までも。何所までも覚悟の上だった。自分一人なら、さっさと逃げていただろう。 だが、今だけは退けない。恐怖の象徴として。畏敬されるべき“鉄の獣”として。 『極緻猟犬』はこの戦場に立っているのだから。 それは、どこまでも唯の残響に過ぎない。 それは、どこまでも既に終わった物語の名残に過ぎないのだ。 けれど、世界は芝居の様に、童話の様に、歌劇の様に綺麗には終わらない。 「来いよ箱舟共。――――“Sieg Heil Viktoria”」 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:弓月 蒼 | ||||
| ■難易度:HARD | ■ ノーマルシナリオ 通常タイプ | |||
| ■参加人数制限: 8人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2014年12月11日(木)22:16 |
||
|
||||
|
||||
| ■メイン参加者 8人■ | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
●Mauerfall 戦争は先ず、物量で一つの決着が付く。 端的にそう言えてしまう程に、数の差と言う物は戦いに於いて重要な要素だ。 例えそれが名も無き有象無象で有った所で、一騎当千とはその言葉程に安くは無い。 「――奇襲など、警戒するまでも無かったか」 「あのバカが……柄にも無い事をしやがって」 翼の加護を纏い、門を開いて突入したリベリスタ達を襲ったのは計15体の屍の群。 これだけでも数の上では彼らの倍近い。 だが、『狂乱姫』紅涙・真珠郎(BNE004921)、『桐鳳凰』ツァイン・ウォーレス(BNE001520)。 先陣を切った2人にとって、例え体躯の大部分が壊れようと組み付いて来る屍達。 その大半は鎧袖一触と表せる程度の力量しか持ち得ない。 何よりも、彼らはその視界にそもそも屍達を入れていない。いや、それは2人に限らない。 「『極緻猟犬』……私、が実際目にした中、では……最高峰の射手。……楽しみ」 「まさか再びヘルムス・ニールを耳にするとはね。世の中、実に面白い」 『無軌道の戦姫(ゼログラヴィティ)』星川・天乃(BNE000016) そして『足らずの』晦 烏(BNE002858)。両名もまた『猟犬』との因縁を抱える身だ。 片や黒い森を踏破した生還者の一人、片や“猟犬最強の狙撃手”の技を引き継いだ魔弾の射手。 その拳が奮われる度、死より蘇った筈の屍達に今一度の死が刻み直され、 その銃弾が爆ぜる度、朽ちて尚主命を果たさんとする偽りの命が地へ伏せていく。 「……この場所は、よほど死生剣と相性が良いんだろうな」 「屍を動かす毒、か……ならば、捨て置くわけにはいくまい」 他方――この場に挑む者が共とする因果は留まらない。屍を動かす黒い粉。 それが、とある研究者の執念が生み出した神秘である事を知る者は多く無い。 けれど『アリアドネの銀弾』不動峰 杏樹(BNE000062)はその痕跡すらも見逃さず、 『無銘』熾竜“Seraph”伊吹(BNE004197)はまるで運命の如き因果の糸に導かれこの地を踏む。 両者共に夢を摘んだ者として。始末を付ける義務があると言わんばかりに。 空には杏樹の使い魔(ファミリア)が元気一杯に飛び回っている。 内部の様子を確認する為に放った物だが、案の定。 地下への階段手前に陣取っていた『天使』に発見され追い払われた物である。 何故迎撃しなかったのか、由縁は知れない物の…… (いずれにせよ、交戦は避けられないか) 雷神の銘を持つ魔弾が屍達を薙ぎ払うと、烏の銃撃を受けていた個体の動きが止まる。 その火勢を潜り抜けたとて、自在に飛び回る伊吹の乾坤圏は屍達に組み付く事をすら許さない。 「先ず一陣は切り抜けられそう、ですか」 「はい、ここは未だ『極緻猟犬』の射程圏に入っていない様ですね」 『現の月』風宮 悠月(BNE001450)が考え込む様に呟くと、 彼女と同道する事の多い『相反に抗す理』リリ・シュヴァイヤー(BNE000742)がこくりと頷く。 一見すれば戦場とは縁の無さそうな2人とて、 アークでも有数の古典魔術師と神の名の下に幾多の異端を葬ってきた神秘狩りのペアである。 月刻む剣が切っ先を向ければ流星が降り注ぎ、二兆拳銃が火を吹けば神罰の雷鳴が轟く。 けれど彼女らが力を奮う前に殆どの屍が動きを止めている。圧倒的なまでの大火力。 何より、全員での正面突破を選んだ事で十分以上の対多攻撃を揃えられた事が大きい。 これにより、動く屍達は文字通り、烏合の集である事が確定したのだから。 故に――まず間違い無い事が1つ。彼女らは決して油断していた訳ではない。 そしてもう1つ。最大限の警戒をしていてすら、仕様の無い事と言うのは存在する。 リスクと、リターン。何かを得れば何かを失う。これは、戦場の必然である。 「げ、あの恐え女、未だ生きてたのかよ……」 場所はタンタロン城に併設されている物見の塔の上。 スナイパースコープなど必要としない天性の慧眼で以って、『極緻猟犬』が小さく呟く。 視線の先には天乃。彼の銃口は既にいつ射程に入っても当てられる様に構えられているが、 そのトリガーに指は掛かっていない。“戦争”には下準備が必要だ。 呼吸を落とす。気配を殺す。待ち伏せる以上、先手は『猟犬』の側に有る。 「良いぜ、クソ餓鬼。始めろ」 足元に置いたトランシーバーに声を掛ける。 神秘的通信が阻害される呪われた城も、科学の産物まで妨げる事は出来ない。 「OKー、3,2,1……Humpty Dumpty had a great fall」 天の上から降り注ぐ雷光。その激烈と言えるエネルギーの全てが、 古びた、補強も十分でない、当然神秘的防御など一切有している筈も無い。 廃城の“内門”に――――――叩き付けられる。 ●Einzelner Krieg 「…………は?」 思わず唖然としてしまったツァインの反応は止む無い所だろう。 普通、誰しも地形と言うのはあくまで戦場として把握する。 それが例え“廃城とでも呼ぶべき古い城”であろうとも、 まさかその内門を破壊して足止めをされる等とは、まず、到底考えない。 経験から、或いは――経験ゆえにか。今迄当たり前であった事が当たり前で無くなる瞬間。 人は、咄嗟に動きを止めざるを得ない。そして『猟犬』は――正しくそれを、待っていた。 「――Tanz mit dem Tod」 放たれた純白の光は4条。正門を越え、中庭と内門の境界線に居たツァイン、天乃、そして真珠郎。 まるでついでとばかりに、空を旋回していた杏樹の使い魔が撃たれて墜ちる。 更にはその弾丸の精度。『極緻』の銘は決して伊達でも酔狂でもない。 反応に長ける真珠郎すらが、わずか一発で以って女神(ヴァナディース)に魅入られた。 「っ、やはり塔の中か!」 伊吹が視線を上げる。が、そこに射撃手の姿はない。 そんな筈は無い。“そんな筈が無い”のだ。 射線が通った以上、一瞬前までそこに『極緻猟犬』は居た。だが―― 「……まさか」 杏樹が息を呑む。塔の上、と言う特殊な地形。相手の存在を把握するには視線を通す必要がある。 だが下から上を見上げる場合、視線は斜角と外壁によって大きく邪魔される。 これを無視して敵を補足するには、まず最低限「透視」の神秘が必要だ。 普段己らが滅多に使う機会が無い“手段”であるからこそ。 「喰えないねえ……塔の上からヒット&アウェイか」 『足らず』の独白通り――歴戦の射撃手はその盲点を突く。 過剰な射撃精度を以ってすれば移動を念頭に置く事のペナルティ等有って無い様な物。 そして崩れた内門を昇って這い上がって来るのは屍の群だ。 瓦礫が邪魔になって城の奥が見えない。全体攻撃をするにも“認識”は必要不可欠。 「この城自体が罠って訳か! くそっ!」 女神の魔弾によってツァインがギリギリで纏った聖鎧は引き剥がされている。 それ故に彼の刃は本来護るべきだった最も近くの対象。 悠月に対し振るわれ、おまけにそれ以外の前衛。真珠郎と天乃の両名は、余りにも。 「くっ、同士討ちなど冗談ではないっ!」 「どれが……ゾンビ、なのか……分から、ない」 余りにも速過ぎた。殺人鬼にして歪夜の使徒の異名を持つ殺戮の刃が続け様に踊り、 そこを駄目押しとばかりに魅了の光刃がツァインの盾越しに叩き込まれる。 「いけない……屍達の二陣が来ます!」 それら全てが物理攻撃である以上、悠月の選択肢は1つしかない。 魔術による対物障壁の展開。“塔の上からのヒット&アウェイ”が止まない以上、 このままだと2手番に1度、当たった者を魅了する女神の魔弾が降り注ぐ事になる。 地上からこれを迎え撃つのは極めて困難だ。少なくとも、持久戦は避けられない。 「射程圏に入れば撃ち合える――と、その見込みが甘かったと言う訳ですか」 「射撃手である以上配置が最も大切ってな、わかっちゃいた心算なんだがね。 相手は『猟犬』――たった1人でも、こいつは戦争だって訳か」 リリが両手に神の戒めと嘆きを刻んだ拳銃を構え、合間を縫って烏の散弾が屍達を射抜く。 続けて雷神の魔弾が放たれるも、流石に此度は火力が十分に足りてはいない。 「……『天使』は?」 「こちらから相手が見えない以上、相手からもこちらは見えないかと」 悠月と杏樹が背中を向けて応答し合えば、これ以上の援軍は屍の群のみと見解が一致する。 それを悪戦況と捉えるか、まだマシだと捉えるかは微妙な所だ。 「今度こそ終わらせる。再び悪夢を繰り返さぬために」 「ああ、すべての子羊と狩人に――安息と、安寧を!」 第三陣が瓦礫を昇ってくる。放たれた魔銃より放たれた銀弾が雷を帯び、 回転する光輪が昇って来た屍達を吹き飛ばす。一歩でも先へ、一歩でも前へ。 足に絡み付いて来る屍の手を振り払い、前に、前にと進まなければ。 『極緻猟犬』の射線から外れるには、城内に突入する以外道が無い。 いや。それは果たして、本当にそうか。 「――っ……先のは、効いたわ犬っころめ。"餓鬼"が少しはマシになったようじゃの」 真珠郎自身には面識が無い。されど『猟犬』の記憶は朧気ながら脳裏に過ぎる。 元々はとても紅涙の“敵”とは呼び難い、益体も無い幼犬だった筈だ。 それが、地形を使い兵を動かし罠を張り、一丁前に戦争を仕掛けて来たと来た。 苦々しくも認めよう、認めざるを得まい。赤い瞳が塔を見遣り、 「また、逢えるなんてね……嬉しい」 まるで同じ仕草を映した隣の女と視線が合う。獲物は1人。狩人は、2人。 ●Duell walzer 「のう、戦姫。競わんか」 「止めても……聞きそうに、ないね」 城内に突入すれば。そんな選択肢は2人には無い。必要が無い。 どちらも共に、安全圏に身を置く事などそもそも興味が無いが故に。 「な、おい、本気か!?」 ツァインの射程圏から外れたならば、両名に魅了の魔弾を避ける術は無くなる。 それを承知して尚、狂乱姫と戦姫。いずれもが外壁を足場に塔の窓へと駆け上がる。 「おいおいおいおい、馬鹿か!? 馬鹿ばっかりか箱舟って奴は!?」 それは無論、対する『極緻猟犬』ヘルムートからしても予測の範囲外だ。 即座に愛銃を構え直し両者が姿を現す瞬間を待つ。 塔の外壁を透過でもしない限り先手取るのは『猟犬』だ。影が奔る。トリガーが引かれる。 女神の名を冠する魅了の魔弾が両名に完璧な形で命中する。 癒し手に乏しい戦場、そして癒しの力を持たない2人だ。 「下らぬよ、『極緻猟犬』。命を惜しむな刃が曇る」 自らの攻撃で傷付いてもいる。運命の祝福も無限ではないと言うのに―― 「元気そう……だね。久しぶり、あの時の決着を……つけよう」 或いは、無限では無いからこそ賭す価値が有るのか。 「また、踊って……くれる?」 「事はシンプルじゃ、喰うぜ喰うよ、喰い殺す――!」 銃撃、斬撃、切り刻まれ血塗れになりならがらも、 祝福を糧に、矜持を足場に、二姫の狩人と猟犬は切り結ぶ。 「は……色男は、辛いねえっ!」 この期に及んで、階下に視線を向ける余地など誰にも当然有る訳は無く、銃撃が止まる。 だが一方で、階下もまた塔の上になど意識を向ける余裕など有りはしなかった。 元より全員が一丸となって始めて十秒間に15体と言う圧倒的質量を駆逐し得ていたのだ。 そこから2人が抜けた穴は小さく無い。間違い無く一流と言えるリベリスタ達であってすら。 「次から、次へと……!」 「話には聞いてたが切りが、ねえっ!」 伊吹とツァインとが奥歯を噛む。 倒れても、倒れても、倒れても倒れても倒れても起き上がって来る屍達。 腕を切り落とした位ではまるで無意味だ。体中を蜂の巣にしようと立ち上がる。 両足を光輪が砕き、雷撃で念入りに炭にした上で流星をぶつけて漸く沈黙する有り様だ。 瓦礫を越えて次から次へとやって来る。周囲全方どちらを見ても屍しか居ない。 「今、どの程度時間が経過しましたか」 「突入から2分弱。援軍も漸く止まったみたいだ」 悠月の問いに、焦れた様に杏樹が応える。 ざっと見回しただけでも残されたゾンビの群は未だ50を割っていない。 場合によっては、この上裏門に配された屍達が増援として来る可能性がある。 「……不動峰さん、晦さん、進んで下さい」 「っ!」 続いた言葉に、魔銃の銃把で屍の頭部を打ち上げた杏樹が視線を返す。 幸い翼の加護は未だ残っている。頭上を抜けられない訳ではない。 けれどこの上更に2人が抜ければ、残りのメンバーの苦戦は必至だ。 「――……もし、“彼女”に出会えたら伝えて下さい。貴女と個人的に、お話がしたいと」 「この上は止むを得まい……亡霊と、悪夢に、相応しい終わりを」 瓦礫の向こうで待ち構える『天使』と打ち合うには最低限。 超遠距離を射抜ける技量と能力が不可欠となる。万が一を考えれば烏の存在は必須。 「……仕方無い、か。不肖役戯れの身とは言え、役割位は果たしてみせるかねぇ」 「分かった……行って来る」 そして杏樹とリリ。両名の内でより対単体突破力に優れるのは前者だ。 予定した流れが崩れた今、全員で一丸となって地下へ突入するには歩みが「遅過ぎる」 「ああ、奴に一発キツいのをくれてやれ」 ツァインが奥歯を噛み締める。言うべき事も、伝えたい事も、有ればこそ。 いや。本心を吐露してしまえば、『猟犬』は生き残るべきだとすら思うのだ。 それでも、もしもここで手を抜いたらそれは、彼らの生き様全てへの侮辱となるだろう。 「くそ、こんなつまらねぇ役、俺に押し付けんじゃねーよ、クソ駄犬……」 屍の侵攻を押さえ込み、両手足を捕まれながらも踏み止まる4人。 流星が降り注いだ間隙を縫って彼らを包む肉色の渦から対の翼がはためくや、 銃撃手は2人。矢の如く瓦礫と化した門を駆け抜ける。 地下への階段には人の姿は無く、灯りもまた存在しない。 だが杏樹には暗視の神秘があり、烏もまた独自改造を施したゴーグルを纏っている。 室内には15枚の壊れた鏡。金属の四角い小箱が無造作に置かれていた。 その中央。輝く4枚の翼。頭には確かに薄っらと光の輪。 少年とも少女とも取れる金の髪の子供が、手に縮尺がおかしく見える大剣を抱えている。 「……お前は」 杏樹から漏れた声。それを耳にして『天使』が視線を向ける。 「救世劇団やらの主張は判らなくも無いんだが」 間髪居れず、銃声。死を冠する抜き打ちの「最適解」が『天使』の体躯を撃ち抜く。 ――直撃。完全なる狙撃は確かに的中し、その体躯から光が毀れて消える。 けれど『天使』はまるで動じる事なく。淡く微笑むようにして言葉を返す。 「ようこそ。遅かったね、と言うべきかな」 さらさらと、黒い剣が砂に変わって行く。さらさらと、剣と言う形状を失っていく。 「君達が戦いを。戦争を。死による死を再現してくれたお陰で、 条件は満ち、そして芽吹いた。地下の穴に育つ死の夢の採取は無事完了した訳さ」 剣が朽ち、残った物は植物の様な形状をしている様に見える。 それを、杏樹は奇しくも見た事がある。つい先日、彼女自身が掘り当てた―――― ●Nursery Rhyme 『アルラウネ』 死と夢とを養分に、罪人と断ぜられた屍人の丘の地の下に育つ“運命干渉器” 賢者の石と似て非なる「フォーチュナ専用のブースター」とでも呼ぶべき物。 タンタロン城の地下で育った「それ」が破界器『死生剣』に根付いていたとするならば、 これをリベリスタが破壊したならば諸共に、この“未来への禍根”を閉ざし得ていたろう。 けれど彼らは間に合わなかった。せめて唯一人でも、最初から突入を喫していたならば。 だが、今となっては栓無き話だ。 「なるほど、と言って通すと思うか?」 「伊達口上は柄じゃないが、唯で帰す訳にはいかねぇわな」 立ち塞がる杏樹と烏。けれど――そう。この場で警戒すべきは『天使』のみではない。 「ってことだから、助けて欲しいな?」 『“――――都合良い事言ってんじゃねえよ、クソ餓鬼”』 肉声と、部屋の奥。四角い金属の箱から聞こえる音が唱和する。 振り返った瞬間には既に遅い。『猟犬』の牙は、それ程に甘く出来ては居ない。 息を切らし、血塗れの上片腕が異常な方向に曲がってぶらんと下がっている。 ほうほうの体とは恐らくこの様な事を言うのだろう。 けれど、手にした拳銃からは既に白い閃光が放たれている。回避運動まで予測した『極緻』の魔弾が。 「あの狩人共、完璧命棄てる勢いで突っ込んで来やがって……2人でなけりゃ死ぬ所だったぜ」 元より、ヘルムートは狙撃手ではなく唯の射手。本質的に乱戦よりも一騎打ちを苦手とする。 もしも彼の居城に突入する術と、意気を持つ人間が単独であったなら、 彼は息をしていまい。無論――その相手もまた、息をしてはいなかったろうが。 魅了された2人。魔銃と古銃が交差し合う。重なる銃撃。その狭間を天使と猟犬が走る。 「トドメは刺し損ねたって感じだねえ、あははっ、ひっどい顔」 「てめえがあと30秒連絡するのが遅れてりゃ俺の一人勝ちだったんだよっ!」 噛み付く男の反論を、負け犬の遠吠えと呼ぶ事は出来まい。 死を纏う剣は失われども、『鉄十字猟犬』の痕跡は今一度西欧の地に刻まれる。 忘れられ掛けていた者。敗北し退けられた者。その誇りを背負う者。 咆哮は矜持と共に、恐怖と共にもう一度響き渡るだろう。 たった一人の『戦争』は――――まだ、終わらない。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||















