
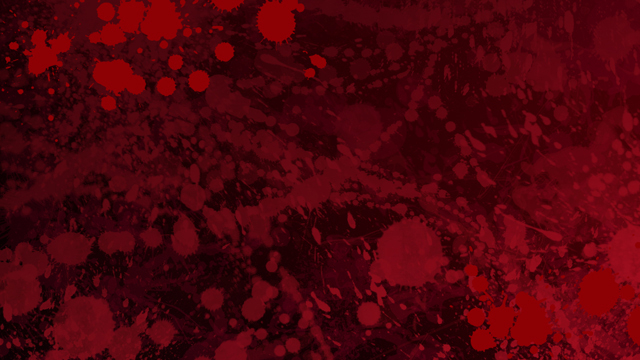

<凪の終わり・剣林>血蛭・真打

|
●研磨 名刀の手入れに砥石が不可欠であるように、人生を砥ぐには適切な人間が必要だ。 こと己が武の道を行こうと思うならば、己より強い人間は必要不可欠。鬩ぎ合い、競い合う好敵手もまた良いものではあるが、標的こそが自分を何より強くすると――少なくともその男、一菱梅泉は確信していた。 ナイトメア・ダウン以降、日本フィクサードの草刈場と化した日本に剣林の敵は居なかった。梅泉が日本最強と畏れられた剣林百虎を標的と定めたのは、大いにその辺りに起因する。病を発症した父では足らず、百虎に及ばぬ他首領では面白味が無い。最も困難で、最も達成し難い百虎のみが彼の食指を動かしたのは必然だった。 「剣林の図体を考えるなら、それもまた良しか。 群れの忠節なぞ、虫唾が走るが……わしが肯定するならその一事よな」 呟いた梅泉の脳裏に不敵な表情を浮かべた百虎の顔が浮かんでいた。 彼は『護衛も置かず』、呼びつけた梅泉に言ったものだ。 ――間もなく、剣林が動く時分だぜ。相手は言わないでも分からぁな? 梅泉からすれば、座して死ぬ等愚の骨頂だ。 同時に、唯永らえよう等という考え方は唾棄すべき最悪でもある。 フィクサード同士のそれですら嫌悪極まるのに、リベリスタと現状以上の協定を結ぶ等、論ずるにも値しない。敵の無い力は虚しく、己が為に振るえぬ力に価値等無いと心底より考えているからだ。 梅泉が目にした『箱舟』なる組織は話が通じそうだが、融通は無さそうだ。 極東の空白地帯を強引に切り開いて出現したリベリスタ共は、協調して歩くより敵に回した方が断然面白いと、彼に『最上級の評価』をさせている。 恐らくは、組織の長たる立場を別にしなくても、百虎の感想も大差はあるまい。 (何れにしても、時勢が大きく動くなら――我が求道にも力が入ろうというもの) 剣林の相対する箱舟を蹴散らすのも、その剣林自体を斬り捨てるにも必要なのは武力である。己が邪魔をさせぬ兵力もあるに越した事はない。小煩い師範代の手先では、梅泉の成就の力にはならない。先の戦いで箱舟の力と、必要なものを確認した梅泉は――本人からすれば些か珍しい事ではあるが、己が武力となる私兵に似た戦力を編成していた。幸いに彼の所属は剣林。力さえ示せばついてくる者等、幾らでも居たのが幸いした。 「後は、わしの武力じゃな」 藍の着流しの邪剣士が手にする妖刀を『血蛭地獄』という。剣林のフォーチュナの探知によれば、その名刀を鍛え上げる為の『材料』が、彼の目指す古寺にあるという。七面倒な過程が要るのならば、御免だが――主要な条件が『それ』を斬る事ならば、彼としては願ったりだ。 邪魔が入る可能性を告げられた時等、小躍りする心持ちであった。 梅には早い季節だが、血の薫る花はその歩みを止める気は無い。 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:YAMIDEITEI | ||||
| ■難易度:VERY HARD | ■ ノーマルシナリオ EXタイプ | |||
| ■参加人数制限: 10人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2014年11月30日(日)22:16 |
||
|
||||
|
||||
| ■メイン参加者 10人■ | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
●山寺I 人も寄り付かない古寺は、長らく忘れ去られた存在だった。 最盛期には霊験あらたかとされ、少なくない人間を集めた頃もあったが――近くの山村が過疎化で無くなった昭和の頃にはその役割も終わりを告げたと言えるだろう。 しかし、『彼』はその頃も今も――変わらない姿でその寺に住んでいた。 人ならざる異能を時に、人々の為に行使し――この日本の片隅で人知れず怪異を破った事もある。 「成る程、久方振りの千客万来と言う訳じゃな」 全身の造りは硬質。僧衣から除く赤銅色の肌は呟いた彼が人間ではない事を雄弁に証明していた。 「半分はわしの手の者、もう半分は――想定通りの余禄だわ」 抜き身の刃をぶら下げた己に対しても穏やかな語り口を崩さない『彼』――山寺の主『赤銅和尚』に邪剣士・一菱梅泉は愉快そうにそう言った。梅泉が全身から噴き出す殺気は余程の鈍感以外ならば一般人でも気付く程に禍々しいものだ。血臭を強く漂わせる妖刀に到っては、名詞代わりにしてもお釣りが来る程。 「主は、拙僧を斬りに来たか。恨まれる覚えも無いんじゃがの?」 「おうとも、わしは主を恨んで等おらんとも。強いて言うならば、偶の配剤じゃな。 わしは主に用は無いが、わしの刀が主を求めておるらしい」 梅泉の言葉に妖刀の刀身が赤く染まる。 この梅泉が今回『赤銅和尚』を斬りに来たのは、言葉通り怨恨を理由等にしていない。 和尚が偶然にこの妖刀を鍛え上げる血の持ち主であった――それだけだ。吐き気を催す邪悪でも無く、さりとて間違っても善良では無く。己の力を求道しているに過ぎない、剣林が剣士の一人、一菱梅泉。 「故に悪く思うな。斬って捨てるぞ」 その言葉は余りにも身勝手で、余りにも毒気無く吐かれていた。元・剣林幹部である一菱桜鶴の実子である彼は、暫く前十年にも及ぶ放浪から剣林に帰参したばかりだ。しかし、出奔の原因が『剣林百虎への襲撃』であった辺りは筋金入りなのである。些細なやり取りだけでその人格を計るには十分と言えるだろう。 「……こりゃまた、厄介な御仁が現れたもんじゃわい」 和尚は苦笑を浮かべて「やれやれ」と溜息を吐き出した。 彼が鋼鉄の錫杖を地面につけば、韻と夜の空気が震えを見せた。 「出来るな、主は。これは存外な楽しみが増えたというもの」 「拙僧はちっとも楽しくないわい」 左目だけを見開いた梅泉の目に歓喜の色が灯れば、和尚はうんざりしたようにそう言った。 古い山寺を煌々とした月が照らしている。 月下の剣士は絵になるが、人喰いの絵は誰も求めていないだろう。 ●山門I 「先の見えない狂人ではなく、ただ純粋なだけなのね――全く純粋なだけ毒が強い」 『レーテイア』彩歌・D・ヴェイル(BNE000877)の下した梅泉への人物評は、全く適切なものと言えただろう。 善悪のイデオロギーよりも先に、目的意識が強過ぎる。六道や剣林のフィクサードには確かに珍しい話では無いのだが、他人や情勢に与える傍迷惑と、本人の毒気という二点を合わせれば彼に勝る人間は然程多くない。 「だから性質が悪いんだけど。何れにしても、あの戦闘狂が半年近くもよく我慢したというか…… タイミングは最悪といっていいけど、剣林が本格攻勢に出る前に出鼻を挫いておきたいのは確かだわ」 「ペリーシュが新潟に現れて、少々事情も変わったが……まぁ、待ってくれるような連中では無いな」 彩歌とそれに応えた 『月下美人』新城・拓真(BNE000644)の言葉は平常ならぬ昨今の情勢を指しての言葉だ。 「人が動けば時代も動く、か。だが、何れにせよ奴等が動くならば、俺達も動くまでの事だ」 「……ま、結局はそういう事よね」 リベリスタは対処療法の難しさを嫌と言う程理解している。 欧州からやって来た『現代版の黒死病』の存在もさる事ながら、姿を消した魔女も気になる。 一言文句位言ってやりたい位の――きな臭い情勢は、彩歌の眉根に複雑な皺を作るに十分だった。 「一菱梅泉たァまた凄ェのがきたなァ! カカッ、まったく面白くなってきやがったぜ!」 「笑い事なの?」と問う彩歌に豪放磊落たる『悪漢無頼』城山 銀次(BNE004850)はやはり笑った。 「ヤツは強ェぞ。なら、こっちも倍は漲るじゃねェか!」 「正直を言えば剣林が力を付ける分には構わない、ぐらいには思っちまうんだけどよ」 「ま、刀は剣士の魂みてぇなもんだからな。鍛えようってぇのは分からんでもねぇけどよ……」 忌憚無い本音を言えば強敵との死合いに意義を見出す気持ちを分かる人間は多い。それに『桐鳳凰』ツァイン・ウォーレス(BNE001520)は剣林というラベルが然程嫌いでは無かった。だが、両方が分からないでもない――同じく大業物を扱う『元・剣林』鬼蔭 虎鐵(BNE000034)は言葉の半分を苦笑で飲み込んだ。 剣林は元の出自だ。全員では無いが、気の悪くない連中が居る事も虎鐵は十分に知っていた。 だが問題は『誰がどう鍛えるか』に尽きる。戦闘狂の辻斬りが更に強くなっては笑える話では有り得ない。 「……ま、ありゃ駄目だな。到底、放っておける男じゃねぇ」 「確かに個人的にも好けないな、あの刀は……」 「『死牡丹』……そんな方法で、とは思いませんでしたが。 あの邪剣士に更に力をつけられたら、厄介の一言では済まないのでしょうね」 (……むしろ、それが良いのだろうに) 虎鐵とツァインの言葉に 『柳燕』リセリア・フォルン(BNE002511)が頷けば、内心だけで呟いた『閃刃斬魔』 蜂須賀 朔(BNE004313)を除いたリベリスタ達は、概ねの認識の一致を見た。 一菱梅泉は気のいい男では無いし、彼の手にした妖刀『血蛭地獄』は弱き命を貪り喰う存在だ。 無論、朔とて基本的な価値観はどうあれ、この任務に異論は無い。 果たして――夜はすぐに決戦を望む。 善良なるアザーバイド『赤銅和尚』の命を助け、一菱梅泉の妖刀の強化を阻止すべく、夜の山寺の石段を駆け上がった彼女達十人のリベリスタが目にしたのは、月と山門をバックに仁王立ちになる八人の戦士達だった。 「君達が山門の番人という訳なのだな?」 段下から低空に浮き上がり、強く視線を向けた『百の獣』朱鷺島・雷音(BNE000003)に梅泉派のフィクサード達は「如何にも」と言葉を返した。精々が三人並ぶの精一杯の山門に敵戦力は八。此方は十。開けた平地での戦いならば数を頼みに強引な突破も叶おうが――状況がそれ程容易くないのは明白だった。 何れも隙無く武装を構えた敵の技量をすぐに看破したのは雷音故だ。 「出来るだけ早く沢山突破していって……って思ったけど! こっちはこっちで怖いんじゃないですかこれぇぇ!」 『息抜きの合間に人生を』文珠四郎 寿々貴(BNE003936)の言葉は全く正しい。 有象無象と舐めれば、斬り捨てられるのはリベリスタの側かも知れぬ。 彼等は言ってしまえば梅泉の前座だが、前座でも舞台によっては主役を張るに相応しい力を持っている。 梅泉がもし『効率だけを重視する男』であれば、和尚を全員で襲撃すれば話は既に終わっていたかも知れない。邪剣士の奇妙なフェア精神は――彼が何処までも楽しみの為に生命(じしん)を燃やす人間である事の証明か。 何れにしても山門の守護者は『あの』梅泉が武力と看做す使い手ばかりという事だ。 「やはり退いては……くれないか」 「彼等は『剣林』だからね」 程無く始まる対決を確信した雷音に『デイアフタートゥモロー』新田・快(BNE000439)が言った。 「だが、相手が誰でも押し通るよ。何て言ったって、俺達は『アーク』だからね」 「そうだな。……そうだ。ボク達は止まらない」 力強い快の台詞に雷音が頷いた。一瞬だけ視線を絡めた二人は、それで十分に通じ合っている。 成る程、この新田快という男は良くも悪くも強さも弱さもアークを体現したかのような男である。 多くの痛みと喪失を両肩に背負い、それでも立ち続ける彼の想いを理解出来るとしたらば、同じアークのリベリスタだけなのだろうが――望む望まないに関わらず高まった名声は彼に『結果』を強いる。 戦う程に許されなくなる敗北はアークが抱えるジレンマと全く同じであろうが、それを外に見せる事は無い。 (ボクも……強くならなければいけないのだ) そして、それを理解するが故に雷音もまた心に勇気の灯を点す。 「――ま、今更グズグズもガタガタも言わねェよ。俺等とテメェ等は敵同士。十分だろ?」 張り詰めたピアノ線のような緊張感を銀次の邪笑が攪拌する。 誰かの足元の小石がコツン、コツンと石段を転がり落ちていく。 瞬間の爆発を待つ山門に大した切っ掛けは必要無かった。唯、強い風が吹いただけで十分だったのだ。 「リベリスタ、新城拓真。罷り通る……!」 黒衣の剣士の低い声が戦場をねめつける。 同時に――彼の動きを先んじるようにリセリアと朔、疾風の剣士二人が石段を蹴り上げた。 ●山門II リベリスタに与えられた任務達成への手段は大まかに二つ。 一つは敵を蹴散らし、山門を突破。最短距離で和尚の救援に向かう事。 もう一つは山門自体を飛行で迂回し、直接境内へ乗り込む事。 何れも一長一短が考えられるプランだが、リベリスタ達は時間のロスこそを大敵と考えた。 「あいつをぶっ殺して……百虎に近づく為にもな。さてさて……まずは山門を突破しねぇとな」 全ては獰猛に笑う虎鐵の言う通り。 故に突破、山門での戦いはリベリスタ側にとっての第一段階である。 フィクサード側――つまり梅泉一派の狙いは、領袖たる梅泉に和尚を斬らせる事である。 梅泉はアークの介入を予期し、彼等を山門に配置したのだからこれは時間稼ぎの意図を持っている。 逆を言えばアークの最終的な目的達成はフィクサードを単純に撃破せしめ、山門を突破する事のみに非ず。突破した上で梅泉の目的自体を挫かねばならぬのだから、この仕事が一筋縄で行こう筈も無い。 ――硬質の音が夜に散る。 (チッ――予想以上に硬いッ) 爆発的な速力を武器に飛び出した朔の『斬劇』がこれを迎撃したクロスイージスの装甲に止められた。 無論、彼女の攻撃力をもってすればこれは確かな有効打になっている。だが、敵を即座に打ち倒せるものになったかどうかと言えば――彼女の感じた『硬さ』がかなりの邪魔をしている。 「喜ばしい事だ! 君達『も』十分に戦(や)ってくれる!」 「成る程、任務に合わせてくるのは貴方達も同じでしょうね――!」 セインディールの青みがかった銀光が敵の大盾へと食い込んでいた。堅牢なクロスイージスを盾に出し、まず敵の勢いを食い止める――梅泉派の戦術も急ぐリベリスタに対して遅延で徹底している。山門をくぐれるのは同時に三人が精々。つまり、近接攻撃が敵を追い詰められるのは前の三人だけである。彼等が前衛・後衛をローテーションする事で長期戦に引き込まんとしている事は初手合わせだけで十分に分かる事実である。 (さて、如何にしてこの場を突破しましょうか) 彼等の背後にはあの一菱梅泉が残っている。単純事実がリセリアを一層緊迫させているのだ。 一方のリベリスタ側は少なくとも継戦能力に関しては梅泉派を上回っている。 「えーと、防御は任せるよ!」 「任された。『一発も通さない』」 その最大の理由には頼もしく言葉を発した快の背中に声を掛けた寿々貴の存在こそが挙げられるだろう。 「そう聞くと俄然頑張らないとって気にはなるよねぇ!」 寿々貴は敵味方合わせて都合十八人の中で唯一の専門職(ホーリーメイガス)である。同じく快がカバーを見せる雷音も天使の歌による回復支援能力を持ち合わせてはいるが、安定感という意味では当然寿々貴に軍配が上がる。雷音の存在は、支援役と言うよりも『指揮者』の側面でより大きくなるのだが。回復能力という意味では専任では無いがツァインの存在もある。彼は堅牢な防御力をも持ち合わせるから緊急時のカバー役としては最適だろう。 何れにしてもリベリスタ側は寿々貴、雷音の二人全体回復役と緊急要員にツァインを持っている。 クロスイージスやインヤンマスターは居るとはいえ、梅泉派がそれを持ち合わせないのは……性格か。 (……でも、現時点で結構厄介なのだ) 雷音は冷静に戦局を見つめ、その結論を打ち出した。 リベリスタ側は段下を余儀なくされる戦闘で不利を得ている。寿々貴による翼の加護は彼等の不利を一定に緩和する事に成功していたが、それでも完全では無い。 「強いだ何だは今更先刻承知、当たり前!」 彼我の理解は双方に恩恵をもたらすものだ。 敵がアークを難敵と看做しているのと同じく、彩歌もそれは『想定内』。 戦闘的論理演算を得手とするプロアデプトの灰色の頭脳が、瞬時に局面の最適解を弾き出した。 (ここは速攻重視――攻めるのみ――!) 立ち上がりの遅さは相手の思うツボ。敵が引き伸ばしたいのならば、その上を行くまでだ。 そう判断した彼女は構えた論理演算機甲(オルガノン)より、強烈無比に増幅された精神波を撃ち出した。 「一応聞くけど、梅泉からのオーダーは『一人も通すな』でいいのかしら? ま、簡単に通してくれるとは思ってないけど。通らないとは言わないわよ」 純粋威力こそ然したるものではないが、彩歌のこの判断と攻勢が敵陣を確かに動揺させた。 「――続いて、これで――!」 ならばこの好機に更に敵を撹乱せんと雷音が閃光の塊を投げ放つ。 閃光は取りついた味方前衛を紙一重で外し、敵陣の中心で炸裂する。 この効果は全てに万全に発揮された訳では無いが、敵の体勢を乱す程度の効果はあった。 「そちらも簡単に通らせる心算は無かろうが、その腕前……我が剣にて確かめよう!」 若干の乱れを見せた敵陣に拓真の放った弾幕が襲い掛かる。一線のデュランダルの放つその一撃は弾幕でありながら牽制以上の威力を持っている。彼の技量が織り成す精密性は少なからず敵陣に打撃を与えていた。とは言え、射線の関係で全員を叩けた訳では無い。敵クロスイージスは強力に自己を回復し、敵インヤンマスターが傷付いた仲間に符術による賦活をかけている。 「けっ――ちまちま面倒臭ェ。ちぃっとばかし『戦争』しようか、剣林よォ」 敵の動きに対して苛烈なる踏み込みを見せたのは銀次だ。 「兎に角、門を突破すりゃいいんだろ? 『巻き込まれ』んなよ――!」 味方の作り出した隙を生かして踏み込んだ彼の武技が八つの首を持つ黒大蛇のオーラで周囲を薙ぐ。 「――畳みかけるぜ!」 一声は戦場を荒らす銀次なる戦神の怒号の如く。 ……例え巻き込まないように配慮はしても、この一撃の範囲は余りにも広い。それでも、そこはそれ。リベリスタの中でも特に身のこなしに優れた前衛の朔とリセリアはこれを上手く外している。 幾らかの計算違いはあったが大事までには到らず。一方の敵陣は攻勢を受け相応に傷んでいる。 (……だが、崩し切るには、もう一歩!) 拓真の見立ては見事な正確性を持っていた。リベリスタ側の打撃をフロントで強かに受けたクロスイージスはダメージを蓄積させているが、敵もさるもの。防御を重視した敵は紙一重で致命傷を外していた。リベリスタ側のプランは早期に敵を減らし、リセリアと朔の二人、次いで雷音を境内に通すというものだ。 「……いや、二、三歩か」 不敵な笑みを浮かべた拓真は迸る戦士の運命が何もリベリスタだけに味方するものでは無い事を知っている。 そして今夜の敵が自分達と同じ運命を背負う者である事を厭うていない。 剣客の高みは、同等の敵を以って初めて拓かれる道である。彼等が目の前に立ち塞がるというのならば。 「――砥石と、するまで」 梅泉派の反撃がリベリスタ達を襲う。 「……落ちろッ!」 「おっと……!」 後方より加速し、姿を掻き消した軽剣士(ソードミラージュ)の瞬撃殺を快の『左腕』が弾いて止めた。 敵側からすれば、リベリスタ達の要である寿々貴を狙うのは当然のセオリー。ならば、リベリスタ側がこれを予期して食い止めるのも又、当然のセオリーである。 「残念ながら、まだまだ軽い!」 刃を押し返す快の膂力に敵が怯む。 「俺を倒したければ――当の梅泉でも連れて来いッ!」 裂帛の気合を帯びた一喝が、敵の威圧を振り払った。 ならば、と放たれたスターサジタリーによる弾幕がリベリスタ達に襲い掛かった。 高低の高を取る敵側は容赦無く弾幕の嵐をリベリスタ達にぶつけてくる。だが、三重にダメージを受けた快はそれでも背後の二人に一撃をも通さず。傷付きながらも、膝を突く事もしなかった。 敵の技量は確かに快に勝る。しかし、彼の防御は最初からそれを見越している。 倒れなければ、倒させなければ――その勝負は彼の勝ちになる。 そして彼の奮迅を間近で見れば、意気に感じない筈も無いのがその背に庇われた寿々貴である。 「これだけの局面だ……そりゃ少しはマジにもなるさ」 嘯く言葉は冗句めいている。しかし、彼女は言うまでも無くこの瞬間に真摯であろう。 『全ての救い』とも称される大魔術――デウス・エクス・マキナは高位のホーリーメイガスにのみ許された戦場の鬼札の一つである。古代ギリシアの演出手法が余りにも容易く人を絶望から救い上げるのと同じように。彼女の呼び掛けに応えた『機械仕掛けの神』はリベリスタ達の受けた手傷を強力かつ急速に塞いでいた。 「こっちはこっちで、やれる事をやるのみだね!」 確かに彼女は純粋に敵と食い合う程の戦闘力を持ち合わせていない。この場に居る中では最も脆弱な一人と言えるだろう。だが、彼女にしか出来ない事は――時に戦いの趨勢さえ塗り替える大事でもある。 雷音の指揮を受けながら、リベリスタ達は戦いを続ける。 「チッ……!」 敵の一撃を受けた銀次が後退を余儀なくされた。 「スペースを埋めるのだ!」 「抜かせるかよ!」 雷音の言葉を受け、即座にその隙をカバーしたのはツァインだった。 銀色の甲冑の上に英霊の誇り(せいがいとうい)なる外套を纏っている。騎士の矜持をその全身に漲らせる彼は、続けて繰り出された敵デュランダルの全力の一撃にあくまで果敢に立ち向かった。 (感じろ。癖で呼吸で匂いで空気で。挙動を見るより尚早く――!) 彼が見たあの夜の老剣士は『きっとそうしていた筈だった』。 「ここで倒れる訳には――いかないんだよ!」 この先に――梅泉が居るのならば。かつて見た剣士・桜鶴に連なる男が居るならば。 猛烈なまでの威力を構えた魔力盾が減衰する。食い止めて尚、その一撃はツァインの体を叩き潰さんと荒れ狂っていたが――その圧力さえ、彼という男を折るには役者不足。 見えた、と表現すれば間違いは無いのかも知れない。 「――おおおおおおおおお!」 目を見開いて吠えたツァインのブロードソードが目前の敵を十字に裂いた。 完璧なタイミングで放たれたカウンターに敵が倒れかかり――辛うじて運命を燃やしてその体勢を立て直す。 確かな好機を見逃さない。 「いよいよ――燃えるじゃねぇか。若い奴の気合を見れば、よ」 虎鐵の抜く斬魔・獅子護兼久は大尺の黒刀だ。夜よりも深い暗黒を纏った彼の刀はその構えより、禍々しい程に危険なオーラを発して、隠そうともしていない。 「ブチ抜くのが俺の仕事だ」 短い一言は圧倒的な自負を感じさせるもの。 事、破壊力において――虎鐵を超えるリベリスタ等、殆ど居るまい。抜き身の大黒刀より放たれた黒気は彼にとって『小技』である。されど彼の『小技』は他人の『必殺』と同等だ。 声も無く、ツァインに斬られたフィクサードが今度こそ吹き飛ばされた。 「――さァて、次はどいつだ?」 とって置きはまだまだだ。虎鐵はその刃を梅泉の為に、百虎の為に研ぎ澄ませている。 ●山寺II 血風舞う山寺の境内に二人の美しい女が降り立った。 否、それは降り立ったと言う程――優雅なものでも、穏やかなものでも無い。 「乱入失礼――ッ!」 空中より落下するように猛烈に加速。衝撃波と共に梅泉と和尚の交戦に割り込んだのはリセリア。 「『閃刃斬魔』、推して参る」 漸く吐き出す事が出来た『決まり文句』と共に彼に全力の斬撃を浴びせかけたのが朔である。 「早かったでは無いか」 「お久しぶりですね、『死牡丹』一菱梅泉」 「生憎と、私は美食家(グルメ)でね。彼等(ぜんさい)では足りないのだ」 「ふん、囀りよるわ! だが、それでこそ、主等よ」 片目は未だに閉じたまま。目前に立つ和尚より視線を外さず、二人に言葉を投げた梅泉は気安い。 瞬間の攻防は梅泉の着物を斬り散らし、その肌から鮮血を零させていた。彼の左手の妖刀から伸びた赤いオーラが零れた血を啜り上げ、しゃんしゃんと音を立てている。 (相変わらずの腕前。ですが……!) リセリアの目は確かに攻防の瞬間、梅泉の動きを捉えていた。 セインディールの切っ先が届いたのは伊達でも酔狂では無い。偶然でも運でも無い。唯の彼女の『練達』だ。 そしてそれは朔にしても同じ事。 「……こりゃ命拾いをしたかの?」 「遅くなりました。彼の妖刀が貴方を狙っています。ここは私達に任せ、出来れば距離を」 「成る程のう。しかし……そう簡単な相手では無いぞ」 「知っている。御坊と同じく、私達もその男とは手合わせ済みだ」 それは承知だ。頷いたリセリア、朔の見た和尚は少なからず傷付いていた。だが、一対一で梅泉を相手にして『多少傷付いた』程度で済ませている彼の実力はむしろ驚嘆に値するものと言えるだろう。 「主等は、あくまでわしを邪魔立てするのであろうな。それは主等の矜持が故か?」 「とんでもない」 『大仰なる構え』を取った梅泉に朔は頭を振る。 「『私は万華鏡の優秀さにはほとほと困り果てている』」 「ほう?」 「御坊には悪いが、刀が仕上がった君と戦ってみたかった。 当代切っての邪剣使いと称される君の全力と、君の至高とぶつかり合ってみたかったとも。 私の『心』を計るならば、むしろ其方だ。この阻止は私の『仕事』に他ならない」 「あの娘、言ってくれるわい」と愚痴る和尚にリセリアが苦笑した。肝心の朔は頓着していない。 「私は『待て』が出来る程行儀良くは出来ていない。 そして、これぞと決めた相手とは全力でやる事に決めている。拒否されても、そうさせる。つまり決定事項だ。 ……その右目、見えぬという訳ではあるまい?」 朔の言葉に梅泉はまさに歓喜した。 「成る程、主は気に入ったぞ!」 賞賛は掛け値無しの本音だろう。感情を表に出した彼は彼女の指摘に初めてその右目を開いた。 ほぼ同時に『左手に構えていた妖刀に右手を添える』。それだけで彼から生じる圧力が倍にも膨れ上がった。 「そうこなくてはな」 「……両目に、両手持ち! これが、本当の『死牡丹』という訳ですか……!」 朔とリセリアも又、今一度その気を引き締める。 戦意旺盛なる朔と、時を稼ぎたいリセリア。対する梅泉は『動かない』。 ならば、朔は――全力を賭して仕掛けるのみだ! 「君は私に似ている。正義も悪も些事。唯、この死闘こそが生きる意味だろう!」 「然り。主は面白き、おなごよな!」 「惚れたら――死ぬぞ?」 境内の土を跳ね上げた朔が葬刀魔喰と軽口を踊るように閃かせた。 空間に無数に咲き誇る華美にして執念深き斬劇を、梅泉の剛剣――妖刀が弾き、跳ね上げる。「まだまだッ!」と声を発した朔のスピードが更に爆発し、彼の着流しをすぐさまに赤く染めた。 (刃桐殿には一菱流の何たるかを見せていただきました、が……) 哄笑した梅泉は、果たして――守りに入ったリセリアの予感を肯定していた。 敵は二人。纏めて片付ける大技を仕掛けるにはロスは多かろう。されど、彼は梅泉だ。如何に体力、気力を減らしたとしても『血蛭地獄』は彼を無限に賦活する、ならば。 (少数で突破したのは――読み違えたか……ッ!) リセリアは瞬時にそれを理解したが、少々遅い。 前回の戦いで苦戦を強いられた梅泉は多数の敵を前にして隙の大きい『裏五光』の選択を嫌った。 されど、敵が二、三人ならば受け切り放ち、そして邪魔を振り切るという判断も当然だったのだろう。戦術の基本は各個撃破である。長く時間をかければリベリスタの増援が訪れるは必然。ならば……応えるべくはいきなりの全力である。有無を言わせぬ選択。確かに伝家の宝刀を抜くならば、これ以上の瞬間が無い。 朔が煽るまでも無く、梅泉の結論はそこにあったのだ。 大上段の構えより邪光を迸らせる梅泉に、二人のリベリスタが目を見開く。 刹那後に突き刺さる破滅の衝撃は、世界を置き去りに間合いを駆けるまさに父よりも鋭き五光の如しであった。 ●決着 (少しでも隙があれば、癖が見えれば……私が何かの役に立てるなら――いくらでも!) 消耗戦の様相を呈した山門で寿々貴がその力を尽くす。 「支えるのだ。まだ、ボク達はまだまだいける。押し通れる……!」 雷音の声は勝利の女神の神託のように戦場に勝機を与え続けている。 「城山の勝利の為に、叩き斬らせてもらうぜ。テメェ等も、テメェ等の親分も!」 銀次はあくまで苛烈に獰猛に敵の喉笛を狙い続け、 「時間稼ぎ? アホ抜かせ、ぶっ倒して合流するに決まってんだろうが! いくぞオラァ!」 噛みつくように目の前に敵に仕掛けるツァインは一歩たりともその場を退く心算が無い。 「私は器用な性質(たち)なのよ」 彩歌の存在はリベリスタ達の勢いを気力の賦活で支え続け、 「スクラム勝負といこうぜ、剣林!」 雷音の式符・鴉と共にリセリアと朔の突破に一役買った快は度重なるダメージにも意気軒昂を失っていなかった。 「山門のも、しっかり数減らしておかねぇとな」 「無論。敵は梅泉だけに非ず。ここを任された以上は――それが俺の仕事です」 攻撃を受け難いロケーションが幸いし、圧倒的な威力を振るう虎鐵も、それに応えた拓真も当初からの勢いを減じていない。 「このままなら……!」 このままなら、確かに突破出来る。 リベリスタ側もダメージが無い訳では無いが、戦局は明らかだ。 雷音の指揮に応えるリベリスタ達は、互いに戦力を減らしながらも確かに山門を押していた。 だが、雷音がすぐにそこを離れるには少し難しい状況があったのは確かだった。彼女は戦いの鍵の一つである。 「――はッ!」 幾度目か、仕掛けた拓真の刃が今度こそ敵のクロスイージスを打ち倒した。 そこでピィ、と甲高い音が鳴る。 「……指笛?」 雷音の呟きと山門のフィクサードが退いたのはほぼ同時だった。 状況から考えれば指笛が梅泉からの合図であった事は想像に難くない。 不吉な予感を覚えながらも、予想外の動きを追いかけるリベリスタ達。 そして彼等が雪崩れ込んだ境内には、倒れた二人の仲間と血染めの和尚の姿があった。 「今、ボクが癒すのだ――!」 三者とも息がある事を確認した雷音の行動は早かった。 二人の仲間は言うに及ばず、和尚とてこの世界と人々を古くから守護してきた存在だ。 ――――♪ 『三人のリベリスタ』の傷に雷音の奏でる清浄なる天使の歌が降り注いだ。 梅泉が配下を退かせたという事は目的の阻止は失敗しているという事なのだろうが…… (良かった、のだ……) それでも、心優しい少女は少なからず安堵の気持ちを抑えずにはいられなかった。 事件はリベリスタの介入で最悪の事態だけは免れたと言えるから。 「ふん、主等は遅かったな?」 雷音を止める事もせず、駆けつけた新手を鼻で笑う梅泉の着物は度重なる打撃・斬撃に破れている。 だが、彼の全身には当初と変わらない――当初以上の力が漲っていた。 リセリア、朔の忠告を受けた和尚は唯一距離を取っていたのが幸いしたのだ。『裏五光』の直撃を避けた彼は、リベリスタに救われた後、己を囮に二人の『トドメ』は免れさせていたのだ。 梅泉派の残戦力は四人。彼方五人のフィクサード、此方八人のリベリスタ。 梅泉を倒すには十全な戦力が必要だ。『血蛭・真打』の存在を思えばいよいよ勝機は薄いか。 「……」 凄絶なまでの梅泉に寿々貴がごくりと息を呑む。 「もう、十分って訳?」 口元を歪めた彩歌が皮肉に問う。 「ここからは、横槍入れさせてもらうぜ……!」 「よぉ、梅泉。今度は俺の修行に付き合って貰おうか――命賭けのな」 それでもツァインは、虎鐵は、あくまでその戦意を緩めていない。 「相も変わらず、殺す為だけに長じた殺人剣か」 静かなる鬼気を纏った拓真がその両刀で構えを取った。 「だが、此方もまた、以前から何も変わっていない訳ではない……行くぞ!」 地面を蹴り上げた拓真の姿が常人の目に掻き消える。 閃いた今夜初めての――正真正銘の120%が、梅泉の両手持ちの妖刀と噛み合った。 二者は鍔迫り合いで顔を寄せる。血管を浮かせ、歯を剥き出しにした梅泉の両目は開いたまま。 「……押し切る!」 「抜かせ、若造ッ――!」 拓真が一瞬、梅泉を押し込んだ。ほぼ同時に梅泉の蹴りが彼の腹部に突き刺さる。 くぐもった声と共に拓真の体勢が乱れた。 勢いを殺さんと後方に跳んだ梅泉は片手を突いて、姿勢を整えリベリスタ達の顔を見回している。 「……逃がすかよ!」 「戯けめ。それは主等の台詞では無いわ!」 追撃を仕掛け、梅泉目掛けて刃を振り下ろしたツァインの刃が跳躍の影だけを切り裂いた。 「こっちも忘れないで貰おうか!」 「忘れて等、おらんわ」 「――――!」 空振り。宙空より閃いた返す刃に反応出来なかった虎鐵を間一髪で快が押し倒した。 「助かったぜ」 「とんでもない話だよ」 快の視野の広さが危機を救った。彼は誇るでも無く肩を竦める。 (……チッ、テメェにビビッて百虎に勝てるかよ!) だが、内心の悪態と裏腹に首筋を掠めた死の影は一瞬遅れて虎鐵の動悸を早鐘のように鳴らしている。 畏れは無い。だが、一流の戦士であるが故に虎鐵はその紙一重を『理解してしまう』。 「主等の刃は背負いが多い程に曇りそうでな。それは退屈じゃ。わしの意に沿わぬ」 梅泉は内心だけで「それにわしもまだこの刀を使いこなせぬ」と言葉を付け足した。 この場での続行は互いに『ベスト』足り得ない。リベリスタにせよ、自身にせよだ。 そんなものは、彼が――一菱梅泉が焦がれて止まない最高の戦いには成り得ない。 「今宵は終いじゃ」 「今宵は……?」 傲然と言い放った梅泉に快が言った。 守護神と呼ばれたリベリスタは、あくまでも不敵に。 剣林が認めじと躍起になる『真実』を呆気無く口にしてみせた。 「正直な事を言うと……アークはもう、剣林は眼中にないよ。やらなきゃいけないことが、ソレ以上の脅威が多すぎてね」 「……」 「『剣林なんかで躓いている時間無いんだ』。だから、俺達は絶対に負けない。邪魔もさせないさ」 「はははははははははははははは!」 挑発めいた快の言葉に梅泉は高笑った。 彼は全くその言葉を意に介していない。代紋を侮辱された、とすら思っていないのだろう。 「然り、然り。大変結構、大層愉快。正直を言えばの、わしも百虎の企てなぞには興味は無いのじゃ」 「大した番頭だ」 「丁稚坊主に言われとう無いわ!」 快との丁々発止のやり取りに梅泉は実に満足そうである。 忠誠心の欠片も無い邪剣士、そしてフィクサード達は月夜にふわと浮かび上がる。 「百虎の企てはくだらぬ。但し、そこには――舞台があろう? 我等の戦いを彩る程度の危機もあろう。 わしは主等を理解しておる。主等は、守らなければならぬものが大きい程に、強くなる。 わしの期待に応え――恐らくは、わしの期待を超える程に、な。わしは、偏にその時ばかりに期待しておるのじゃ」 その武力と研ぎ澄まし、その武威を己が最高潮まで高めながら。一菱梅泉は待っていると語る。 「わしを斬れ」 「そう遠くはない時に俺達と剣を交わす事になる……それが、決着か」 「さてな、賽は振ってみなければそもそも分からぬ」 「成る程、確かにその通りだ」 だが、賽(てんめい)はその通りでも尽くすべき人事は山とあろう。 敵が己を研ぐならば、新城拓真はそれ以上にも、誰よりも鋭利でなければならぬ。 月夜の群雲は、純粋なる人斬りだ。彼の望みは容易く、同時に至上の難題なのだから。 「最悪の相手だね、こりゃ」 「最悪の相手なのよ、残念ながら。……あっちこっちで色んな奴に言ってる気もするけどね」 寿々貴の言葉に彩歌が苦笑した。 (未練さえ無く……? 嘘吐きめ、羨んだのは……どちらだったか……) まるで似ていないのに血は争えない。 彼の心よりの期待をその身に受けた時、確かにツァイン・ウォーレスは皮肉な歌を思い出していた。 痛烈なる想いが彼の眼光に乗る。射抜いた影は愉快気に肩を揺するばかり。 「アンタはその剣閃の向こうに何を見る、梅泉……!」 瞼の裏の桜鶴も、今ここに在る梅泉も、空の月も。 今はまだ――騎士の問いに答える事は無いだろう。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||

















