
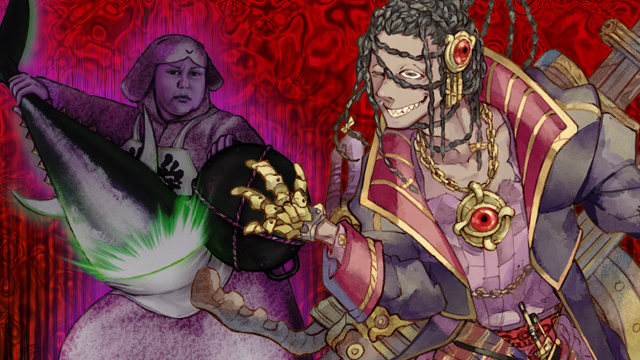

<混沌組曲・急>Balletto op.90 A' paura

|
● 『福音の指揮者』ケイオス・“コンダクター”・カントーリオ総指揮、混沌組曲事件の混乱は未だ醒め遣らぬ。けれども指揮者はタクトを下ろさない。クライマックスは此れからだ、とばかりに跳ね上げられたタクトは新しい場所を示したのだ。 芸術家であるケイオスは、自身の公演を劇的に彩る事に余念がない。アーク本部には、彼と同じく厳かな歪夜十三使徒の一人であった『The Living Mystery』ジャック・ザ・リッパーの骨が眠っているのだ。 『伝説』を打ち倒した『箱舟』を、蘇った『伝説』にて討ち滅ぼす――。 ドラマティックを望む指揮者に、これ以上の展開があるだろうか。 「おーおー、賑やかにやってんなぁ」 「遊んでる暇は、」 「は、ゾーエ。お前俺が遊んでる様に見えんのか」 ピッコロを手に神経質な調子で咎めるゾーエ・エピファーニをバレット・”パフォーマー”・バレンティーノは鼻で笑った。ケイオスの様にシングルアクションで千を起こす、と言う訳には流石に行かず、操れる限界も及ばないが――それでも今バレットが『楽器』とする死者の数は四桁を下らない。 彼は第一バイオリン。オーケストラの花形が、ここで華々しく鳴り響かせずして何とする。自分が指揮者の望んだタイミングを外す、等という事は意図的でなければありえない。加えてそれは、アドリブの内として容認され得る時のみだ。この状況での『ズレ』を指揮者は容認すまい。不協和音は程々に、だ。 バレットはシアー・”シンガー”・シカリーの様にケイオス個人に傾倒している訳ではなく、また楽団に忠誠を捧げている訳ではないが、それでも現状、自身の望む状況へと導いてくれる確率が最も高いのはこの集団なのだ。 死は間近に迫り来る恐怖でなければならない。 奪われる生に怯え足掻く瞬間がなければならない。 多数の生と死がぶつかり合って立てる音こそ至上。 自身を疎むモーゼス・“インディゲーター”・マカライネンもバレットは別に嫌いではないのだが、彼は少々効率や成果を気にしすぎる。無論それは悪い事ではない。明らかに見合わないリスクを選び、より多いリターンを逃すのは愚かだろう。けれど、効率だけでは自分にはあまりにも呆気なく物足りない。 だからこそ、バレットは『しぶとい』アークをこれ以上なく歓迎する。ポーランドの時の様に濁流に巻き込まれながら、逆らい生き抜こうとするその姿が飲まれるその瞬間は――どれだけの歓喜か。 それは有象無象であろうがアークであろうが、楽団員であろうが大差はない。誰も別に嫌ってはいないが、同時に誰が死のうがその瞬間は『音楽』に過ぎない。 フェリチャーノ、ゼベティ、ロマーニにミオーネ、チェレーレ、フェレス、フラミーニア、ネーロにヴィオーラ、チェーザレ、エルヴィーノ……見知った彼らが死に際に奏でた音は果たしてどんなものであったのか。聴く事が叶わなかったのは少々残念ではあった! 神経質な我らが指揮者殿にとっては苛立たしい出来事だろうが、予想外もイベントの花。 群れを操りながら、その内の一人に向けて笑う。死人の事など基本すぐに忘れるバレットではあるが、『三高平の肝っ玉母さん』丸田 富子(BNE001946)――生前を知る者ならば、別人に思える程に表情を無くしたその姿――の事は未だ記憶に新しい。 鍛え抜いた男が死にたくないと悲鳴を上げるのを幾度聞いた事か、今際に生にしがみ付こうとする断末魔を幾度踏み躙った事か。生と死の境目で生きていた様な存在であっても、間近に迫った『死』には大方が絶望する。最後の最期まで生に満ちた音は久々であった。 正直に言えば、大将ほどに『箱舟』に興味を持っている訳ではなく、常と変わらぬ、それでも愛すべき生と死の『公演』の一つだと思っていたけれども。 こんなちっぽけな島国が、かのポーランドよりも何倍も良い音を奏でてくれるとは! 「なあ。お前みたいなのが何人いるんだ? 山程いるのか? 全部死ねばいいのにな!」 その手で『子供』の生を守り抜いた彼女から、答えは当然返らない。人形遊びをする可愛げは彼にはない。 迫り来る『死』を厳然と身を以って現すがいい。返らぬ日々を、帰らぬ人を。 冷たい肌で知らしめよ、不帰の恐怖を。 生の模倣ではなく、死の体現を。 水底から死者が這い上がる。 二月の凍れる冷たい夜に、顔を青褪めさせた彼らはそれでも決して怯まない。 凍える体温も溺れる呼吸(いき)も、既に彼らは失せてしまった。 冷え冷えとした空気に息を吐きながら、生から死への転落の熱望と狂気で染めた声で、バレットは大きく笑った。 「Con passioneと行こうじゃねーか、ゾンビども!」 ● 「はいはい、緊急ですねとは言わなくとも分かって頂けると思いますが言っておきます、皆さんのお口の恋人断頭台ギロチンです」 いつもの通りに薄っすら笑った『スピーカー内臓』断頭台・ギロチン(nBNE000215)は、一度息を吸って話し始めた。 「まず。ケイオスの軍勢の出現はアシュレイさんの結界によって本部の水際で食い止められています。が、完璧な守備とは行きません。本部に向けて、各所から死者が迫っているのはご存知の通りです」 街に灯る明かりは、生者の為。 それが今は死者に蹂躙されかけている。 「皆さんに向かって頂きたいのは三高平湖付近。そこに、バレット・”パフォーマー”・バレンティーノの出現が観測されました」 映像は未来視ではない。現在の出来事を映している。周囲一帯を埋め尽くす死者の群れ。 濁った瞳の男は、確かに笑った様子であった。 「ご覧の通り、死者の数は軽く千を超えています。この死者達を中央地区まで招き入れる訳にはいかない。一箇所崩れれば、彼らネクロマンサーはそこから加速度的に勢力を伸ばします」 被害は甚大、されど勝利、とは中々行かない。被害が増えれば増える程、楽団は勢力を増すのだから。 「バレットを直接仕留められれば勿論簡単です。けれど、真正直に大勢が彼に向かっても叩き落されて死人の群に加えられる。じわじわと死に飲み込まれて終わりです」 皆を見詰めて、ギロチンは言葉を紡ぐ。 「あと」 一度言葉を止めた。笑みはいつの間にか、強張っている。 「……。……バレットは前回、ぼくらの仲間を連れて帰っています。丸田 富子さん。彼女も間違いなくこの死者の群れの中にいる。間違いなくアークの精鋭の一人でした。……決して、油断しないようにして下さい。言うまでもありませんが、あれは、……生きている頃の富子さんとは、違うものです」 だけれど。彼女を『本当』の状態に戻せる機会には違いない。 だから、叶うならそうしてくれ、と、フォーチュナは首を振り――。もう一度前を向いた。 「――ぼくらは終わる訳にはいかない。死者を削り、戦力を殺ぎ、『パフォーマー』の演奏を止めて下さい。……皆さんならできると信じています。嘘じゃないですよ」 笑みはだいぶ薄れたけれども、視線はいつもと同じく何処を見ているのか分からないけれども。 ギロチンはゆっくり、頭を下げた。 「生きて、またお会いしましょう。ぼくは嘘吐きですけど、……これはどうか、本当に」 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:黒歌鳥 | ||||
| ■難易度:HARD | ■ イベントシナリオ | |||
| ■参加人数制限: なし | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2013年03月16日(土)23:35 |
||
|
||||
|
||||
|
●0 歪められた死が夜に這い淀んだ。 リベリスタの街三高平に引かれた譜面の五線の上で、死を響もし生を蹂躙する音が奏でられる。 今宵の演目は『福音の指揮者』ケイオス・“コンダクター”・カントーリオによる終わらない夜。 さあ――死者の夜の幕開けだ。 ●1-1 夜が、闇が、街を覆う。 常日頃ならば静寂と安寧の眠りに満たされる時間だが、今日ばかりは酷く酷く騒がしい。 「この街には笑い声が似合うんだよね」 砕かれる街灯。降り注ぐガラスの雨の中を翔けて、比翼子は赤い目を細めた。 視界に映るのは、人。人。人。祭りか何かと見紛うばかりの人の群れは、けれど誰も息をしていないのだ。そこに彼女の求める笑い声はない。喜びはない。 三高平。命懸けで日々戦うアークのリベリスタの『帰る場所』であるここには異質な存在。 「きみたちは……ちょっとだけやかましいぜ」 足に構えた刃が、複数の死者を切り裂いた。 流れる血の色は同じでも、比翼子に跳ね返るそれは――冷え切っている。 「何という敵の数だ……」 雪佳から漏れた声は、恐怖のそれではない。僅かばかりの感嘆を含んだ事実を示しただけである。 中央地区への水際、外周に当たるこの位置に存在するリベリスタの数は決して少なくはない。増援の半数近くもここで死者の進軍阻止、及び支援を行っていた。 それでも、死者の群れは数を圧倒する。死ねないリベリスタと異なり、最後まで使い潰される死者の数は軽く四倍以上。 雪佳が抜き放ったのは百叢薙剣。百の敵を薙いだと伝わる家宝。それが真実かどうか、今や誰にも知る術はなかった。けれども、雪佳が頼りにするのは剣の性能ではない。 「この場に必要なのは――窮状においても、臆さずに果敢に立ち向かう意思の力だ!」 穢れなく煌く刃が、夜に踊った。 「微力ながら、僕もできる事を頑張ります」 握った魔力杖を中心として、春人の体に魔力が巡る。癒す為に、傷ついた体を守る為に。 「誰も死なせないように!」 周囲に固まるのは【なのはな荘】の名に集った仲間たち。誰一人として喪わせない。死者の群になど加えさせない。この場に存在するリベリスタ、叶う限りへと歌を届かせんと春人は音を奏でる。 死者とは違う、生の歌。 「皆でお家を守るのです」 小さな体に大きな魔術書を背負ったとよが呟いた。目の前に広がるのは死者の海。遠く遠く、遥か遠くまで続くそれは、彼女の小さな体では果てが見えない程。 だとしても、逃げたりしない。とよの家はここなのだ。それに、彼女は一人じゃない。 「なのはな荘を守るため、しょうがないですねー」 ポニーテールを揺らしながらダルそうに呟いた小梢が、ルーメリアの前に立ちはだかり死体の腕の一撃を受け流す。びしゃりびしゃり。肉が飛んで満ちる血の臭いは、彼女の好む香りとは違いすぎて溜息も出ようと言うもの。 しかも一撃二撃受けたからと言って消える訳でもない。溢れんばかりに存在するのだ。 大きなカレー皿で受け流し損ねた所で、小梢の頑丈な体には致命傷にはなりえないが、それでも重ね続けられればうっとおしいに違いはない。全く、早く帰ってカレーが食べたい。 「ルメ達の任務はここを食い止めること……!」 小梢に向けて、仲間に向けてルーメリアが叫んだ。遠い海の色の瞳が、前を向く。巡る魔力は体力を保ち続ける為に、ルーメリアは春人と合わせて回復を唱え続ける。 「必ず平和な三高平を取り戻す!」 ルーメリアの声を聞きながら、前へと突っ込んだマーガレットがダンスを踊る。赤で彩る刃の舞。何度かの攻撃を重ねられていた死体が、切り刻まれて肉塊となって地に落ちた。 「今度こそ、安らかにおやすみ」 切るのは十字。悼むのに十分な時間はないけれど、弄ばれた『死』へと送るささやかな祈り。 死体に殴り倒されたとして、マーガレットの目の鋭さは消えやしない。 先なんて見えない。守りきれるのかも分からない。余りに数が膨大すぎる。 増援も加えてここに位置するのは134名。対する死体は600余り。 「でも諦めちゃダメ……」 ぎゅっと、ルーメリアは拳を握る。仲間が『頭』を潰すか、或いは敵の群れを疲弊させるか、ともかくこれ以上の進撃をさせない為には諦めなど投げ捨てなければならない。 ちらりと、マーガレットがそちらを振り向いた。 「ルーメリアの癒し、期待しているからね」 とよの放ったフレアバーストが、赤々と燃える。久嶺と零児は、仲間の中心近くに位置してダメージを与えた死体に追撃を重ねんとしていた。 「先が見えないわ、本当」 「だとしても、僕もリベリスタの一人として……いえ、なのはな荘の一員としてなんとしても三高平を守ってみせるのです! 大体真ん中くらいで!」 「うるさい」 「あっ久嶺さん痛い! 蹴らないで!」 平均を愛する零児を横目に、久嶺が構えるのはBHF。 「諦めるつもりはないわよ……全部残らずぶっ潰す、覚悟なさい!」 どんな運命でも打ち破ってみせる。決意を込めた弾丸が、死体の頭を弾け飛ばした。尚も動こうとする死体を切り裂く銀の光。放ったのは、輪。 「全部ばーん! ってぶった切っちゃうのです!」 親玉――指揮者であるケイオスを防ぎに向かった仲間に付いて行くには、些か実力が足りない。だからこそ、輪はこちらで他の仲間と共に死体を食い止める。速度は煌く刃の威力を増し、赤を散らした。 大好きな虫さんはいないけれど、そこに容赦は必要ない。 別の死体に、零児のフィンガーバレットの弾丸が重ねられた。 「ここで負けたら、帰るべき場所も人もなくなってしまう」 他の仲間より半身程度高い位置から見下ろしながら、紅葉は呟く。光景だけ見れば、見慣れた市内だ。生きる人が歩く、リベリスタの平穏の地である三高平だ。 例え今死者がそこに蔓延るとしても――生きる為に、守る為に、負ける訳にはいかないのだ。 「さあ、今宵の演目は葬送曲。哀れな亡者を黄泉へと還しましょうか!」 奏でる音。騒々しい死者の音ではなく、編み上げられた黒鎖の音。 乗り越えてきた死者を防ぐのは、へクスの役割。 「さぁ、砕いて見せて下さい。ねじ伏せて見せて下さい。この絶対鉄壁を!!」 構えるのは鉄鍍の盾扉。小柄な体に大きな盾。浮き上がった紅葉を守る為に、掲げるように持ったそれ。仲間と共に、見慣れた景色で、見慣れない戦い。 だとしても、ヘクスのやる事は何も変わりはしない。 守るのだ。防ぐのだ。仲間を。敵の攻撃を。鉄壁の防御と回復力を以って、全て受け止めてみせよう! それを信じているから、紅葉も攻撃の手を休めはしない。最強の盾がいるのに、何を心配することがあろうか。 黒鎖に飲まれた死体に向け、香夏子の放つ紅い月。不吉の象徴、歪夜の月。擬似の月光が、血の如く死者へと降り注ぐ。 自身のか、或いは死者のか。赤に染まった香夏子に降り注ぐのは、仲間の癒し。 小梢と似て、平素はやる気の薄い香夏子ではあるが――この危機に置いて働かない訳にはいかないのだ。 不吉の赤を見ながら、与市が諦めたように小さく笑う。 「嫌な風景じゃの……こんな風景を失くしたくてわしはリベリスタになったと言うのに……」 不甲斐ない。そう呟きながらも、与市は絡繰義手・蜂羽堕を引き絞った。目に映るのは死体。死体。死体。濁った目の、空ろな人型。 的は充分、当て切れない程に存在する。 「これだけ敵がいても……どうせこの矢はあたらないわけじゃがな」 ぎちり。最適の一瞬に、絞られた矢が放たれた。星の光を宿したそれは空中で別れ、死体へと降り注ぐ。口では当たらぬとは言うが、そこに外す気はない。 例え目前の光景に心を痛めたとしても、仲間同様、与市に諦めるつもりはないのだ。 それを見ながら、礼子は微かに笑う。ネガティブを呟きながら、『先』を見据える少女の近くで胸を張る。 「さぁこい、死者共……。わしらは光ある未来を掴んでみせるのじゃよ!」 外見通り幼い少年少女が多い『なのはな荘』の中で、礼子と悪紋は重ねた年月が違った。 「ゾンビどもうじゃうじゃおるの……こ、怖くなんてないんじゃぞ!」 おばけは怖い。けれどここで怯えている訳にはいかない。それでも震える足は隠しきれない悪紋の背中を、礼子が小さな手でばしりと叩く。 「ほら、根性いれるのじゃ悪紋! このような子供達も戦っておるのじゃ、安心せい!」 「いたっ!? わかっておるわ! 我が居ればこんな烏合の衆、いちころなんじゃぞ!」 お返しとばかりに礼子をぺちぺち叩き返しながら、悪紋が唱える守護の結界は、仲間が立ち続ける為に。彼女等にとっては子供どころか孫よりも幼い少年少女らは、決して諦めてはいないのだ。 ならばそれを、自分達も信じなければなるまい。 「諦めるな、若者よ……わしが生きてきた80年間、朝日が昇らない事など1度も無かった!」 明けない夜。死者だけの夜。そんなものが続くはずはない。 「生きて帰るように尽力するのじゃ!」 礼子と悪紋の声が、死に満ちた夜に響く。 数の暴力を生かしブロックを乗り越えてくる死体の前に、春人が立つ。とよにその腕を届かせまいと。未だ大人というには遠い春人ではあるけれど、それでも更に小さな子が頑張っているのだ。 痛くとも、怖くとも、その手が全てを守るには遠くとも――できる事を。 「みんな、頑張って!」 死んでも食い止めるのではなく、生きて帰る場所を守る為に。 「敵の数は多いが……アークに所属する以上、高みの見物という訳にもいくまい」 黒いスーツに身を包み、カルベロは一つ嘯いた。ネクロマンサーは同郷ではあるが、今の彼はアークのリベリスタである。ならば止めねばなるまい。 幻想纏いは多くの者が起動させたままだが、それだけでは細かな指示は伝わり切れないだろう。 だからカルベロは、タイムロスも少ないマスターテレパスで増援を誘導する。 「全ては味方の有利の為に、ね」 目的は共に三高平を守るためであれば、その誘導に異を唱える者などいようはずもなかった。 死者に囲まれる者に癒しが降り注ぎ、息切れをする者にはインスタントチャージの支援が与えられる。 暗い夜。月が不吉に笑っている。 死者の海を越えて、死者を操る者へと向かう仲間を見送りながら、由利子は天を仰いだ。 彼らの向かう先にはこの死者の海の元凶と、『彼女』がいるのだろう。由利子と同じく、『母』であった彼女が。 「……彼女は死んで良い人じゃなかった」 振り下ろされる魔力鉄甲。聖なる力を込めた一撃に、死者の肩が砕かれる。今は彼女も、この死者と同じ。操られるだけの物となった。 その在り方に親近感を覚えていた彼女が、今や遠く。団地に住まう由利子と同じく、食堂にいつもいる存在として、三高平の帰る場所であったはずなのに。 「私は絶対に死なない。必ず生きて戻る」 大切な子供達を残して、逝けるものか。――大切な子供を守る為に散った彼女と、決意は同じ。 さようなら。紡ぐ言葉は遠く、遠く、例え目の前にいたとしても通じないのだろうけれど。 「もう一度だけ、貴女と話がしたかった」 唇を噛んだ由利子は、息を吸って前を見据える。 ああ、そう、遠い『彼女』を憂えるのは一人や二人ではなかった。 愛されていた。彼女は間違いなく愛されていたのだから。 だからこそ、彼らは眠らせねばならない。安寧を与えなければならない。 「珈琲を手向けるのは、墓を立てた後で良い」 その身に染み付いた珈琲の香りも、今や死の香りに塗り潰されている。周囲に展開する仲間へと指示を出しながら、朋彦は首を振った。 憂うのも、弔うのも後だ。今は生きる為に、守る為に。 「双方凄い数でごぜぇますなぁ」 偽一の煙草の香りも、血に塗れた。前に立つ仲間の肌が爪で、骨で切り裂かれて血飛沫が飛ぶ。 自身を端役と称し、前に出る事はしないけれども。彼の手は癒しの符を、傷付く仲間に送り続ける。 銀幕の中で華々しく活躍する主役は遠く、けれど偽一が存在しなければ、その輝きは鈍るのだ。 「世界は緩やかに滅びに向かっている。それは約束されたこと」 偽一の傍らで、ライサが独り言のように呟いた。 世界は滅びる。いつかは必ず。生者に死が訪れるのと同じく、始まりがあればいつかは終わる。 だけど、それは。 「死を弄ぶ者の手で来る訳じゃない」 約束された滅びだとしても、それはずっと先の事。今はまだ、滅びる時ではない。 故に生きよと、ライサが奏でるのは天使の歌。死なせるものか。死自体は否定しないが、死を弄ぶ事が肯定されてなるものか。そんな事、許しはしない。 「逝く為の戦いなんぞさせはしない」 幸蓮が、ライサの言葉に首肯した。 「これは未来と生存の道へ征く為の戦いだ!」 月の色と花の色。左右異なる目が見据えるのは『未来』に他ならない。『終わり』なんて見てやらない。 彼ら【支援】部隊が自分達に課した役割は、その名の通り皆を支える事。 朋彦の優れた戦闘指揮が、偽一の回復とインスタントチャージが、幸蓮のブレイクフィアーが、ライサの天使の歌が、傷付き落ちようとする仲間へと降り注ぐ。 守る為に、護る為に! ●2-1 全てを穿ち尽くす銃弾の雨、弱点を狙う気糸の群が荒れ狂う。 けれどそれは、味方によって放たれたものではない。 死者の群れに混じる革醒者の死体、遠距離攻撃に特化した者が多く存在するここは、楽団員の一人、ピッコロ奏者ゾーエ・エピファーニの存在する場所。 ピッコロの音は場に満ちるが、小柄な体は溢れる死者に覆い隠され視認は困難。 だが、リベリスタは困難だから、と諦める訳にはいかないのだ。 文音が幻想纏いで各所の状況を仲介する中でも、戦況は刻々と変化していく。 「非道! 外道! 無道! 貴様らの狼藉はこれ以上許さん!」 小柄な体で大きな声を張り上げて、ブリリアントはDreihanderを構える。 目標、遠くから仲間を撃つ狙撃手の撃破。死体の群に飛び込んだ彼女が放つは戦鬼烈風陣。刃が暴れ、肉を切り裂く。正面から撃ち合うよりも、懐に飛び込んで一気に叩き斬ればいいじゃないか! 簡潔と言えば簡潔で、ある意味では正しいのだろう。 「何故にうちのたいちょー殿は射撃メインの戦力に全力で斬り込みに行く! の! か!」 が、数の利は圧倒的に敵にある。絶叫したノアの言葉も尤も。斬り込むより先に蜂の巣では笑い話にもなりやしない。けれど、そんな彼女を見捨てるわけにはいかないのだ。 「ええい一丁援護してやりゃあにゃるめえ。上官見捨てたとあっちゃあ下士官の端であります!」 「まあ地道に行きましょう」 ブリリアントの傍らにはレイがいる。すらりと伸びた脚から放たれる斬風脚が、死体の一人の腕を切り刻んだ。砕いても死体は怯まない。ならば確実に一つ一つ潰して行くまで。 「連携こそ我等の力、でしょう?」 靡かない硬い髪を指先で退けレイが首を傾げれば、ノアも笑って弾丸をばら撒いた。彼らの体に降り注ぐのは、後ろに控える増援の回復だ。 進め、進め、我らは一人ではない。 「はっ、上等じゃねぇか!」 にっと笑みを浮かべたソウルが、死者の群れを前に立ちはだかる。その身で死者の行軍を押し止め、放つのは気糸に絡め取られた仲間を解放するブレイクイービル。 強面の外見に反し、彼が行うのは主に壁とフォローの役目。 「俺が耐える事で他が全力を出せるってんなら、身体を張る価値ってのもあるもんだ」 刻まれた傷は男の勲章。そう考えるのは、少々古い価値観だろうか。だとしたら、年下の者にこの役目を任せて置く訳にはいくまい。 「でっかい一発、頼んだぜ!」 叫ぶ彼に答えるように、紅蓮の炎が死者の群の中で弾けた。 「頼むぞ。勝利を、切り開いてくれ」 目に入るのは、ほぼ死人。リベリスタの数も決して少なくはないのだが、それでも溢れんばかりに集められた死者には及ばない。その状況に細く息を吐きながら――けれどシビリズは諦めない。 「私はその道を照らし続けよう」 金の瞳が、前を見据える。勝てるのか。この群に。死者の群れに。 誰かの疑念を、浮かべてしまった弱気を、シビリズは微かに笑って打ち消した。 「ああ、勝てるとも! さぁ、行こうではないかッ!」 彼が呼ぶのは、神々の黄昏。現状のアークの最上級のクロスイージスのみが使い得る、絶対の加護。 一撃を耐え得る、もう一撃を叶えるその加護を宿した仲間が、死者を薙ぎ払う。 「……うん。守るべき物はどう足掻いてでも守る」 細い目を更に細め、与作はそう呟いた。ここは自分達の帰る場所。守るべきもの。 できるかできないか、を問われている訳ではない。問うている暇にやる。 「では、状況を開始します」 難所用革靴“AREION”が血で汚れた地面を蹴って、仲間から贈られたK-3R“ACONITUM”を手に与作は死者の群れへと飛び込んだ。繰り出されるのは、神速の斬撃。 「ゾンビが都市を襲うなんて、まるで映画やゲームのようじゃないか」 直死の大鎌を肩に担いだ紗夜が笑う。元引き篭もりの彼女が暫し過去を再体験している間に、世間はまた違う賑わいを見せていたらしい。 「……ぞっとしませんね。暫くこの手の映画も見たくない」 目を伏せて溜息と共に言葉を吐き出したのは、オリガだ。街に溢れる死者の群れ。呆れる程に取り上げられるモチーフだけれど、現実になればこれほどの悪夢は余りない。 おまけに襲われるのが自分の住む街で、襲われるのが見知った顔だというならば尚更だ。 「まぁ、歓迎できない状況なのは私にでも分かるけどね」 例えた紗夜とてふざけて言った訳ではない。ぐっ、と構えた鎌に力を込めて放つはギガクラッシュ。一回一殺を願えども、強化された死体は決して柔くはない。革醒者の一撃に耐え得る肉体だ。 そこに雪崩れ込むのは、オリガが呼んだ黒鎖の呪い。濁流が死者を飲み込み、押し潰す。オリガが両手で握りしめるのは、恩寵を以って赦しと為す。主よ、憐れみたまえ。 次いで荒れ狂うのは、付喪の放ったチェインライトニングだ。 「楽団連中が調子に乗って。これ以上、この場所で好き勝手はさせないよ」 金の鎧が血に濡れる。精密さにはやや欠ける雷ではあるが、こと乱戦に置いては役立つ攻撃だ。 何しろ敵の数は多いのだ。この場所だけで500体。増援を含めたリベリスタの約5倍。このエリアの戦力差は、"パフォーマー"の作り上げた戦場の縮図である。数の暴力。それは全く間違いない。 「でも、こんな所で負けてなんていられないよ」 雷撃を放った後も、足を止めずに付喪は走る。ここは、皆の帰る場所だ。 「僕に……できることは……少ない」 小太郎は死者の群れの中を駆けながら、そう呟いた。別の仲間が攻撃を加えた相手に重ねるハイアンドロウ。肌を軽く焼きながら、小太郎は首を振る。 「けれど……先に行く……人たちの……露払いに……なるのなら」 黒髪がちりりと焦げて、嫌な臭いがする。それでも、止まってなどいられない。 「全力で……戦う」 覚悟を決めた少年の魔力鉄甲が、炎に照らされた。 「アークの危機におとなしくしてなんていられないよ」 金色の髪をなびかせて、せいるが唇を尖らせる。彼女は戦闘が得手という訳ではなかった。それでも、戦場に出なければならない時というのはある。 死体に群がられていたデュランダルを見付け、振るうのはソニックエッジ。刃によろめいた死者を切り裂いて、抜け出た彼は一度手を挙げ回復を受けると新たな敵へと向かって行く。 「楽団をやっつけて、皆で生きて帰るんだからね!」 昨日まで生者しか存在しなかったこの地を闊歩するのは、死者の群れ。 「なんつーか…久しぶりにお仕事なんだけど、なんか凄いことになってるよな」 愛用のサックスを片手に戦場に立つ楓は、当然ながら楽団員ではない。音楽を愛する一人のリベリスタだ。状況に多少呆然とすれど、そのまま呆けている訳にはいかないのだ。 「こういう時は何を演奏するのが良いんだろな……」 悩みながらも、奏でるのは癒しの曲。アポカリプスには未だ早い。 闊歩する死者も、元は何でもない日常を送る人々であったはずだ。 「酷い、こんなにたくさんの人が……」 溜息を漏らしながら、アルメリアはショートボウを構えた。老若男女を問わず、その人々は全て死んでいる。生者を死の波に飲み込もうと、望まぬ行進をさせられていた。 「ここで絶対に止めないといけないわね」 遠距離攻撃は届かずとも、数の差で壁を乗り越え寄って来る死者ばかりはどうしようもない。けれど傷を受けながら、アルメリアは狙いを定めハニーコムガトリングを撃ち放つ。 きょろりと周囲を向いた目は、倒れた人がいないかどうかを探す視線。哀れとは思えど――仲間をあれに引き込まれる訳にはいかないのだ。 「さて……どのような戦略でこのピンチを切り抜けるか……」 外見よりやや大人びた調子で呟く三郎太の手から気糸が放たれて死体を穿つ。 「頭脳だけではない、コブシ系の心意気見せましょう!」 金髪が舞い、跳んだ血が眼鏡を汚す。けれど怯んでなどやらない。仲間との距離を測りながら、彼はしっかり一歩を踏み出す。無理をして倒れる気はないが、動ける内は動かずして何をしよう。 死体は感情を現さない。容赦なく三郎太を殴り、抉り、叩き付ける。痛みは決して軽くはない。けれど。 「まだ動ける、手も足も動く! 今全力を出さずにいつ出すんですかっ!」 吼える彼に向け、癒しの音楽が奏でられる。 「守りたいもののために。みんな、もう誰も失わなくて、済むように」 前を見据えたひよりが降らせた癒し。奏でるのは子守唄。 戦場に響くのは、死という絶望。抗うように、多くの仲間が生を歌う。 回復手に向けて放たれたソニックエッジ。けれどひよりは、そんな事で惑わされたりはしないのだ。 紫の髪が夜に踊る。終わらない夜を終わらせる為に。 ●3-1 この戦場は、どこも死者が多い。 バレット・”パフォーマー”・バレンティーノが『本気で』操る死者の数は四桁を下らない。 三高平を攻め落とすため、十全の戦力で組まれた死者に対するのは、増援を含め約70名。 増援全体の四分の一にも満たない数だが、これは不要な犠牲を出さぬ為のもの。どの戦場でもそうだが、一人死ねば、一人相手に手駒を渡す事となる。ましてやこの戦場の本命とも言える『パフォーマー』がいる場所で、戦力増強を許す訳にはいかないのだ。 その分、一人ひとりに掛かる負担は大きくなる。けれど、泣き言を言う暇もつもりも、ここに集ったリベリスタにはない。 何しろ、ここには『彼女』が存在するのだ。 「いや! 嫌なの! あんな優しい笑顔が……」 カシスが叫ぶ。三高平において、多くの人に愛された――丸田 富子が。その体が、ここにある。 ただし動けども、その体は既に彼女のものに非ず。操られるばかりの、ただの物。 「自分の意志もなく操られるだけ、か……」 そうはなりたくはない。なる気もない。これ以上の犠牲など出すものか。 蠢く死者とて、望んでそうなった訳ではないと吹雪は知っている。だから呟く。すぐに解放してやるから、と。 こぶしを握ったカシスが、きっと前を向いた。 「『あたし/私』たちで終わらせるのよ!」 裏表。カシスの中の私とあたしが引っ繰り返っても思いは一緒。 「丸田さんを止め、取り戻す。そのためにこの場で私に出せる全てを費やしましょう」 かるたが地を蹴り、空中に存在する革醒者の死体へとメガクラッシュを叩き込む。空中では分が悪い。地上に降りて貰おうか。 富子と直接の縁が深かった訳ではない。けれど知っている。幾度も話を聞いた。このまま楽団に飲まれたままになどさせやしない。 「僕も料理人の一人として、相打ち覚悟で必ず止めてやるさ」 生きていた頃の富子であれば、縁起でもない、と笑い飛ばしたのであろう。何よりも、誰よりも『生きる』為に散った彼女はそんな方法を好むまい。けれど達哉は、また違う覚悟でここに臨んでいる。 死者の群れの中、富子の姿が見え隠れした。 遠くに見える懐かしい顔に、絹が目を伏せる。 ほんの少し前までは、会おうと思えば会えたのに。思い描く『お母さん』そのものだったあの人は、遠く遠く隔てられた場所へと行ってしまった。 「早く、ちゃんと眠らせてあげたいです」 死体を、それを弄ぶ楽団を癒すなんて、彼女は決して望むまい。指先が守護の結界を張る印を描く。 「はいはい。さて、スーパー支援たーいむ」 気楽に呟いた寿々貴が皆に齎すディフェンサードクトリン。口調とは裏腹に、それは強力な支援となる。支援であり回復手。 「人がのんびりしてたら……何よこの騒ぎは」 聞けばこの騒ぎの中心にいる生者はたった二人。楽団員は一人でも寂しくなさそうで妬ましい事。 妬んでも愛美にはできない芸当。ならばできる事をするまでだ。打ち込むのは、死者の群れを狙ったインドラの矢。 「ふふ……よく燃えるでしょ?」 愛美の炎は嫉妬の炎。死体であっても燃やし尽くす。生きて動いているなんて、ああ妬ましい。 後ろから、星の光を宿した弾丸が叩き込まれる。 「人が足りなかったようなのでな。増援に来たぞ」 アリシアはそう肩を竦め、蠢く死者を見据えた。雑魚とは言えど、溢れる死体は呆れる程に丈夫だ。 ならば薙ぎ払うための人員は多いに越した事はあるまい。 「どけええぇぇぇ!」 佳恋の一撃が、死者を薙ぎ倒す。しぶとい。数は溢れんばかりにいる。けれど彼女が探すのは、バレットの姿。一撃を加えるチャンスを待ち、彼女は刃を振り下ろす。 直接の付き合いがあった訳ではない。けれど、富子は自分達仲間を生かすために倒れたのだ。 その覚悟を、無駄にはしてはいけない。 「富子を返すのだ!」 続いて降り注ぐのは、雷音の氷雨だ。富子を喪った戦場に、彼女もいた。『母』に庇って貰わねば、死んでいたのは雷音だったかも知れない。 だからこそ、彼女に繋いで貰った命をここでむざむざと落とす訳にはいかない。 怖くないはずがない。死は間際だった。今も周囲に溢れるのは死だ。 「ボクらはまけるわけにはいかない」 けれど震えている場合ではない。ケイオスを破るためイタリアに飛んだ父と、同じ街で戦っている兄と、もう一度会う為にも。弱気を振り払い、雷音は仲間に指示を飛ばしながらも敵を探して周囲を探る。 「……皆で生きて帰るって、貴女が言ったのよ」 ちらちらと見える、知った顔。頭一つ、二つ。死者から抜けて戦況を見るエレオノーラは小さく呟いた。死ぬ気はなかった。それは今も同じ事。 だけれど、必ず生きて帰ると笑ったあの人は、帰ってこなかった。 ならばせめて、体だけでも。とん、と跳ねた手に握ったHaze Rosaliaが、鈍く月光を照り返し赤に染まる。 許せない。もう一度会いたい。ぐるぐるとした心は落ち着かないけれど。 「……今は、みんなで生き残る為に、戦わなきゃ」 ヘルマンは吐き出しそうになった溜息を押し止め、脚を振って斬風脚を繰り出した。 死なせない。誰かが死ぬところなんて見たくない。 願いはするけれど、視線が追うのは優しい姿。背中を叩いて励ましてくれたあの『母』の姿。 見えるその姿に、俊介は目を閉じる。 「母ちゃん」 富子は俊介にとっての母である。血の繋がりなんて関係ない。ナイトメアダウンの後、各所を盥回しにされていた俊介を引き取って温かさをくれたのは、誰でもない富子なのだから、彼が『母』と呼ぶのは富子である。 大きくなったね、そう言って触れた手の温もりだって、未だに残っている。 「大好きだよ、母ちゃん」 既に声が届く距離だ。けれど『母』は何も言ってくれやしない。 自分は悪い息子だっただろう。きちんとした親孝行なんて一度もできていなかったかも知れない。 だからこそ、母が愛した三高平の仲間を傷付ける前に――止めるのが、自分の役目。 その様子にふう、と溜息を吐いた魅零は、俊介の前に立ちはだかる。 「ちょっと、一人でなんとかできるとか思うんじゃないわよ!」 死者はそんな思いなど読み取らない。ただの道具に過ぎない体は、ほんの一時の感傷すら、想いすら踏み躙ろうと手を伸ばす。だから魅零は、そんな攻撃に晒される俊介の前に立った。 「スイーツをおごりなさいよ!! それもとびっきりの数ね!」 いつも通りの軽口を叩きながら、魅零は決して落ちるものかと唇を噛み締めた。俊介の手は震えているに違いない。幾ら覚悟を決めたって、彼にとって『母』へと攻撃を加えるのは辛い事に違いない。 だから。 「お姉さん、頑張ってあげる」 今日ばかりは、自分が俊介の為のナイトをしてあげよう。 俊介を憂うのは一人ではない。 「あまり、無理はしないといいんだけれど……」 ゆらゆら揺れながら、那雪が呟いた。生きてまた、会いましょう。約束だ。 「破ったら……アイス奢って貰わなきゃ」 微かに笑って紡ぐその言葉。那雪の気糸が、空中に散開する飛行部隊を貫いた。 目前に迫った富子に、富江は目を見開いた。顔立ちだけなら、よく似ている。けれど感情豊かな富江の表情と異なり、今や富子の顔は何も写しやしない。 「富子!! あんたいったい何やってんだい……たかが死んだくらいでもう何もわからないっていうのかい!!」 叫びが無茶だというのは分かっている。死ねば終わりだ。そこに彼女の意識は存在しないのだから。 けれど双子の妹に、彼女は叫ばずにはいられない。 「目の前にいる皆を見てみなっ。あれは誰だ!! アンタの目にはどう映ってるんだい!!!」 存在するのは、リベリスタ。富子が命懸けで守ったはずの、可愛い子供たち。 それを自らの手で、害そうというのか。 そんな事は、許しはしない。 「……アンタの意思は、アタシが継いだ!」 富子の前に、立ち塞がる。物言わぬ死体となった彼女を止める為に。 「その決意を……アンタと同じ折れない心を……今アンタに見せてやるよ!!!」 守ってやるのだ。 今度こそ。誰一人失わず。生きて帰るのだ。 「愛しているよ、母ちゃん」 両手を広げた富江の後ろ、俊介の放つ破邪の詠唱が呼んだ炎が――富子の体を包む。 ●1-2 隙間に、じわじわと死者が浸透していく。全てを防ぐ事などできない。最初から誰にも分かっていた。数の差は圧倒的だ。多くは前衛も後衛もなく、入り乱れての乱戦となった。 だが、その数を相手取るのを得手とする者も存在する。 「ふふっ、ワラワラしちゃって……潰し甲斐があるわ、今夜はお祭りね」 不敵な笑みを浮かべた杏が鳴り響かせるのは、ギターの音と轟く雷鳴。THE STAR PLAYER XVIIが秘めるのは多大なる魔力。そこに杏のお得意、チェインライトニングが加われば――雷撃の威力は恐ろしいものとなって死者へと降り注いだ。 とは言え、最大限に巻き込む為には死者の只中に突っ込む事が必要だ。自覚するように、魔術師である杏の防御性能は、物理に寄った死体の攻撃が降り注ぐ最前線で立ち続けるには少々心もとない。だからこそ。 「この私が来たからには存分に力を振るっていただければと思います」 「期待してるわ。ところで初めましてだっけ?」 「……何度かお仕事一緒させて頂きましたよ?」 冗談か本気か、杏の言葉に思わず振り向きながら、アンリエッタは死体の攻撃をナイフで弾く。その身に多数付けた懐中電灯の光よりも遥かに強い杏の雷光は、とても頼もしい。 今宵の自分は彼女の為に、彼女が万全に力を奮う為に。 例えその身に降る回復より、重ねられる攻撃が重くとも――運命を燃やしてでも立ち続けるのが、アンリエッタの今日の役目。 「さ、もう一発行くわよ」 「お任せを」 血と肉片に塗れた腕を振り払い頷いたアンリエッタを見ながら、杏はピックを構えた。 三つ編みを揺らしながら最前線を駆け回る理央が前衛に掛けて回るのは、エル・バリア。 器用貧乏を自称する理央の能力は、確かに個々だけ見ればそれらを得手とする人々には及ばないかも知れない。だけれど、その分できる事は幅広い。 「ボクはボクの、必要とされる役回りを」 一人で何でもできる必要はない。けれど、皆がうまく回る為に多数をこなせるのは優れた利点なのは間違いなかった。 倒れそうな仲間へと送るのは天使の歌。彼女の癒しが、仲間を立たせる。 そう、必要なのは前に立つものだけではない。支えがなければ、彼らは立ち続けられない。 リベリスタはそれを知るからこそ、誰もが自らの役割を果たすべく奔走した。 「私は私にできる事をするのみです」 ルカは加護の切れた、或いはブレイクで消された仲間に再度翼を授ける。 他の仲間と距離を取り、回復が満遍なく行き渡るように。 「こっちは回復大丈夫、右側にお願い!」 忙しく駆ける智夫は、回復が重ならぬように増援のリベリスタへと声を掛ける。その目は注意深く、誰かが倒れないかと周囲を窺っていた。 味方が誰一人として殺されないように。智夫が最優先としたのはその一点。死ねば楽団の戦力となる、というだけではなく――誰かが失われる事は、彼にとって望む所ではない。 死体の数は多くとも、智夫を含め回復手も数多く。だからこそ、ここは落とさせない。 「僕もここでめいっぱい、お手伝いをするです」 智夫の指示の先、傷の深いリベリスタへと玲が送るのは癒しの風。速やかな移動の為に小さな体を宙に浮かしながら、孤立はしないように回復を振り撒いた。 「信じてます、先輩さん達!」 蠢く死者は、もしかしたら自分だったかも知れない。過去に救われていなければ、この群の中にいたのかも知れない。何気なく過ごす日常を奪われて、死へと転落していたのかも知れない。 「……ごめんなさい、”僕”。でも、きっと、大丈夫。アークの先輩さん達が……この状態からは、絶対に。助けてくれるです」 アークのリベリスタに憧れてここに来た少年が、『先輩』に寄せる信頼は絶対だ。 彼らは自分を助けてくれた。だから今度も、きっと。 「……徹子も、そろそろ、アークのお手伝いもできるころだと思うのです」 小さな体、うかんだそばかす。素朴な少女の体をして、徹子はけれど非日常に立つ。 両手に構えた樫の木刀。振り上げたそれが、像を残す速度で死体を打ち据えた。肉が砕けて血が飛んで、降り掛かる血に軽く眉を寄せる。 「勝った方が意を徹すのが力で生きる物の掟」 ならば今回も、徹子は名の通り罷り徹るのみ。徹子の徹は、とおるの徹。 死体に彼女が望む武はない。どちらかと言えば木刀と似た道具に過ぎぬ。ならば余計に負ける訳にはいかないのだ。 「退路確保の為にも、ここは絶対に譲れない場所ね」 奥に進めば進む程、死者に囲まれ危険は増す。外周に当たるここを護らねば、中へと向かった仲間達が死者の檻へと閉じ込められるのだ。それは決して、見過ごせない。 すう、と夜の冷気と饐えた臭いを吸い込んで、ウーニャが呼ぶのは紅い月。 「紅蓮の月光よ、あまねく死者を照らし出せ――!」 手に構えたFOOL the Jokerが赤の光に妖しく照らされ、白い肌を染め上げた。不利益そのものの効果が及ばなかったとしても、その呪いは死者に積み重なっている。呪いが招くは、紅の殺意。 幾つかの死体が、赤の光にその身を崩れさせた。 「もう戻ってこないでね」 起こした元凶は、遠く仲間の向かった方。仲間が彼らを、同じ場所に送ってくれるから。 ばいばい、と呟いた言葉が、未だ続く戦闘の音に消えた。 死者が溢れる。溢れて淀む。視界の定まらない目が、無数に伊藤を見詰めている。 「酷いよ酷いよ怖いよ怖いよ。何でこんな事するんだよぉ」 怖い。死にたくない。涙交じりの声で呟く伊藤と背を合わせ、暖簾が小さく笑った。 「……大丈夫さ伊藤。お前さんは強い子だ」 ぐすり。鼻を啜る音が聞こえた。ぎゅっと拳が握られる。泣いて怯えて怖がって、けれどそれで怖気づいて逃げるような者ならば、最初からここになど来なかった。 「後ろはじーじに任せな。俺の後ろは頼ンだぜ」 「……うん。――正当防衛だ。ぶっ殺してやる」 最後に一度、目を閉じて、振り切った様子の伊藤から目を離し、暖簾はブラックマリアに軽く口付けた。 「往くぜマリア。力を貸してくれ」 倒れる訳にはいかないのだ。伊藤の傍に立ち、最後まで立ち続けなければならない。暖簾が倒れれば、彼だって危ないのだ。帰る場所を守る為、そんな事を言ったとして、命がなければ帰りようがない。 「有象無象悉く、凍り付いちまえばいい!」 呼ぶのは雨、氷の雨。覚悟を込めたド鉄拳。高く上げられたそれから氷に続いて降り注ぐのは、伊藤のインドラの矢。 「燃えろ燃えろ、燃え尽きろ。全部全部全部消えて燃えて死んで無くなれ――!」 泣き叫ぶのは生きているから。燃えて焼けてもう一度死んでいく死体から、目を離さない。 目を閉じて永眠するのはごめんである。大事な命を、大事な人を、喪うまいと家族が寄り添った。 「はいはーい、範囲殲滅いきますよー!」 明るく叫んだセレアが、長い詠唱を速やかに済ませ招くのは黒鎖の宴。魔術師が扱う中でも凶悪なそれは、発動までに僅かとは言え時間を要するのが難点だが、彼女はその不利も難なく乗り越え唱え続ける。 とは言え決して打たれ強くはない術師として、敵の攻撃の矢面に立つのは宜しくない。なるべく前衛の後ろに隠れ、火力で敵を押し切るべくセレアは前を窺った。 「一般人の死体とか相手にしてて全然楽しくないけど、この際贅沢は言ってられないわねー」 革醒者の死体よりは劣るとは言え、それでも決して楽な相手ではない。潰して潰して潰さねば、リベリスタにとっては確実な脅威となるのだ。だからセレアは、ひたすら数を減らす事に尽力する。 「戦いとは非情なものです」 剣を構え、明が目を細めた。平素から表情に乏しい顔は、激情やそれに類するものを映しはしないけれど――この状況を肯定している訳では、無論ない。 「ですが、既に生を終えたものたちの安寧を奪い、戦場に駆り立てるとはあまり趣味が良いものではないですね」 纏うのは闇。それは悪性ではない。細い体に纏わりつく闇が、彼に耐える力を与えてくれる。 セレアの黒鎖によって痛んだ死体に向け、明は刃を振り上げた。 「やれやれ、こんなにも大変な事態になるとは」 白いコートを血に染めて、省一は小さく溜息を吐いた。アークが大規模な敵の攻勢を受けるのは今に始まった事ではないが、それは名が知れる事が導く宿命というものか。 「まあ、良いでしょう」 フィンガーバレットを握り、省一は軽く首を振る。その体が鈍っていないか確かめるかのように腕を振り、眼帯で隠された視界一杯に死者を捉える。 「この体が錆び付いていなければ良いのですが、きっちりと仕事をこなすのみ」 握った拳は、死体の腹へと叩き込まれた。 「流石に、この街がなくなったらなんてぞっとするしね」 溢れる死体、一般人。濁った目や傷さえなければ、街中にごく普通にいるような彼らと馴染む格好をした縁は、首を振って呟いた。 幾ら馴染むとはいえ、死者と生者という高い高い壁がある。だから決してそこには飲まれないようにしながら、縁は血を撒き散らした。 「自然も、人も好きだけど、こういう光景は被写体にしたいとは思わないねっ」 縁の生業はカメラマン。けれど死で溢れる光景は、決して魅力的ではない。 明るい光を、生の息吹を取り戻す為――現代の忍者は、銃を構えた。 「己が身で攻めてくるならいざ知らず、死者の肉体を使役するなど言語道断!」 縁が現代の忍者なら、ジョニーが憧れるのはまた異なる『ニンジャ』である。拳を使い前に立ち戦うスタイルを選択する彼にとって、他者の肉体を剣や盾とするネクロマンサーの戦術は実に許しがたい。 「このジョニー・オートン、死力を尽くす所存。いざ、尋常に推して参る!」 滑らかに紡ぐ名乗りと同時、荒れ狂うのは雷撃を纏った拳と蹴りの嵐。体力に重きを置いた彼にとっては些か消費の大きい技ではあるが、尽きる前に施されるのは増援からのインスタントチャージ。 死者のように、一方的な盾とするのではない。支えて支えられて、それを知るリベリスタは強い。 粘り強くしぶとく。死者を操る彼らが呆れる程のしぶとさを以って、この戦場を乗り切るのだ。 「大丈夫? 美月部長」 「だ、大丈夫だよ明……」 振り向いた明奈に、美月は一度口篭って大丈夫だよ、白石部員、と言い直した。けれど額に浮かぶのは脂汗、体はガタガタ震えている。 美月の前に立ちはだかる明奈は、既に無傷ではない。美月が歌を唱えても、傷付く事自体は避けられないのだ。だとしても、誰も倒れないように、誰も死なないように、彼女は歌い続ける。 震える美月を気遣わしげに見る明奈に、彼女は首を振った。 「丸田さん、良い人だったよね。差し入れしてくれたりさ」 「……うん」 ここにはいない。遠くに『いる』はずの人を思い出す。物理的な距離ではなく、生と死に別たれてしまった人を。 「僕、結局ろくにお礼してない。もうできない……」 足が震えている。怖い。怖い。怖い。心は悲鳴を上げているけれど、逃げる事なんてできない。 「またそうやって、顔見知りや友達が死んじゃうのに比べたら……こんなの! ちっとも怖くなんてない!」 涙で視界を曇らせながら、震える声で紡ぐ美月に、明奈は小さく笑った。が、即座にその即頭部を死体に殴り倒される。舞うのは赤。 視界が、ブレる。 「明奈!」 「……はは、大丈夫だよ部長。劇的(ドラマティック)な展開はネクロマンサーの専売特許じゃあないんだぜ」 美月の悲鳴を聞きながら、明奈は紅く染まった頭を振って、立ち上がる。 映画のヒーローやヒロインの如く、最後の最後で踏み止まって、決して彼女は折れやしない。 美月が泣いて、けれども自分はその傍らで明るく笑って慰めて。 そんな光景を、もう一度この場所で行う為に。 心根の優しい少女らは、血と涙に濡れながら戦場に立つ。 「例え心は既に離れていようと例えその器だけになって操られたとしても、母は……富子様は皆さんを傷つけたりはきっとしません……」 遠くにある人を思うのは、リサリサも同じ。母と呼ぶ彼女とは死で別たれた。 ならば自分にできるのは、自分の役目を全うできると遠き彼女に見せる事。不利は通らぬ絶対者、手弱女の体に秘めた硬い芯。後ろに控える支援担当を、沈ませてなるものか。 「皆様は攻撃に集中を……遠距離からの攻撃は……ワタシが」 取ったのは防御の構え。耐えて耐えて食い止めるのが、彼女の役目。 決して崩され抜かれはしない。母へ捧げる最後の務めとして、青い目のヤマトナデシコは眼前を見据えた。 濡れた音は湖を這い上がってきた死者のものか。死から時間が経過した者もいるのか、腐敗の香りも漂っている。 「そう、こんなに『日常』を踏み拉いてきたの」 エクリが乾いた声で呟いた。 溢れる死は、壊された『日常』の成れの果て。死体一つ一つにも人生があった。生があった。大事な人が、夢が、未来があった……はずだった。 それは全て、踏み躙られた。死を弄ぶだけのネクロマンサーに。 「絶対、許さない」 エクリを含めた複数名が現在相対するのは、死体の中でも特に異彩を放つ存在。 成人二人分は優に超える大きさのキマイラ、『オーナメント・オーナメント』。 奏でるのは、楽団とはまた違う呪詛の歌。いたい。いたい。いたいいたいいたいいたいいたい。 生者の模倣に興味がない”パフォーマー”の部隊の中で、ただ一つ。生と死の苦痛を紡ぐその声。 けれど、その声に姓は縛られない。 「回復宜しくね」 増援の一人、歌を唱える翼の少女に声を掛けながら、姓は灯りで照らされたキマイラを見遣る。 表皮に浮かぶ無数の顔、内部に見える赤い球。六道によって作り出された、異形の化け物。それを作る為にも、多くの命が使われたのだろう。生を弄ばれて死して尚、彼らに安寧は訪れない。 死した後の苦痛か、生の時の苦痛か。浮かぶ苦悶の顔は、何も示してはくれなかった」 が、その異様に眉を顰めるものだけではない。 「キマイラ、いいね、すっごく楽しそう!! 勝負だ、ボクとキマイラどちらが強いかね!!」 ケラケラ笑いながら、沙羅がその顔に噛み付いた。ぐじゃりと潰れる感覚。顔と言う形を取ってはいるが、本体は透明なスライムのようなもの。悲鳴も上げずに顔は溶けて消え、再び新しい顔が表皮に浮かぶ。 ぎちりと透明な触手が伸ばされるも、沙羅は笑って振り解く。 「あっはあ!! すごい! 君強いね、楽しいよ」 戦いは恐れるものではない。だから彼は怖がりはしない。痛みも消して、ただただ残るのは背筋を走る快い緊張感。 推し量るのは、一撃を叩き込む為の最良の瞬間。 「君の命をボクに頂戴よ!!!」 構えた直死の鎌が、ぎらりと光る。 そんな様子を眺めながら、リリスはぼんやりとしていた目をエル・ブーストで叩き起こす。この状況は、かつて彼女の故郷ラ・ル・カーナでリベリスタが行った防衛戦を思い出させた。 大事な物を守る為に、彼らはいつだって戦うのだ。だから。 「リリスもしっかり此処の守りを手伝うよ!」 この場にリリス以外のフュリエはいない。少し離れた場所や遠くの戦場にならばいるのだろうが、色々なものを共有してきたリリスには少々心細い。けれども、ならば余計に自分が頑張らねば。 「リリスだって、戦えるようになったんだから……っ!」 氷精となったリリスのフィアキィが、舞い踊る。エクリの拳が、氷を纏ってキマイラを打ち据える。 「おぞましいね」 顔。顔。顔。そこに並ぶのは、死者の群にも劣らない狂気の塊。怖くないはずがない。嫌悪しないはずがない。だとしても。生きてもう一度、と願った『友達』の笑顔を曇らせるものは、エクリの敵だ。 凍りついたオーナメント・オーナメントに、弾丸が、魔力の矢が、真空の刃が、四色の光が降り注ぐ。高い再生力を誇れども、ネクロマンサーの強化を得ていようとも、全て耐え切れるものではない。 「チェックメイトよ」 前に躍り出た杏の放ったチェインライトニング。ぐったりしたアンリエッタを抱え、最後に爪弾いた音が――異形のキマイラを、弾けさせた。 ●2-2 アークの本拠地、三高平。 本来ならばリベリスタにとって安寧の地であるそこが、今宵は戦場だ。 「楽団員ですか……まさか此処まで攻めてくるとは思いませんでした」 R-Type攻略の為に作られたリベリスタの街。そこに控えるリベリスタは数千を数え、容易に陥落するような作りにはなっていない。だからこそ、此処に攻めてくるような無茶無謀を行う敵は今まで存在しなかった。 だが、この度の敵はバロックナイツ。歪夜の使徒、世界最高峰の敵。 「戦時中も、常に兵器や人が多い工場や繁華街が空襲の対象でしたし……おっと、私もできる事をやらないと」 ふわりと靡くピンクの髪。儚い少女の外見をした芙蓉は、年月を少しばかり多く重ねていた。 彼女の指揮によって、リベリスタ達が適切な場所へと振り分けられる。 「けれどあなたたち、ほんと厄介な相手と喧嘩してるのね……」 呆れた様に呟いたサタナチアは、けれどキッとその双眸を前に向けた。 「まあ私も今はアークの一員よ。だ、だから少しでも頼りなさい!」 ボトムに来てまだ日は浅い。けれども彼らの役に立ちたいと願って訪れたのは嘘ではない。 素直になれない分は、行動で。 「しゃんとしなさい、まだ戦いは続くわ!」 彼女の連れた紫色のフィアキィが、傷付いた仲間を癒して行く。そんな彼女を庇うのは琢磨だ。 血に濡れた眼鏡を拭いながらも、回復手である仲間を庇う事は止めない。 何しろ飲み込まれたら終わりなのだ。固まって、少しでもダメージを防がねばならない。 頭に響くのは、愛しい愛しい妹の声。 『お兄ちゃん……あがたはお兄ちゃんと一蓮托生だよ』 その微笑さえも目に浮かぶ。 「アガたん……ぼくはアガたんに死んで欲しくないっす」 例えその妹が、可愛い妹が脳内にしか存在しないにしても――いや、脳内にしか存在しないからこそ、琢磨は死ぬ訳にはいかないのだ。自分が死ぬのは、彼女が死ぬ事と等しい。 「だからぼくは、死にましぇん! あ、あっちにインスタントチャージお願いするっす!」 誰も死なせはしない。 自分にできる事を。 メッシュは考える。この状況で、自分には何ができるだろうかと。結果は、皆を支える事。 「ここは任せて!」 他のフュリエと同じく、彼女は戦闘経験が豊富と言う訳ではない。一人ならば不安であろう。けれど、ここには友が、アークの皆がいる。 氷精となったフィアキィが凍らせるその姿に、一度目を閉じた。なんて悲しくも痛々しい光景か。 彼らは死ぬべきではなかった人たちばかりなのに。 どうか、安らかに。 願いながら、メッシュは遠く天を仰ぐ。黒い闇が、広がっている。 「エクスィス、ボクは正しい道を歩めているでしょうか……?」 友人を、その世界を守る為に武器を取った少女に、今は世界樹は何も語ってはくれない。 死者の群れに紛れる楽団員を探すのは骨が折れる。 そう判断したリベリスタは、一つのチームを組んで捜索に当たっていた。 戦場は面で、目標は点。障害物が溢れる中で、気の遠くなるような作業だが――不可能ではないのだ。 目を凝らし、耳を澄まし、熱を探り、感情を辿り、たった一人の楽団員を見付け出す。 「まともに相手してたんじゃ明らかにこっちが不利だね」 死者を叩き伏せてどうにか進みながら、七が首を振った。ネクロマンサーの操る死者はしぶとい。呆れる程に。一般人の死体でもそうなのだ、革醒者となれば何をか況や。 「死者の海の中で息が続く内に、ゾーエ殿を見付け、倒さねば……!」 交霊術で語りかけれども、死体は答えてはくれない。それが玄吾には悲しい。何らかの意思を繋げたい。それさえもネクロマンサーは許さぬというのか。 辺りを探る。溢れている感情は、仲間のもの。悲しみ、怒り、死の恐怖。 だが、楽団員であればそうではないはずだ。負ではない感情。何かは知らぬが、そんなものが。 円陣を組むのは七、ティアリア、カインにラシャ、モヨタに蘭月、玄吾、コーディ、純鈴の探索部隊。 ティアリアはそんな周囲に注意を払いながら、聖神の息吹で仲間を癒していく。 「富子の方が気になるのだけど……だからって、ここを疎かには出来ないものね」 誰一人として死なせはしない。死を望む楽団の思い通りになどさせない。 この場所からやや離れた所に、ティアリアの知る彼女はいるのだろう。望みもしない死の行軍に加わって。 「今、あなたの愛する子供達が行くわ」 あなたを眠らせる為に。紅の瞳が空を仰ぐ。相対叶わぬとしても、願う事はただ一つ。 「アークの人まで……ちきしょう。ほんっとタチが悪い『クソ野郎』どもめ」 「全く、胸糞悪いな」 モヨタが顔を歪めて悪態を吐くのに蘭月が同意した。楽団との戦闘で失われた人員は片手よりも多く。けれど、それでも足りないと憎き敵は笑うのだ。尚も飲み込もうと、今夜も死を奏でている。 奏でられるピッコロの音は近い。白い髪が、肉の海の中に見えた。 「あそこ!」 鍛えられた五感、マスターファイブを持つ純鈴はその先を辿る。逃げたって探し出すのだ。 死を奏でる彼らは生きている。生きている事が異質とは何と言う皮肉か。 コーディの放ったフレアバーストが弾け、死者が揺らいだその隙間から、確かに幽鬼の如き少女が見えた。 「そこか……! 見つけたぞ臆病者め!」 死者の群に逃げ込むゾーエに、コーディが叫んだ。返答は、ピッコロの音と降り注ぐ骨の矢。 「ラシャ、いた!」 「逃がすか」 カインの声に応え、ラシャが振り上げた刃が、死者を切り裂く。分厚い壁だ。けれど超えねば、ゾーエには届かない。蘭月の刃が、死者を弾き飛ばす。少女の姿をした楽団員へと、刃を届かせる為に。 「ちょっとどいてね」 仲間を巻き込まぬよう前に出た七が、前方に向けて放つダンシングリッパー。切り刻む舞踏。 先には――ピッコロを手に忌々しげに見詰めるゾーエ。 「……死にに来たの、ありがとう」 か細い手で奏でるピッコロの音は揺るがねど、先日リベリスタからの集中砲火を食らった彼女はその記憶を忘れてはいないらしい。 とん、とん、と幻想纏いの通信で居場所を知った五月とフラウが、その場へと翔ける。 「いつもうちの我儘に付き合わせて悪いっすね」 「大丈夫、フラウ。オレが我儘で君の隣に立ってるんだ」 目配せしあい、微笑んで。銃弾の雨が、魔力の矢が降り注いだって、その勢いは止まらない。 ほんの一度だけ手を触れ合わせて、二人は前を向く。 「今回も最後まで付いてきてくれ、メイ」 「もちろんだ」 隣にいてくれと願うのは、隣にいたいと願うのは、どちらも我儘。だけれど傍にいてくれるなら、どこまでも強くなれるから。喪うのはご免だ。誰かが泣くのもご免だ。 この世は理不尽だらけだけれど、優しいに決まってる。 フラウの攻撃をゾーエに届かせる為に、五月が振るうのはメガクラッシュ。邪魔な死者を吹き飛ばし、真っ直ぐ楽団員への道を開く。 ナイフが煌き、フラウの残影剣が死者ごと少女を切り裂いた。 「お前たちの『演奏』は胸糞悪ぃんだよ!」 外見だけは自らと変わらぬ相手へと向け、モヨタが生死を別つ一撃を放つ。死者に体を引かれたって叩かれたって、止まってやらない。こんな音はもう沢山だ。 「償う必要はない。即座に死ね」 蘭月の刃が、今度こそゾーエを捉える。黒い礼服を更に色濃く。血が滲む。 ピッコロの音は止まない。奏でる音は美しく、だけれどどこか悲鳴のように。 麻痺を齎す弾丸を撃ち込めど、カインのブレイクフィアーが打ち払う。傷を癒すのはティアリアの息吹。 倒れない。倒れさせない。使い潰すだけの死体と違い、リベリスタは支え合う事を知っていた。ゾーエの顔が、僅かずつ焦りに染まる。 「今度こそ、お別れっすよ」 フラウの刃が、ゾーエの胸を捕らえた。 「君が居れば、強くなれるから」 フラウと目を合わせた五月のデッドオアアライブが叩き込まれる。 細い体が、ゆらりと揺れた。運命を燃やさねば、立ち上がれないその一撃。 げほり。血を吐いて、ゾーエが叫んだのは救援要請。 「……バレット! こっちが持たな――」 マスターテレパスも届かぬ距離に存在する相手。恐らくあちらも通信装置の類を繋げていたのだろう。 『――三十年ありがとうよ、俺の「目」! 精々良い音奏でろよ!』 けれど、血に塗れた悲鳴に返って来たのは死刑宣告。響く笑い声。 ああ。この男に『情』なんてものは存在しないと、知り尽くしていた筈だったのに。 「この街は貴様等の居て良い場所ではない……!」 「嫌――」 コーディの放ったフレアバーストが、その小さな体を燃やし尽くす。暴れる彼女に触れたのは、七の指先。埋め込まれた爆弾が、少女の体を弾き飛ばした。 黒く焦げた体が、緩やかに、沈む。けれど、死体は未だ、多数が蠢いている。 ゾーエが操っていたと思しき死体も複数倒れこんではいるけれども――この戦場の三分の二を超える死体を操るのはこの奥の"パフォーマー"。 未だ動きを止めず襲い来る死体を潰す為、一息吐く暇もなくリベリスタは刃を翻した。 ●3-2 ケタケタと。笑う声が響く。 バレット・”パフォーマー”・バレンティーノの顔が、死者の群れの中に現れては消える。 その手に携える銃口と共に。 「あちらです」 九十九の熱感知が、他とは違う温度を捉えた。 同時に降り注ぐのは、ハニーコムガトリング。答えるように、バレットからも銃弾が放たれた。 「ようアーク、流石にしぶといな、楽しんでるか!」 降り注ぐのは骨の弾丸。撒き散らかされるそれはリベリスタの肌を抉り、肉に沈む。 身を侵すのは、毒と呪いと、生への憎悪。打ち払われる翼の加護。 だが、消えた翼は再び小夜によって齎される。 「最前線で戦えるほど実力はないですが、お手伝いぐらいなら……」 ――次はそちらにおねがいしますじゃ。 戦況を見極めながら、小五郎が小夜にハイテレパスで指示をする。 地上に溢れるのは死体の群。効率よく動くには、翼の加護はあるに越したことはない。 だからこそ、小夜はそれが途切れないように、小五郎は効率よく掛けられるように注意を払う。 「惑わされるな、今払う!」 アウラールの放った光が、埋め込まれた骨の弾丸の幾つかを消した。けれどそれは消える際に、消滅を厭い体の内を荒らしていく。 それを癒すのは、傍らに立つキリエだ。富子に一瞬視線を向けて、吹かせるのは大天使の吐息。 誰に対しても分け隔てなく愛情を注ぐ彼女が、先に旅立ってしまうなんて先日は露ほどにも思わなかった。 「あの腕が、もう温かくないなんて」 誰かを癒す手。喜びを齎す料理を作り出す手。それがもう、温度を持たない死体となってしまったなんて、考えたくない。 だからこそ、終わらせねばならないのだ。この、混沌組曲を。 「それ、すごく面白い。ボク達もやりたいな」 肌の下で蠢く骨の弾丸を感じながら、ぐるぐがにいと笑った。ブレイクフィアー、清浄の光で消し去られた骨は、酷く暴れてぐるぐの中に爪痕を残す。 クアランタオット、48、喋る死者。バレットのネクロマンサーとしての腕と、その手に持つバイオリン――巨大なアーティファクトが合わさって叶う技なのだろう。 だとしても。 「いひひひ! やっぱ強い人は面白いや!」 運命を燃やしながら、ぐるぐは笑う。その手に美しい世界の記憶を持って旅立った『怪盗ぐるぐ』を継ぐ『ぐるぐ』は諦めやしない。 対して、その力を見るヘルガから漏れるのは溜息だ。 「……本当は、敵の力なんて嫌よ」 死に塗れた技。生を呪う弾丸。けれどそれが生を繋ぐ役に立つならば、彼女は得たい。 そう願いながら、歌を唱う。 「バレット、お前はここで倒ス! そしテ必ずお富さんを連れて帰るのダ!」 カイは叫んで、十字の光を放つ。それに一瞬照らし出されたのは――。 「……って、藍!? どうしてココに居るのダ、 子供たちはどうしたのダ!?」 「ここ三高平が戦場になってるのよ。どこにいても危険なのに変わりはないわ」 いつの間にか傍らに立つ藍の姿に目を見開けば、彼女は背の翼を羽ばたかせながら首を振る。 自分ひとりで戦うなんて。子供たちの為なんていいながら、自分の好き勝手やってるだけじゃない。 こんな危険な戦場に、一人で行くなんて。 「藍……」 「カイ、しっかり治してよ」 守ってくれるって、信じてるんだからね。 「……ああ、絶対一緒に帰るのダ!」 藍が放つ思考の奔流が、カイの聖骸凱歌が、共に戦場に響き渡る。 「ここは絶対通さない。わたし達が帰る場所なんだから、奪わせない」 「一人では出来なくとも……皆が傍にいる。それだけで、あひる達は……アークは絶対に負けないんだから!」 回復の要、絶大なる回復力を誇るあひるを守るのは壱也だ。 少女らは死者の群れの中、離れぬように身を寄せ合い戦っている。 だが、溢れているのは死体だ。山の様な死人だ。 そしてネクロマンサー最大の武器は言うまでもない、死者だ。 「さあさ踊れよPulcinella! 観客がお待ちだぜ!?」 撃ち出されたのは骨の弾丸。けれども狙うのはリベリスタではない。死者達だ。無数に放たれた弾丸が死者に食い込み肉を穿って体に泥む。 「……っ!?」 ぎちり。死者の一撃を受けた壱也が目を見開いた。華奢な彼女の細い腕の筋肉へと多大なる負担を掛けたそれ。元より損傷になど頓着しない死者だが、最後の箍さえ外れたかのように……己の肉が自身の放った攻撃の威力に弾ける程に、骨が内部で砕けて飛び出す程に、強化された肉体のリミットさえも越える一撃を繰り出して来る。 リベリスタが死者の多くを巻き込める位置を探すのと同様、バレットが動き回るのは効率よく強化した死者の群れの只中にリベリスタを放り込む為。 無論それは諸刃の剣。長期戦には耐えられない特攻使用。壊れるまで踊れ、哀れな道化! バレットを止めれば死者達は止まる。故に彼の撃破に向かう数が優先されたのは間違いではないだろう。だが、死者の群れは単なる賑やかしではない。ネクロマンサーの『武器』だ。 「おごっ」 ユーフォリアの傍らで、仲間の一人が引き込まれた。めきめきと、骨が折れるいやな音がする。 「おっと……これはあまり相手をしたくはないですね~」 言いながら、ユーフォリアはソードエアリアルを叩き込む。切り裂かれた死者の中、覗いた手を握ったのは忌避だ。 群れから引きずり出しながら、唱えるのは天使の歌。 「みんな、死んだら駄目なんだからねっ! 怒っちゃうんだからね!!」 忌避は死を忌避するのだ。目の前で死になんて飲まれてたまるか。 「御厨の名に懸けて頑張っちゃうよ、おー!!★」 死者の腕がその体に減り込んでも、引き摺り出す手を緩めない。それが、忌避にできる事。 「面白ぇなあ、どんだけ殺せば倒れんだよお前ら!」 「それは此方の台詞だよ」 笑う声に、クルトが応えた。辿った音、弾丸が放たれる度に、死者がうねる度に聞こえるピッツィカート。彼の耳は、それを逃さない。幾度も聞いた、あの音だ。 「よう、クルトだったか。気が変わって参加する気にでも?」 「いや。お前の最期の客になりにきた」 繰り出されるのは、虚ロ仇花。パフォーマーの肌に鮮血の花を! クルトは油断しない。侮らない。余力のある内にバレットを討たんと、その全力を以って相対した。 「ははは! やってみろよ、出来るんなら……」 バレットの目が細められる。ぎちりと腕を吊り上げたのは、憎悪の鎖。 「バレット、貴方とはこれで4度目ね」 放ったのはエーデルワイス。彼女もまた、バレットの蛮行を、最も多く見てきた一人。 薄っすらとした笑いが、にいっと深くなる。 「今日こそは貴方の命を貰い受けるわ! ――楽に死ねると思うなよ」 「ああ。じゃあどうする? 抉って砕いて引きずり出して、頭を砕いて啜るってか?」 「ノー。呪縛の鎖に苛まれながら全身を蜂の巣とするがいい!」 この度の鎖は振り払われども、何度だって吊ってやる。彼には絞首が相応しい、この手で処刑してやらねば! その額に食い込んだのは、九十九の弾丸。 「銃弾の音を沢山聞かせて差し上げますな」 バレットを支える霊の守り。楽団を不死たらしめる守護を打ち砕くピアッシングシュート。 それを打ち払えば――後は只管、叩くだけ。 「貴方の死の音は他人ばかり。その身を以って死がどういう音か、味わえばいい」 骨の弾丸を掠めるだけで避けたエレオノーラの刃が、瞬く間に距離を詰めてバレットの髪の一房ごと頬を切り裂いた。 焦点が合わないが故に交わらない視線。けれどバレットは確かに、彼を見ていた。 「ああ――最高の一音を味わえるようにな。俺の死を、お前はサイコーに奏でてくれんのか!?」 弾丸が荒れ狂う。強化された死者達が、リベリスタの前に立ちはだかる。 富子が歌う。 癒しの歌を。 死者を弄ぶ生者を癒す歌を。だが、それが唐突に途切れた。 「……おやすみなさい」 血に塗れた魅零を片手に抱いて、俊介が呟いた。彼の前に倒れた達哉が最後に放ったパーフェクトプランが、富子の体を貫いたのだ。その一瞬を見逃す俊介ではない。庇われながら集中し続けた彼が放った浄化の炎が――今度こそ、富子の体を覆い地に伏せる。 「あの優しい人が、もう戦わなくて済むように……!」 服を血でぼろぼろに汚しながら、ヘルマンが斬風脚を放つ。 「パフォーマー、お前が初めてだよ。どんな代償を払っても何を歪めてでも勝ちたい。腹の底からそう思えた相手は」 クルトが放つ、目にも留まらぬ武芸の極み。骨の弾丸に幾度も貫かれながら、けれど彼は逃さない。彼の『敵』を真正面から見据えている。 運命を歪めたって構わない。その音を超えられるのならば。 「は、はは」 雨霰と降り注ぐ攻撃に、答えるのは笑い声。狂気を孕んだその笑みを、死者の群れが覆い隠す。 影で青白く燃えるのは、運命の恩寵。 「ひっさびさだなあ、オイ」 ぬるりと血で滑る額を拭い、バレットは呟いた。 彼は確かに、近くで足踏みする青白い『死』の足音を聞いたのだ! 何年、それとも何十年ぶりか。これだけ楽しいものが、こんな場所にあろうとは! 「ああ――勿体ねぇ」 漏れたのは本心だ。勿体無い。ああ。こんな楽しい『演奏』をここで終わらせるのか。 当然、リベリスタは終わらせるつもりだ。 アンコールはない。そう呟いた九十九の心は皆の代弁。これ以上、こんな『演奏』を続けさせてなるものか。けれど、死者が立ち塞がる。 パフォーマーを覆い隠す。強化された死者は、容易く抜けさせてはくれない。 ただ一人、逃亡を危惧していた佳恋も――その腕は、運命を歪めるのに届かない。 暗闇へとその姿が躍る。彼は光を必要としない。暗所を選んで、消えていく。 暫し後に、死体は糸が切れたかのように抵抗を止めた。 死が死に、戻っていく。 生を死に引き込まぬまま。 「……おかえりなさい。母ちゃん」 倒れた『母』の傍らに座り込み、俊介が笑う。零した涙が、血に濡れた地面に広がった。 死体が溢れている。 幾つもの死が、そこに転がっている。 けれどリベリスタは、確かにこの地を守りきったのだ。 遠くの戦場で、誰かが叫んでいる。 生きている、誰かが。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||

















































































































