


一撃決着・2012

|
●模擬戦ふたたび 「本日、皆さんをお呼びしたのは他でもありません。ちょっとデータ収集も兼ねて、模擬戦のお誘い、ということで」 やや広いブリーフィングルームに集められたリベリスタたちに向け、『無謀の予見士』月ヶ瀬 夜倉(nBNE000202)は会話を始めた。 手にある資料の束は、どうやら昨年行われたと思しき模擬戦のデータである。といっても、決して普通のものではないのだが。 「昨年、一対一での『一撃決着』形式の模擬戦を催しました。ですが、ルーリングの点で大いにムラがあり、確実性に欠けるということで、それなりにブラッシュアップしたものを用意したつもりです。 今回はVTSを経由して行う戦闘なので、一括管理もできますし負傷はデータ上ですから、問題無いでしょう」 一応、前の一件を踏まえて色々と腹案はあるらしい。只の模擬戦では効率的ではない、というのは当然だが、一対一、しかも一撃で決するそれが使い物になるかは正直、難しい。 「言うまでもないですが、個々人の希望は詮索しないとしても、実力差はある程度考慮して下さいね。マッチングの際、フリーなら僕も考慮しますが……配慮を、お願いします」 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:風見鶏 | ||||
| ■難易度:VERY EASY | ■ イベントシナリオ | |||
| ■参加人数制限: なし | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2012年11月01日(木)22:57 |
||
|
||||
|
||||
|
●たった、一合 それがたった一撃のために与えられた猶予だとするならば、人智を超えた身である彼らにとって或いは長すぎるのかもしれない。 たった一合のために研ぎ澄ます時間だとするならば、神経は擦り減らされ潰れてしまうだろう。 だが、たった十秒は余りにも重い十秒だということを彼らは知っている。 だからこそ、浮かぶ瀬もあれというところか。 「まぁ、腕試しってのもたまにはいいよねぇ」 恰幅のいい身をかるく解し、富子は正面を見据えた。 魔力を操り、遠間から戦う彼女からすれば、相手となる御龍は決して相性のいい相手ではない。 とは言え。そも、彼女が間合いを取る、であるとか避ける、というクレバーな戦術を取るわけがない。 彼女の戦術はシンプルであるが故に異常である。 ……更に言うなら、このルール下にそぐう戦い方ではなかった。 それでも、数十秒を置いて彼女が勝利を手にしていたのは恐らくは偶然の連鎖である。 偶然ではあれど、それを引き寄せる決意の差である。それを理解できないままに結果を受け入れられる程度には。 その戦いは、本当に「たまたま」であっただけのこと。 その意味は、恐らく何れ知る事となるだろう。 リンシードは、目を輝かせていた。 胸を借りる気持ちで望むこの戦いは、レイラインと培った経験を彼女自身にぶつけるという意味では重要な一戦だ。 「では、バイデン流で……戦士リンシード……行きますっ!」 最速の勢いをそのままに、(リア充への怨讐含めて)踏み込んだリンシードに、一切の躊躇は無い。 本来なら善戦もありえただろうが、この期に及んではリンシードの意思が勝った。 「リア充に負けるわけにはいきませんでした……!」 誰か、この幼女に見合う筋骨隆々な男をはよ。 「一撃決着……つまり初撃を食らったら終わりってことだよね~?」 「体力無い耐久力無い避けられ無い、一撃で沈む可能性が高い……」 陽菜と依季瑠は、互いにビビ、じゃなかった慎重派である。 慎重という言葉は戦闘に於いて殊に捨て去られるケースが多いが、この二人に限っては策を弄すことで己と仲間を活かすことを識るタイプだ。 要は、集団戦で敵に回したくない類い、と言って差し支えない。 「初撃さえ凌げば」 「このルールでならば」 ――勝てる! 取り立てて理論武装はない。だが、『そんな気がする』のだ。 そして、動き出したのは数瞬、陽菜が早い。その外観からは考えられない安定性をして、ブーツサンダルが鮮やかに地を蹴り――、一目散に後退した。 「えっ?」 あっけにとられた依季瑠だったが、遅まきながら状況を理解したか、慌てて動き出す。焦り気味に放った魔矢が、しかし地形を活かした陽菜を捉えることは叶わず脇に抜けた。 (このまま行けば……!) 陽菜は、確信を持った。初手を凌いだことへの自信が、次手への余裕を作る。落ち着きを得た彼女がいつもどおりに動けば、勝利は難しくなかったろう。 しかし、タイミングは何時だって残酷だ。次手を確信し突き出された彼女の手を、二度目の魔矢が掠め過ぎた。 そう、たった一瞬。遅れをとった一度目を挽回するように、天秤は依季瑠に采配を与えた。 そして、彼女はそれに応えた。 「……希望くらい、持たせてください」 普段攻勢に魔力を割かない彼女の、肩で息をするほどの決心の一言であった。 「私如きで相手に足りますか、分かりませんが」 「このルールなら私の出番だね」 命中に捧げ回避を削ぎ落した、という身は恐らくジョンとシャルロッテを語るに於いて同一項ととっていいものだろう。 ただ、両者共に遠間を主体とする戦士である、ということだけは確かだ。 ジョンの指先が気糸を紡ぎ、広範へ向けて叩き付けられた。間合いに飛び込んだシャルロッテの身を強かに打ち据えるが、耐えられぬダメージ量ではない。 当てればいい。ただそれだけを意識して反撃を行えば、その精度から逃れ得る者は寧ろ少ない。 痛みを威力に変ずる一撃は、確かにジョンへと届く。互いの精度は互角――だったのだが。 次手を避けることで、確実な一撃へと備えようとしたジョンを、しかしシャルロッテの暗黒が無慈悲に圧し潰す。 策が悪いのではなく――相手が悪かった。それだけのことだろう。 実力を測る、という意思で戦場に身を置いたのは、セラフィーナと愛音とに共通するところである。 互いの戦いの特性が異なる以上、如何にそれを制圧し、自らの戦いに引きこむかが寛容であるとも、言える。 例えそれが不得手なものの類だとしても愛音は退かないだろうし、実力差があろうとセラフィーナは怯まないだろう。 「推して参るでございます!」 気を吐いた愛音に対し、納刀したまま僅かに身を引くことで先を促したセラフィーナだったが、愛音は彼女の予想を大きく上回る程度には――狡猾だった。 数歩引き、すかさず影人を喚び出した愛音へ踏み込もうとするが、当然の様にブロックに回ったそれへ、セラフィーナは容赦なく抜刀し、斬撃を放った。 (自分が思っている以上に、実力差は無いのかもしれない) 愛音へ先手を許したことが間違いということはなかろうが、彼女と同等程度の能力を有する影人を突破してたどり着くのはなかなかに困難だ。 二撃をしてなんとか影人を打倒したセラフィーナを待ち構えたのは、腰を据えて構えた愛音の手に顕れた鴉。 「一対一だとしても、引くわけにいかないのでございます!」 「これが……姉さんと私の技です!」 再びの納刀。そして抜刀。斬撃が七色の光を引いて抜け、鴉は己の役目を果たし符に還る。 一瞬の静寂のあと、一撃の傷の深さが勝ったのはセラフィーナのそれだった。 ……或いは、愛音が勝利する見込みもある程度には策で拮抗した戦いだったといえるだろう。 「ありがとうございました! LOVE!」 元気だなあ。 「ぜんえーがたれいざーたくとミミルノけんざんっ!」 「どうぞよろしくお願いします、お手柔らかに」 熊のグローブを高々と掲げたミミルノに対し、メイスを構えたメリッサは飽くまで真摯だった。 氷上の足場を確認するように軽く踏みしだいたメリッサは兎も角、対策の無いミミルノには戦いづらい環境だろう。 余談だが、胸を借りるも何も彼女の方がいやなんでもありません。 間合いを詰め、攻撃を受け止める覚悟でメイスを構えたメリッサに対し、ミミルノは \でぃふぇんさーどくとりんっ/ 自付してた。 だが、それで手を止めるメリッサでもない。慎重にだが確実に距離を詰め、上段から一撃を振り下ろす。 回避行動をとったミミルノは氷に足を取られ、バランスを崩すも回避し、返す刀で拳を振り上げる。 「ちょうひっさつ! みみるのくまぱーーーーんちっ!!」 ぺこぽこぺこぽこ。 バランスを欠いた状態での拳は決して精度の高いものではない。 だが、メリッサの胴を打つには十分な精度であったことは確かである。 ――とはいえ。受けるだけで反撃しない少女でもない。足を止めての殴り合いを想定したメリッサには望むところということか。 「うおー! とゃー! ちょぁー! せいやー!」 「私で、はまだまだ歯が立ちませんね……」 決着はついている。ついているが……「まいった」を言わせたかったミミルノのだだっこぱんちは暫く続いたとかなんとか。 誰が相手でも変わりはしないのは、隆明もアルフォンソも同じである。 自らの才を識る彼らの戦い方は、しかしその扱いでは真逆であった。 リボルバーと閃光弾が交錯し、互いの間合いへと打ち込まれる。 両者の精度は決して低くはなく、相手の回避を凌駕してその身へ当てることが可能なそれだ。 だが、その一撃の精度は――僅かばかり、アルフォンソが上回る。 「時の運、というやつでしょう」 「遠慮なしにやったんだ、満足行く戦いだったぜ」 堅調な戦いだったとはいえない。だが、その一撃の集中力は確かな糧となりうるだろう。 「西部劇っぽくいきませんか? この帽子が落ちた時に試合開始ということで」 「いいでしょう、どっからでも来い!」 エーデルワイスの提案に対し、ベルカの反応は至極好意的だった。 というか、彼女にとって状況や相手はさしたる問題ではない。要は、一撃に掛ける気迫の程度である。 高く帽子を放ったエーデルワイスを前に、ベルカは音もなく膝射の体勢へ移行する。 伏射に次いで射撃精度が高いと言われる姿勢ながら、構えがずれれば精度を大きく落とすテクニカルなそれを操るのは簡単ではない。 僅かに陽光が氷を穿つと同時に、ベルカとエーデルワイスの銃弾が放たれる。 「早撃ちこそ、美学!」 「息を吸って吐いて、撃つ!」 狙いは、両者とも同じ。 故に、銃弾の軌道も近く、互いのそれが掠めて脇へ抜ける。 ――一瞬の後に。デジタル化して強制終了を受けたのはベルカだったが。 エーデルワイスの側頭部の髪を削り飛ばしたのは、他でもない彼女の銃弾だったことは言うまでもない。 「……かつて、見る事が無かったその刃。如何程の物か、見せて貰う」 「おう、見せてやんよ。俺様の剣は――痛いぜ?」 自らを不利に置くことで。 自らの有利を認識することで。 創太と拓真は対等であることを認識した。 彼らの言葉を借りれば、地の利を借りた『癪に障る』戦い方なのだろう。 だが、それを押しても互いを高めあおうと思うなら、それは『対等』であることの証である。 両者が限界を超えたのは、氷上を奔る僅かな罅が証明している。 「加減は一切抜きだ、互いの最高の一撃を以て決着をつける……!」 「さあ、ド派手に真向に!喧嘩の華と、行こうじゃねーか!」 声を同じくし、存在証明を賭ける。 創太の空中移動を処理し、同時に移動の慣性を殺しながらの攻撃は決して拓真に有利ではない。だが、それでも四合もの連撃を同格として凌ぎ切ったのは特筆に値する。 相対した二人の構えは、同じ。デッドオアアライブ、生死を文字通り賭けた一撃をして五合目とする。 「行くぜ、新城。互いの全力を以て――」 「我が渾身の一刀――」 直進し、或いは待ち構え、その一撃は放たれた。 「今日は『死』だったか、惜しかったな畜生……」 「いい一撃だったよ、十凪創太」 本当に僅かの差。僅かに深く入っただけの一合は、拓真にその勝利を預けたのだった。 「廃墟での戦いって何だか燃えるよね」 大型の散弾銃を肩に担ぎ、飄々と語る喜平へ向け、綾兎は自付ありでの戦闘を提案する。 元より先手をとれるならと想定していた彼にとっては渡りに船だったか、二つ返事で承服したわけだが……表情のアレさ加減がすごい。やる気だ。 「宜しく。まぁ正々堂々……おっと手が滑ったぁ!!」 素晴らしいまでの不意打ちである。リベリスタにあるまじき? まさか。戦いをして確実な状況を導くなら、多少の騙し討ちなど対抗できないほうがおかしいのだ。 「うん、ちょっと気付いてた」 だが、ビーストハーフであり集音装置を最大限に活かしていた綾兎にとっては、それも戦闘を楽しむためのスパイスに過ぎないことは確か。 柊還を前方に掲げ、打ち払うように踏み込んだ彼の肩が僅かに裂ける。 流しきることは出来なかったとはいえ、直撃コースだったものを逸らしたのは大きいか。 そのままの勢いをナイフに載せ、速度を威力として放った一撃は――しかし、僅か届かず。スーサイダルエコーの表面を滑るように抜け、喜平に一歩届かずに消えていく。 「さすが……だね。勉強になったよ……その、ありがと」 素直に謝意を述べる綾兎に、しかし喜平の表情は僅かに渋かった。 もう少し複雑に、確実に不意打ちを放てるように、などと。考えていてもおかしくはないのだろうか。 「ん、あんたが相手ってわけか」 「ウム、宜しく頼む」 氷上をしっかりと踏みしめたモノマへ、僅かに浮遊した状態で一礼を向けるフツの様子は、僅かに、ほんの僅かだが申し訳なさげに感じなくもなかった。 目上の人間に厳格な彼の事だ。僅かでも頭が高い状態になっていることに後ろめたさを感じてしまうのは仕様のないことなのだろう、とも言えるが……。 相手が誰であれ、確実に闘いぬくモノマの前では些末事、なのかもしれない。 先に動き出したのは、モノマ。滑るように――本当に慣性のまま滑る動きは、ともすれば交差するものと感じてもおかしくない。 囁きが漏れる。フツだけに向けて、フツだけに聞こえるように。 「一対一の勝負中だ! 少し黙ってろ!」 その怒号か、或いは、滑るように交差したモノマの足がしっかりと氷を捉えたのが早いか。 雷撃を纏った拳が、フツの胴を打ち据える。徹った感触はモノマに猛りを与えるに十分だったが、その後に訪れた悪寒は確実にフツの動きに起因するものだと、彼は理解した。 至近での槍捌きは、かなりの技倆を必要とする。だが、その囁きを敢えて聞くフツにとってみれば、その言葉に応じ戦うことは難しいことではない。 モノマの肩を、槍の穂先が貫く。 互いに、精度は同等。 次撃を、とモノマが構え、拳を振るおうとしたところで、僅かに奔る違和感。動きは確かにいつも通りなのに、当たらない、と感じるそれ。 「呪いのお裾分けだ」 「……こ、のッ!」 槍が、呪ったか。タイミングに、呪われたか。 一瞬の不幸は、モノマの拳を逸らせるに値したのだった。 ……で、この後。フツはモノマに奢ったそうです。徳たけえな。 「有意義な試合にしたい。宜しく頼むよ」 「『有意義』にはなると思うわ。此方こそ宜しく頼むのよ」 ブロードソードを構え、しっかりと足場を踏みしめた零二に対し、エナーシアの反応はそっけないものだ。 だが、彼女とて相手を軽視しているわけでも自分を過大評価しているわけでもない。 ただ、『自分の在り方』に挑戦しているが故に周囲に視線を向けていない、という形に近い。 斯く言う零二はといえば、氷上での戦い方を相手から学ぶため、同時に自らの身で実証するための戦いだ。 相手への注意が入るとしても、結果的に帰着するのは自信の技倆。 そういう意味では、彼らは実に『利己的』なのだ。 故に、零二はエナーシアのとった『対策』に目を瞠った。単純だが、しかし誰も普通ならやらない手段。 「普通」なら、絶対に行わない――伏射姿勢での戦闘。 一瞬の思考ブランクを振り払うように、零二はエナーシアの元へ踏み込み、刃を振るう。 狙いは、彼女とその周囲。氷を切り払うことで踏み込む余地を作り、優位に立とうとしたのだが……刃は、尽く少女の身へは届かなかった。 堅実な狙いをとった筈だ。確実に当てにいった。それでも、彼女の持つ『悪運』はこの時は彼女に味方した。 (外したか、だが足場は固めた。いける……!) 「……ない」 相手の一撃を避ける、と決断した零二の耳に、声が響く。底冷えのするような感触は、しかし 「君と! 決着するまで! 引き金を引くのを止めない!」 酷い話でありました。 これはひどい。決着的に。 「よろしくお願いしますね」 「お、相手はキミ? おっけーおっけー! 宜しく!」 律儀に挨拶を向けたカイに対し、宵子は軽く腕を回し声をかけた。 この戦闘に於いて全力を尽くそうと構えていたカイに、しかし宵子は正面からの殴り合いを希望した。 避けず動かず正面から殴りあう。それが彼女の希望である。 尤も、カイとて近接での戦いが不得手であるわけではない。 ただ、拳での戦いではないというだけの話だ。 宵子が、拳を固める。正面からその拳をカイの眉間へと向け構えたところで……彼女の動きが、操り人形のようにぴたりと止まった。 対するは、縦横に張り巡らされたカイの気糸。ほぼ紙一重のタイミングで止められたそれは、僅かな技倆の差であることを感じさせた。 「お互い、日々精進の気魄を忘れないようにしましょう」 「や! キミ強いねーまたやろうねえ」 カイの言葉に対し、宵子の応答は爽やかなものだ。戦いを好むがこその在り方、ということだろう。 「よろしく、守護神」 ユーニアと快は、共に護り手を自称する者である。 殊に、ユーニアは未だその成長の途上にある故に、快から教えを請うことをこの戦いで選択したのだ。 (盾役としての俺流の立ち回りを、この一戦に込め、彼に見せよう) 故に、請われた側の快はその在り方をユーニアに教えるためにここにいる。 先を行くものとしての義務を、彼は正しく理解している。 「あんたの持ってるもんを見せてくれ」 「ああ、いいだろう。ついて来い!」 二人の声が呼応したところで、先んじて動いたのは快だった。 ナイフを構え、一直線にユーニアの間合いへ踏み込んだ彼は、上段からその刃を振り下ろす。 「阻止対象の敵に先んじて踏み出し確実にブロックする。盾役の初動一つが戦況を左右するんだ」 「受け止められるか分からないけど……なら」 全力で応じ、自らを叩きつけるだけだ。 敵意ではなく害意ではない、この感情を叩きつけるために。 命を奪う刃を、奪うためではなく識るために使う。 この感触を覚えるために――その一閃は、快の肩を掠めるのみ。 一瞬の精度は、快にその采配を与えた。 「……ありがとう」 戦い方を学び取ったユーニアにとって、去来したのは感謝だ。 戦場で、それを証明する義務と共に多くを得たという確証が、この戦いの実りである。 「よぉ、焔。偶には本気で殴り合うのも良いかと思ってよぉ、どうだよ?今の気持ちは」 「遠慮も容赦も要らん。偶にとは言わずいつでも掛かってくるがいい、葛木」 友人であり、競うべき相手である優希と猛にとって、互いは自らの成長の指標となるべき相手である。 対等に、確実に競い合うことで自らを理解することが出来る相手だ。だからこそ、手を抜けない。 「ハハッ、まぁ、滅多にねぇ機会なんだ。派手にやろうぜ」 「望むところだ、葛木」 なので、かわす言葉は最小限でいい。 向ける技も、ただ一度でいい。 「……猛! 俺の全てを、叩き付けてくれる!」 優希が、猛を『名前で』呼ぶ。 低く、地を這う姿勢から一気に踏み込んだ彼の掌底は猛の胸元を貫いた。 打ち上げるのではなく、強引に下方へのベクトルに切り替え、叩きつけようと振り下ろす。 轟音が空間を響かせる。会心とも言えるそれに感じた手応えは確かだ。だが、違和感もある。 「いい一撃だった……行くぜ、焔アアアアアアアッ!!!!!」 握り締めていたのだ。彼の手首を。猛の手が。 驚愕を覚える間も、受け流そうとする動きも間に合わない。 これは正に、肉を切らせて骨を断つ思考そのもの。 ――雷撃が、優希を貫いた。 「一発で終わりとは生ぬるい! 倒れるまで殴り合ってくれる!」 「いいぜ、最後までやってやらァ!」 勝敗ではなく戦いではなく。 ただの、男同士の下らない喧嘩――それも、いいのだろう。彼らの『言葉』として。 「尋常の勝負なれば、我が剣の誇りをかけて、お相手致します」 「わ~☆ 思ったより滑るね~☆」 ……ノリ違うなあ。もとい、終と舞姫の(戦闘開始時の)ベクトルは全く異なるものだった。 氷上での安全靴の感触に僅かに驚きつつも、終は常通り。冷静である、ともいえるだろう。 対する舞姫も、彼女なりの全力を感じさせる。 「いや~ん、足下の氷に映って、ぱんつがみえちゃーう! きゃー、おわるくんの、えっちすけっちわんたっちー!」 (条件は同じなんだ、無い部分は手数で補う……!) 「チッ、引っかかりませんか」 戦闘開始前から場外戦とか何やってんだお前。そうだよ舞姫だよコノヤロウ。一瞬感心したこの想いを返せ。 「先手必勝……っ!」 ほら、終とかすげえ綺麗なソニックエッジだぞ。軌道が完璧だぞ。 でも、それをきっちり捌いて鍔元で受け流す舞姫とかマジ恐ろしい子。再動の機会を得た終が神経を研ぎ澄ませるが、それで知覚したのは攻撃精度の上下ではなく、舞姫の行動意図。 「ああ~ん、すべっちゃって、舞ちゃんこわーい! ……乙女の涙もガン無視ですかコンチクショウ」 「それはちょっともうオレの台詞じゃないかな!? ……あ」 ええ、そうです。アッパーユアハートです。入りました。 分かったから舞姫、終の想いを汲み取ってその反復横跳びはやめろ。かわいそうだろ。 冴は、眼前に立つ竜一から立ち上る鬼気を感じ取っていた。 常の軽い調子ではない。戦いで見る彼よりもより重く、鋭い気配だ。 (無様な自分が許せん。心を洗うために、この戦いを耐えなければならない) 「蜂須賀示現流、蜂須賀 冴。参ります」 (何を考えているかは分かりませんが、手を抜くわけにはいかない) 故に、竜一が何を目論んでいようとも冴は全力をぶつけるだけである。 そうでなければ、相手にも自分の剣技にも嘘を吐くことになろう。それだけは、耐えられぬ。 「チェストォォオオ!」 「……!」 大上段から、鬼丸が振り下ろされる。竜一に、攻めの意思はない。振り下ろされるそれを、雷切(偽)で――弾き飛ばす。 彼の選択肢はひとつ。初手二度を、尽く弾くという絶対意思。 だが、冴にその感情の機微などわからない。一度目を流されたなら、二度目を打ち込む。何度でも、同じく。 二度目のギガクラッシュが、竜一の刃と打ち合わされ――その軌道を逸らし、竜一の脇腹を僅かに裂いた。 「……俺の負け、か。耐えられなかったな」 事実上の「耐え忍ぶ」とは違う。凌ぎきることができなかった、という事実を冗談めいて笑ってみせる。だが、その言葉の重みは冴にはよく分かる。 「竜一さん、それでは……鍛錬に付き合って下さい」 「え、これから?」 「決着はついたんですから、此処から先は自由でいいでしょう」 だからこそ、何も考えなくていい時間は必要なのかもしれなかった。お互いに。 「バーチャル空間なのだからな。遠慮など要らんのだ」 自分に言い聞かせるように、火縄銃の状態を観察する龍治の表情は硬かった。 相手が、優秀な射手であるから――だけではない。 自らの大事にする相手だから、ということもあるだろう。 互いに、避けることを捨て当てることに特化した射手同士だ。最大射程の相互距離は、そのためにとったと言って過言ではない。 「初めから食らうつもりでいくぜ。肉を切らせて骨を断つってやつだ!」 それについては相手である木蓮も同じようで、既に十分な戦意を以て視界の先を見据えている。 三十メートル。一般的にやや遠く感じられるだろうが、彼ら射手にとっては刹那の距離だ。 そして、銃弾が放たれたのは……些か以上に、龍治のそれが速い。 硬質の物体同士がぶつかる、剣戟音にも似たそれは、銃弾同士の貫徹音だ。全く同じ軌道、同じ狙い、そして僅かなタイミングのズレも許さない交錯が、銃弾同士の衝突を許したのだ。 ――遠間の『剣戟』は都合三度。当てることも敵わず避けることも適わぬそのぶつかり合いは、四度目にして逸れた。 龍治の脇を、轟音が抜ける。 「ふう、終いか。バーチャル空間とは言え、長々と続けたくは……おい、大丈夫か」 駆け寄る龍治の声に抑揚はない。だが、焦っているのは表情からも読み取れた。 「…………ぷはっ! へへ~、驚いたか?」 「……全く」 気絶したフリに興じた木蓮の頭を、龍治は乱暴に撫で付ける。 ただ、この相手に現実で勝てる気もしない、と心の中で少し感じる龍治であったりもするわけだ。 「……鉄鬼や粘液との戦いでご一緒させてもらって。 貴方の力強く華麗な舞踏に、どうしようもなく魅せられちゃいまして。 ぜひ挑んでみたい、そう思っていたんです」 「じゃ、楽しんで遊びましょう?」 自らの心に留まった『憧れ』を、レイチェルは隠すこと無く吐き出した。 応じたエレオノーラも、軽く笑いながらも受け入れる。だが、その内実はレイチェルに同じだ。 多くの死線を共に歩んだ同士である彼女を、決して軽く見るつもりなど無い。或いは、現時点最強の敵と目してもいいだろう。 それだけ互いの癖をしっている、という同士として。 レイチェルの思考が加速し、エレオノーラの速度のギアが上がる。互いを高め合うからこそ、レイチェルは工場の中を駆け抜けた。 隠れた場所は、エレオノーラには判断できない。だが、待っていれば勝てるわけではない。 熱の律動を察知した気糸が、レイチェルの隠れた位置を僅かに逸れて穿たれる。 返すように放たれた気糸の乱舞は、狙っていないにも関わらずエレオノーラを襲ってくる。確実に、追い詰めるように。 その位置を割り出しながら、エレオノーラは距離を詰め、レイチェルは移動経路を狭めていく。 そして、互いの姿が露見したところで――両者の動きは加速した。互いにとって、互いがコマ送りになっている感覚。 空中に追い詰めようと、気糸を放ったレイチェルは息を呑む。 その瞬間には、既に。 エレオノーラは、その間合いに入っていたのだから。 「……とってもドキドキしました」 「久々にスリルがあって面白かったわ。こちらこそありがとう」 灰色のナイフを掲げ、笑うエレオノーラの手を取ってレイチェルは立ち上がる。 本当に刹那。その刹那が遠いと、感じながら。 「群体のリーダーの方ですね。まおは知ってますよ」 「何度も夢想したシチュエーションです……負けませんよ」 「まおも、頑張ってぺちぺちします」 弐升とまおの挨拶は、シンプルで静かだった。 だが、互いに相応に戦いに真摯な者同士である。美学がある。 故に、たった一撃で決着をつける戦いに滾らぬ筈がないのだ。 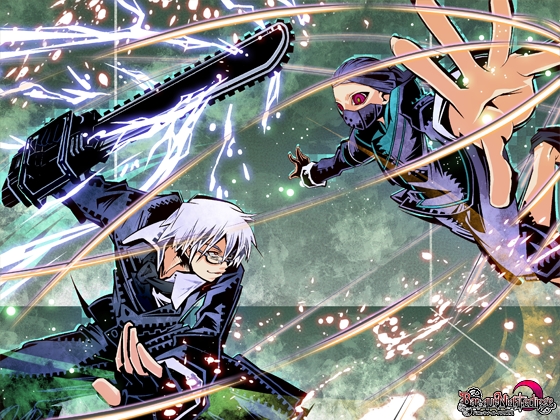 「群体筆頭アノニマス。我が戦鬼烈風陣、馳走致す」 動いたのは、弐升が僅かに速い。 だが、彼の刃が振り仰がれるタイミングで、既にまおの気糸は初動を開始していた。 それでも止めることは適わない。互いが同時なら当ててしまえばいいだけ。より深く、より疾く。 ほぼ、同時に。弐升の服が裂け、まおの胴に裂傷が刻まれる。 そして、両者は同時に動きを止めた。動かないのではなく、動けないのだ。 本来なら先手を打つべき者が勝利する局面。両者のそれを招いたのは、間違いなくその意志の強さだ。 ――無論。そこからの再動が速いものが勝利するわけだが、その辺りは各々の判断に任せるとしよう。 「慧架とやるのは初めてか」 暴れ兎と彼女が呼ぶ布の感触を確かめながら、杏樹は慧架と対峙する。 近接を主体とする者同士の戦いを所望した彼女の目は爛と輝き、これから始まる打ち合いを十分に期待していることを伺わせた。 訓練で叩きこまれた拳の使い方を、実践を以てその身に改めて刻みこむ。 勝利や敗北の慮外にある、経験則を積むための戦いだ。 尤も。経験を積むだけでは足らぬ。得るのは経験以上の何かである。 「貴女か私、どちらかが回避してあてるまで遣り通します!」 「望むところだ、それでいい」 構えをとった慧架の目に灯ったのは闘争心。 付き合いの長い相手との闘争を、拳に映し一撃に灯す。 意味を持った殴り合いを、真正面から敢行するのだ。 間合いを詰めた両者が、拳を振るう。方や仁義、方や炎を纏った拳が、正面から二度三度ぶつかり合い、互いの身を砕き、焼こうと突き進む。一合ごとに完調へ復帰する殴り合いで、最後に差を付けるのは覚悟と気合だ。 「拳の頑丈さなら、慧架にも負けない……!」 がつっ、とぶつけられた拳が互いの軌道を逸らす。 非ぬ方向へねじ曲げられた慧架のそれを掠めるように、杏樹の拳は、その胴を、静かに打ち据えた。 ほんの一瞬の差による、結末だった。それだけの、ことだったのだ。 「っしゃ! 金髪メガネ、アークの覇界闘士として正々堂々やり合おうぜ!」 「手合わせするのはバイデンの村が初めてだったからニ回目だね。いくよ、色黒ヘタレ!」 覇界闘士としての先をひた走る彼ら二人にとって、互いを(ある意味)蔑称として呼び合うことは、彼らの想いがその真逆、互いを認め合っているということの証明でもあった。 ただ我武者羅に拳をぶつけあうのに、これほどの同格、これほどの強者を今の彼らが思い浮かべることができようか。 ……自らの在り方を捉えるという意味では否だ。 互いを誇りと思うから、互いに乗り越えたいと願うのだ。だからこその、たった一発の重みが他の人間に長じて重い。 「お互いの得意な一撃で行こうぜ、当たったほうが勝ち!」 「あぁ! そう簡単には負けないよ!」 氷上で軽く跳ね、タイミングを測る夏栖斗と、低く身を伏せ、一撃へ向けて溜めを作る悠里。対局であるが故に、同格の重みを持つ二人に、差異など無い。 悠里が氷を蹴り飛ばし、雷撃を振り下ろす。あたり一帯を雷光が包んだ刹那、彼を切り裂いたのは夏栖斗の放った虚空だったのは語るまでもない。 「お互い一番戦いたくないのは同じ覇界闘士ってとこだな」 「全くだね。攻撃は当てにくいし、こっちには当ててくるし、面倒な相手だよ」 互いが互いに向ける憎まれ口は、それだけ認め合っているということの表れだ。 そして、互いにまだ、戦い足りぬということの表明でもある。そして、決着は未だ、ついていない。 「そんじゃま、続き、手加減なしだぜ!」 「ああ、じゃあ、続きと行こうか!」 雷撃と真空が舞踏する、その戦いは正に突風であった。 結局のところ、最終局までもつれこみ、ほんの僅かの差で悠里が勝利を得たことは、ここだけの話である。 「確か去年の今頃も、月の冴える夜に貴女と戦ったわね」 月を背にして戦った、風流の名残。ミュゼーヌと彩花とが戦う理由は、対等でありたいがためだ。 「もう一年ですか。早いですね」 無論、彼女自信もそれは覚えているし、それの再現とは言わずとも、ここに至る理由は同じだ。 対等で有りたいと思うのは、それだけ相手を認めているということでもある。 「彩花さん。一曲、踊って頂けるかしら? 舞闘のダブルスを演じるとしましょう!」 「ええ、喜んで」 シンと静まった氷の上で、互いの声のみが存在証明であり。 互いから放たれた一撃が、自らの在り方を見せるのだ。 ミュゼーヌの蹴り足が、彩花の手甲を打ち上げる勢いで放たれる。 至近距離で受けるにはあまりに精度の高い一撃は、確実に彼女の腕にクリーンヒットし、衝撃を叩き込む。 痺れを受け止めた彩花が、返す刀で壱式迅雷を放つが、打ち据えられた手の感触は僅かに鈍い。 至近での雷撃の冴えに出来た陰りは、ミュゼーヌが身を捩るだけの余地を与えた。そして、その勝敗はその一瞬で、決す。 思えばあっけないものだと思うだろう。口さがない者ならつまらない、とも。 だが、この一合に凝集された一瞬のやり取りは、彼女たちをして互いを誇りに思う程度には重く、勝敗を問わず健闘を称えるに足る戦いだったのだ。 亘の口元は、自然な笑みが溢れていた。 戦うべき相手――リュミエールとの、均衡をとったとも言える力量差。そこまで肉薄した自分。 そして、勝敗が解らない現状など喜ばずしてどうしろというのか。燃え上がるにきまっている。 「ふふ……リュミさん勝負です!」 「ヤッテヤンヨ」 互いの声が聞こえるか否かの刹那で、工場跡から互いの姿は消え去った。 速度など、吹けば移ろう些細な差。 精度など、ほぼ同等。 剣戟が閃き、時に二度の攻め手も可能とする。それでも決着はつかない。 時間にも重力にも、ルールにすら縛られそうにない互いの交錯は数十秒を置いて決着にもつれ込む。 獣のように変幻自在に立ちまわるリュミエールと、翼を操り狂喜を見せ戦う亘と攻撃が、もつれ、絡む。 「さぁ,煌き舞い吹け、音さえ越える微風の技――アル・シャンパーニュ『光風煌星』!」 とても痛、じゃなかった格好いい名乗りが出たところで。 亘の勝利です。ええ、五合目にしての勝利ですとも。 「益母相手なら遠慮無く殴れんだろ?」 「丁度いい、俺もテメェと話がしたかった」 宮部乃宮 火車の苛立ちは、静かながら重々しく、そして激しかった。 そして、それを見据えるランディも、僅かながら苛立ちを覚えていた。 (以前は火の様な野郎だったが、今は精々『灰皿で燻ってる吸殻』ってトコか) だが、その視線は冷たかった。戦友を見る目とはとても言えない。火車が、そんな状況で居る原因などわかっているから、余計にだ。 (理由解ってっけどよ……!) そして、火車とて。 理由だって、妥当性だって、分かっている。でも、どうすればいいかなんてわからない。だから、拳に炎を灯して殴るしか無い。何を? 目の前にたついけ好かない奴の顔面を、だ。 「……そんなもんか?」 「……クソッタレがぁ!」 受け止めた姿勢のまま、ランディは烈風陣を放つ。 それは火車を吹き飛ばすに十分な威力で、彼を苛立たせるに十分な精度だった。 どうすればいい? どうすればよかった? なんだというのだ? 「どうしろってんだ!? あぁ!?」 「どうすりゃいいかなんてオメーが一番解ってるだろうよ」 二度目は、火車の拳が届く前に。ランディの構えた戦斧が、その身を横合いから吹き飛ばした。火車の息が詰まったような呻きが漏れ、転がる。 もう、模擬戦などどうでもいい。そう思った。そう思えた。ただ目の前の相手を叩き伏せたいという意思だけで、火車は立ち上がった。 「泣いて喚いて暴れて無様晒して、奴の魂に殉ずるってんなら、もっと無様に足掻いてみろよ」 「あぁ!? 殉ずる!? そうだろが! それ以外に……!」 「それでお前の女は喜ぶんだろ? あぁ!?」 殉ずる以外に知らないし、解らない。火車の苛立ちは『それしかできない』現状に起因するものだ、ということ。 そして、ランディの苛立ちはそれしかできない『と、思い込んでいる火車』の状況に起因する。 想いを継ぐことと、忘れないことと、それに殉ずることではそれぞれが大きく異なる。 「……クソッ……あぁ……そうかい……そりゃあ……クソッ!」 だから、多分それは自身でたどり着く必要があったのだ。 それを叩き込むためなら、憎まれようが構わない。 「……よぉ、益母。こりゃあ確かに……スカッとしたぜ?」 荒い息を吐きながら、何度殴りあったか解らないままに、火車は顔を上げ、ランディを見据える。 恐らくは、殴り合う前よりはずっとすっきりした表情で。 「……そういやお前に飯奢る約束してたな。腹減ったろ、行くか?」 「……食うに決まってんだろ!」 「今度こそ! 当たればいいと言ったな!」 当てるだけなら、彼のセバスチャンを、それ以上の存在を、超えることが出来る。 至上最必中を誇る比翼子の一撃は、全てに約束された勝利の糧である。 だが、それに挑もうとする果敢な者もまた、存在する。 「勝てるか勝てないかはいいんだ。少しでも可能性を上げることが大事なのだよ」 彩音、リベリスタとしてやっと一人前になったばかりの彼女が比翼子に挑んだ理由は、経験を積むためというだけではない。 恐らくは、自らの価値観、勝利概念に挑戦しようという腹づもりなのだろう。 恐ろしいまでの執念である。 そして、比翼子だって執念は同じだ。絶対に勝てる筈の技をして策に落ちるなど許されない。 だから、彼女は過去を省みながら振り返らない。 「――行くぞ! 星と月と太陽に最強を約束された我が奥義! ひよこデイブレェェェイクッ!!」 宇宙で一番かっこいい蹴りだ。 圧倒的な角度と精度と勢いで放たれたそれが、外れることなどありはしない。 それに応射した彩音のピンポイントは、あと僅かというところで比翼子の脇を逸れていく。 「見たか! これこそが勝利を約束された一撃……!」 七夕ってすげぇよな、ホント。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||



























































