


Rose of May

|
● 木香薔薇が咲き乱れるアーチが見える。 徐々に徐々に力強さを増してゆく陽光と、穏やかな風に乗る甘く深い香りが辺りをやさしく包み込んでいる。 時刻は正午付近だろうか。注視すればするほど進まぬ砂時計のように、時が静かに刻まれていた。 ただ、それだけであればよかったのに。 ただ、それだけであるべきだったのに。 ● 「五月の大型連休のことをゴールデンウィークと呼びます」 グルメ公主――もとい『翠玉公主』エスターテ・ダ・レオンフォルテ(nBNE000218)が披露するのは、誰もが知る一般常識である。 桃色の髪の少女はイタリア生まれらしいが、何年も日本で暮らしていたのだから別段新しい知識という訳でもないはずである。 とりあえずの相槌代わりにリベリスタは曖昧に頷いておくことにした。一体何の用事なのだろうか。 「フィクサードと推定される人物達が、薔薇とハーブの農園で何らかの会談を行うようです」 よりにもよって、こんな時に。こんな場所で。面倒な連中も居たものである。 「へえ。そりゃイイご趣味のフィクサード様で」 突然話がきな臭さを帯びてきたのであれば、皮肉の一つもこぼしたくなる。 エスターテの観測では、会談の内容は知れないが、フィクサードは偶然にも居合わせた野良リベリスタを、その場で始末する未来であるようだ。 「つまり、そのフィクサードを倒せってことでいいのかな」 「いえ、アークのリベリスタがその場に現れる場合、フィクサード側はそれを事前に察知して『現れない』ようです」 おそらく相手方にもフォーチュナが居るのでしょうと、エスターテは付け加える。 勿論、並のフォーチュナに神の目を欺くことなど、早々出来るはずもないのであろうが―― 偶然か必然か、可能性はゼロではないということか。 「なるほど」 少々の間を空けて、リベリスタが答える。 ずいぶんと警戒心が強いフィクサードらしいが、万華鏡の威力に加え、リベリスタの華々しい戦果を何度も見せ付けられれば無理もないことかも知れない。 結果として、アークのリべりスタが現場に居ることで少なくとも今回は、フィクサード達の計画は頓挫することになるということだ。 「未来を、変えて下さい」 少女が放つ抑揚に乏しい言の葉が無機質な空調の音に溶けて行く。 「じゃあ、遊べばいいのかね」 「はい」 結論は見も蓋もない。そんなこともあるのだろう。 後はフィクサードの情報が気にならないこともない所だが。 「フィクサードの情報はアーク本部が解析しています。だから」 静謐を湛えるエメラルドの瞳を閉じて、フォーチュナの少女は言葉を切った。 この件における幸福は、悲劇の未来を変える要素が死闘だけとは限らないという一点に集約される。 きっと羽を伸ばせばいいのだろう。 ただ行けばいい。すべきことなど何もないのだから。 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:pipi | ||||
| ■難易度:VERY EASY | ■ イベントシナリオ | |||
| ■参加人数制限: なし | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2012年05月13日(日)22:16 |
||
|
||||
|
||||
|
●開園 わたしは、MAI†HIME―― 華やかに舞い踊る美しき定めに生まれたプリンセス…… 可憐に咲き誇り、やがて散りゆく薔薇の花々。 ああ、これがわたしの宿命。 薄幸の美少女、舞姫…… 彼女が歌うのは、哀しみの調べ。 けれど、この短い時を駆け抜けるのよ。 一輪の薔薇のように気高く美しく。 ああ、ここに咲き誇る薔薇たちよ。 絢爛豪華に今を彩りなさい。 颯爽華麗にこの時に香りなさい。 わたしも、一輪の薔薇のように今を鮮烈に生きるわ! ――――『ぼっち』戦場ヶ原・ブリュンヒルデ・舞姫 ●花開く五月 夏に向かう日差しは、時折吹き抜ける涼風にかき乱されて心地よい温度を保っている。 待ちに待った大型連休も終盤に差し掛かり、平素は贅沢に感じられる遊び疲れが蓄積され始めた。そんな頃。 こんな日はどこか遠くで寝ていたい。 日常を離れ、新たな気持ちで。 たとえば丁度満開を迎えているであろうカモミールの花畑であるとか。 ちらほらと咲き始めたラベンダーの隣であるとか。そんな場所で。 兎に角ハーブというものはアロマの力で気分を落ち着かせて癒しパワーで露骨に眠くなるのである。 そもそも折角の連休だのだから、寝ないほうが失礼というものではなかろうか。 ハーブに囲まれて思いっきり寝てやがるのが、我等の小路である。 小豆色のジャージを寝巻きにして、みんなの憧れお布団に包まれてすやすや寝ている。 「……さん。ちっちゃくて、白くて……へへ、いい香り……キミ、とっても可愛いね」 常に生真面目な仏頂面を貫く彼の事、ほんの微かな囁きは余程近づかなければ分からないだろう。 安心して頂きたい。少年が声をかけているのは小さな花々に対してであるから。 生のカモミールというのは、思ったより鮮烈で深い芳醇な香りがする。あたり一面を優しく包み込んでいるのだ。 きっと沢山の愛情をもらっているのだろうなとルークは考える。 花達をほんの少しだけ分けてもらって、お茶にしようと思う。 夕暮れまでは、ここにずっと留まるつもりだった。 (……はぁ……ずっとここで暮らしたいなぁ、キミ達に囲まれて) ため息一つ。 視線を移せばそこにはみずみずしいローズマリーの姿があった。 ずっと留まり続けるなんて、無理だとは分かっている。いつか袂を分かつた親友と相見える為にも、彼はこれからも歩み続けなければならないのだから…… その程近くで本を頼りにハーブを採取していた少年が顔をあげる。 あたり一面のカモミールにローズマリー。ほんの少しのラベンダーとタイム。こんな所だろうか。 折角クラリス・ラ・ファイエットの執事になったからには、リラックス出来るハーブティーでも淹れたいものだ。喜んでもらえるように。 丁度その時、桃色の髪の少女が近くを通り過ぎた。 「こんにちは、エスターテちゃん」 「……こんにちは」 嫌がる様子はないが、どこか引っ込み思案な少女は会話を続けるのが得意ではないらしい。 「天風亘と申します。よろしければご一緒していいですか?」 そういえば、この前も見掛けたら話してみようと思ってはいたのだが、あまりの気候の良さに寝てしまったのだった。 少年の言葉に少々戸惑ったように、エスターテが頷く。少女は元来あまり社交的なタイプではないが――翻る少年の右手に薔薇の花が現れた。 突然の光景に少女が僅かに笑う。 「よろしければどうぞ。お近づきの印です」 「ありがとう。ございます」 花を受け取るエスターテがぺこりと頭を下げる。見かけは白人だが日本暮らしは長いらしい。 とはいえどんな生活を送ってきたかもわからない。まずは世間話でもしようかと少年は考えていた。 「エスターテちゃんは、好きなハーブとかありますか?」 「え、と。桃のコンポート、とか」 ……ハーブ? ともあれ香りの主張が強いのならば、煩わしいと感じることだってある。 (花畑とか、普通の子なら喜ぶのかしら……) 己自身は、むしろ鼻につく匂いが寧ろ煩わしい思っているのに。 普通なら綺麗であるとか、可愛いであるとか感じるのだろうか。 たとえば彼女の大切な恋人(ニンキモノ)を、時に取り囲むことがあるような娘達であるならば。 何より、二人を常に取り巻き苛むのは、命を削るような激戦に続く激戦であり―― 「自由に摘んでいいんだってさ」 そんなこじりの黙考をさえぎったのは、夏栖斗の人懐こい笑顔だった。 指に身を預ける一輪の花は、二人を覗き込むように首をもたげている。 「全部摘んでしまっても?」 僅かに天を仰ぐように、こじりが返す。 たとえばそのまま中央に御厨くんを横たえて。 『嗚呼ロミオ、今私が傍に行きます』 なんて。 「こじりもさ、最近余裕ないだろ?」 ままならないよな。 リベリスタってのも、しんどいよな。 「この香りはリラックスできる香りなんだって――まあ、妹の受け売りだけどさ」 少女達の日常は逸脱してしまっている。少女にとって、ただそれだけが辛かった。 いつだって怜悧に、眼前の全てを氷刃で切り裂いて歩む少女が僅かに見せる微かな弱みは、きっと夏栖斗と自分自身にしか見えないものだろう。 「薔薇もいいけど、君にはこういうおとなしい花が似合うと思う」 夏栖斗が一輪のカミツレを差し出す。 「リベリスタが辛いのではないわ」 やや間をあけて、受け取ったこじりは言葉を返す。 「あとさ、花言葉は『逆境に負けない強さ』だってさ。なんだか笑い話みたいだよな」 もっとこう、たとえば。 「『君が好きだ』とかそんな花言葉のを差し出すほうがカッコイイかもだけど。『今は』さ、こうやって誓うってのも、悪くないかなって」 「そう」 めぐる思考から生み出され、ため息のように紡がれた言葉。 もしも自分達が『普通』の人間だったならなどと、考えても詮無きことなれど。仮にそうであったなら二人は出会えなかったかもしれない。 「今はまだ、その花言葉に対して何も言えないわ」 少年はこれからも、少女の戸惑いや、時に溢れる秘められた激情も全て受け止めるのだろう。 だから少女は鼻につくカミツレの香りが、少しだけ好きになれた気がしていた。 ●Linseed(Perenial Flax)[Search Enter] 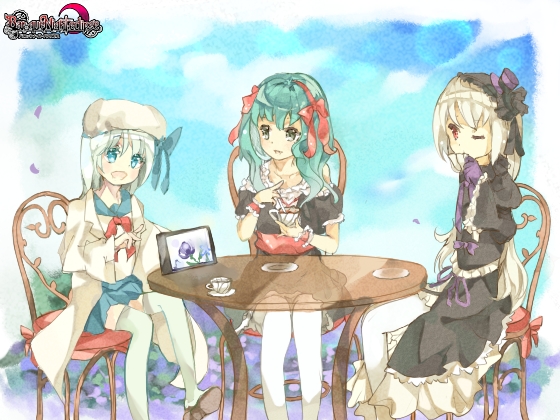 「今いちばん目立つのはカモミールですね」 タブレットPCを開くチャイカの解説に、webカムに捉えられた二人の少女が聞き入っている。 糾華等は、正直に言えばハーブについて全く詳しくはない。 「名前と、花と、香りがイコールで結びつかないのよね……女子力の限界を感じるわ」 「一番古い薬草として有名なんですよー」 聞きながらもリンシードの脳裏に張り付いているのは昨今の依頼の事。 折角誘って貰った以上は、どうにか気分転換したかったのだが…… 「ラベンダーなら、こうやってこするといい香りがするのですよー」 チャイカは解説を続ける。 「さすが、ですね……とっても、博学です……」 「ラヴェンダーはよく聞くわね」 「避暑地の看板植物ですよね」 確かにその通りだ。糾華は映像として見たことはあっても、そんな場所にこれまで行ったことはなかった。昔のことはどちらでもいいと首を振る。 「リンシードというハーブもあるんですよ」 「私と同じ、ハーブの名前、ですか……」 「はい、今は咲いていませんが亜麻の別名をリンシードと言うらしいですよ」 五月に入ってしまえば少し時期が遅いだろうか。次に花開くのは秋空の下だろう。 亜麻色という言葉を聞いた事があるだろうかとチャイカが尋ねる。そう、あの亜麻だ。 タブレットPCに表示されたのは、 「でも、亜麻色って感じじゃないわよね」 髪を糾華に撫でられ、道具のように扱われ続けてきた虚ろな少女は僅かに身を固める。 「綺麗な空色」 亜麻の髪と言えば、栗毛といか、榛というか、そんな色である。 ミルクティーにハチミツを加えると、タンニン結びついた鉄分の黒味が加わり、丁度そんな色合いにもなる。 リンシード当人は、これまでそんな事を考えたことはなく、なんとなく不思議な気分で話を聞いていたのだが…… 「花はこんな色なんですよ」 思い出を焼き付ける小さなカメラに少女達を捉えたままチャイカがタブレットを翻す。 「これって」 バックグラウンドで静かに動画の保存を続けるタブレットの表面に現れた亜麻の花弁は、澄み切った空色だった。 ●Rose Garden 五月といえば薔薇が最も美しく咲く季節とも言われている。このハーブ園には隣り合うように薔薇園が併設されていた。 その境は曖昧で、ハーブの隣に薔薇が植えられていたり、突如木香薔薇のアーチが姿を現したりする。 存人はそんなアーチの一つを潜り抜け、あてもなく散策していた。 別段薔薇に詳しいわけではないから、彼にとっての薔薇とは『ここに咲いているから薔薇なのだろう』という程度の認識だった。強いて言うならば花弁が多いものが好みだろうか。 赤白ピンクに黄色。ずいぶん色々な種類があるものだ。花弁が少ないものなどは、誰もが思い描く薔薇の一般的なイメージとはずいぶん違って見える。 こういうものを見せられれば、仮に香りさえ似ていたなら、これまでの道すがら咲いていたカミツレすら薔薇だと疑うかもしれない。 彼は目が好きだ。営む雑貨店『眼望』で彼を囲む商品達も、色とりどりの眼球をモチーフにしている。だからこうした光景は新鮮ではあった。 「……薔薇に眼球を置いた飾りとか売れますかね」 たとえば黒薔薇の中心に赤い目玉を配置すれば、退廃モチーフ好きのお客さんに人気が出るだろうか。 こんなに良い天気なのに、こんなことばかり考える性根は変えられそうになかった。 得意技は一人遊びだ。そんな自分が好きでもあるから問題はない。もう少し散策を続けようと、彼は再び歩き出した。 元はといえば万華鏡が映し出すことで変えられ消えた未来には、ここでフィクサードの会合があり一人のリベリスタが犠牲になるという事件があるはずだった。 結局アークの出現を感知したフィクサードは会合を取りやめ、今この時がある。 ただここに来るというだけで、フィクサード事件を未遂に終わらせることが出来たのだから、日夜激闘に身をやつすリベリスタ達にとっては願っても無いことだった。 悠月は思考を振り払う。折角の機会でもある。今この時を楽しまねば勿体無いというものだ。 「……何処かの物語の世界の中にでも迷い込んだ様だな」 拓真の呟きに、悠月も感心していた。 「本格的ですね……中々、素敵です」 山奥と言えば言いすぎになるかもしれないが、ずいぶんな田舎である。 そんな場所に本場英国の庭園に劣らぬ雰囲気があったのだから、拓真が感じる違和感も頷ける。 ここに到着するまでは、山間部独特の曲がりくねった道路に住宅が点在していただけなのだから。 木香薔薇のアーチを抜け、拓真は足を止める。 「……あなたにふさわしい人、か」 思い出されたのは花言葉。それに値するのだろうかという思考。 苦笑する。思考の渦に深く沈み込むのは己の悪い癖だった。 思い悩みながらも剣を振るい続ける己が身。悩む己の心の弱さすら、また彼の心を焼き焦がす。そんな循環だった。 どこかで断ち切りたいと思えど、どうにもままならぬが、そんな思考を追い払うように彼は一つの言葉を固めていく。 「悠月」 ゆっくりと先へと進む少女の背に、彼は呟いた。 君を……愛している。 「……確か。『純潔』『初恋』という意味もありましたね」 薔薇の香りを運ぶ風に揺られるように、悠月がゆっくりと振り返った。 「愛しています、私の初恋の人。だから……」 微笑む。だから自信を持って下さい。 「……そうだな」 拓真が頬を掻く。見透かされている。 「俺の月は、手の届く場所にあるのだから」 アーチの木漏れ日に照らされた二人の影が静かに重なった。 こんな日に、想いを重ね合わせているのは彼等だけではない。 「薔薇ってこんなに種類があるんだね。知らなかったなぁ。」 呟く悠里はカルナの手を握っている。 「赤の印象が強いのですが、薔薇にも色々あるのですね」 二人が恋仲になってから、ほんの少しだけ時が流れていたが、未だこうして手を握るだけで心臓は早鐘を打ち始める。 自分でも子供のようだとも思うが、こればかりは仕方ない。だがそんな想いを抱いているのは悠里だけではなかった。 隣のカルナとて努めて平静を保っているに過ぎない。恥ずかしいと思えば余計に恥ずかしくなるのだから、彼女はこうするほかなかった。 「うん、どれも華やかでとても素敵です」 のんびり出来る機会を設定した桃髪の少女に、こうしていられる祝福を天にまします我らの父へ。敬虔な少女は感謝を抱く。 平静を努めながらも垣間見えるのは、どこか嬉しげな表情だ。悠里はそんな少女の横顔を見やり、悠里は心中で良かったと呟く。 大きなアーチは恋人達の背を飛び越え、手をつないだままでも通り抜けることが出来た。期待通りの見栄えだ。 気持ちはカルナとて同じ。薔薇やアーチの出来栄えに喜んでも、それを大きなものにしているのは悠里が居るからだ。 むしろ彼と共にであるならば、どこであったとしても嬉しいのだから。 「とても綺麗でしたね、悠里」 「こういうとこに来るのは初めてだけど楽しかったよ」 「折角ですので、後で直売店へも寄ってゆきましょうか」 カルナはここで昨今ようやくお目見えした青い薔薇が売られていると聞いていた。 「うん、いいね。今日の思い出に買っていこう!」 これからもずっと二人の思い出を作って行きたいから、この日の思い出も形に残すのだ。 悠里の言葉に緑髪の天使が優しく微笑む。 ──青いバラの花言葉は神の祝福・奇跡らしいので。 少女の視線の先。 見渡す限りの薔薇は優雅で美しく、アーチは日常の風景を離れ、幻想的ですらあった。 深い緑の中に凛として咲く真紅は素晴らしいと夜鷹は思う。 「レイの瞳も同じ様な色をしているね、綺麗なワインレッドだ」 広い手の平に撫でられて、レイチェルが頬を染める。 「あ、せっかくだし一緒に写真取りませんか?」 咄嗟に言葉が紡げず、少女の口をついたのはまるで別のことだった。ともあれ人を探さねば。 「ふふ。任せて~」 程なく通りすがったニニギアが構えるカメラに、再び頬を染めて微笑むレイチェルは夜鷹の腕を取る。そんな仕草も愛らしい。 刹那。突然巻き上がるフラワーシャワーが二人を彩る。こんなこともあろうかと、ニニギアがこっそり用意していたものだ。 「わっ……」 頬を染めたまま少し驚いた顔を二人の思い出に収めて、そろそろお昼を頂きたい時間になってきた。 程よいベンチに二人は腰掛け、ランチを広げる。サンドイッチとミルクティだ。 「サンドイッチはレイの手作りなのか? 嬉しいね」 一口に頬張る青年の姿を、レイチェルはどこか不安げに見つめていた。 「うん。美味しいよ」 一緒に居る時間が、こんなにも心地よくて、こんなにも幸せで。 いつの間にか、こんなにも好きになっていたと、レイチェルは確かに思う。 「レイは良いお嫁さんになるな」 甘酸っぱくて、ほんの少しほろ苦い。十六歳の少女の想いに青年は天を仰いだ。 彼女はまだ幼いのだろうと彼は想う。向けられた好意は、彼女の兄への好意と同じだと感じているからだった。 彼女が兄から離れる時、きっと己からも離れてゆくのだろう。きっと誰かに恋して、誰かを愛して…… だから彼女は妹なのだと。いつか背を押すその日まで兄で居ようと。 思春期の少女の好意をそのまま信じきるほど、二十三歳は子供ではない。世の中全てを見透かすほど大人でもない。 そんな風に想われていることはレイチェルも心のどこかで感じている。それがどこか歯がゆくもあり、ほろ苦くもあった。 ミルクティ。少しだけ濃すぎたろうか。 たとえそうだとして。たとえそんな日が来たとして。 それがやっぱり目の前の相手だったとしたら、その時彼はどんな顔をするのだろう――なんて。 ●純薔薇 そんな薔薇園の一角。エインシャントの手で白亜のテーブルの上に広げられたのは自前のティーセットだった。 卓上に並んでいるのは薔薇のソースにジャム。爽やかな甘さは紅茶やヨーグルト、スコーンやトーストに良く合う。 「わぁ、きれい。いい香り……」 そんな光景に、通りかかったニニギアが吸い寄せられるように現れた。 手にするカゴには花弁が沢山集められている。家に帰ったら薔薇のお風呂に入るのだ。 それにしてもお風呂何回分になるのだろう。先ほどばら撒いた量を差し引いても相当残っている。 それならポプリも作って、サシェも作って――ぐぐう。思考を巡らせど時間も時間。やはり大食淑女は伊達じゃない。 「どうぞ、お嬢さん」 「お嬢さんだなんてっ」 ニニギア・ドオレ。三……二十一歳。 そんな風に呼ばれれば頬も綻ぶ――等々と茶化してはみたが、彼女が非常に美しいことは地の文で保障しておきたい。 それはさておき、お茶会である。 「おや……レオンフォルテ公」 これまた偶然通りかかった少女をエインシャントは呼び止める。 「御時間があれば少々薔薇を口で楽しまれては如何でしょうかな?」 「……はい」 なぜだかグルメ公主等と呼ばれる少女は、お腹を鳴らして頬を染めた。 ボーンチャイナに注がれたファーストフラッシュの香りがほのかに広がり、エインシャントがいくつかの疑問を少女に投げかける。 伯を名乗る由緒あるヴァンパイアとしては、どことなく貴族的な少女の名が気になったのかもしれない。 桃色の髪の少女が静かに口を開く。 少女に物心がつくかつかぬか頃――夏のシチリア。 レオンフォルテと呼ばれる小さな村の路上に、うずくまる四歳の少女が居た。彼女を抱き上げた男の腕が、思い出せる限り最古の記憶だった。 そんな歳になれば、己の名を知らぬことなど多くないはずだが、彼女にはたどたどしい母国語以外は何も分からなかったらしい。 やがて男は羽陽曲折の末に彼女の義理の父親となるのだが、それは去年の夏の事である。 ともあれ、だから彼女の名は『レオンフォルテ村の夏』なのだと言うことだった。 ●Hazey 何をしていても、吸い寄せられる場所がある。 これがここだ。 「これはどうも……以前はお世話になりました」 だから煙管を取り出す雷慈慟とヴィンセントが顔を合わせたのは偶然なのだが、ある意味では必然とも呼べた。 青年は無言で会釈すると、ライターをそっと手渡す。 「む……。ありがたく」 「……仕事で何度かご一緒しましたね」 二人は顔見知り程度だが、互いに頼りになる僚友と認識している。例えば最近では鬼ノ王との戦いだろうか―― 「まあ、こんな所まできて仕事の話は抜きにしましょう」 「そうでありますな……」 どこか不器用な二人は表情を変えぬままなれど、つい仕事の話になってしまうことに内心苦笑したのかもしれない。 体中を駆け抜けるニコチンが、じわりと血管を締め付ける。視界が鮮明さを取り戻して行く。それで雷慈慟は、あることを思いついた。 「名産のエールを購入し、所持していますが……」 そういえばレストランでエールを購入したばかりだった。 「御一緒に一献如何です?」 「いいですね。頂きます」 深々とした丁寧な礼が、青年の生真面目さを物語っている。 コクが喉を駆け抜け、潤していく。 「……そういえば以前 うら若き御婦人と御一緒の所を拝見したのですが 一体……?」 ヴィンセントがむせた。 「ああ……その、僕の段取りが悪くて都合が……今日はふられてしまいました」 「む……」 「言い訳になりますが、僕は不器用なのですよ。銃しか取り柄のないつまらない男です」 せつせつ、こんこんと聞く。たゆとう紫煙が天へ溶けて行く。 「でも彼女と出会えて、楽しいことをたくさん知ることができました」 「左様でしたか……心魅かれるお話です……」 正直羨ましい限りだ。 そんなやり取りを聞きながら、睡蓮は白い煙を吐き出した。 久しぶりの一服だった。あまり吸わないがたまにはいいものだ。 とはいえ、こんな時くらいしか落ち着いて吸えやしないというのもまた事実でもある。 彼はここに来るまでに何人かの兄弟同士と思しきリベリスタと出会っていた。そういえばアークには彼自身の妹が居るとのことだが―― 会うべきか、会わざるべきか、ループタイを弄びながら彼は未だ決めかねていた。 (僕の記憶は不良品だからな……) 彼の人間関係は高校時代に起きた事件によって清算されてしまっていた。それまでの記憶がないのだ。 それに、元フィクサードの兄など、いまさら現れてもどうなるというのだろうか。 (まあ、いつか機会もあるかもしれない) 彼が土産物屋にでも寄っていこうと決めた空の下。陽光に目を細めヴィンセントが呟いた。 「……いい天気ですね」 「……何時までもこのような。穏やかな日が続けば良い」 ……そう思案する次第です。 ●Tea of Noon 「涼しいッスねぇ。初夏の匂い。風が気持ちいッス」 リルが目一杯伸びをする。先ほどまで凛子と共に様々なハーブを見て回っていた。 とはいえ余り詳しくないリルは、熱心に凛子の説明を聞いていた。それからカモミールを摘んで、今ここに居るわけだ。 彼女はと言えばハーブの専門家ではないが、かつて紛争地を渡り歩いていた経験上、薬が足りない時には野性のものを用いていたから実用的な知識がある。 たった今乾燥機から取り出された摘みたてのカモミールは、一般的にはリラックス効果を中心に唄われるが、消化器をやられた時にも中々の効果を発揮してくれる。 万能薬ではないのだから、お腹が痛ければ飲めばいいというものでもないが、それはどんな薬にも言えたことであるのだが……と、例えばそんな知識だ。 彼女と一緒に花々を見て回ることも、彼女から知識を仕入れることも楽しかったが、まだ次の楽しみも待っている。 ともあれ、ようやく使い物になる状態になったのであれば―― 「折角ですから御茶にしましょうか」 余り上手ではないと、凛子はシフォンケーキを取り出す。お手製だ。 最も彼女が謙遜するのは、ある方面のプロフェッショナルであるが故に、料理等はそこまでのレベルには達していないという客観的観測の結果に過ぎない。 「凛子さんのシフォン、美味しいッスよ。上手いッス」 実際には口に運ぶリルの笑みが、普通の豊かな感性と舌には、ものすごく美味しく感じられることを示している。 「凛子さん甘いのは大丈夫ッスか?」 精一杯のお礼を込めて、リルも手作りのクッキーを差し出した。可愛らしい模りで、バターやスノーボール、ココア等、様々なものを用意してきた。 「好きな味があれば、また作るッス」 「甘いものは好きですよ」 暖かい微笑み。すっと差し出されるハンカチが、リルの口元のジャムをぬぐう。 これも先ほど売店で購入したものだ。少年がはにかむ。 「これでいつもの素敵なリルさんですよ」 ●続・ぼっち いくら己に酔いしれたとて、現実は変えられるものではなかった。 通り過ぎる道すがら、薔薇やハーブの香りに包まれて彼女の胸に突き刺さるのは甘いカラメルに覆われたナイフだ。 ガッデム! その心をずたずたに引き裂かれ、それでもなお彼女は駆ける。 ジーザス! さみしくないし! 舞姫が吼える。別にさみしくないし! 「レストランでやけ食いして帰ってやるぅ!」 ファッキュー! 舞姫が走る。別にさみしくないし! 一人ぼっちでも雑草のように、強く生きるんだ…… さみしくないし! ないし!! ●Rose & Herb. そんな光景からやや離れ、 レストランと売店の隣にはガラス張りの大きな建物がある。 中を覗けばそこには鉢植えの薔薇とハーブが所狭しと並んでいた。 カルラが園芸に興味をもってくれた。 彼にとってそれまでは興味はなかったのだが、先日聞いた盆栽の話が面白かったのだ。 話に惹かれたのか、話す人物に惹かれたのかは分からないが、趣味を持たぬ彼にはそれが望外に心地よかったのだった。 「とりま無理ない範囲で俺もやってみようと。初心者向けを選んでもらえると」 とはいえカルラは薔薇の知識やこだわりがあるわけではないから、どうせならそれらしい赤がいいかなあと思う程度だ。 「うむ! 任せておいてくれ!」 それでも雷音にとって、彼が気にしてくれたものが園芸だったことが嬉しい。 「育てやすくて似合うのをえらぼう」 初心者でも育てやすいものはなんだろうと雷音は思案を巡らせる。 薔薇というのは存外丈夫なもので、逞しく育ってくれるものが多い。ならばやはり、いかにも赤くてそれらしいものがいいだろうか。 カーディナルであればその名が連想させる通り、正に枢機卿の衣のような真紅の花を咲かせてくれるだろう。 その花言葉は情熱だ。いつか彼がそんな気持ちをもってくれたらという願いも込めて…… 雷音はいくつかの鉢植えに語りかける。そのうちの一株が小さく葉を揺らした。この子だ。少女は鉢を持ち上げ、少年に手渡す。 「君にかわいがってもらいたいそうだ」 「よろしくな。大きくなったら、一緒に礼をしにいこうぜ」 カルラはお礼に、隣に鎮座していたもう一株を雷音にプレゼントした。 雷音だけは、それが少しさびしそうだったことを知っていたから、丁度よかったのかもしれない。彼女は可愛がってやろうと思う。 「今日は楽しんでもらえ……てそうだな。何よりだ」 「や、ボクは。同じ年代の異性といえば兄としか遊んだことがなくて」 つい笑顔を見せた雷音は、なぜか慌てて手を振る。 「兄と共通点が多いせいか、同じようにはしゃいだみたいだ! すまない」 なんだか良くわからない解説に、少年は呟く。 「兄同然? 俺の株も上がったもんだな」 きゅん。 (シエスタでの……最適で最善なお昼寝環境には、緑も、必要よね……?) そんな二人の近くには、ぽややんとハーブを見ている眠たげな少女が居た。 カモミールならリラックス効果でばっちり快眠出来そうだ。 彼女はとにかく本当にすごく眠くて、いやむしろいつも眠いのだけれど、お昼寝のためにふわふわと頑張っているのだ。 だからこんなにねむいのだ。え、ちがう? ねむいからいいのだ。 そんなこんなで那雪は目をごしごしとこすりながら、どうにか抱えたカモミールの鉢植えを店員さんに手渡す。あくびが零れる。 とにかくねむくてうごきたくない感じだけれど、かんぺきなしえすた――略して『んえす(ふわぁ)』の為には知っておかねばならないこともあった。 (簡単な、お世話の仕方、教わるの……) 店員さんの説明を聞きながら、彼女は眼鏡をちゃきっと取り出す。那雪さんきりっ。 「なるほど……」 風通し良く、収穫は晴れた午前、と。秋にももう一度収穫出来るだろう。 店員の話ではカモミールはジャーマンとローマンの二種類があるらしい。思えば鉢植えも二種類だった。 「普段見かけるのはジャーマン種なんですよ~」 店員の説明に那雪さん(くーるもーど)が頷く。なら、そちらを買って帰るとしよう。 (あぁ、今が時期だというならフレッシュな物もハーブ園で少し摘んで帰るとするか) 無事に購入を終えた少女は颯爽と眼鏡を外し、ぽややんと大きくあくびした。 それにしても……いくら古賀のニーサンの誘いだからとは言え、ずいぶんと己には似合わぬ場所に来たと瀬恋は思う。 そもそも理由も述べずに付き合えときたものだった。それがよりにもよって、なんでこんな所に来たのだろう。 建物の中に入ってからというもの、源一郎は瀬恋と共に、ただ黙々と鉢植えの間を巡っているように見える。 一体なんだというのだろうか。彼女とて花を綺麗だと思わない気持ちもない訳ではない。訳ではないのだが―― (なんつーか、ガラじゃないよね) そんなことを思っていると、源一郎は小さな白い薔薇の鉢植えを丁寧に包んでもらっている。 ボッディチェリの絵画に登場するような、華やかなオールドローズだった。 (意外と乙女チックな趣味だなニーサン……) もしかして、こういうものが買いたいがために、わざわざ自分を付き合わせたのだろうか。 買った鉢植えにはリボンなんかつけてもらって。 おいおいニーサンまさか本当にそんな趣味が――等と考えていると、そんな可愛らしい薔薇の鉢植えがいきなり目の前にやってきた。 「あ?」 思わず変な声が出てしまった。こんなことは予想もしていない。 「いつぞやの戦いの礼、遅くなったが受け取っては貰えぬか」 深く響くバリトンは意外な結論を彼女に告げた。源一郎が考えていたのは、未だ済んでおらぬジャックとの決戦に同道して貰った礼だったのだ。 こういう機会にしかタイミングもなく、こうでもせねば受け取ってくれぬかもしれないから、渡すまでは口に出せる話でもなかった。 果たして興味をもってもらえるかという所から源一郎は不安を感じていたのだが、そこはどうにかなったらしい。口にも態度にも出さずとも、見るべき所は見ている男だった。 こんな時には花束が常道なのかもしれないが、それではいずれ枯れてしまう。だから長く楽しめるものが良いだろうと彼は考える。その結果がこの白薔薇だ。 「……まぁ、そういう事ならありがたく貰うとするよ」 こんな白薔薇が己に似合うなどと、彼女自身は考えたこともないが。嬉しくないと言えば嘘になる。 どことなく彼女が硬直していると、良ければこの後は薔薇園を見て回りたいと源一郎が提案した。 それもやっぱりガラではないけれど、たまには悪かないと瀬恋は想った―― ●真実(まみ)さんと正義(まさよし)さん 二人はいつだって皆の人気者なのだ。 折角の休日なのだから、探偵ごっこでも楽しんでみようと、エナーシアは敷地を散策していた。上等の暇つぶしだろう。 彼女は、フィクサードと言えどもわざわざ初見の場所で会談などしないだろうと考える。つまり過去に訪れたことがあるのではないか。 でも野良リベリスタなどというのが彷徨っていることを知らなかったというのであれば、地元民ではなさそうだ。 あるいはそのリベリスタのほうが余所者だったのだろうか。それとも、そのどちらも、か。 可能性を狭めてゆく為、彼女はそれとなく施設の人間に尋ねてみることにした。 (大体の場合においてリベリスタやフィクサードというのは、一般人の私とは違って独特の雰囲気というか変態性を醸し出しているものだから) 仲間が聞けばどんな顔をするだろうかというようなことをしれっと思い描いてみるが、少なくとも彼女は指先から火を出す手合いの能力者ではない。 兎も角、掃除夫の話によればクラシカルなドレス姿の少女を見かけることがあるといったものだったが、場所が場所なれば真偽はいかほどのものか。 能力者でなくとも、全く居ないこともないだろう。 さて。最もこの程度で真相を探り当てることが出来るとはハナから思っていなかった。正直な所、物見遊山が八割といった心境である。 今もこうしてサンドイッチを頬張っているのが何よりの根拠だ。チキンに添えられたマスタードの刺激が心地よかった。 そろそろあのカフェレストランに戻って飲み物でも頂こうかしら。 こちらの美散は周囲の散策を丁度終えた所だった。 駐輪場に停車した自動二輪の熱されたマフラーは、未だかちかちと乾いた音色を奏でているだろう。 哨戒程度はしておいたほうがよかろうと考えたのだ。 敵方のフォーチュナが偶然捕らえたのが、そんな彼のバイク姿であったことはまた別の話であり、知る由もない事である。 現れるはずだった野良リベリスタとやらも姿を見せない所を考えると、アークに積極的に接触する手合いではないようだが、実際に声を掛けてみなければ分からない所もある。 どうせなら会えればいいと思っていたが、結局収穫は無かった。 後は腹ごしらえでもしようかと彼はレストランへと歩き出す。 ●続いて真理(まり)ちゃん 真実と正義が居れば、こんな子だって姿を現すのが常である。歩き回った後はお腹が減ると、これもまた世界の真理の一つである。 時刻が正午を廻ってから、既に幾ばくかの時間が過ぎ去っているのだった。 「やっぱりさ! 美味しく食事出来る機会は逃しちゃいけないと思うんだよ!」 片思いの宗一を前にして霧香は力説する。そうは言うものの、出かけるたびに何か食べているような気もしていた。 とは言えど、宗一の眼前に運ばれてきたコース料理を一瞥すれば、別にかまわないという気にもなってくる。 美味しい。美味しくて、ちょっと不思議な風味がする。種類までは分からないが、きっとこれがハーブなのだろう。 食べる宗一を前に霧香は力説を続けていた。やれ人の体は食べたもので作られるだとか、美味しいものを食べたほうが強い肉体が作られるだとか。 つまり美味しいものを食べられる機会は出来るだけ逃してはいけないのだと少女は胸を張る。 「……いや、うん。そんなに力説しなくても」 食べることが好きなのは十分分かっているから、そう口に出すが。 「あたしが食べるのが好きなのはつまりそういう事で、決して食い意地張ってる訳じゃなくて……ほ、ホントだからね?」 剣の道を生きる凛とした少女が、宗一の前で垣間見せる、歳相応の反応だ。そんな所も可愛いのだけれど…… 「ほらっ、宗一君ももっと食べて!」 「ああ、大丈夫大丈夫。ちゃんと食べてるから」 好きな料理を聞いてみたり、聞かれてみたり。 最前線で傷つくことが多い彼への想いを一方通行のまま終わらせたくない。ある日突然宗一が消えてしまわないように。 急がないで、と。今はただ。少女は切に想いを綴る―― 同じころ、祢子も二階のレストランへと足を運んでいた。既に階下の売店で、数種類のハーブティーやお菓子等を購入してある。 彼女はアークに着てからそれほど長くないが、色々な敵と出会ってきたものだ。 偶然か必然か『ホモタウロス』だの『けも耳愛好』だの、ちょっと変態的な奴らばかりであったから、ちょっと休んでおきたい気持ちも頷ける。 目の前に運ばれてきたコース料理は彩りも美しく、おいしそうな香りを漂わせていた。 (こういう場所に、連れて来てくれる人とか出来たら良いなぁ……) ほんの少しだけ、そんな風に思わずにはいられない。 彼女もきっとこれから様々な経験をしてゆくのだろう。今はこうして英気を養って、もう一度走り出すのだ。 席に着いた美散の元にも程なく運ばれてきた地鶏のローストが運ばれてきた。 慣れた手つきで器用に切り分けサラダと共にパンに挟んでいると、ふと桃色の髪の少女が姿を見せた。 「――食べるか? レオンフォルテ」 有り体に言えば餌付けだ。小動物のように頷くエスターテに美散は語りかける。 子供には優しくしろというのが、祖母の遺言だった。最も彼の一族には姿だけは子供に見えるような連中が多い。 そんな手合いは対象外としたい所ではあるのだが…… 「いや、この話は止めよう。余りにも不毛だ」 望まずとも家事に追われる日々のことなど、折角の休日に思い出したくはなかったから。 「其処に居るガキ、エスターテだったよな?」 ぴくりと肩を揺らす少女が振り返ると、そこでは仏頂面の見慣れた巨漢が手招きしていた。 ランディは休めと言われてこんな場所まで来たのだが、どうにも手持ち無沙汰で落ち着かない。どうせだからのんびりさせてもらう心境ではあるのだが。 奢ってやるから付き合え等と口に出してはみたものの、まるで悪漢のようだと彼は自嘲する。 エスターテとて人付き合いが良いほうではなく、ともすれば何事にも怯えがちではあるが、赤毛の同僚が粗野に見えるのは言葉尻だけだということは知っていた。 「お前蝮ん時のいきさつでこっちに来たんだったな」 詳しい名前は覚えていないが、確か『影主』と言ったか。 「そいつは強いって聞いて興味はあったんだよな、そのうち戦ってみたいもんだ」 生真面目な少女はこくりと頷く。少女が述べるにはアークが解析している戦闘データではリベリスタと同程度。仮にランディであれば問題なく勝てるだろうという話だが。 そんな少女の解説にランディは笑う。少女は問う、青年は戦うことが好きなのだろうか、と。 「俺? 俺は戦うのは好きじゃねぇよ。単に強い相手に勝つのが好きなだけだ」 「はい……」 「今更連中の所に乗り込む気もない、たまにはこういうおしゃべりもいいだろ?」 少女の話では、組織は関東仁蝮組の傘下として戦闘よりも政治や経済の面に特化しているという話だ。 そこは本来戸籍も何も無い、社会から忘れられた人員の集まりらしい。いくつかの企業を持ち、ホテルを点々として暮らしているという。 彼女はただ時折予言をしていただけだから詳細は分からず、仮に知っていたとしても口に出すわけにもいかない話だ。 かつてのフィクサード組織も、いまやリベリスタではあるのだった―― まだまだ春野菜が美味しい季節である。筍に山菜、春キャベツに新ジャガ。それから苺。 しれっと甘い果実が並ぶのは、果樹と野菜との微笑な境に位置し、分類学上は主に野菜とされるのが常だから。 そんなことを考えながら綺沙羅はメニューに視線を走らせる。 春野菜のピザに、地鶏の香草焼き、野菜のスープとデザートと目移りしてしまうが、十一歳の少女の事、余り量は食べられない。 (別腹なんて都市伝説……) 少女は内心呟く。 脳が無理やり、胃に隙間を作るだけだ。無理に食べても詰め放題の袋みたいに凄い事になる。 ぴちぴちのビニール袋にはなりたくなかった。 少しだけ悩んだ後に、結局彼女は香草焼きを諦めて、小さなピザを頼んだ。 女性向けのランチコースも存在はしたのだが、そこには残念、春野菜のピザが付かないではないか。 ピザにサラダとスープのセット、苺のデザートをつけるなら、こうする他なかった。またのご来店をお待ちしております。そんな声が聞こえたような気がした。 同じくエリスも、それほど量が食べられるほうではない。彼女の前に並んでいるのは、女性向けのランチメニューだ。 あくまでボリュームは控えめに、ハーブティーとデザートまでセットになっているから、丁度彼女の望みにも叶っていた。数種類から選択出来るのも嬉しい。 こうして美味しく食べられることを感謝して、彼女は野菜スープを口に運ぶ。 二種類のパンは焼きたてで、香ばしい。みずみずしいサラダにちりばめられたベビーリーフが程よいアクセントになっている。 こんな日常を守るためにリベリスタが――彼女自身が居るわけで、それによってリベリスタといえども、殺伐とした毎日を送らずに済むのなら…… 所変われば人も変わる。 こんな休日までシックなテーブル席で生真面目な面を覗かせるリベリスタが居ても、そよ風に撫でられるテラスのほうまで足を伸ばせばまた違うようだ。 昼食に呼ばれていたエスターテが足を運ぼうとした矢先のことだ。 「さあ、一緒にオーガニックでご飯を食べよう! 俺のおごりだよ!」 突然現れた竜一に、少女は身を震わせる。ある日、突然スカートをめくられた事を忘れはしない。かぼちゃぱんつだった。 どうすればここから逃げられるだろう。お腹にパンチすればいいだろうか。物騒なことを考えながら怯えている。 「お詫びにね! お詫びだよ! 別にまた狙ってないからね! 心配しないで! ホントだよ!」 どうすればいいのだろう。近くに妹さんとか、普通を名乗る恋人さんとか居ないものだろうか。後は某しぇんぱいとか、アークの白い悪魔とか……ダメだ。誰も居ない。 「イタリア生まれだって? ピッツァやパスタ食おうよ!」 一方の竜一(ロリコン)は、お構いなしである。リア充の癖してなんて奴なのだろうか。少女の瞳に涙が滲む。 「好きな具とかトッピングしよう! 何がすき!?」 怖いものは怖いのだが、竜一は有無も言わせない。 「はい、あーん! よしよし(なでなで) メキシコのタバスコをビシビシかけて食べるのが日本流だよ! オリーブオイルかける!? 追いオリーブ!」 「え、えと」 「はい、パスタも音を立てずにくるくるフォークにまいて、あーん!」 四秒後に現れる店員のお姉さんに、わずか一瞬だけ視線が移る事を感知したフォーチュナの少女は、その隙に――辛うじて逃げだした。 ●宴~俺達は未来を変えに来た!~ 「まずはピッツァを頼もう」 それならみんなで楽しく食べられるだろうと、翔太は考えた。 「ああ翔太、先にピッツァを頼むか?良いチョイスだな」 「それとサンドイッチにパスタ、〆はデザートとハーブティー」 「サンドイッチも望むところだ」 彼は注文を終える。楽しみでしょうがない。 だが―― 「じゃんじゃん来い!」 結局テラスの広いテーブルに並んだのは各種ピッツァにパスタ、サンドイッチ、色とりどりのオードブル、鳥や魚の煮込み料理に香草焼き、パンと、中世の王宮を描いた絵画のようである。 なんと! 全て優希の奢りらしいのです。日ごろお疲れ様の打ち上げなのだ。更に全員分のコースをツァインがしれっと追加注文している。中身が違うのだ。 「ちょっと待てツァイン、この単品に加えて全員でコース料理を頼むのかっ!?」 「勝手に食べ放題なのだっ! ごちになりまぁ~す!」 かわいくていい香りのお店だった。こんなにステキであれば壱也だって食欲も出ようというものである。 「わたしね、デザート類制覇したいんだ~!」 ここからここまでください! みたいなのは、夢だったのだ。しかも奢りである。ここはどーんと行きたい。 「壱也、この料理の山に加えてデザート全制覇だと、食えるのか!?」 「ちょっと! ここの水香りついてるよ!?」 それを横目にサンドイッチを一口に平らげたツァインが水を飲み干す。鼻腔に香るのはほのかなローズマリーだ。 「流石ハーブ園……! はふぅ……いい匂い……」 視線の先のほむほむこと優希は、死んだ魚の目でもしているかと思いきや、質実剛健な生活の成果――つまり分厚いお財布を卓上にたたきつけたまま黙々と食べている。これぞ男気というものだ。 これだけあれば安心だろうと思えるが、料理やデザートまで次々に運ばれてくる。眼前の料理全てがほむほむの血と汗と涙の奇跡であり――幸せの味だった。 「しょーたんのピッツァも、もらう~! もぐもぐ。これ、ワッフルだよ!もちもちおいしい!」 「お?壱也のそれいいなぁ、俺にもくれよって――」 ツァインのダブルアタックが炸裂し、目の前のサンドイッチが瞬く間に消失する。 「ツァイン欲張り過ぎだぞ!」 「何を言ってるんだ翔太、もう一皿頼めばいいじゃないかっ。すいませ~ん、もう一つ追加で~!」 そんな様子に少しずつ静かになっていくほむほむ。財布に入っているであろう具体的なお札の枚数を脳裏に数え始める健気なほむほむ。 これだけ食べれば十九歳の少女には、はたと気になることもある。 「どうしたイッチー! 脂肪判定なんて怖くないぞ! 優希のフェイト(残金)を燃やして立ち上がるんだ!」 大丈夫だ。超再生だ。高速再生だ。 「ツーくん、わたし結構食べるし! ……た、食べるし」 それでも戦いを止めない壱也の健闘ぶりに、どことなく顔色が白くなっていくほむほむ。 「か、カロリーとか……! う、うん、そう、脂肪判定なんてこわくない! ……ない」 「ふ、優希よ、これなら間に合いそう、とか安心している様だな……」 そろそろ小刻みに震え始めたほむほむ。 「ほむほむ、どうしたの? たくさん食べよ~!」 目に見えぬはしばぶれーどが優希の心と財布を容赦なく切り刻んで行く。 「こんな時の為に助っ人を呼んであるのよ! 先生、先生! お願ぇしますッ!」 「え、と……」 グルメこうしゅ が あらわれた!!  「エスターテ、全部タダだから。遠慮なくどうぞ!」 「何ぃグルメ公の登場だと。どうなってしまうのだ!?」 少女はほんの一つまみずつではあったが、ずいぶん食べさせられてしまった気がする。 優希はと言えば、大枚つぎ込んだはずの財布のライフが半分飛んでしまっていた。全て綺麗に片付いた皿が気持ち良い。 「優希さん、ゴチになりましたーッ!」「「「ごちになりましたーッ!」」」 手を合わせられるほむほむ。とうとう神になったのだろうか。 「も、問題ない俺の財布はまだ生きて……」 「コーポの皆にもお土産買っていかないとなぁ」 ツァイン(+2714.8g)の呟きに、各々が視線を合わせる。 「……まだ財布の中はあるようだな?」 翔太の鋭い瞳が優希を射抜く。肩に置かれた手が重い。 「皆にお土産買っていこうぜ! もちろん優希の奢りだってよ」 「え!? お土産も!?」 歓声。 「さぁ行こうか、お土産屋さんに」 「ほむほむの奢り!? わぁーい!! 太っ腹~!」 優希の全身が白くなっていく。 「な、ほむほむっ」 「フ、思い出はプライスレス」 燃え尽きた少年は、静かに崩れていった―― 「ところでこれ、何の打ち上げなんだ?」 ――なんだろう。 初夏の風に吹かれて舞い上がる薄い財布は誰のものであろうか。 ●Souvenirs on Your Memory. 閑話休題。 そあらさんは人類である。 生物学上の区分であれば、どうにか(´・ω・`)や犬ちくしょうではなかったから、ドッグランで走り回ったりはしなかった。 彼女が居るのはレストランの階下にある土産物を中心に扱う売店である。最もお土産というよりはずいぶん実用的な品物が並んでいるのだが…… そうそう。おしとやかでステキな彼女は、ちゃんとこういう所を見て廻るのだ。 本当はさおりんとドッグラン――もといローズガーデンデートがしたかったのだが、多忙な室長はこうした催し全てに顔を出すわけではない。 致し方ないから違う路線で攻めるのだ。お土産だ。さおりんと休憩時間に飲むハーブティー、お茶菓子、茶器をいろいろ選ぶのだ。 『そあら、気がきくな、さすが未来の妻になる女だ』 「やだもう、さおりんってば照れるのです」 語りかけてくる『ぶれいん・いん・さおりん』(非戦)に照れるそあらさん。いちご好きの二十二歳。 ともかく色々あって迷ってしまう。リラックス効果のあるお茶だとか、丁度カモミールの季節である。 愛のスパイスが入ったクッキーだとかっ。どうかしら? どうかしら? 「ほわ~こういうのって久々やなぁ~。 お土産屋さんってなんでこうわくわくするんやろうなぁ♪」 望は楽しそうに商品の棚を物色している。 「あ~これもええなぁ……あれもっ……うわ~どれにしよっ」 これだけ色々あれば頷ける。お土産屋さんと自然食系雑貨店が混ざり合っているのだから、それは豪勢なものだ。 「あ、噂になっとったんはこのジャムやな……これはキープしとかないかんなぁ」 それにこちらには料理の本もある。 「図書館で料理とか出したらあかんかな(てへっ) まぁ料理のうまい女子はもてるらしいし、あーしもそろそろ得意料理のひとつくらい作っとくかなぁ」 これもカゴに投入。 「くんくん…ええ匂いがするんはこれみたいやな~」 今度はアロマキャンドルだ。落ち着いた香りが心地よい。 「うん、この香りは図書館にばっちりあってる気がするっ」 「えーと、ローズ&ラズベリージャムはっと……」 終は母の日のプレゼントを選んでいるのだ。孝行者である。 ローズコーナーという看板に目を惹かれて足を運ぶと、そこにあったのはローズソルトであった。 「丁度、岩塩切らしてたんだよね~☆」 これも買わなければならない。 「で、ジャム…ジャム…あった! うちのママン、最近パンにはまってるんだよね~☆」 パンも美味しいと評判だった気もしてきた。欲しいものが多くて困ってしまう。確かラベンダーのお茶も好きだった気がするし…… 「これとセットにしよう♪」 決めた。 「すみませーん、プレゼント包装ってできますか~??」 他にはどんなものがあるのだろう。 特に予定も決めていなかったリサリサは、同じく販売コーナーを覗いていた。 (どうしましょう、これは迷ってしまいます……) ハーブにクッキー、食器にアロマオイルまで、色々とあったものである。 何気なくティーカップを手に取った彼女がはたと思い描くのは誰だろうか―― あの方は紅茶など飲むのだろうか。 ハーブティーとティーセットなんて、突然送っては驚かれてしまうだろうか。 「あ、はい、大事な方への贈り物なんです。綺麗に包んでいただけますか?」 それでも彼女は勇気を振り絞って、購入する。梱包は贈答用だ。 いつか渡せるといいけれど。その時には、もっと大きな勇気が必要だ。 たとえば、あの方のような…… こちらのペアは従兄妹同士で買い物だ。 折角可愛いお店に来たのだから、お土産を買わねばとすばるは思う。いつも思うのだけれども、相方がどうにもこうにもそうでもないのだ。 あきらの方はと言えば、別に記念日も誕生日も思い浮かばなかったから、正直に言えばあまり気乗りしていない。 「あきら、家に送るお土産何がいい?」 「そうやなぁ、饅頭でも送っといたらいいんちゃうかな」 あきらは適当に相槌を打ちながら、ぼーっと棚を眺めているとそこにはガーデニングの本があるではないか。思わず手に取る。 「ちょっとあきら、聞いてんの?」 「そうやなぁ、やっぱ饅頭やないかなぁ」 もはや気もそぞろに本を手に取る。毎度毎度、いつも土いじりにばかり夢中になっているのだ。 温泉街ではあるまいに、饅頭なんてどこにもないではないか。 すばるとしては、好きだというのは理解出来るがたまには一緒にお土産を選んで欲しいものだ。 いつも自分だけの意思で選ぶことになってしまう。 「ほら、こんなんどうやろ? おばさん好きやったんちゃう? ハーブ系」 「そうやなぁ、ハーブ饅頭とかえぇんちゃうかな。」 普段は和風だが、こういう洋風の手法もいいものだなあとあきらは思いつつ、もはや何を返答しているのかよくわからない。 早く帰って試したいのだ。また別の本を手にとっている。 「あーきーらー!!」 さすがに堪忍袋の緒も切れたのか、すばるは強かにあきらの耳を引いた。 「この耳は飾りか!?」 「いたたたた!? あかん! 千切れる! ちゃんと聞くから放してや!」 さすがにそろそろ選ばなければまずい。その気にさせるまでが大変なのだ。 ようやくあきらも、真剣に選び始める。彼女の両親には色々と思うこともあるのだった。 こうしてその気になってくれさえすればすぐに決まるのも常であるのだが、世話がやけるものだと、すばるは小さくため息をついた。 「世間じゃゴールデンウィークか……」 棚に視線を走らせながら猛は呟いた。リベリスタには関係ない話か。 「そんな時期だからこそフィクサードも人の波に紛れて活動をするんですね……」 だからといって、こんなハーブ農園で会談とは、さすがに如何なものだろうかと思う。 偶然居合わせたリベリスタを殺害とまでなると、間抜けが過ぎるのではないか。 脳裏に過ぎるのはどうしても仕事に関連しがちだった。 リベリスタというものは、ある意味では年中無休である。休暇と言えども待機のようなものでしかない。 「ま、任務で遊んでも良いってんだから、折角だ」 こんな機会でもないと、なかなか遊ぶことなど出来はしなかった。だから今日は思い切り楽しみたいものだ。 「……土産物に、ガーデニングやらハーブの本……。や、場所が場所だからありっちゃありなのか」 なんとなく一冊を手に取った猛の隣で、リセリアは目の前のハーブティをカゴに入れた。美味しそうだ。 「良さそうなハーブティーを幾つか、買おうと思います」 「へえ、ハーブティーか。……やっぱりリセリアは紅茶だよな」 そんな彼が手に持っているのは名物と言われるローズ&ラズベリーのジャムだった。 「美味しそうです」 二人の笑顔が交差する。そろそろ他の場所も見て廻りたい所だった。 「……時間は……まだ少しあっかな。色々、見て回るか」 「ええ、他の所も見に行きましょう」 手を取り合い、二人は次の場所へ―― アルフォンソはローズ&ラズベリーのジャムが美味しいと聞いていた。まずはそれを購入してみようと思う。 店員に聞いた所、スコーンやトーストに良く合うとのことだった。紅茶にいれるのもいいそうだ。 丁度どれも売っているから、それも買おうと注文する。帰宅したら試してみるつもりだ。 それから数種類のハーブティーも購入しておきたい。 安眠だとか、リラックスだとか、美肌とか。はたまた食欲を抑えるとか。様々なお茶が用途別に並んでいる。 どれにしようか。複数購入するのもいいかなと思う。食の充実は人生の充実でもあるのだから―― 「エスターテちゃんっ」 ようやく姿を現した大好きな友人を、ルアはぎゅっと抱きしめる。 友人の愛情表現に、エスターテがどこか照れたような素振りを見せていたのはつい一月半前のことだ。 二人の少女は小さな背中に世界を背負うリベリスタ同士でもあったから、親しい友人同士と言えども、こうした機会がなければ遊べることは余り無い。 どちらもそれぞれ多忙な日常を送っているのだ。 だから今日こそはと少女は思い切りルアを抱き返す。エスターテの髪は微かに桃の香りがした。 そんな二人の様子がスケキヨにはどこか新鮮だ。恋人が同性の友達と親しくしている所に割り込んだことはなかったから。 手をつなぐ小さなお姫様達がどんなガールズトークを繰り広げるのだろうと、あえて一歩退いて観察しようと思っている。 「どれも可愛いね」 「はい」 二人が和気藹々と手に取る小瓶のジャムに薔薇のポプリは、質もさることながらデザインにも十分な気が配られていた。 ルアの笑顔は、スケキヨと二人きりの時とはまたどこか違う表情だ。 恋人であれば当然、ほんの少し悔しくて、独占したい気持ちがないと言えばウソになるが。 はやりスケキヨは表情豊かで幸せそうにしているルアが一番好きだった。 「随分楽しそうだね。二人を見ていると、こっちまで楽しくなってくるよ」 恋人に頬を染めながらも、ルアは小物を指差す。恋人も友達も。どっちも絶対すごく大切だから。 「エスターテちゃんはどれが欲しい?」 「え、と……」 エスターテが遠慮がちに選んだものは、小さなハーブのサシェだった。 「えへへ、おそろいね♪」 ルア自身も同じものを選びながら、少女の横顔を眺める。 以前のエスターテが放つどこか堅苦しげな雰囲気と、なぜかいまにも泣き出しそうな表情を思い返せば、ずいぶん柔らかな顔をするようになったものだ。 「そういえば、エスターテちゃんは一人暮らしなんでしょう?」 「はい」 少女は三高平市内のマンションで暮らしているという。 「今度、このジャムを使っておうちでお菓子作らない?」 「どこかで」 スケジュールを調整しますと少女は述べる。 立て続けに起こるエリューション事件と、フィクサード事件の合間を縫う自信は正直あまり無かったが、友人と遊びたいのは彼女自身の望みでもあったから。 「わぁ! 嬉しいっ! 約束なの♪」 ルアは少女と小指を結ぶ。 「おや、二人で遊ぶ約束かい?」 姫君達が頷く。 「それじゃあボクは、お菓子に合うお茶でも入れに行こうかな」 その日のために、スケキヨは可愛らしいハーブティーを手に取った。 ●Extra Chapter:Prunus tomentosa. 一組の男女が歩くのはハーブ園のはずれだ。探し物はここでも見つからなかった。 快が一体何を探しているのだろうかと思うが、レナーテとしては何だか誘われたから付いてきたと言った所だ。 彼女は首にかかる都合八代目のヘッドフォンを指先で弄ぶ。 ふと、快が指差したのは駐車場との境目の辺りにひっそりと佇む小さな木だった。紅玉のような果実が美しい。 「……何かと思ったら、ゆすらうめ、ね」 薔薇でもハーブでもなかったが、メジャーな樹木だったから、快はどこかにあるのではないかと思って、勝手に連れて来たのだ。 かの『烏ヶ御前』の櫻だ。こんなことは彼自身、ただの自己満足だとは思う。そもそも烏ヶ御前の件に関しては報告書でしか知らなかった。 夢は醒め、花は散った。ぽつりと零れるレナーテの言葉。 「彼女の言葉は、生き方は何を残したのか……まだ上手く整理できていないのよね。 馬鹿にならなきゃ恋はできない。ああ、それは確かにそうなのかもしれないな、とは思う。 ……でも、ね。割り切るのはなかなか難しいよね」 ……ねぇ快さん、一つだけ質問良いかしら。 『下手をしたら、相手に辛い気持ちを味わわせる事になるような事でも、手にしたいと追うべきなのかしら』 「仮に、俺が誰かと両思いになったなら。 恋人に喪失の悲しみを与えることは、すごく怖い。 けれど、そう思う相手がいるからこそ、生死の境を乗り越えてくる奴も一杯見てきた」 快がユスラウメの実を摘む。 「どれが正解かなんて、分からない」 「参考にさせてもらうわ」 口に運んだ実は、仄かに甘酸っぱくて、そして仄かに苦かった―― |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||





























































