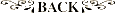●獄炎の檻にて赤に堕つ●

| ●IF:赤の世界 (――夢を) (……夢を、見ていた気がする) 空を仰ぐ。夕日に染め上げられた天蓋も、足元も赤い。 地上は見事に染め上げられていたが、それを共有する相手はいなかった。 今日も暇だ。 宮部乃宮 火車にとって、それは革醒する前も後も変わらない事の一つ。 日常は退屈だ。 飛んで行く烏が黒い点となって、夕日に染みを付けて行く。 彼らは地上に広がる赤なんて、気にした風もなかった。 ……日々、思う。 世界は自身に対して興味がない、と。 火車は岩に座って夕日を眺めている。だが、例えばこれが呼吸を止めて濁った眼球を空に向けて見開いているだけだとしても、変わらず日は沈み何事もなくまた昇るのだろう。新聞の片隅に載るかも分からない。岸の向こうに見える車は関係なく行きかうだろうし、川だって流れを止めたりしない。世界はちっぽけな一つの消失なんて気にも留めないに違いなかった。 それでも火車は、この世界を比較的好んでいる。 夜の帳に煌く鮮やかなネオンライトは美しく、桜に新緑、紅葉に雪景色、四季折々で色と姿を変える風景だって中々良い。今は日没だが、暗闇に光の差す日の出だって悪くない。 世界は美しい。 だからこそ、火車は――この世界を守るより、この世界を消してみようと決めたのだ。 己に興味のない素敵な世界を、自分よりも先に。 そうしたら彼は、フィクサードと呼ばれる存在になった。 彼自身は、特に何も変わってなどいなかったのに。 風は吹かない。夕日は少しずつ高さを落としながらも、赤々と輝いている。 視界に入る流れる血を連想させる色に、火車は一つの組織を思い出して微かな笑みを浮かべた。 アーク。方舟、聖櫃、希望の象徴。 一般的な単語のイメージと実態は少し違うかも知れないが、彼らの在り方は『正義の味方』とでも言うべきもの。何も応えてくれない世界の為に日々骨を折って尽くす、火車にとってはマゾヒスティックにも見える奉仕者達。 『世界の為、人の為』 大義名分として掲げればそれはそれは大層耳に優しい言葉だが、実際は多くの独善と自己欺瞞の混ざり合った坩堝。世界の為に刃を取るが故に、彼らは自由に駆け回れない。人の為に引き金を引くが故に、彼らは自由にその力を振るえない。人の為にと動きながら時に人に恨まれ罵られ、自らの為と嘯きながら他者の在り様に左右されねばならない不自由。 彼らが自らに課した手枷と足枷は時にたった一人の人質で動きを封じられるものであり、哀れみにも憐憫にも嘲笑にも似た感情が湧き上がる。 「大変だねぇ、マジ」 くつくつと、腹の底から笑いが漏れる。脳の髄までおめでたい連中だ。 人間なんて自分の欲求に素直なのが一番だ。 誰かの為、世界の為なんて、彼らはどれだけ尽くしたって自分達に興味がないのに! そんな事は彼らも知っているだろうに、掲げた言葉は下ろせない。 けれど、だから火車は今ではアークに対する『嫌がらせ』が楽しくて堪らないのだ。 そうだ。凡庸でありながら守護者として立ち塞がる彼はいつだってしつこくしぶとく前に立ち仲間を守り続けるし、金の髪が血に塗れても決意を揺るがさず睨み付けてくる眼鏡の彼はウザい事この上ない。褐色の肌をして明るく軽い言動を繰り返す小僧は幾度も似た様な事を繰り返し、アークで最も名高い男と正義を求める二刀の二人は何時だって猪の様に突っ込んできて酷く笑える。ああ、正義と言えば隙だらけの正義を掲げるパンダの様な彼には、女を食い散らかしてないで自分を見詰め直せとこの間告げたばかりだっただろうか。 全く、あそこは変わり者ばかりだ。 彼らが何を思いアークで武器を持つのかは知らないが、主義主張の違い以前に個性というかアクが強い。思い出しても笑いが込み上げて来るのは、馬に乗っていた彼だ。王様、たしかそんな呼び方をからかうように行った記憶がある。間違いない。何て偉大な国王。 ああ、笑える。どれだけ笑える連中なのだろう。 呼吸が苦しくなる程に笑えて来た。ええと、他には何だったか。 斧を担いで現れる、赤鬼にも似た巨躯の男。癒し手でありながら前に出たがる強情張りの少年。紫の瞳に涙を浮かべ、怖いと言いながらも逃げずに唇を噛み締め正面を見詰める臆病者。 そして。 鈍く光る色。機械の両腕。 ひらひらとした服から覗く背中も機械と化していて、突き出た部品が小さな羽にも見えた、あの。 暗闇の中に点る、一つの火の様に違えぬ何かを持っていた、あの。 あの。 ふと、空を仰ぐ。 夕日が赤い。 燃えるような太陽が。 赤い。 赤々と燃える火の様な。 赤い。 赤。赤。赤紅赤あか丹赤赤紅紅赤赤丹赤赤紅紅赤赤あか赤紅あか紅丹丹丹紅紅赤赤赤赤赤赤赤丹丹朱紅丹紅紅紅丹丹あかあかあか紅赤丹紅紅赤赤紅紅赤紅あか紅あか丹赤赤紅紅赤赤丹丹丹丹紅紅赤赤丹赤あかあか紅丹紅紅紅丹あか紅赤丹あか紅赤丹 朱。 ぐらりと視界が揺れた。 「……あ?」 何だったのか。何なのだ。ぱたりと、何かが落ちた気がした。 赤に紛れて、すぐに分からなくなった。笑い過ぎて、涙が出て来たのだろうか。 何だろう。何だったのだろう。 まぁ、いいか。浮かんだ何かを消すように立ち上がり、己に聞こえるように呟いた。 「さぁて、次はどんな嫌がらせをすっかなぁ?」 楽しい愉しいアークとの『お遊び』は、彼が世界を消そうとする限り続くだろう。 世界を守る側の彼らの可愛い足掻きを見るのは、暇潰しにもなる。 赤い髪を掻き上げた。 火車の拳が生み出す炎は地獄の業火、彼らの間でも警戒されている。 前面に出て嫌がらせを行えば、見知った顔が今度こそとばかりに止めに来るだろう。或いはもっと面白い誰かが飛び出してくるか。どうやら正義の味方志望の人材には事欠かないらしい、いいねぇ。 歩みだした。何故かまだ足元が若干覚束ない。視界が歪んでいた。 頭を打った覚えはないが、夕日を見すぎて目が霞んでいるのだろうか。 目を細めて、空を仰ぐ。 赤々と光る夕日が、消えない炎の様だった。 炎が沈んで、いく。 (夢を) (夢を、見ている気がする――) |