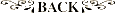●猫と忍者と茜の空●

| ● 晩秋の夕暮れ、三高平公園のベンチ。 空になった缶コーヒーを片手で弄びながら、『どうしようもない男』奥地 数史(nBNE000224)は傍らのキャリーバッグを覗き込む。中では、やっと落ち着いたらしい愛猫が毛繕いをしていた。 名を『テツ』という、この猫が目の不調を訴えたのは昨晩のこと。飼い主ばかりが傷を負う格闘の末、目に入っていた異物を取り除いて事無きを得たのだが、念の為に先ほど獣医に診せてきたのだ。 結果、異常無しの所見に胸を撫で下ろしたものの、帰り道でテツが大暴れしたため、ベンチで休憩がてらクールダウンを待っていたという訳である。 そろそろ帰ろうと腰を上げかけた時、不意に名を呼ばれた。 「む、奥地殿では御座らんか!」 黒のピーコートを着込み、ドラッグストアの袋を提げたサングラスの青年が、こちらに歩いてくる。 確かに聞き覚えのある声で、自分が知っている人物なのは間違いない筈なのだが、名前がすぐに出てこない。 「いやあ、こんな所でお会いするとは奇遇で御座るなあ」 時代がかった口調に、顔の左半面を覆う蛇の鱗――そこまで認めて、数史は漸く彼が『影刃』黒部 幸成(BNE002032)であることに思い至った。 あ、と声を上げた数史を見て、幸成が首を傾げる。 「……如何なされた?」 「や、悪い。いつもと雰囲気が違うから、一瞬分からなかった」 正直に打ち明けると、幸成は合点がいったように頷いた。 「奥地殿とは依頼にてよく顔を合わせて御座るが、こういった自分の姿を見せるのは初めてで御座るか」 忍者の家系に生まれたという幸成は、戦闘服として黒一色の忍装束を愛用している。彼が普段からあの格好で街を歩いているなどとは流石に考えていないが、第一印象から来る思い込みとは恐ろしい。 キャリーバッグをベンチの隅に寄せつつ、幸成が座るスペースを空ける数史。 「買い物帰りか?」 尋ねると、幸成は手に提げた袋の中身を数史に見せた。お徳用と思しき使い捨てカイロが、ぎっしりと詰まっている。 「寒さに弱い性質故に、カイロが欠かせぬので御座るよ」 変温動物の因子を宿していると、そういう部分も微妙に引っ張られるものだろうか。 ビーストハーフやアウトサイドも大変だな、と数史が零した瞬間、幸成がキャリーバッグに視線を落とした。 「もしや……この方は奥地殿の飼い猫殿に御座るか!」 言うが早いが、バッグの前に屈み込んで中を凝視する。サングラスをかけていても、彼が目の色を変えて見入っているのは明らかだ。メッシュ越しに熱視線を浴びて、テツが軽く身じろぎする。 すっかり返答のタイミングを逸した数史が呆気に取られていると、幸成は彼を見上げて声を弾ませた。 「も、もし宜しければ、もふもふさせて頂いてもよう御座ろうか……っ」 ええと、うん。――ああ、はい、どうぞ? ● 「いや実は自分、もふもふしたものには目が無くてな……。 その手の依頼に参加致そうといつも狙ってはいるので御座るがこれが中々!」 テツを抱え上げた幸成が、やや長毛がかった灰と白の毛並みを撫でさする。 獣医にも「少し太り気味」と言われたテツは、猫としては割と体重がある方なのだが……革醒者である幸成が、そんな事を気にする筈もない。 一方のテツも、相手が『自分より遥かに強い』ことを動物の勘で知っているためか、普段とは打って変わって大人しく身を任せている。もっとも、彼がとりわけ聞き分けの無い態度を取るのは、もっぱら飼い主と獣医に限られるのだが――。 愛猫の微妙に垂れた腹肉を見るともなしに見る数史の隣で、幸成がうっとりと口を開く。 「猫はいい……」 無論、その間もテツを愛でる手は止めない。 「己が気の向くまま自由に生きる姿。時にふと見せる甘えたがりな姿。もふもふした毛並み――」 どうも、スイッチが完璧に『猫かわいいモード』に切り替わっているようだ。 暫くの間そっとしておこうと決めて、数史は天を仰ぐ。 ああ、夕焼けが綺麗だなあ。今日の晩飯、どうしようか。 冷凍庫に鮭の切り身が残ってたから、それ焼いて。あとは何があったかな……。 やがて数史の思考が明後日の方向に突っ走り始めた頃、幸成の声がひときわ熱を帯びた。 「そして――気配を悟らせぬ軽やかな足取り。全てが自分を癒してくれる、至高の存在に御座るよ……!」 力説する幸成の腕の中で、テツが太い尻尾を揺らす。その動きを視界の隅で認めた時、数史の意識はやっと現実に戻ってきた。 隣を見ると、やはり我に返ったらしい幸成が「ごほん」と一つ咳払い。 「……斯様な具合に、普段は忍びとは程遠い顔もあるので御座るよ、うむ」 ここまで、アーク本部で目にする姿とのギャップに圧倒されっ放しだった数史は、そんな彼の言葉を聞いて初めて笑った。 「本当に、猫が好きなんだな。何だか意外というか、妙に納得したというか」 「まあ、依頼の時の自分が本来の姿では御座るがね」 テツを抱いたまま器用に肩を竦めてみせる幸成を見て、果たしてそうだろうか――と数史は思う。 一切の感情を排して“忍務”の遂行に務める、冷徹な“忍び”としての一面と。 猫を前にして盛り上がり、ついつい熱を入れて語ってしまうような陽気な一面と。 どちらの顔も、この『黒部 幸成』という青年の真実であり、それらは矛盾なく彼の裡で同居しているのではないか、という気がしてならないのだ。 「良いんじゃないかな、そういうのも。……いつも張り詰めてばかりいたら、疲れるだろ」 あるいは、日常とは過酷な世界に生きる者に用意された、一抹の救いであるのかもしれない。 ● 縫いぐるみの如く撫でられるままに任せていたテツが、大きく口を開けて欠伸をする。 それを見た幸成は、少し名残惜しそうに眠たげな猫をキャリーバッグに戻した。 「さて、日が落ちて寒さが増す前に帰ると致そうか」 「そうだな」 立ち上がった幸成に頷き、キャリーバッグを肩に担ぐ数史。 お疲れ、と言って別れようとしたその時、幸成が彼を呼び止めた。 「……奥地殿」 「ん?」 振り返ると、青年はおもむろに表情を引き締め。真摯な声で、静かに語った。 「己以外の他人をも思うことのできるその情の深さ、心の痛みを抱え続けるその強さ、自分は尊敬して御座る」 思わず目を見張る数史に向けて、幸成はさらに続ける。 「この先も辛い物を視ることを強いることになるやもしれぬが、どうか我らに力をお貸し下され」 暫しの沈黙。彼の言葉を心の中で反芻した後、数史は迷わず答えた。 「力が及ぶ限り、そうするつもりでいるよ。俺に出来るのは、これだけだからな」 ありがとう――と告げて、幸成とは逆の方向に歩き始める。 肩にかかるキャリーバッグの重みが、少し軽くなったように思えた。 |