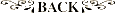●クロスファイヤー●

| ● そのバケモノは何度倒しても蘇ってくるという。 そんなばかなことがあるか。どうせ同じような姿かたちのエリューションが複数いるだけのことだろう。まとめてぶっ飛ばしてやる。仲間とともに笑いあいながらブリーフィングルームを出たのは、柔らかな春の日差しが降り注ぐ風のない午後のことだった。 それは簡単に終わるはずの仕事だった。 ● 「よう、また会ったな」 オレは手を上げて、塀の上を悠然と歩く猫に声をかけた。 やつが王者然とした歩みを止めて、沈む夕日を背に冴えた瞳の一瞥をくれる。 それで充分。 オレたちはゆっくりとすれ違った。 アウトロー同士、なかながと語り合う言葉も暇も持っちゃいねぇ。通じ合う一瞬が あればそれでいい。 ヤツとの出会ったのは、なぞのエリューションとその背後に見え隠れするフィクサードらしき人物の影を追って路地裏を歩いているときのことだ。 ふと強い視線を感じて頭を上げると、塀の上に奴がいた。 雑種。首輪はつけていない。どこの街にもいるノラ猫。 いつもなら気にも留めない所だが、やつはオレの気を引く何かを発していた。 帽子のツバを親指で押し上げて光の向うに目を凝らす。 小さな体躯に無数の傷。そこに大切な何かを守るため、己の命をかけて戦うものの生き様が見て取れた。 オレと同じと、やつも感じ取ったのだろう。 『あいつもアウトローだ』、と。 その日はこれといって有力な情報を得ることなく、ただ1日が終わった。 ● ヤツと出あって2日後の朝。 「あの情報は本当だ。やつは……やつは何度倒しても蘇ってきた」 帰ってこなかった仲間のひとりが血だらけになって戻ってきた。重症だ。調査中にくだんのE・ビーストと交戦したらしい。運命を大量に消費してなおノーフェイス化せず、命からがら逃げ帰ってこられたのは幸いというべきか。 ホーリーメイガスが癒しの風を吹かせる傍らで膝をつき、ぜいぜいと耳障りな呼吸音を発している男に、なんですぐに連絡してこなかった、と問うた。 「襲われてすぐにアクセス・ファンタズムを壊されたんだ。まるで狙っていたみたいに……執拗に、腕だけを……攻撃された」 「なんだと?」 確かに。ほかと比べて右腕の損傷が激しい。 嫌な感じがした。 覚醒して知能をあげたにしても、元は猫だ。AFのことなど知っているはずがない。となれば―― 「背後でフィクサードが指示を出しているな」 「ねえ、福松くん。E・ビーストのよみがえりも、そのフィクサードの能力なんじゃない?」 立ち上がり、膝についた汚れを手で払い落とす。 ホーリーメイガスの問いかけには、「さあな」、と一言だけ返した。 朝日が薄く金を刷いた生垣に目をやる。スズメの鳴き声に耳をすませながら、オレは受けた依頼の内容を頭の中で思い返した。 三高平の隣町で塾帰りの子供を犬のE・ビーストが襲い殺すという事件が発生。フォーチュナの予見ではE・ビーストのフェーズは1、しかも1体限り。すぐさまアークから6名のリベリスタが派遣されたが全員が返り討ちにされてしまった。 ――リベリスタを倒したのは同じ固体であると確認されています。 ――ええ、何度倒しても蘇ってくるのです。傷ひとつない体で。 ――気がかりな点がひとつ、現場から立ち去る人影が見えました。それが本件に関係ある人物かどうか分かりません。 ――先日、また別の場所で子猫を抱いた子供が襲われました。幸い、何者かが助けに入って事なきを得たようです。 ――予知は……出来ませんでした。理由はわかりません。 新顔とはいえアークのフォーチュナには違いない。予知できなかった、ということは何かあるのだろう。ともあれ、万華鏡に映らなかっただけでE・ビーストは複数いる、とオレたちは考えた。E・ビーストの巣を探し出し、容姿は愚か性別すら分からない不審な人物がフィクサードであれば本件とのかかわりを問いただした上で処分を検討する、ということで話は纏まった。 「とにかく、これからは単独行動はなしだ。2、2、3で3班に分けて調査を進めよう」 重症を負った仲間を三高平へ送り出したあと、オレたちは手がかりを求めて街へ出た。 ● またヤツと同じ場所で出会った。 すぐにオレはヤツの歩き方がおかしいことに気づいた。僅かに左の後ろ足を引きずっている。 ケンカして負けでもしたのだろうか、傷から出た血がべったりと茶の毛皮を濡らしていた。 ポケットからハンカチを取り出した。 手当てをしてやるから降りて来い、と塀の上へ腕を伸ばす。 肉球で手を軽く叩き戻された。 動物会話がなくとも解る。『余計な事をするな』、と言っているのだろう。 素直に腕を下ろした。 「誰とやったかしらねぇが、しばらくはおとなしくしてるんだな」 そいつぁ、できねぇ相談だな、とヤツが低く唸った。 オレは肩を竦め、足を引き摺るヤツを見送った。 「禍原、いいのか今の猫? ずいぶんひどいケガをしてたじゃないか」 「ヤツが構うなといったんだ。見た目ほどひどくはないんだろう……大丈夫だ」 そういいながらも、オレはヤツが残していった血の跡を目でたどっていた。 かなりの出血量だ。ほんとうに大丈夫だろうか? となりでパートナーがAFを開いた。 「――なんだって!?」 頭を起こし、何があった、と片眉をあげてパートナーに問う。 「また子供がE・ビーストに襲われたらしい。このすぐ先だ」 パートナーの指の方角と、地に落ちた血痕の続く先が重なった。 まさか。 「……ああ、子供は無事なんだな。……逃げた? なぜ? え、茶トラの猫がE・ビーストと戦っていた?」 おいおい、マジかよ。 振り返る。 ヤツの姿はもうなかった。 ● 「いらねぇ、とっときな」 「なに?」 「次のチャンスなんぞいらねぇていったんだ。てめぇらはここでオレたちがぶちのめすんだからよ!」 「ぬかせ、負け犬が。せっかく見逃してやると言っているのに、バカかお前は?」 倒れた仲間たちの体を夕日が刺す。 いま、ここで立っているのはフィクサードとエリューション化したペットの猫、オレ、そして―― ヤツが体を弓なりにして威嚇の唸り声を上げた。 オレは目でヤツに待ったをかける。 因縁のライバル対決に首を突っ込むほど野暮ではないが、先にアーティファクトを砕かないことには勝負にならない。 そう……、ここにきてやっと蘇りのからくりが解った。 戦いながらオレはある事に気づいた。フィクサードが手に持つ赤い数珠の一粒がが、E・ビースト復活のたび黒くなることに。どういう仕組みか解らないが、どうやらアレの中にはコピーされたE・ビーストの魂が入っているらしい。数珠は半分黒くなっているが、まだ半分が赤いままで残っている。そのうえ厄介なことにこのフィクサード、回復能力に特化しているときたもんだ。まともにやりあったら、そりゃ身が持たねえだろうさ。 「ここに坊主がいりゃ、正確な残機数が解るんだがな」 フィクサードが数珠を持った手を背後ろへ隠した。 「へ、図星かよ」 「な、なんのことだ」 さて、ヤツはオレの意図を正しく汲んで動いてくれるだろうか。 やるしかない。チャンスは一度きり。 銃を構える。 狙いは―― E・ビーストが飛び掛ってきた。 目をフィクサードに据えたまま、伸ばした右腕を左斜めに向けた。その下をヤツが足の傷をものともせずフィクサード目掛けて駆けていく。 断罪の魔弾が青黒いE・ビーストの横っ腹を撃ち抜いた。 ヤツの爪に手首を深くえぐられて、フィクサードが数珠を落とした。 あと一撃。耐えろよ、オレの体。ヤツの働きに応えるために! 左手のアウトロウ・アピアランスが火を噴いた。 数珠が砕け散る。 「うおぉぉぉぉっ!」 駆けた。駆けた。オレは駆けた。 駆けていって、呆然とアホズラさらすフィクサードの鼻っ柱へ固く握った拳をぶち込んでやった。 どさり、と重い音がして振り返る。 ヤツが仕留めたE・ビーストの背に前足をおいて、みゃう、と勝ち鬨をあげた。 ● あれから数ヵ週間後。 (ち、油断しすぎたぜ。なさけねぇザマだな……) 痛みに顔をしかめた。 塀を背に、太ももの傷を押さえて座り込む。 見上げるとそこにヤツがいた。 舌を出して前足の毛を繕っている。 フィクサードの追撃を逃れ、足を引き摺ったオレが辿り着いたのは偶然にもヤツのいるあの街の路地裏だった。 ふと、黄色い目がこちらを見下ろした。 ――オレは勝ったぞ。お前は負けたままか? 「余計なお世話だ」 オレはヤツを睨み返しながら立ち上がった。 ――何処へ? 「決まっている。ケリをつけに戻るのさ」 ふっ、とヤツか笑った気がした。 路地裏を新緑の風が吹きぬけていく。 背を押されてオレは歩き出した。 ● 数ヵ月後。 オレはまたあの路地裏にいた。ビルの影が落ちる、すこしうらぶれたその風景もヤツも健在だ。 何だ、まだ生きていたのか、とヤツが夏の熱気を孕んだ風にヒゲを振るわせる。 「ふっ、それはオレのセリフだぜ」 オレンジキャンディの封を切って口にくわえた。 すれ違うヤツに向けて右手をあげる。 ――またな。 ――ああ、またな。 言葉を交わさない奇妙なツレとの関係は今も続いている。 |