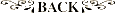●蛇と十字架、それから銃火●

「全く、神様も意地悪だな」 修道女が毒突いた。自動拳銃の声と一緒に。 銃口から吐き出された暴力は真っ直ぐに、螺旋を描きながら闇色の異形の頭部を撃ち貫いた。硝煙。空薬莢。されど、『アリアドネの銀弾』不動峰 杏樹(BNE000062)が魔銃バーニーを下ろす事はない。 月が見下ろす廃墟の町。彼女の橙睨が見澄ますのは、彼方のバグホールより這い出てくる数多の黒い異形達。アザーバイド。うぞうぞ、胡乱に蠢いては緩やかに杏樹を包囲し間合いを詰めてくる。 思い返す――課されたオーダーはバグホールの破壊という簡単な仕事だった筈なのだが。湧いてくる。撃った傍からわらわらと。 舌打ち一つ。薄闇の修道服を翻し、肩口に喰らい付いて来た異形を『錆び付いた白』の名を持つ盾で殴り飛ばした。 (流石に……一人じゃ厳しいな) 四方八方からの攻撃。踊る様に回り、巡る様に躍って。裂けた頬の一筋の赤。己の息が上がっている事すらも忘れてしまう敵の津波。くそ。悪態を吐く暇すらありゃしない。銃声。銃声。 しかし、天の神様は救いの手を忘れないらしい。なんとも憎らしい事に。 「よう修道女さん、俺を差し置いてデートかい? つれねぇなぁ」 含み笑いの軽口一つ。 その声に聞き覚えがあって、杏樹は思わず顔を上げた。瞬間、廃墟から跳んだ男が、その背中が、彼女の眼前にざんと降り立つ。靡く黒外套。鈍色の銃が火を噴き、襲い掛からんとしていた異形達を薙ぎ払った。 「……まさか、援軍が咬兵とはね」 杏樹は思わず小さく苦笑を浮かべてその男の名前を読んだ。蝮原咬兵。相模の蝮。まさかのまさかだ。視線の先、短くなった細巻きを吐き捨てた横顔が彼女に言う。 「嬉しいか?」 「さぁな。……背中を預けてもらうには、まだまだか?」 「あ? ――『さぁな』」 そんな一言、背中合わせ。 杏樹は魔銃を握り直す――少し折れそうだったけど、まだやれそうだ。仲間という存在の心強さ。大きな背中から伝わる体温が頼もしい。 凛然と前を向く。この大きな背中には護って貰ってばかりだから――せめて、足手纏いにならないように。せめて、隣に立てるように。 さて。 精一杯、頑張るとするか。 「反撃開始だ」 高らかに言い放つ。たった二人。されど一騎当千×2。恐れるものなど何も無い。 応と答えた声、銃と拳が唸る音を背後で聞きながら杏樹は異形へと指先を向けた。ユラリ。奪い取るのは精神力。エナジースティール。燃料補給(リロード)は完了した。 「インドラで焼き尽くす」 「任せたぜ、不動峰」 目も合わさずとも、事前の打ち合わせをしなくとも。直感。アドリブ。されどそこに隙はなく。 踏み出す靴の音が重なった。 「全ての子羊と狩人に安息と安寧を。Amen」 修道女は天へ。無頼は前へと銃口を向けた。 引き金を引く。 空から降り注ぐのは神の名を冠した紅蓮の焔嵐。 地を吹き荒れるのは神の名を冠した覇気の奔流。 襲撃にして強襲、急襲、猛攻、圧倒的に、あらゆる全てを薙ぎ倒す。 焼き尽くされ、八つ裂きにされた哀れな異形達が塵と化す。 それを踏み締め、踏み砕き、撃ち、薙ぎ、払い、殴り、蹴り。二人は進む。目指す先は際限なくアザーバイドを吐き出すバグホール。 「邪魔だ、退けッ」 一気に薙ぎ払ってやる。杏樹は異形が吐き出す弾丸に弾丸を以て応えた。狙撃には狙撃で。落ちる硬貨すら撃ち抜く精密射撃がアザーバイドの頭部を吹っ飛ばす。咬兵を護り、自分達の進路を切り開く。 それを見、足は止めず、咬兵は言う。 「流石だな」 「どうも」 寸劇のやり取り。咬兵が殴り飛ばした異形を杏樹が正確に撃ち貫き、杏樹が撃って怯んだ異形の咽を咬兵が掻ッ切る。 修道女と無頼の進撃。二人が通った後に出来るのは、敵の骸で出来た道。減速など、ましてや後退などするものか。 戦闘音楽は熾烈さを増していった。 「突っ切るぜ、尻込みすんじゃねぇぞ!」 「当然!」 ここまで来たんだ――咽から張り上げる鬨の声。闇のオーラを引き連れて、最後までこの勢いで。 「咬兵の前だ。一発だって外さないよ――撃ち抜くッ!」 射手の意地を見せてやる。弾倉に込めるは神なる炎。逃すものか。 その目は獲物を遍く捉え、狙い、撃ち放つ。 勇ましく大気を轟かせるのは激しい銃声。 降り注ぐ炎の矢が、廃墟の夜を紅く赤く染め上げた。 煌々と。火を宿す瞳の視界にはもう、歯向かう愚者の生き残りなど何処にも居ない。 一陣の風が、修道服を揺らめかせた。 ● 「やれやれ、散々な目に遭った」 修道女が毒突いた。安堵と疲労の溜息と一緒に。 傍らには紫煙を燻らせる無頼が一人。周囲に異形の影は無く、バグホールも既に閉ざした。今、廃墟にあるは静寂と硝煙の残滓のみである。 「立てるか?」 咬兵が壁に凭れ座り込んでいる杏樹に問うた。「そうだな」と彼女は肩を竦める。 「ボロボロだ。動けないくらいには」 「そいつぁご苦労さん」 で。ふーっと紫煙を吐いた咬兵が視線で問う。どうして欲しいんだい、と。ちょっと口角に遊ぶような笑みを浮かべつつ。 「……」 杏樹は視線を逸らした。そして、たっぷりの間を開けてから徐に両手を差し出して。 「悪いが、」 おぶってくれないか。呟いた。 甘えても、いいのかな。それ位。これ位。今日だけ特別。挫いた脚も、疲れ切った体も、歩く事を拒絶しているし。 良いだろうか。どうだろうか。そっと窺おうとした、その瞬間。身体から地面が離れる感覚。 「軽いな。もっと食えよ」 杏樹は咬兵の背中の上。零の距離と体温と。 「ちゃんと食べているんだが」と素っ気無く応えながら――杏樹は彼の背中に身を預ける。その温もりに安心感を覚えたのは、人恋しいのは、命の恩人で養父だった神父を思い出したからだ。 靴音と、鼓動とを聞きながら。回した腕にちょっとだけ力を込めて。杏樹はそっと目を閉ざす。抗えぬ睡魔。咬兵の外套に染み込んだ煙草の匂いを肺腑に満たし、深呼吸一つ。 そうだ――眠りに落ちてしまう前に。言わないといけない言葉がある。 なので、言った。眠気が声に滲まぬよう、小声だけれどハッキリと。 「ありがとう」 「はいよ」 ――夜は静かに更けてゆく。二人分で一つの影を、月が静かに見守っていた。 『了』 |