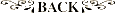●偶にはカフェで一時を●

| ● 「ねえ数史ちゃん。貴方、甘い物好き?」 アーク本部の休憩室にて、『逆月ギニョール』エレオノーラ・カムィシンスキー (BNE002203) に声をかけられた『どうしようもない男』奥地 数史 (nBNE000224)は、少し驚いたように目を丸くした。 「……ええ、割と」 その答えを聞いて、エレオノーラは彼をカフェに誘う。 「あたし一人で行くと色々とまずいの。保護者は? とか言われるから」 続くエレオノーラの言葉で、数史もようやく合点がいった。 神秘界隈において、革醒者の外見ほど当てにならないものはない。年齢も性別も、書類に記載されている内容と大幅にズレがある、といったケースはザラにある。 エレオノーラ・カムィシンスキー――“彼”こそは、双方の項目において『見た目で判断してはいけない』人物の代表格であった。 プレティーンの少女としか思えぬ美貌と、それに違わぬ立ち居振る舞い。 “三高平名誉少女”として認定される彼が既に傘寿を越えているとは、数史をしても俄かに信じ難い。 半世紀も歳が離れている相手にタメ口もなかろうと、敬語で話しているわけだが。 「奢るから、あたしを助けると思って。ね?」 そんなエレオノーラにこう頼まれては、断る理由など無い。 無精髭の三十男と、ロリータ・ファッションのロシア系少女(外見)の組み合わせは、それはそれで別の誤解を招きそうな予感もするが、あまり深く考えないことにする。 「――今日はこのまま上がりですから。俺で良ければご一緒しますよ」 かくて、実年齢平均57.5歳の男二人によるカフェ行きがここに実現したのだった。 ● カフェとは、その単語の響きからしてお洒落なオーラが漂っている場所だと思う。 何となく気後れしつつ席についた数史の向かい側には、慣れた様子で品良く座るエレオノーラの姿。背景との違和感が皆無なのは、流石と言うべきなのかどうか。 「ここ、本当に美味しいのよ。珈琲、紅茶、ジュースも種類豊富で」 エレオノーラの言葉通り、メニューはかなり充実しているようだ。とりあえずドリンクは珈琲から選んだものの、肝心の食べ物に悩む。 「数史ちゃんはどれ食べる? あたしは大体決まったけど」 「……同じの頼んでいいですかね。どうにも絞りきれなくて」 頷いたエレオノーラ、店員を呼んで注文。 「イチゴのミルフィーユとバゲットのフレンチトーストを二つずつ。あとプリンアラモードね」 え、と思わず顔を上げる数史。予想より、二品ばかり多い。 それに気付き、エレオノーラが彼を見た。 「――あ、多すぎた? あたしは全部食べるけど」 「いえ、大丈夫です……たぶん。ずっと書類仕事ばかりで糖分欲しかったですし」 「そう。じゃあ頼んじゃうわね」 「お願いします」 待つこと暫し。まずは一品目、『イチゴのミルフィーユ』である。 粉砂糖が振られた二枚のパイ生地の間には、カスタードクリームと大粒のイチゴ。さらに、イチゴ味と思しきアイスまで添えられている。これだけで充分にメインを張れるだろう。 「いただきます」 一体どうやって攻略したものかと思いつつ、フォークを手にする数史。 この、いかにも崩れやすそうなケーキを綺麗に食べられるエレオノーラには感嘆を禁じえない。 幾層にも重なる生地を口に運ぶと、軽い食感とともにバターの風味が広がる。 バニラの香り豊かなカスタードクリームは、控えめな甘さでイチゴの酸味を爽やかに引き立たせていて。 「ね、美味しいでしょう?」 「……ですね。正直驚きました」 心から頷く数史に、アイスも食べてみて、と勧めるエレオノーラ。 言われるまま一匙すくえば、イチゴの味にほのかな薔薇の芳香が加わって。 「それがこの店の特徴なのよ。――ほら、イチゴってバラ科だし?」 「イチゴにバラって連想すら出てきませんでしたよ、俺」 続く二品目は『バゲットのフレンチトースト』。 「軽食に近いけど侮れないのよ」 エレオノーラ曰く、チョコレートソースがかかったバニラアイスと一緒に食べるのが正解だとか。 狐色の焼き色がついた厚切りのバゲットは甘さ控えめで、冷たいアイスとのハーモニーが舌に心地良い。 カリッとした外側と、卵液でふんわり仕上げられた中身のコントラストも見事だ。 味や食感にバリエーションがあるためか、甘い物続きでも意外と飽きない。 「別の味が欲しい時は添えたグレープフルーツが良いわ」 そう言って優雅にカップを傾けるエレオノーラを見て、数史は思わず一言。 「どんだけこの店のメニュー知り尽くしてるんですか……」 少なくとも、エレオノーラの前では若い連中とのジェネレーションギャップなど語れそうもない。 彼と数史の間ですら、親子どころか“祖父と孫”に近いレベルの年齢差があるというのに。 こういったものは、実年齢というよりは個人の資質だったりするのだろうか。 まったく、恐れ入るばかりである。 そして、いよいよ三品目――。 満を持して運ばれてきた『プリンアラモード』は、これまでと違い一皿だけだった。 「これ、二人以上じゃないと頼めなくって」 確かに、一人前と考えると量が多い。 皿いっぱいに敷き詰められたカラメルソースの中央には、花の形をした大きめのプリン。 その周りには、等間隔に絞った生クリームの間にメロンやグレープフルーツ、パイナップルといった果物が惜しげもなく飾られている。 先に二品を平らげた後だと二人でも大変ではなかろうかと思ったが、どうやら要らぬ心配だったらしい。 絶妙な苦味のカラメルソースと、程よい弾力のプリンの相性は抜群で。酸味のある果物と生クリームが、また良いアクセントになっている。 「生クリームも実は甘さが抑えてあるの」 「ああ、成る程。道理で食べやすいというか……」 そんなやり取りを交わしつつ、プリンアラモードを胃に収めていく二人。 完食するまで、さほど長い時間は必要としなかった。 ● 会計を済ませた後、二人は揃って店を出た。 「今日は付き合ってくれてありがとね」 「こちらこそご馳走様でした」 同行の礼を述べるエレオノーラに、軽くお辞儀を返す数史。 レジで一度は財布を出しかけたものの、「奢るって言ったじゃない」と告げられて最終的に言葉に甘えることにしたのだった。 「フォーチュナって常日頃大変そうだし、たまにはこういうのもいいものよ」 老人のお節介ってところね――と言う彼に、数史は畏まって答える。 「痛み入ります。現場で戦ってる人達に比べたら、どうってことありませんけどね」 それは、紛れも無い彼の本心だ。 視るだけの自分よりも、直に事件と向かい合う人々の方が、よほど心身の負担は大きい筈だから。 しばし会話が途切れた後、エレオノーラが数史を見上げる。 「今度は数史ちゃんオススメのお店も教えてね。特にお酒の美味しい所!」 それを聞き、数史は「喜んで」と笑った。 「――日本酒の旨い店を見つけたんですよ。和食屋でも大丈夫ですか?」 |