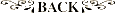ふたつでひとつの物語

| 人は一人だ。 此の世に生まれ落ちたその瞬間から、どうしようも無く一人なのだ。 血を分けた親子さえ、兄弟さえ、何時か永遠を誓う恋人でさえも――その隔絶は絶対的なものである。 他は真に他を理解する事は出来ず、また分かり合える筈も無い。 どれ程にそれに『近しい』関係を築けたとしても――肉体の檻の前に魂の繋がりは希薄にして脆過ぎる。 されど、もし。もし――孤独な世界に唯一つの例外を夢見ようと思うならば。 無垢な少女のように、真っ直ぐな少年のように――その例外を強く信じようと思うのならば。 これは一つの可能性。あくまで『可能性』の物語である―― ふたつでひとつの物語 ・Ch、1 「……うそだろ」 呟いた自身の言葉がまるで他人のもののように遠く響く。 爆発的に高まった動悸は目の前を眩ませる程に彼の体の中で暴れていた。 「……うそだ」 少年はその日、全身の血が凍り付く感覚というものを初めて知った。 『家の中』に出現した『敵(エリューション)』の気配に武装を済ませたジース・ホワイトは『物音の発生源』に『ルアのへや』と書かれた花模様のプレートがぶら下がっているのを確認した時、確かに堪えようも無い程の不安と衝動的な吐き気を自覚したのだ。 安住の地だと思ったのだ。 日本の新興都市が革醒者の為の街だと聞いた時、自身が生きる場所を見つけたと思ったのだ。 姉と生きていける場所はそこに違いないと確信した筈だった。 しかし、現実はどうだ? ドアを強く開け放てば、そこは女の子らしい可愛い部屋。 歳が上がるにつれて姉の部屋にお邪魔する機会は減っていたが――それでもそこは見慣れた姉の部屋だ。 自身にとっての日常、それそのものに不似合いな『侵食』が起きていた。 朝の爽やかな光景に酷く違和感を生じる、鉄分の匂い。姉の部屋に悄然と立つ『見知らぬ緑髪の少女』を中心に、赤いびろうどのような血が床に染み痕を残している。 風がざわざわとレースのカーテンを揺らしていた。 「おまえは、だれだ」 口の中をカラカラに乾かせて、ジースは問う。 端的な問いはだが、彼が一番知りたい情報をこの一言の中には含んでいなかった。 「ルアを、どこへやった――!」 烈火のような鬼気を含んだその言葉に少女が体を硬直させた。 ドアの向こうに現れたジースを呆と見つめていた彼女は彼の剣幕に押され、酷く不安そうに唇を戦慄かせた。 「……ジース……」 「……っ……!」 短い呼び声にジースは息を呑む。唯それだけの言葉がある意味で彼の問い掛けた二つの問いに応えていたからだ。 「……ジース、身体が変な感じなの。怖いよぉ」 泣き出しそうな少女はそのまま駆け出してジースの胸元に縋りつく。何処か懐かしい体温と鼓動は――『例え姿が幼いものに変わってしまったとしても』間違いようもないものだった。 ――思えば、姉は何時も怖がりで泣き虫だった。嵐の夜は何時も弟であるジースにくっついて泣いていた。その度に「大丈夫だ、俺が居る」と何度も言い聞かせてきたのだ。 思い出のシーンと現在が重なる。同じように目の前の小さな少女も自分に抱きついている。 ジースは研究者では無い。革醒を果たしているとは言え、言ってしまえば唯の少年である。この瞬間、理屈では姉の身に何が起きたかを正確に理解する事は難しかっただろう。 しかし―― 「ルア。大丈夫だ、ルア。俺が居る」 ――考えるよりも早くジースの口を突かせたその言葉は大凡理屈を超越していた。 此の世に生まれ落ちたその瞬間から一人――人間(ひと)の孤独に敢然と立ち向かう少年は、ある意味でドン・キホーテのようなものなのかも知れない。されど少なくとも彼はあの騎士殿と同じように――否、狂わず、迷わず、それ以上にあの日、あの時、あの瞬間、『魂を分け合うように此の世に生まれ落ちたルア・ホワイト』の事をかけがえのない半身であると、自分自身にも等しい存在であると確信していた。 或いは『共鳴』と呼べば良いのかも知れない――双子特有の超感覚はジースに姉の――ルアの置かれた状況を正確に理解させている。 ――フェイトを得ない革醒は世界に望まれない運命の忌み子である。 ――それが誰かの愛する者だとしたら? ――然り。ルールに例外は無い。 ――ならば、ルア・ホワイトは? ――然り。運命を失う者は悪人とも、誰にも愛されぬ者ばかりとは限らないのだから―― 短いながらもアークと呼ばれる組織に身を置き、リベリスタの仕事を知るジースは危機的状況を余りに正しく自覚した。 そしてその思考は圧倒的で絶対的に――彼の行動方針を決定付けていた。 「……逃げよう」 「……………え……?」 「逃げるんだ、何処か遠くへ。ここにいたら、いけない」 無慈悲な神の目が『悲劇』を掴むその前に。 あのオッドアイの少女が悲しげに『運命』を語るその前に! 「ルアは俺が、絶対、護るから」 こくりと小さく頷いた姉の手を引き、少年はその日――三高平市を後にした。 限りなくゼロに近い可能性(すくい)を追いかけて、それを境にフィクサードと呼ばれる事となるジース・ホワイトとノーフェイス、ルア・ホワイトの双子は冷たい風の吹く街へと駆け出したのだ。 ・Ch、2 何時も、守られてばかりだった気がする。 物心ついた時から――ううん、物心がつく前から一緒だった誰より身近な男の子。 わたしとは何もかもが違っていて、強くて、頼りになって……わたしは甘えているだけで良かったの。 ジースはわたしの自慢の弟。他の姉弟より、双子で近い事が何時も誇らしかったのよ。 だから、ジースが――一緒に逃げようって言ってくれた時も嬉しかった。 きっとジースならわたしを助けてくれるって……大丈夫なんだって…… でも、どうしよう。どうしよう、あの人達、とっても強い。凄く怖い顔でわたし達を見ているの。 ジース、うん、一緒に逃げよう。大丈夫だよ、私、走れる。走るのは得意なの。知っているでしょ――? 「お前、ノーフェイスだろ? ちょうど良かった退屈してたんだよ!」 『リベリスタ』と呼ぶには些か柄の悪い、些か以上に倫理に欠ける理由を口にした彼等と双子が出会ってしまったのはあてのない逃亡生活が一ヶ月を数えた頃の事だった。 「ノーフェイスに生きる価値など在りません」 最初の男より冷酷にそう告げる痩せぎすの眼鏡の男は愉悦を隠さない調子でそう断定する。 自身等を『カインド・オーダー』と名乗ったフリーの『リベリスタ』三人の事をジースは小耳に挟んだ程度に知っていた。執拗に獲物を追いかけ弱らせ、懸命に生きようとする人間だった者の命を踏みにじる、誇りなんて無い外道達。『ノーフェイスに生きられる理由は無いかも知れないが、生きる価値は存在する』そんな当たり前さえ理解しようとしない『正義の味方』。 「はぁ、はぁ、は――」 「……大丈夫?」 「当たり前だ。あんな奴等……」 逃げ延びた山小屋で身を寄せ合い、自身を心配そうに見つめるルアに嘯く。 その実、ジースの全身は満身創痍で、敵が諦めぬとあらば限界が近いのは明らかだった。 ……執拗に自身等を追い回す『カインド・オーダー』との鬼ごっこ、交戦は幾度かに渡っている。ジースは傷付き、その身を挺してルアを庇う。格上とも呼べる敵に立ち向かい、その時間を永らえんと死力を尽くす事でその猶予を伸ばしている状態だった。 「はぁ、はぁ、は――」 荒い呼吸が静寂の山小屋に酷く鮮明なノイズを醸す。 外に出現した粘つくような――悪意の気配に得物(ハルバード)を握り直したジースが腰を上げる。 「やめてよぅ……」 「何が」 大きな宝石の瞳を潤ませたルアにジースは問い掛ける。 姉が何を言おうと知っているかを百も承知で、それを受け入れる心算は彼には無い。 「やだよ。ジースがいたいのも、傷付くのも……もう…… そんなことになるくらいなら、私は殺されてもいいから、だから……」 思いつめた少女が『お守り』代わりのナイフを自身の首筋に押し当てようとする。 ぬるりとした熱い液体がパタパタと少女の頬を濡らす。ルアがうっすらと目を開ければ、その瞳には刃を強く握り締めたジースの姿が像を結ぶ。 「……ぁ、あ、ジース、ごめ、ごめんなさ――」 「――ばかやろう」 カラン、と床に落ち乾いた音を立てたナイフに構わずにジースは随分と小さくなった姉の身体を抱きしめた。 小刻みに震えている何よりも大切な存在を――仮初でも、一時でも安心させてやるように。ウェーブがかった柔らかな髪――自身と同じ赤色を失った姉の髪をくしゃりと撫でる。 「大丈夫。だいじょうぶだから。ルアは絶対守ってみせるから」 ジースの青いその瞳には誰にも侵せざる、何者にも砕けぬ強い決意の色だけが浮かんでいた。 その為ならば、自分は。 ――悪鬼にも修羅にもなれよう。唯、この願いが叶うなら――悪魔に魂だってくれてやる――! ・Ch、3 リベリスタ達の前に立つ小柄な少女――真白・イヴの表情は晴れやかなものとは言えなかった。 机の上に置かれた資料は少年がリベリスタであった頃の報告書だ。 「フィクサードがノーフェイスを連れて逃げた。元プロト・アークの少年リベリスタよ」 イヴの難しい表情をリベリスタ達はすぐに察した。 アークのリベリスタからフィクサードが出てしまったとあれば、近々本格始動予定のアーク内に開始早々、波紋が広がるかもしれない。確かにそれは回避しなければならない事態である。 「ノーフェイスはこの少年の双子の姉。今は覚醒したばかり、だから力も一般人と変わらない。 今、フリーのリベリスタ3人組と交戦中。地の利はフィクサードにあるから――何とか逃げている状態」 彼女の言葉に応え、モニターに映し出されるのは木々の間を縫うようにして走っていく二人の子供。 「今から行けば間に合う」 集まったアークのリベリスタが怪訝な顔で彼女を見やった。 ノーフェイスは撃滅せざるを得ない存在だ。 少年がそれを認めるとも思えないから――納得づく等、冗談にもならないだろう。 しかし、イヴはリベリスタの反応には構わず、資料の中にあった双子の写真を手に取った。 「このノーフェイス、フェイトを得る可能性がある」 リベリスタに少しばかりの動揺が広がった。目の前の少女の言葉を聞き逃さないように集中する。 一度は少女を見放し、逃避行に走らせた運命が彼女を掬い上げると言うのか? それは大いに理不尽ながらに――いや、運命とは理不尽なものである事をリベリスタは思い出した。 「でも、このままじゃフリーのリベリスタに追いつかれて二人とも殺されるわ」 淡々とカレイドシステムがはじき出した未来を言葉に乗せるイヴ。 ブリーフィングルームが重たい空気に包まれる。 「今から行けば、ちょうどフリーのリベリスタとフィクサードが交戦を始めるぐらいに着く。フリーのリベリスタと協力してフィクサードとノーフェイスを殺すか、フェイトを得るまで守ってあげるかはあなたたちに任せるわ」 イヴはそう言ったが彼女が『期待』するのはどちらだっただろうか? 少なくとも感情の読み難いその顔からそれを断言出来るリベリスタは居なかったが―― 「ただ、フェイトを得る可能性は低い。 彼女がフェイトを得る条件は、弟を庇うために誰よりも早く走る事。それが出来ないのならノーフェイスだけでも殺して」 ――そう言う彼女が祈るような顔に見えたのは、きっと気のせいではなかっただろう。 ・Ch、4 ――ぜったいに、やらせない―― まるで翼が生えたように――少女はその一歩を踏み出した。 涙を溜めたその両目は真っ直ぐに前だけを見つめ――震える膝はそれでも思った通りに動いてくれた。 視界の中で血を流す弟に凶刃が振り下ろされようとしたその時に――少女は両手を広げ、その間合いへと飛び込んだ。 これまで少女は優しい世界に生き、少年は優しさと勇気を持っていた。 二人が双子で『おなじもの』だと言うならば、きっと少女には最初から勇気も又眠っていたのだろう。 「――――ッ!」 肉を切り裂く生々しい音が少年の上げた言葉にならない絶叫にかき消される。 しかし、この時――駆けつけたアークのリベリスタ達は確かに見たのだ。 常人ならば致命傷に足る一撃を受けた少女が死の淵に踏み止まり、青く咲かせた運命の炎、その華を。 「ジースは、わたしがまもる――わたしは、『わたしたち』はだって――」 ――最初から、ふたつでひとつなんだから―― ……強い結び付きを持つ別個が真に互いを思い遣るならば、この世界は存外に孤独から守られているものなのかも知れない。 運命もそれを察して時を繋いだとするならば、案外話の分かる悪女だと見直したくもなる。 しかして感情も、繋がりも、人の心は余りに移ろいやすい不定形そのものだ。 絆は時に脆く、時にその形を変える。 永遠を誓った『魔女』はその全てに絶望し、神さえ無限の時間に磨耗する事もあるだろう。 故にこれは一つの可能性。あくまで『可能性』の提示に過ぎまい。 永久を願い、永遠を夢見てみたくなる――『有り触れた双子の物語』。 ルアとジースの――始まる前の、物語。 |