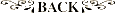鳥篭の鴉

| ●鳥篭の鴉 ぬるり、と。 温かくぬめった何かが頬を撫でた、気がした。 次に、ひんやりとした感触。 僅かに感じる空気の流れが、湿った肌から熱を運び去っていく。 その刺激が、ぼんやりとした意識を少しずつ引き戻すのだ。 ここはどこだろう。 だれかいるの。 霞がかかった思考を、彼女は少しずつ、少しずつ進め。 目を開けようとして、けれど視界は暗いまま。 ああ、そうか。 今はまだ夜なんだ。 ここはゆめの中。 まだおきるには早いから、このままうとうとしていよう――。 「フフフ、余程疲れているのでしょうかね。これからが楽しいというのに」 びく、と。 もたれた背が、海老反りのように固く引きつった。 一瞬にして覚醒する意識。 わたしはだれ。曳馬野・涼子。 身をよじる。動かない。 目を開ける。光は見えない。 間近に感じる、生暖かい息遣い。 「おはようございます、涼子さん」 後宮・シンヤ。 ジャック・ザ・リッパーの懐刀。 逸脱の殺人鬼。 ただ一言、そう嘯いたこの男の声が、少女の耳朶を舐めて。 蛇のようにするりと、ずるりと潜り込んだ。 「――あ、あ――」 身を捩って、手首に走る痛みに眉を顰める。 拘束されているのだ、と気づくのに時間はかからない。 せかいがまっくらなのも、きっと、目を塞がれているから。 「さあ、どうしますお嬢さん」 「どうします、だって……」 搾り出した返答に向けられたのは、何を今更、という嘲り。 「判っているんでしょう? それは、ただの紐ですよ」 手首の戒め。 ただの紐。 力を込めれば、引きちぎることが出来る、と言っている。 そう、ちからをこめて引きちぎれば、アンタを。 「やれやれ、怖いですねぇ」 だが。 膨れ上がった殺意は、急激にしぼむ。 見えない。見えないのだが。 感じたのだ。 溜息をつかんばかりの口調とは裏腹の――。 「――っ」 彼女の怒りなど足元にも及ばない、ねとりと絡みつく――蛇の目線を。 だめだ。 コイツは、だめだ。 かてない。かてない。かてない。 男が面白半分に叩き付けたプレッシャーが、少女を悶えさせる。 「そんなに怖がらなくてもいいと思いますがねぇ」 なんで、こんなことになったんだっけ。 混乱した頭で記憶を辿る。 それは今日のこと、それとも昨日のこと。 六道のフィクサードとの戦いに、この男は割り込んできた。 ジャックの名の元に集まったフィクサード達――通称後宮派を率いて。 ボロボロの彼らに、抗う術はなかった。 嬲るようにシンヤが示したのは、人身御供の供出。 その先の記憶にかかったもや。 なんで、わたしはそんなものにしたがったんだろう。 ぼんやりと思い出す。あの時、あの場所に居たのは。 斃れた六道。 傷ついたリベリスタ。 そして――。 「あのかぞくは、無事なの」 「ええ、約束は守りますよ。守りますとも、ゲームなのですからね」 うそだ。 直感的にそう考え、けれどすぐに打ち消した。 ――あのかぞくには、無事でいてほしい。 超常の戦場に放り込まれ、震えているしかなかった彼らには。 「……やくそくは、守れ」 でなければ。 でなければ、また夢に見てしまう。 いちめんのあか。 倒れ伏したからだ。 うつろなひとみ。 「怖い怖い。リベリスタというものは皆こうも強情なのでしょうかね」 視界を遮る目隠しの向こうで、きっとあの男はニタニタと見下ろしているだろう。 ぎり、と歯を鳴らす。 悔しかった。 力で守りきれなかったことが。 こうして囚われ竦んでいる自分が。 天涯孤独の自分を助ける仲間など居ないだろうことが。 違う。 守れた気になって、許された気になっている自分に、唐突に気がついたからだ。 そしてもう一つ。 「アークのリベリスタはみんなつよいよ。アンタを、きっと放ってはおかない」 助けに来る、とは言わなかった。 それでもお人よしのアークは助けに来てくれると、縋りたくはなかったから。 自分の力では何も出来なかったのだと、知らしめに来る彼らに。 「フ、フフフ。楽しみじゃあないですか。それはそれは!」 男の声に熱が加わった。あるいは、嘲りの色が濃くなった。 どれほどの敵が来ようと相手にはならぬ。言下そう告げる逸脱者の意思。 その圧倒的な自信に、彼女の頬が歪んだ。 恐怖。反発。期待。不安。――苛立ち。 ほう、と男は面白げな様子を見せて。 次の瞬間。 「――っ!」 無言で、冷たいものを頬に押し当てた。 それが何か、言われずとも判る。 ナイフ。 あの赤いナイフ。Ripper's Edgeの名をシンヤと共に冠する凶器。 数え切れぬ命を奪ってきたもの。 「ひ……っ」 思わず声を漏らした彼女を、誰が責めようか。 思わず身体を固くした彼女を、誰が笑おうか。 意識が途切れる前の最後の記憶で、やすやすと六道の命を奪ったそれに。 そしてリベリスタ達を歯牙にもかけなかった圧倒的な力に。 くく、と喉を鳴らす男。 冷たい刃が肌から離れ、そしてまた生暖かいものが彼女の頬を濡らす。 こんどこそわかった。 ぬめりと這いずるそれは。 舌だ。 「フフフ、時間はたっぷりとあるのです。それまでじっくり楽しむとしませんか、涼子さん」 そう、貴女の言うとおり、アークの皆さんが助けに来るまでね――。 耳元で囁かれた嘲笑に、彼女の華奢な肩が震えた。 たすけて。 |