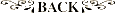無題

| 一体何故こうなっているのか……。 深春・クェーサーがその時考えていたのは、そのようなことであった。 場所は慣れぬカフェテラス。目の前に鎮座するのは紅茶とケーキと、一人の少女。 「ケーキには紅茶! ミルクティーならなおよし! そう思うだろう!?」 「いや……確かにその通りだが」 景気よく騒ぎ立てるその少女、斎藤・なずなが今の状況を引き起こしたのは間違いはない。 正直深春にとって今の環境はアウェイと言っても過言ではない。なのに何故このような場所に、なずなと二人きりでいる羽目になっているのか……原因は数時間前に遡る。 なずなが深春を見つけたのもまた、偶然であった。 時間を持て余し、町をぶらついている時にたまたま目についたのが深春だったのだ。 見かけた深春はいつものブレザー姿。その様子になずなは問うたのだ。普段どんな服を着ているのか、と。 「大体はこれと同じだ、実用性に勝るものはない」 その言葉になずなの中の何かが疼いた。 「お前も年頃なんだからたまには可愛い格好とかだな……」 「……そうか?」 そうなのだ。深春にとって実用性第一、ファッションは行動を阻害しない程度の要素であればいい、といったレベルなのだ。 自らクェーサーであることを義務づけた彼女にとって、戦う事以外は些末な問題なのだろう。……いや、少女らしい点がなくもないのだが。 「……女に生まれたからにはお洒落しないとダメだと思うのだ」 その言葉におずおずと深春が差し出したのは……いつも身につけているヘッドフォンだった。 「……お洒落」 ――その様子になずながキレた。 「遊びに行くぞ! お前に拒否権はない!」 ……こうして二人は町に買い物に出る事になったのだ。 町に出た深春の様子は借りてきた猫、といった生やさしいものではなかった。完全に敵地において警戒を解かない兵士のそれである。 なずなはそのような深春を連れ回した。雑多なファッションの満ちたモールを引っ張り回し、様々なファッションをあてがったのだ。 「これを着てみろ!」 そういってなずなが押しつける服を、戸惑いながらも深春は素直に身につける。普段纏わぬ少女めいた服装に、彼女は照れるではなく不安に満ちた表情になる。 状況に戸惑う深春を、なずなは散々に着せかえさせた。満足の行くまで、徹底的に。 「いや、私はこういう服はあまり……」 「文句を言うな! とりあえず着れ!」 渋る深春。強引に押し通すなずな。押し問答のようなやり取りが散々繰り返され、最後には深春が折れるという流れが繰り返される。 普段ならば毅然と深春は断るだろう。だが、ここはショッピングモール。深春にとってはアウェーで、健全な女子であるなずなのホーム。単身敵地に投げ出されたインテリが生存できる確率はゼロである。 なずな率いる怒涛のファッション軍に深春はただなす術もなく蹂躙され着替えさせられたのであった。 ……そして今に至る。 「疲れた……」 深春の口から漏れるのはそのような言葉であった。 普段と違う環境は必要以上に体力を使う。今、深春は戦場に立った時より疲弊しているといえよう。 途中に押し付けられ着せられた服などは致命傷であった。フリルがついたワンピース、そのような類のものはいままで深春は着たことがない。なずなは満足げであったが、深春は借りてきた猫どころか死んだ猫のような有様であった。 正直なずなにとってしてみれば、ただ遊び歩くだけで戦闘より疲れている深春の様子は溜息ものである。娯楽に馴染みがない人間は三高平では珍しくはない。だが、深春のそれは群を抜いて見える。 戦いにおいては一切ぶれることもなく、苦もなく手足のように仲間を操る指揮官だというのに……今、眼前にいる深春は、精魂尽き果てたかのようにぐったりとしている。 (まったく困った奴だな) そのような深春に、心中呆れながらもなずなが紙袋を差し出した。 「……これは?」 「おそろいだ! 色違いのやつだが!」 その袋の中には、なずなが今身につけている花をあしらったカチューシャ――その色違いのものが入っていた。 「たまにはこういうお洒落もしてみるがいい」 有無を言わさぬ様子のなずなに、深春は口を開く。 「……だがこれはヘッドフォンと干渉するのでは」 「うるさい! ヘッドフォンはお洒落の道具とは言わん!」 大声を張り上げるなずな、どうしていいか戸惑う深春。そんな奇妙な状況ではあったが、なずなの思惑は上手く行ったのかもしれない。 少なくとも今の深春は、作戦会議室にいる時とは違う、張りつめた空気はなくなっていたのだから。 |