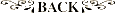Apply Apple 24/7

|
●1 P.M. 三高平中心部のショッピングモールから足を伸ばして十数分。 住宅地の入り口に位置する小さなスーパーマーケットはどこか鄙びた空気を纏っている。 華やかなモールの大手スーパーマーケットとは違い、こちらの店には小じゃれている以上の特徴はなさそうに見える。だが地産地消を意識した新鮮さと、自然派だかなんだかの品揃えに魅力があるらしい。余りお安い事を売りにした店ではないようだ。 食料品を積み込んだ多数のカートが主婦達に引かれている。店内は夕暮れ時の本番を前に商品入れ替えの真っ最中だ。軽快な電子音楽は一度目のタイムセールを告げている。そんな休日の午後。十四時十五分の事。 銀色の髪の少女は毎週、このスーパーマーケットへ足を伸ばしていた。 週に一度は林檎を食べ、林檎料理を自作するというのが彼女の習慣だ。 今日も今日とて何を作ろうか、どの林檎を買おうか。そんなことまで既に決めているのである。 こうして。お目当ての棚の前で『みかんは敵なのー!』八月十五日・りんご(BNE000827)は、いつもの果実を掴み取ろうと手を伸ばす。 突然触れ合う、手と手。指と指。 あ、と。小さな声を上げ、会釈と共に謝罪する桃色の髪の少女にりんごは頬を綻ばせる。 だって。二人が同時に手にとろうとしたのは、赤くて瑞々しい林檎だったから。 きっとこれは―― ―― ―――― 運命の出逢いだから。 ●2 P.M. 「え、と」 「クッキーング! なの!!」 桃色の髪の少女『翠玉公主』エスターテ・ダ・レオンフォルテ(nBNE000218)は懸命に餃子を包んでいる。 エスターテは右へ右へと皮を手繰り寄せ、不器用に閉じて行く。 「そこで、そう! こうすると上手くいくの!!」 手際よくヒダをこしらえて行くのはりんご。見よう見真似のエスターテ。 なぜ斯様な事へと至ったのか、仔細を語れば長くなるのだが、その実、本筋は非常に単純でもあった。 りんごはかくかくしかじかの末、スーパーマーケットで購入した材料を使って林檎料理を作る為、エスターテが住まうマンションへと押しかけたのである。 「その……」 急な話もなんのその。とにかく小学校の跡地を利用したと言われる堅牢な佇まいの一室で、二人の少女は一生懸命に餃子を作っているのだ。 「そうなの! その調子なの!!」 「は、はい――」 りんごはと言えば、エスターテの答えなど最初から聞いていなかった。調理姿から垣間見える今の光景、空気をそのままに、とにかく強引に押しかけた格好になる。 最も、翻弄されるように買い物をしていたエスターテとてまんざらではなかったのか、そもそも交友関係の少ない彼女はなんとはなしに、そのままりんごを招きいれたのであった。 こうしてエスターテはりんごに習い、不慣れな手つきでとにかく餃子を作っている。沢山作っている。 「大丈夫なの! いけるの!」 「え、と。はい」 お誕生日も一緒なの。 え、えと。 奇しくも。偶然か必然か、二人の少女は年は違えど同じ日に生まれたらしい。 みかんは敵なの! え、えと、その。 たじたじ。お構いなし。 エスターテの家にある調理器具の数々は、どれも使われた形跡がまるでない。おそらく彼女がこのマンションに一人で住まうにあたって調達したものなのだろうが、生憎とこの少女は料理が出来なかった。だがそんな調理器具達も、なんやかんや、こうして日の目を見たのだから、それはそれで良かったのではないか。 兎も角。りんごとエスターテは共に少女であり、アークに所属するリベリスタであるから、まあ、初対面とは言えど部屋に入れた所で害はあるまい。それになんだか和やかな光景なのであった。 そんなこんなで、今、台所に漂うのは、なぜだか甘い香りである。 なぜか。二人の少女が作っているものが餃子であるならば、おかしな話だ。 なぜならば餃子の皮に包まれている餡は、林檎のコンポートにシナモンパウダーを振りかけたものであったから。この餡も勿論手作り。林檎を小さく切って、たっぷり時間をかけてレモン、砂糖と共にお水でコトコトと透明になるまで煮込まれている。エスターテが知る良しもないが、だから肉質がしっかり締まった、小振りで酸味の強い品種が選ばれたのだろう。りんごはその名の通り、林檎のプロフェッショナルであるらしい。 ところで、これが果たしてどんな味になるのかエスターテには皆目検討がつかない。りんごにリードされるがままに餃子をこしらえているのだが、何をどうすればどんな味になるのか、どんなものが出来るのかという所は、まるで頭の中にはなかった。 それに質問をしようにもなんだか気が退けてしまう。だからとにかく押せ押せなりんごの指示に従っては居るものの、己の作業にまるで自信が持てないのだ。 そもそもエスターテにとって餃子というのは醤油、お酢、ラー油につけて、ご飯と一緒に食べるものだという先入観がある。言葉には出せないがなんだか気色悪い気もするのである。 エスターテの頭の中で様々な不吉な事象がぐるぐると巡る。ご飯に乗せる餃子。林檎とシナモンの味。そこに醤油と酢とラー油が混ざって―― 「失敗しても大丈夫なの!」 そういうものなのだろうか。怪訝そうな表情を浮かべ続けるエスターテの様子を察してか、それとも天然か。後者である気もするが、それはさておきりんごの作業は澱みなく、滞りなく、手際よく丁寧に餃子を包んでは並べて行く。見た目だけならば、まるで豚肉と香味野菜を包んだ普通の餃子そのものだ。 なるようになれと、半ば思考を放棄したエスターテは、言われるがまま、フライパンに少量の油とバターを張る。 くつくつと微かに煮え始めたフライパンにりんごが菜箸をつけ――揚げ時だ。 「今なの!!」 「え、と、はい」 りんごの勢いに背を押されるように、次々に餃子をフライパンに投入するエスターテ。餃子がしゅわりと油の中を半身泳ぎながら滑走してゆく。油を、餃子を、焦がさないように、温度を上げすぎず、丁寧に、丁寧に。 程なく皮が揚る香ばしい香りが漂い始め、食欲をそそる。 もうすぐ三時。昼食は食べたけれど―― ぐぅ。 ついついお腹の音がしてしまう。聞こえたろうか。てきぱきと片付けながらも作業を進めるりんごを横目に、エスターテの頬は林檎のように赤かった。 ●3 P.M. こうして、お皿に並べられた餃子は熱々で、おいしそうで。 見た目だけならば本当に普通の餃子。ご飯によく合いそうな出来栄えだ。 幸い皮が破れることもなく、綺麗な狐色に焼き揚っている。 だけど――中身は―― 「紅茶を淹れてほしいの!」 エスターテの不安と打ち消すように、まるで使われていない食卓を拭きながら林檎のお願い。矢張り、有無は言わせない。 「は、はい」 こうなれば致し方ない。エスターテは細かく砕かれたセイロンの茶葉をティースプーンから落とし、こぽこぽと沸騰するお湯をポットへと一気に注ぐ。 そのままケトルの横でコージーをかぶせて蒸らすこと数分。食卓に運べば、りんごはりんごで台所に戻って餃子をお皿に並べている。見た目は餃子。お皿とフォークはスイーツ用。無表情な中にどこか諦めと怪訝さの入り混じった表情を崩さぬまま、エスターテはテーブルに着く。 対するりんごはきらきらと満面の笑みのままエスターテの瞳を覗き込んでいる。エスターテは消え入りそうな声でいただきますと述べて餃子を口へと運んだ。 ゆっくりとかみ締める。 溢れるのは肉汁じゃなくって、甘い甘い林檎のソース。 あれ――? パリっと香ばしく揚った皮はパイ生地のように林檎のソースと絡み合い、爽やかな酸味と共に、焼きたてのアップルパイのように口の中に広がって行く。 一息つけば、ほんのりと香るシナモンが鼻腔をくすぐった。 「美味しい、です……」 本心だった。 あまあま、ほくほくのりんご餃子は、冬の終わりを彩るとびきり贅沢な一時をプレゼントしてくれた。 冬の終わりと共にやってきた不思議な友人が教えてくれた変り種のスイーツメニューは、この日からエスターテの定番になったのである。 りんご餃子。 フランスブランドの林檎紅茶に沿えて。 お味は―― ―― ――――星三つ☆☆☆です。 |