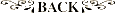●バロックナイトイクリプス・イフ・アナザー『ゾンビナイトサバイバル』●

|
●プロローグ。そして前振り。 2010年12月、とある千葉工大・雀田研究室。 それが、この世界で最初に崩壊した場所だった。 工業大学だからといってビームライフルだのジェット居合い刀だのを開発しようとする頭のイった(褒め言葉)学生達の通う大学は、やっぱり教員もどこか頭がイってる(褒め言葉)らしい。 「俺はゾンビ映画を再現するんだそしてホームセンターにパツキンのチャンネーと閉じこもって……いいことを……する!」 なとど文化人とは到底思えないような発言を残し研究室に一年籠もった雀田教授。 単位を必要とする学生達を自動的に一年間留年させ、このままでは車買えちゃうくらいの学費を吸い上げられちまうぞと焦った学生達による一揆が起きかけたまさにその時、謎の爆発と共に大量のガスが発生した。ガスに乗った特殊ウィルスは意思があるかの如く周囲の人間達に吸い込まれていき、脳を中心にたった数秒で支配。肉体構造を超神秘的に変化させ、強靱な身体能力と自己回復能力、そして衝動的な暴力性と飢餓感を発する生命体……つまり『ゾンビ』へと作り替えてしまったのだった。それは宿主の体内で成長・増殖し、唾液を使って他者の体内へと感染するというまさにゾンビ映画さながらの特性を有していた。 パッと見た限りでは特殊メイクしたやんちゃさんにしか見えないし、出てくる場所が千葉でも特にオタ率が高いと有名な大学だったために近隣住民の無防備っぷりは激しく、みるみるうちに千葉市全域に拡大。このままでは日本全土に感染拡大が起きると見た国会は千葉の県境にバリケードを形成。土地の殆どを海に囲まれた千葉県は日本から……いや世界から隔絶されたのだった。 無論千葉県民達は激怒した。大抵のことは受け入れるし千葉で開催されるイベントに東京の頭文字がつこうが舞浜が東京扱いされようがまあいいじゃないかの精神で頑張ってきたがまさか国から切り捨てられるとはおもわなんだ。彼らは行政が頼りに出来ないことを悟り、それぞれの力で生き残りを図ったのだった。 こうして千葉県内にあるヘリコプターをはじめとする飛行手段とフェリーや輸送タンカーといった海上移動手段によって多くの人々が逃げ延びることに成功したが……全ての県民が逃げ切れたわけではない。 もうこうなったらオカルトでも何でも良いから逃げるんじゃいと言い捨て、頭のイかれきった(褒め言葉)千葉工大の若者たちは千葉県で最も本が手に入りやすいといわれる土地柄を活かしてついに異世界とのゲートを繋げることに成功。 しかし作成したゲートは『異世界→こっち側』の一方通行のみ。こりゃ失敗だと頭を抱え、もう近くのカラオケ屋で自棄カラしようぜと捌けていった……その後。 「一方的に呼び出されたのが私たちになります」 「大学生っていうのはどうしてこう……」 「いや、大学生が悪いわけじゃないだろ」 「せめてゲート閉じていってくれたらよかったのにね」 絢堂霧香、結城宗一、設楽悠里の三人はそろって額に手を当てていた。 二十歳前後の男女がそろって頭を抱えている様子としてご想像いただきたい。 そんな三人の前で無表情にたたずむリンシード・フラックス。 シュールな絵だった。 この世界(何という世界なのか?)に一方的に呼び出され、その上放置されるという事態に陥った霧香たち。 彼女たちがこの世界の状態を察するまでそう長い時間はかからなかった。 町中を闊歩するゾンビの群れ。彼らはリベリスタおなじみのアンデッドとは違って神秘技が全く通用しない。というか一般人レベルまで身体および神秘能力がダウンしていた。この世界自体に神秘能力をキャンセルする何かがあるのか、それともうっかり『そういうたぐい』のものに触れてしまったのか……理由はわからないが、とにかく知恵と根性で乗り切るしかなさそうだ。 「そんな状況でも、積み上げてきた知識は私を裏切らないはずだ……」 へメモ帳片手に扉を閉めるミリィ・トムソン。 霧香たちはビル上階にある飲食店に立て籠もっていた。ここまで紛れ込んでくるゾンビは少なかったし、何より施錠できるところがいい。 まあ、本気で破ろうとすれば数分も持たないのだろうが。 「情報を集めてきましたよ。なんでかこの辺は有識者が多いみたいで……何やってるんです?」 「いえ……」 「いや……」 「うん……」 三者三様にそっぽを向く二十歳前後チーム。 ミリィは首をかしげつつ、メモ帳をめくった。 「今後の指針がないと動けないですからね。まず『私たちの世界に帰る方法』、これを調べました。学生の開いた穴はこの通りですが、県外……つまり東京にはそれが可能な技術者がいるようです」 「あ、じゃあその人に頼めば帰してもらえるかな」 表情を明るくした悠里だったが、リンシードは目を細めて首を振った。 「たとえば悠里さん、街角で出会った他人に今すぐ二十万くれって言われたとして、あげます?」 「……いや、そっか、相手にとっては手を貸す理由がないんだよな」 「『手を貸す』程度で済めばいいが、組織レベルの承認が必要だったり、リスクが犠牲が伴ったりすると簡単には行かないだろうな。命を助けるくらいの貸しを作らないと……」 アイスコーヒーを片手にうなる宗一。 彼の顔を横目に見ながら、霧香は口元に手を当てた。 「最悪この世界に閉じ込められる可能性があると考えると……」 「家族を人質にとって脅しましょう」 「いや、それは駄目な気が……」 さらっと犯罪に手を染めようとしたリンシードへ、控えめにツッコミを入れてみるミリィ。 メンバーの中では唯一の同年代なのでできれば仲良くしたいのだが、いまいちその取っ掛かりがつかめないでいた。 それはまあ、さておき。 「有力なカード……になるかどうかは分からないですけど、近くのホームセンターに大学教授が立て籠もっています。なんとかその辺から攻められないかなって……」 「なるほど、コネクションか……」 「ホームセンターってところがいかにもだなあ……」 腕組みをする宗一と悠里。 とはいえほかに手があるわけでもない。 彼らは拠点にしていた飲食店を後にし、ホームセンターへと向かったのだった。 ●ドロップアウト 世界の様相が現代日本のそれとほぼ同じだったことからも分かるとおり、ホームセンターの様相も(リベリスタたちの)知っているものとほぼ相違ない。 というわけで、小柄なミリィとリンシードが屋外ダクトを通って内部へ潜入し、そっと裏口の鍵を開けて霧香たちを招き入れることにした。 このとき、霧香も体格的に入れそうな気もしたが、宗一悠里ともに『見えなかったこと』にしておいた。なんだか怒られそうな気がするのだ。 「それにしても、どこへ行ってもゾンビだらけだな……謎電波とかで俺らの位置を探ってるんじゃないのか?」 「まさか」 二十歳前後の大人組は、裏口に放置されていた鉄製のダストボックスに身を潜めてゾンビたちをやり過ごしていた。 「少なくとも嗅覚は発達してそうだよね。死んでない奴の臭いをたどる的な……」 「だからといってゴミ箱に潜まなくても……」 ダストボックスの構造上、万一居場所がバレて襲われそうになっても防御できるのだが、まあ……乙女はいろいろ気を遣う生き物である。非常時とはいえ。 「まあ、リンシードちゃんたちの合図を待つことにしましょうか」 彼らはダストボックスの隙間から外をうかがいつつ、じっと息を潜めた。 一方その頃、ホームセンター内では。 「広くはないですけど……迷いそうですね」 「そう、ですね」 天井の空調フィルターを突き破ったリンシードが、平たいタイルの上に着地。バランスを崩して落っこちてきたミリィをお姫様だっこでキャッチした。 「わっ! あ、ありが……」 「ミリィさんは頭のよい方だと聞いています」 相手の言葉を遮るように語りかけるリンシード。 「私と違って、生存のために役立つでしょう」 「え、えっと」 どぎまぎしたまま返答に詰まるミリィ。だがこの時、リンシードの言葉の意味を考えておくべきだったのかもしれない。もしくは反論するべきだったのかもしれない。 だがどのみち、訪れるものは訪れるのだ。 まるで運命のように。 「君たち、ここで何をしてるんだ!」 バールを重たげに担いだ男が小走りにやってくる。 一見して四十代後半くらいの、白衣を着た男だ。 少女が少女をお姫様だっこするという状態を見て、非ゾンビ体だと認識したのだろう。周囲を警戒しながら、リンシードたちを店舗の奥へと案内してくれた。 「私は工業大学で非常勤教授をしている者だ。ゾンビウィルスを作った教授は友人でね、多少はこいつらへの知識がある。あいにく頭脳労働者なりの体力しかないが……君たち、お父さんとお母さんは?」 「いません……」 リンシードが無表情に答えると、教授の男はバツが悪そうに黙った。誤解されていることは分かったが、あえて訂正しないことにする。 しかし、これはチャンスかもしれない。彼を県外へ連れ出せば、大きなコネクションになる筈だ。場合によってはエスケープ手段を都合してもらえるかもしれない。 リンシードが『話し合いは任せました』という目でミリィを見てきた。頷くミリィ。 「あの……大人が一緒にいるんです。裏口に三人。一緒に逃げることはできませんか?」 「裏口か。丁度いい、そこに車を泊めてある。この辺から適当な道具を見繕って、一緒に逃げよう。私にはヘリを都合するアテがあるんだが、一人で出て行くのは少し不安でね……恥ずかしい話だが、タイミングを待っていたんだ」 「それなら!」 とんとん拍子じゃないか。 ミリィは手をたたいて顔を明るくした……が、次の瞬間表情が凍ることになる。 何故か? ガラスの割れる音がしたからだ。 それも、正面玄関にある自動ドアが盛大に破壊された音だ。 なり始めた警報器(現状、これほど無意味な装置はない)を上回るほどの唸り声をあげ、沢山の足音が近づいてくる。 「しまった! 君たち、裏口まで案内する、ついて……うおお!?」 走り出そうとした男がうつぶせに転倒。見れば、商品棚の下からゾンビの手が生え、男の足首を掴んでいたではないか。 「もうこんなところまで!」 「は、早く!」 見たところ子供の手だ。リンシードたち同様ダクトから進入したのかもしれない。 ミリィは必死に男の足を引っ張るが、子供とは思えぬ怪力でしっかりと捕まれて動かなかった。 「だめだっ、こうなったら君たちだけでも」 「いいえ……」 リンシードは男の手からバールが引ったくると、子供ゾンビの腕めがけて全力でピック部分を振り下ろした。 『ごぶじゅん』という、聞いたこともないような音をたてて手首が吹き飛んでいく。 反動でひっくり返る男とミリィ。 リンシードは少しだけ振り返ると、(彼女にしては)早口にまくし立てた。 「ここは私が引きつけます。ミリィさん、教授さん、あなたたちはこの先に必要です。私は……まあ、この辺が妥当でしょう」 「リンシードさ……!」 「危ない!」 ミリィの体が抱え上げられる。 その途端、商品棚を破砕せんばかりの勢いでゾンビが雪崩れ込んできた。タイミングを見計らってバールを振り込むリンシード。一般人並みの体力に落ちているとはいえ、相当の重量があるものを振り回すのだ、相手もただでは済まない。 ゾンビの頭が一つそげ落ち、ぐったりとうずくまる。だが後続のゾンビがリンシードの顔をつかみ、仰向けに押し倒した。 「早く……行って……」 この期に及んでもトーンの変わらない口調で、リンシードは言った。 教授の男は歯を食いしばると、ミリィを抱えたまま裏口へとかけだしたのだった。 「リンシードさん!? ちょっと待って、離っ、離してください! リンシードさん!」 悲鳴のように叫ぶミリィの声が、店の中へこだました。 ●カウントダウン 鎌ケ谷と名乗った教授はミリィを抱えたまま裏口から転がるように脱出した。 それを見つけた霧香たちも合流し、裏口に泊めていたワンボックスカーに乗り込んで街を脱出したのだった。 むろん、その際にリンシードが犠牲になったことを聞くことになる。 霧香はひどく落ち込み、宗一は彼女のフォローに戸惑い、悠里はどうしようもない憤りばかりをため込むことになった。 だがそれ以上に、ミリィへの精神ダメージが深刻だった。 「リンシードさん……私……私は……」 焦点の合わない目をして、時折指先を小刻みに震わせた。鎌ケ谷は過剰なストレス故の症状だと話したが、だからといって彼女をケアする方法まではわからなかった。 実際、どうしろというのだ。 目の前で人が死んだとして、『もっとできることがあったはずだ』と後悔するのは、仕方のないことではないか。 「ミリィちゃん……」 悠里にできるのは、彼女の頭をなでてやるくらいのことだ。慰めの言葉は沢山思い浮かんだが、どれも誰かを責めるような言葉ばかりで、結局彼に残ったのは憤りだけだった。 どんよりと沈む車内の空気。鎌ケ谷は強いて無感情に、もうすぐ目的地だと呟いた。 ゾンビをひとり、車で轢きながら。 車はビルの地下駐車場へと入っていった。 周りにゾンビがいないか警戒しつつ屋内へと滑り込む。 宗一は先頭を歩き、曲がり角を警戒しながら進む。 「ここはどこだ?」 「科学施設だ。国内でも特に規模の大きい企業で、医療や薬品に強い。屋上にはヘリがあって、私が来るまで停めておいてもらえる約束だ」 一方で悠里は最後尾をミリィとともに歩いていた。子供を守る名目なのか、怖がって最後尾についているだけなのか……その両方なのか。 「ヘリを!? 大丈夫なの?」 「お偉方と交友があってね。周りがこんなじゃ、最後に頼れるのは親しい友達だけさ。金も権力も使えやしない」 「そりゃあ、そうだろうけど……」 しかし丸腰で進むのはいささか不安だ。 屋内のどこにゾンビが潜んでいるかわからない以上、使えるものは何でも使っていきたい。 彼らはいくつかの部屋を物色しつつ、武器にできそうなものをいくつか持って行くことにした。 今回の場合リーチの短いナイフ類は使えない。銃は生憎手に入らなかったので、間をとって長くて堅い棒状のものを武器にすることにした。 ゴルフクラブや鉄パイプ、金属の二メートル定規などだ。 「これだけあれば、その場しのぎくらいはできるか……」 鉄パイプの持ち手にガムテープを巻き付け、握りを固定する宗一。 「いくぞ設楽……そんなところで何やってるんだ?」 「うん、今行く」 薬品の並んだ部屋で何かごそごそとやっていた悠里が小走りにやってくる。 すると、宗一や霧香たちが扉の前で固まっていた。 「階段は強化シャッターでふさがってる。確か会議室から回っていけたはずだが……」 「よりによって、ね……」 悠里は皆に習って扉の隙間から会議室をのぞいてみる。 のぞいてみて、後悔した。 「うわあ……」 かなり広めに作られた会議室には、大量のゾンビが詰まっていた。 生前の習慣でも残っているのだろうか。彼らは椅子にも座らずテーブルの周りをぐるぐると回っている。 小さくうなる鎌ケ谷。 「一気に抜ければ、あとは屋上まで突っ走るだけで済むんだが……」 「強行突破するしかないか」 「宗一君……」 心配そうにする霧香の手を、宗一は軽く握ってやった。 「大丈夫、霧香は何が何でも守るぜ。絶対一緒に帰ろうな」 「宗一君がいれば、怖くないよ。信じてるから……」 間近で見つめ合う二人。 「カルナさん今何してるかなあ……」 半眼で目をそらす悠里。 そして、未だ小さく震えるミリィに目をやった。 「ミリィちゃん、大丈夫? がんばろうね」 「はい……大丈夫、です。悠里さんも、気をつけて……」 青い唇でそんなことをいう。 大丈夫なわけがない。 「はは、ボクはお化けとか怖くって、腰が抜けちゃうかもね」 悠里は冗談めかしてそう言うと。 眼鏡の奥で、そっと、目を細めた。 ボクがやるしか、なさそうだ。 ●エスケープ 隊列は宗一、霧香、鎌ケ谷教授、ミリィ、悠里の順番になった。 即席で集めた武器でもって宗一と霧香が道をかき分け、鎌ケ谷がミリィを抱えて移動。最後は悠里が追いすがるゾンビを追い払うという役割分担だ。 当初は宗一、霧香、悠里が鎌ケ谷たちを囲む形で進む案があったのだが、悠里が『ゾンビにまっすぐ突っ込んでいくのは怖くって……』と弱々しく言うのでこんな配置になった。 この期に及んでまだゾンビを怖がるとは……とちょっぴり呆れた宗一だったが、いざ敵中で詰まったりしたら最悪だ。ここは素直にできないことを述べた悠里を立ててやるべきかと納得することにした。 「3カウントでいくぞ、いちにの……さんっ!」 宗一は扉を思い切り蹴飛ばしてゾンビたちを押しのけると、鉄パイプを大きく横にスイング。しかし『殴って倒す』ためではない。わずかにでも開いた隙間をさらに広げるために『掠って弾く』スイングだ。 「霧香!」 「大丈夫、行ける!」 霧香も金属製の定規を掲げ、相手の上半身を押しのける形で突撃を始めた。 流石に恋人同士というだけあって息はぴったりだ。二人の武器を矢の形にして、ちょうど矢印形になるようにゾンビの群れを突き進んでいく。 ミリィは恐慌状態寸前まで来ていたが、鎌ケ谷が抱えて二人の間を駆け抜けていく。 ゾンビが何人か追いすがろうとしてきたが、悠里がネイルハンマーを使って打ち払っていった。 「もう少しだ、ついてきてるか!?」 「なんとか……!」 相手がゾンビだとしても群衆を抜けるテクニックは万国共通、『押しのけて突きぬける』につきる。 多少力が強く手でも、全員が互いに腕を組み合って肉壁にでもなっていない限り、お互いが押し合うことで微妙に隙が生まれる。宗一と霧香はそんな隙をギリギリでついては進路を作っていった。 そうしてようやく、屋上への階段にたどり着いた。 たどり着いたが。 「……くそっ!」 宗一は思わず舌打ちした。 上へ向かう階段にゾンビが数人転がっているのだ。宗一と霧香だけなら一気に駆け抜けることができるかもしれない。しかしミリィを抱えた鎌ケ谷は無理だろう。そうなると悠里も詰まることになる。もたもたしていたら会議室側からのゾンビに追いつかれることになってしまう。 「…………う」 ミリィは震える唇を開いて言った。 「私を置いていってください。そうすれば」 「それはちょっと、イヤかなあ」 鎌ケ谷の腕を逃れようとしたミリィの手に、悠里はそっと手を添えた。 首を振って、自分の唇に指を立てる。 「行って」 「悠里、さん……?」 「あ、ごめん。言い方間違えた」 悠里は照れくさそうに笑うと、きびすを返しながら言った。 「ここは任せて先に行け」 言ったきり、悠里は会議室へと舞い戻り、これ幸いと群がるゾンビたちへと笑いかけた。 「備えあれば憂いなし……か、はは」 扉に背中をあてる。 そして彼は、ジャケットのボタンを飛ばす勢いで胸元を開いて見せた。 懐にぎっしりと詰められた、即席の科学爆弾を晒して。 電池式の即席起爆バサミを握りこんだ。 「来いよお化け、めちゃくちゃ怖いけどさ……いや、怖いからさ」 紫電が走り。 笑う。 「一緒に逝こうぜ」 激しい爆発音とともにドアがひしゃげた。 強い揺れがおこり、鎌ケ谷が転倒。ミリィが地面に転がった。 そのせいで扉が引っかかり、すぐには開かなくなる。 「…………っ!?」 驚いて振り返る霧香。 宗一は先刻よりもさらに大きな舌打ちをして、通路上のゾンビを殴り倒した。 ミリィが声を上げる。 「悠里さん! 悠里さん、何をしたんですか!? いま、いま……!」 「早く行け」 感情を押し殺した声で言って、ミリィの手を引く宗一。 「でもっ」 「悠里の犠牲を無駄にするな」 「……!」 「ま、待ってくれ!」 慌てて最後尾を追いかけてくる鎌ケ谷。 宗一はミリィと霧香の手をつかんだまま、強く強く歯を食いしばった。 「馬鹿野郎……!」 ●ラストショット 階段を駆け上がり、屋上フロアへ続く扉を蹴り開ける。 「ゾンビはいないか!?」 「大丈夫……!」 ミリィを引っ張るようにして、宗一と霧香はコンクリート敷きの屋上へ転がり出た。 ヘリポートマークの上には発進準備を整えたヘリが停まっている。 「鎌ケ谷さんが来たぞ! 早くこっちへ!」 「はぁ、はぁ、やった……!」 荒い息をしながら屋上へ上がってくる鎌ケ谷。後ろ手に扉を閉めた。 ヘルメットとサングラスをした男たちが駆け寄ってくる。 「あなたが宗一さんですね。その子は?」 「だいぶ弱ってる、丁重に扱ってくれ」 男にミリィを預け、安堵の息をつく宗一。 毛布にくるまれ、運ばれるミリィ。 その中で、ミリィはふと考えた。 『あなたが宗一さんですね』と、彼は言った。 なぜ分かった? 髪の色も年も背丈も悠里と同じだ。なぜ断定できた? 眼鏡の有無か? だがこの緊急時、一目しただけの顔と名前がなぜ一致した? 「そ……宗一さん、離れて!」 叫んだ途端、ミリィは鈍器のようなもので殴られた。地面にたたき落とされる。 起き上がろうとするが手足がしびれて動けない。スタンロッドのたぐいだろうか。 「トムソン!?」 鉄パイプを振り上げようとする宗一だが、その腕を銃弾が貫通した。 銃弾である。 武器といえば鉄パイプか定規くらいしかなかったこの場に。 しかも射撃手の方向は後ろ。つまり……。 「鎌ケ谷……教授……?」 腕を押さえてうずくまる宗一をかばうように、霧香は立ちふさがった。 拳銃を構えて立つ、鎌ケ谷との間にだ。 「そうだ、僕は鎌ケ谷という。ただ、ごめん。教授っていうのは嘘だ」 「嘘……って……」 「この製薬会社の研究員だよ。雀田教授が生み出したウィルスは明らかにこの世のものではなかった。僕は『この世ならざるもの』の存在を知った。それを呼び出す方法もね」 「てめぇ……!」 体を起こそうとする宗一だが、後ろの男に注射を打ち込まれた。睡眠薬だろうか。意識が遠のく。 残った霧香も二人がかりで拘束され、見たこともないフォルムの手錠をかけらてた。 「まさか人間が出てくるとは思わなかったが、これも貴重な収穫だ。人類の未来のために微塵切りになってくれ。とりあえず全身の断面図をとりたいから……宗一くん? まず君を刻んで、ミリィくんは博識みたいだから、『そっちの世界』にある知識を絞り出させてもらう。薬品ならいくらでも都合できるから、苦しませたりしないよ、大丈夫大丈夫」 「あなたは、最初からこうするつもりだったんですか……」 「あわよくばって感じかな。リンシードくんと悠里くん? 彼らが抜けちゃったのは残念だったけど、ね」 今にも噛みつきそうな顔で睨む霧香の顎を掴み、鎌ケ谷は顔を近づけた。 「あ、でも君は結構気に入ったかな、美人だし。世界間ハーフの子供とか、産んでみたくない?」 「……ッ!」 顔に唾を吐きかける。直後に頬を思い切り殴られた。 「もういいよ、連れてって。あとは施設でゆっくりやるから」 霧香とミリィがヘリへ運び込まれていく。 その様子を見つめるしかなかった宗一は歯を食いしばった。 前進に力が入らない。 それでも動かなければならない。 こんな終わり方は、許されてはならない。 「動け、うご、け、俺の……!」 「無駄だって」 鎌ケ谷が宗一の前に立ち頭を蹴飛ば……そうとした、その時。 「備えあれば憂いなし」 ライフル弾が鎌ケ谷の胸を貫通した。 目を見開き、崩れ落ちる鎌ケ谷。 「な……誰……が……」 「忘れましたか……私の声を?」 扉を開き、屋上へと現われる少女の姿。 前進を血まみれにしてぼろぼろだったが、背の高い男に支えられ、二人で協力してライフルを構えていた。 誰あろう。 「悠里さんに……リンシードちゃん!」 「ごめん、生きてた」 はにかんで笑う悠里。 宗一は自分の指をへし折って意識を無理矢理覚醒させると、鎌ケ谷の銃を拾い上げて発砲。霧香を拘束していた男の頭を吹っ飛ばした。 そのままヘリに飛び込み、操縦者の後頭部へ銃口を突きつける。 「おい、このタクシー……初乗りいくらだ?」 ●エンドロール 県境に敷かれた隔壁が眼下に見える。 揺れる座席に身を納め、リンシードとミリィは肩を寄せ合っていた。 「リンシードさん、無事だったんですね。でも、なんで……」 「神秘の力が使えないので忘れてたんですが……私たち、フェイトがあったので」 「あ……」 視線をやると、悠里が咳払いした。 「あの時は必死で気づかなかったんだ、ごめん……」 「しかしどうしましょう、アテにしていたコネクションがつぶれちゃいましたけど」 「そうだね、ほかの手段っていったら……」 「人質とってねじ込みましょう」 頭を巡らせていた霧香はリンシードに目をやった。 同じくリンシードに注目する悠里とミリィ。操縦者に銃口を向けたまま振り向く宗一。 「「それだ」」 後日談というほどではないが。 彼らは都内にいるという技術者を見つけ出し、唯一の家族だというチワワに銃口を突きつけてホールを開かせることに成功した。 そしてゲートを通り、こちら側へと帰ってきた……と、言っていいのだろうか。 なぜなら、ゲートに足を踏み入れた次の時には、彼らは自室の布団で目を覚ましたのだから。 今までのことが夢だったのか。 それとも異世界での冒険だったのか。 それは、わからぬことだ。 ただ一つ確かなことがあるとするならば……。 彼らの絆がほんの少し、強くなったことだろう。 |