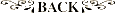●×××××××××のそれはそれは気紛れな発言●

|
● 地獄とは、なんだろうか。それはつまるところ、かくも恐ろしいものである。罪人を閉じ込め、その根源から擦り切れるまで罰に処すというのだから、きっと。想像も出来ないほどに恐ろしいのだろう。だって、それでも。人間は罪を犯すことをやめないのだから。どれだけ恐ろしいのか想像もできないから、想像できるものでしか無いと思うから。人は罪を犯すことをやめないのだろう。誠実に生きることとの天秤にかけてしまうのだろう。ローリスク・ハイリターン。実のところ、その真逆。だからそれはとても深く、不可解で。不快で不可思議なものなのだろう。 嗚呼、わかっている。反論しなくてもわかっている。こんなものは戯言だ。ひとつの前提を立てた上での言葉遊びでしかない。つまるところ荒唐無稽で、人類進化にも思想確立にも役だってはいない。ただのごっこ。御為ごかしに過ぎないものだ。無論、だからこそああだこうだと並びまくしたてられるというものなのだが。反論にそのとおりとニタニタ笑う。これほどの愉悦は他にあるまい。否、あるか。どうだろう。どうでもいいか。くつくつと笑い、けらけらと笑う。その有様を知ってか知らずか、彼女はそれに話しかけ、彼女はそれを承ったのだ。 「ごきげんよう。気分は如何?」 「見ての通り、最低よ。嗚呼でも、最高でもあるのかしら。どちらでもないのかしら。いいえ、どうでもいいわ」 「貴女は―――いえ、誰でも良いわ」 「そんな冷たいこと言わないで。私を見てよ。ひとくくりにしないで。人間だって寂しくて死んじゃうのよ?」 ころころと、よく喋るものだ。その上で、ひどくちぐはぐな。目的のないルーブ・ゴールドバーグ・マシンでも見せつけられてでもいるかのような、酷い空虚さを覚える。錯覚だと決めつけてしまおうか。否。否。これが彼女だ。これが彼女らだ。わかっていたはずだろう。わからないことなどとっくのとうにわかっていたはずだろう。それでもだ。それでもここに来たのだ。それを掴みたいから、ここに来たのだ。 「貴女は殺人鬼? それとも少女?」 「二択の質問としては酷く乱雑ね。でも答えてあげる。答えたげるわ。人はいつまでも殺人鬼でなんていられないものよ。あら、少女だったかしら」 答えていない。否、彼女からしてみれば答えたつもりだったのかもしれない。思考の堂々巡りに行き尽きかけて、息疲れて、逝き憑かれて。れて。首を振る。振った。けむにまかれるな。思考ルーチンが違う相手だ。共感も理解も同調も不可能だと自分に何度も言い聞かせたではないか。 分からないもの。分からないものだ。自分達とはまるで違うものだ。違う生き物なのだと断定してもさして異ならないものだ。だからこそ、だからこそ欲しい。それ故にか逆説か、革醒者としても類稀なる極質を組み上げた彼女らの特異性が。欲しい。欲しい。その為に観察する。この、種族『殺人鬼』を観察する。その為にここに居るのだ。目的を忘れてはならない。 「貴女の家族は今如何しているの? 聞かせて頂戴」 「家族。家族。うん、良い質問ね。どうでもいい質問なのかしら。そうね、お父さんは山へ芝刈りに。お母さんは川へ洗濯に。嘘よ、怒らないで。私は桃からなんて生まれてないわ。本当はね、ただのサラリーマンと専業主婦。どこにでもあるでしょう? つまらないでしょう? 今日もあくせく日常を繰り返しているわ」 普通。解答への緒はここではなかったかと思考をシフトしようとした瞬間、彼女は「これも嘘。昨日死んだわ。一昨日だったかも。ずっと前かも知れないわ」と付け足した。 からかわれているのだろうか。そうも思ったが、少しだけ引っかかる。彼女は殺人鬼だ。それなのに、今は『殺した』ではなく『死んだ』と発言していた。その差異を掴もうとして、それも諦めた。やめておこう。推測は無意味だ。こうであるのだと、想像してはならない。仮定してはならない。幻想づけてはいけない。 「そう、それで貴女が先生に出会ったのは何歳の時?」 「先生。先生ね。どの先生かしら。わからないわね。わかる気もするけれど、同じことよね。ええと、そうね。きっと、ずっと一緒なのよ。生まれた時から、今まで。これまで。ここまで」 ずっと、一緒。生まれた時からというのは、殺人鬼として生まれた時からという意味だろうか。そうだとすれば、ひとつの結論に光が見えてくる。 つまるところ、彼女らは種族『殺人鬼』である。それを、それこそ、精神的なもの、思想的なもの、哲学的なものではなく。物理的に、最早『人間』ではなくなってしまっている。それが正しいのであれば、彼女たちを変容させた『先生』という存在。それは、このボトムではなくもっと上位に位置する何かなのかもしれない。 そこまで考えて、もう一度振り払った。これも、結局は仮定に基づいたものだ。それは意味が無い。確固たる物証はなく、精神のトレースは不可能であり、それらを再計算する材料は失われている。 いっそ、拘束、拘留などではなく、解体できれば良かったものを。皮一枚から骨の髄まで余すところなく、ばらばらのばらばらにできてしまえば良かったものを。 そう考えて、そう巡らせることは、意地の悪い愉悦を生んだ。本当にこの場へ残っているわけではない彼女に向けても意味のないものだが。それでも、思わず零れたそのものを悪意として笑いかけていた。 「ふふっ、残念ね。貴女達はとても興味深い存在なのに」 「嗚呼、怖い。恐ろしいことを言うのね。まるで人間みたい。いいえ、殺人鬼みたいなのかしら。ねえあなた、なってみない? 殺人鬼。そうよ。ねえ、そうだわ。少女は殺人鬼であるべきだもの」 何度か耳にしたフレーズ。少女は殺人鬼であるべきだ。彼女らの共通思考。そのままの意味のようで、まるで別義でもあるようで。分からない。嗚呼いっそ、彼女の言うとおり。本当に殺人鬼に生ってしまえば分かるのだろうか。その時、自分が今の自分である保障はないのだけれど。嗚呼。 「なんて、ねえ。あはは。少女は殺人鬼であるべきだ。あの時もそう言ったわ。皆、面白いくらい同感しちゃって、ねえ。おかしいったらないわ。あなたもそう思うでしょう?」 「――――――え?」 一瞬、思考が凍りついた。ふたつのフレーズが脳内で木霊する。「あの時もそう言った」「皆、同感して」。 何だ、何を言っている。そんなことは不可能だ。誰に言い聞かせ、誰が同感したというのだ。混乱しても、少女の言葉は止まらない。 「ええ、そうね。少女は殺人鬼なのよ。殺人鬼が少女なのかしら。同じことよね。同じ事だわ。皆簡単に信じちゃって。あはは、思春期よねえ」 止まらない。彼女の言葉が止まらない。流れでて溢れでて止められない。留まらない。堰を切って零れ出すそれらを脳が受け止めていられない。 実際のところ、彼女の言う半分も理解できなかった。彼女なりに言えば、何も理解できなかったのかもしれない。同じ事なのだ。きっと、生れないというのなら同じ事なのだ。 時間がない。終わりが近づいて来ていた。それでも、あとひとつ。あとひとつだけ、何よりも優先して尋ねなければならない。 声が震えている。それがどんな心境から来るものか、自分では分からなかった。 「貴女は―――誰?」 「 」 了。 |