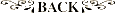●ある高校教師の本音●

| ● 腕時計を見ると、既に日が変わっていた。 仕事は、まだまだ終わりそうにない。腹を括り、『どうしようもない男』奥地 数史(nBNE000224)は小休止しようと席を立つ。 どうせ長丁場になるなら、このあたりで気分転換しておこう。 そう思って訪れた休憩室には、既に先客の姿があった。 「ぁ゛ー……働きたくない」 ぼやく『自堕落教師』ソラ・ヴァイスハイト(BNE000329)の前には、答案用紙の束。赤ペンを手にしているところを見ると、どうやらテストの採点中であるらしい。 外見上は小学生そのものの彼女が、三高平学園で教鞭を執る高校教師であるという事実を数史が思い出した時、ソラが顔を上げた。 「そこのあんた……えっと、奥地だっけ? 暇そうね」 いや俺もまだ仕事中なんだけど、と答える間もなく、さらに声がかかる。 「話し相手になりなさい。このままだと寝ちゃいそうなのよ」 ――拒否権は無しですか、そうですか。 まあ、深夜に一人で仕事と向かい合う辛さは分かる。割とリアルタイムで。 「俺で良ければ」 ここに居合わせたのも何かの縁だろうと、数史が席につこうとした時。 「まずはちょっと缶ビール買ってきて」 「……はい?」 休憩のつもりが、のっけから使い走りである。 そもそも、このタイミングで酒なんて飲んで採点を誤ったりしないのだろうか。 色々な意味で突っ込みたくはなるが、数史に断れる筈もない。 かくて、彼は缶ビールを買いに行く羽目に陥ったのだった。 ● 「500ml缶で良かったかな」 「ありがと」 ソラに缶ビールを手渡した後、数史は向かい側の席に座って自分の缶を開けた。 普段は禁酒している身だが、話し相手になることを望まれている以上、自分だけ素面というのも失礼だろう。 後に控えている残りの仕事については、今は考えないことにする。幸い、酒には強い方だ。たかだか500mlのビールで影響が出ることはまず無い。 ちなみに、缶ビールの代金はソラへの労いを込めて自腹である。 「……でも、何でここでテストの採点なんてやってるんだ?」 ソラの様子を見れば、彼女がアークの依頼を終えて帰って来たばかりなのは予想がつく。 そこまでは分かるのだが、わざわざ本部に居残らずとも、学校なり自宅なり、もっと仕事に適した場所があるのではなかろうか。 「今から学校とかダルいし。家に帰ったらそのまま寝る自信があるわ」 ビール片手に赤ペンを走らせるソラの言葉に、数史はなるほどと納得した。 「先生も大変だな」 「本当は仕事なんてしないで寝ていたいのよ! アークの仕事含めて!」 苛立たしげに声のトーンを上げるソラだが、その手はまったくと言っていいほど止まらない。 心なしか、酒が入ってからスピードが上がっていないだろうか。 すらすらと淀みなく、時にはダブルアクションを交えて採点を進める彼女を暫し眺めた後、数史は遠慮がちに口を開く。 「一つ、訊いてもいいかな」 「何?」 「教職とアークの兼業って、楽じゃないだろ。 フォーチュナにも何人かいるけど、実際に戦いに出るとなるとまた違うだろうし」 「そうね」 「だから、その……どうして戦ってるのかなって」 当たり前のように、ソラは即答した。 「だって嫌じゃない。気がついたら生徒の席が減ってるとか」 その言葉に、数史は思わず目を伏せる。 自分がアークに来てから、まだ一年も経っていない。 にもかかわらず、既に見知った顔が何人も欠けているという現実がある。 ある日突然、教室の片隅で永遠に空いてしまった席。 教壇に立つ彼女がそれを目の当たりにした時、果たして何を思うのか。 心中は、想像するに余りある。 「私の力で生徒達の負担をちょっとでも減らせるなら、やるしかないじゃない」 リベリスタの任務は、常に死と隣り合わせだ。命を落とすまでには至らなくても、深い傷を負った痛々しい姿のままで授業を受ける生徒も、決して少なくはないだろう。 「成績が悪くてもいい。態度が悪くたっていい。無事に帰ってきてくれれば、それでいいのよ」 ハイペースで手を動かし続けるソラの幼い顔は、すっかり『先生』の表情になっていた。 「……いい先生だ」 数史の呟きに、彼女は「もちろん、生徒たち以外だってそうよ」と答える。 知り合いが傷つく姿なんて見たくないの――。 そう言ったソラの気持ちは、常にリベリスタ達を送り出す側に立つ数史にも痛いほど理解できた。 返答に詰まる彼の前で、ソラは赤ペンをテーブルに置く。 「なーんてね……さて採点終了!」 いつの間に飲み干したのか、ビールの缶はもう空になっているようだった。 お酒の勢いで変なこと喋っちゃったわね、と言いつつ、ソラは答案用紙を両手で揃える。 「オフレコよ! オフレコ! 誰かに喋ったら命はないと思いなさい」 念を押す彼女に、数史は一も二もなく黙って頷いた。 どうしてこう、リベリスタに命を狙われたり脅されたりするんだろうと思わなくもないが、それをここで考えても仕方がない。 「ありがとね、付き合ってくれて」 「遅くまでお疲れさん。帰り気をつけてな」 席を立ったソラに手を上げつつ、声を返す。 目の前でくるりと踵を返した小さな背中が、ふと止まった。 「あ、そうだ」 何かを思い出したように言って、答案用紙の束から一枚を選んで抜き出す。 ソラはテーブルに向き直ってそれを置くと、再び赤ペンを取った。 採点漏れでもあったのだろうかと、何気なくその様子を眺めていた数史の目が、驚愕に見開かれる。 これでよし、と休憩室を後にする彼女を、黒髪黒翼のフォーチュナはただ呆然と見送るしかなかった。 ● ソラが去った後、数史はすっかり温くなったビールを一息に飲み干した。 「……あれ、皆の前で返すのかなあ」 缶を潰しながら呟いた後、はっとして周囲を見回す。大丈夫、誰もいない。 さっき目にしたものは全力で見なかったことにしようと、彼は固く心に誓った。 三高平学園高等部に通う、とあるリベリスタの答案用紙。 氏名欄に書かれた苗字と名前の間に、赤ペンではっきりと『ハーレム』と書き足されていただなんて。 ――絶対に、見ていませんから。 |