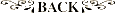●おてつだい●

|
● かしゃ。 「次」 かしゃ。 「次」 縦のものを横にもしない『スキン・コレクター』曽田 七緒(nBNE000201)も、真面目な顔をする。 本業に精を出している時だ。 影ができないように調整された照明設備の下、小さな手が、被写体を取っ替え引っ変えしていく。 『もぞもそ』荒苦那・まお(BNE003202)は、初めての写真スタジオの雰囲気に飲まれて、おっかなびっくり手を動かしている。 アーク本部内、撮影室。 天井も壁も境目のない平面的な白に見える。 影のない空間。 「次」 パソコンと被写体を交互に見定めている七緒の横顔をチラと伺った。 話は、十数分前のことだ。 「まおちゃん! みんなびっくりするから、人のいるところでは床を歩きなさいっ!」 アーク本部内、中央通路。 まおの目には、逆さまの制服のお姉さんが腰に手を当てて、まおを見……見上げているのだろうか、見下ろしているのだろうか、とにかく、まおを見ている。 が、まおの意識はそこから10m先に釘付けだ。 その声を聞きつけたのかどうか、まおには分からないが、真っ白な肌をした七緒が、床にへたり込んでいる。 「うええ。くさぁ! かぼちゃくさっ! 気持ち悪いぃ。換気扇止まってんじゃないのぉ」 なんとなく天井に届く、かぼちゃの甘い匂い。 飴菓子の匂いだ。 まおは、恐る恐るちかづいた。 ぺとぺとと天井から壁を伝っていく。 顔にかかる影の動きに、うぐぁと呻く七緒の目線が上がる。 少女ミーツ喪女。 七緒は、まおを見上げて、にったぁ~っと笑った。 「荒苦那ぁ」 幼女でも、苗字呼び捨て。 そんな七緒クオリティ。 「おねーさんの説教とぉ、あたしの手伝い、どっちがいぃい~?」 白い指が、反射的に天井にかけ上がろうとしていたまおの足首を掴んだ。 「仕事のためだから、拉致るかぁ」 「曽田さん、めっ」と、お姉さんに叱られる七緒が、小声でまおに「たすけて」と呟いた。 割と必死に見えたので、まおはおとなしく頷いた。 実際、七緒は、途方にくれていた。 先々月のハロウィンでばらまかれたパンプキンヌガー。 今年のアークは総出で頑張った。 バイデン戦で疲れたリベリスタの顎を酷使させるわけには行かない。 で、一般職員含め一生懸命食べたあとの包み紙。 なんか、これ、パズルになってない? それに気がついたアーク職員たちは、顔を青くしたのだ。 あいつらなら、こういうしょうもないものに重大ヒントを忍ばせるくらいの嫌がらせはする。 で。 アーク中のゴミ箱があさられ、回収された包み紙を映像データにする仕事が回ってきたのだ。 よかったね、飴の「皮」だよ、七緒ちゃん! これから、この紙のシワを伸ばして、いつ尽きるともない撮影作業が始まるお。 でも、せめてこれ、セットしてくれる人手が欲しいなぁ。 そんな時、廊下から声が聞こえたのだ。 渡りに船だった。 ● まおにとって、七緒は知らないお姉さんではない。 今年の晩夏、一緒に線香花火を何百本とした仕事仲間だ。 七緒にとっても、線香花火の映像に目を丸くしていたまおは記憶に新しい。 パンプキンヌガーの残り香の中、黙々と作業は進む。 飴の包み紙がすべて撮影済みのファイルに貼られたところで、七緒はようやく「お疲れさん」 と言葉を発した。 「荒苦那の頭は、きれいだねぇ」 本業では、タトゥーをモチーフにすることが多い七緒にとって、真央のスキンヘッドに咲く赤いバラは好ましいものだ。 「これは頂いた花なのであげられません」 まおは、自分の頭を抱えるような仕草を見せる。 さすがの七緒もいきなりピーラー振り回したりはしない。 「そっかぁ」 「はい」 髪飾りです。と、微笑む少女に、七緒は余計なことを言う口を持たない。 七緒もクリミナルスタアの端くれである。 暴力と神秘と犯罪がどのように組み合わされ、目の前の少女にもたらされたのか、手に取るようにわかる。 それは、大人の都合いいように、綺麗に包装され、リボンをかけられ、無知な子供が喜ぶように歪曲されたに違いない。 珍しいことではない。 神秘界隈ではよくあることだ。 「じゃあ、写真撮るだけで我慢しようかなぁ」 「それは大丈夫ですよ」 いつか。 真実に自分でたどり着く年頃になる。 そのとき、どれだけの衝撃がまおを襲うか。 穢れ無き子供の時間はそれほど長くはない。 その時、まおは、この笑顔を浮かべられるだろうか。 七緒は、善人とは言えない。 自分のためなら、多少の無理は通してきた。 それゆえのクリミナルスタアだ。 それでも、いまは。 祈るような気持ちで、シャッターを切っていた。 蜘蛛の子よ。 外の嵐に負けぬよう。 方舟に、強固な巣をかけるがいい。 |