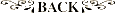●自然のままに●

|
● 戦って戦って戦って。 アークに来てからの日々はそれなりに楽しいけど、戦うことが多い。 「報われる事が無くても、それが誰かの為に。笑顔に繋がるなら嬉しいよな」 その言葉が戦う原動力。誰かのために。笑顔のために。 戦うことは怖い。 でも、それが誰かの笑顔に繋がるのなら、怖くても戦おう。それが自分だ。 ミリィ・トムソン(BNE003772)は戦う。誰かの為に、笑顔のために。 戦うことに関する怯えを必死で押さえ込みながら、戦場を奏でる。 ● 三高平湖から海に流れる川沿いに、一軒の店がある。海鮮料理を作る店で、三高平市にある店よろしくリベリスタへの理解も深い。店の名前は『あゆかわ』。店主の名前がそのまま店の名前になっていた。 依頼から帰ってきたリベリスタが労いのために食事会をする時に利用されることもあり、リベリスタが馴染みの店の一つとして認識する場所でもある。 ミリィはこの店の存在を知っていたが、お酒が出ることもあり店の前を通り過ぎるだけだった。日本料理に興味がないわけではないが、スシはそれ専用の店で頼むし、鍋を囲むときは店ではなく友達の家で囲む。 自分には縁のない店だと認識していたのだが、 「どうした? 入らないのか?」 「はぁ……」 ミリィは縁のないと思っていた店の暖簾を前に、足を止めていた。 店の窓から突き出るように作られたベランダ。その真下に流れる川。一定の音を奏でるように流れる川は、涼を与えると同時に心を清らかにする。 川床っていうんだぜ、と教えてくれたのは九条・徹(nBNE000200)という同じアークのリベリスタ。 会話したこともそう多くない。ミリィがアークにはいったときには既に仁蝮会との抗争は終わったあとである。ホタル狩りに誘われたことはあるが、正直同じリベリスタでも住む世界が違うのでは、と自分でも思うことがある。 (私、何故ここにいるんでしょうか……?) そんな疑問符を浮かべながら、ミリィは店の暖簾をくぐった。 ● 河川法という法律がある。その中に川床に関する法律もある。 大雑把に言えば『川の上に建物作るのは危ないから禁止でぷー』というものだが、近年規制が緩和され、相応の手続きを行なえばいいですよ、となった。『あゆかわ』もその手続きを行い、許可を得た店なのだ。 ……とまぁ、事前にミリィが調べた知識はそういうものだった。後は川床の写真やそれを楽しんだ人のブログとか。事前知識は完璧と思っていたのだが。 「わぁ……」 実際にその場に来て見れば、その光景は圧巻である。 頬をなでる風は川の水で冷やされているのか、ひんやりとして心地よい。目の前を流れる川は夕日を反射して淡く輝いていた。 目を閉じる。河の流れる音が確かに聞こえる。ざぁざぁと流れる川の音は、イメージだけでも涼しさを感じる。木々がこすれあいはがさわさわとなる音が、さらに納涼感を増していた。 運ばれた料理も魚を中心とした料理で、見た目からして食べる前から一流の料理人が作ったことを思わせる。器も料理の為に作られたのだろう。プラスチックではなく、陶器が中心だ。 「エアコンのような直接的な冷気じゃなく、五感全てで感じる自然のままの納涼だ。気に入ったか?」 「――綺麗」 それ以外の言葉が思い浮かばない。 「そういうミリィも綺麗じゃねーか」 「徹さんが普段から着ている物に合わせてみたのですが、ど……どうでしょうか? 似合っていると良いのですが……」 徹は、ミリィの格好を眺めて賞賛の言葉を送った。薄紅色の着物は金髪のミリィによく似合っている。 「ああ、良く似合ってるぜ。立てば芍薬座れば牡丹、だな」 はにかむようなミリィの言葉に、徹は笑って言葉を返す。その言葉にミリィも微笑みを返した。くるり、と回転し薄紅色の絹がふわりと舞う。さながら花びら。色も、動きも、その美しさも。 「じゃあ、頂くとするか。魚料理は鮮度が命だぜ」 「はい。いただきます」 二人は川の風景を楽しみながら、運ばれてきた料理を口にする。貝のお吸い物、魚のや山菜の天ぷら、刺身に茶碗蒸し。そして美味しいご飯。 舌鼓を打つ、というのは美味しい時に思わず言葉がでることだが、まさか本当にそれを実践するとは思わなかった。 ミリィと徹は作られた舞台の上で、深く自然を感じていた。 ● 話題は料理のことからアーク内の話題に流れ、そしてミリィの話になった。 「で、最近はどうだ?」 「どう、とは?」 「やっぱりまだ戦うのは怖いか?」 あ、と言葉を詰まらせてミリィの箸が止まる。 怖くないです、と即答できない自分が恨めしかった。戦いを怖がる自分は、まだリベリスタとしては未熟なのかと攻められている気分になり―― 「そうか、怖いか。ならよかった」 そんな気分は徹の一言であっさり霧散した。よかった? 「え? あの、私は……」 「怖いんだろう。エリューションやフィクサードと戦うのが」 「……はい。怖いです」 それは事実だ。ミリィはまだ戦いに関する恐怖が抜けきっていない。戦場に立てるのは、共に戦う仲間がいるからだ。一人で戦うことなんで、怖くてできない。 それをこの男は『よかった』という。 「あの、なにがいいんですか? 戦いが怖くて、逃げ出しそうになるのが」 「怖いのに『怖くない』って虚勢を張られるよりはずっといいさ。こと、戦場を注視してコントロールするレイザータクトならなおさらだ。 圧倒的な暴力と、指示を出し間違えれば仲間が危険に陥る。その危険に怯えてるんだろう?」 意外に思われるかもしれないが、徹の戦闘スタイルは『前で殴りながらの戦闘指揮』である。前後ろの違いこそあるが、戦場を指揮するレイザータクトの気持ちがわからないでもない。 「指揮者が強気になって冷静さを失う事態こそ、避けるべきだ。怯えながら震えながら、それでも仲間のことを想い勇気を出して戦場を奏でるミリィは、すごいと思うぜ。 その怯えはミリィの助けになるぜ。俺が保障する」 ああ、そうか。 この人はこれをいう為にわざわざ川床に私を誘ったのだ。自然の美しさと素晴らしさを感じさせることで、自然体の自分でいろと遠まわしに告げたかったのか。 戦いに怯えることを受け入れて、その上で戦えと。恐怖を無理に押さえ込むのではなく、それを受け入れてなお自分自身を失うことないようにと。 ミリィはわきあがる感情を現すように、徹の徳利をもって彼の御猪口に酒を注いだ。 「私が大きくなって、徹さんと同じようにお酒を飲めるようになったのなら、こうしてまた、一緒にお出かけして貰えますか?」 「嬉しいねぇ。大歓迎だ」 数年先のデートの誘いを受けるように、徹は注がれた酒に口をつけた。 ● ミリィ・トムソンは戦う。誰かの為に、笑顔のために。 戦うことに関する怯えを胸に、声高らかに鬨の声を上げる。 「さぁ、戦場を奏でましょう」 |