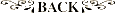●おゆはん。●

| ● 地上を苛烈に照りつけていた太陽はなりを潜め、繁華街の片隅に蝉の声は届かない。そんな夏の終わり。夕刻過ぎの出来事。 「取っておきのお店って言われてたけれど、ここ……で、いいのよね?」 黒塗りの車を降りた少女――斬風 糾華(BNE000390)は、同じく降りようとするエスターテ・ダ・レオンフォルテ(nBNE000218)の手を取り眉を潜める。 「……はい」 繁華街の路地、奥へと視線を走らせれば怪しげな看板さえ目に付く。こんな場所は可憐すぎる二人の少女には余りに似つかわしくないように思えた。 「でも、私達で天ぷら屋さん……」 どう見ても大人の空間であるからして、少女二人には敷居が高い。価格的にも雰囲気も、駅前のファーストフードのほうが馴染み深いのは双方にとって同じである。 「いえ、良いわ。貴女のチョイスを信じる、いきましょ」 平仮名で『わかもと』と書かれた緑の看板。鈴の声に気後れを隠していないこともないのだが、いいお店だと言うのだから覚悟は決めた。 糾華とエスターテはそれほど親しいわけではなく、嫌い合う仲でもない。 二人は同じ年齢だが、学年は一つ違う。どちらもそれほど社交的な性質ではないから、単に言葉を交わしたことが少なかった。だから馬が合う合わないという以前の状態だったのだ。 糾華がエスターテを誘ったのは、エスターテが一押しする店に興味がなかったわけではないのだが、仲良くなる切欠を掴みたかったのである。 二人は依頼を渡す側と、渡される側という向かい合う関係ではあるのだが、アークでは何度も顔を合わせている。双方に信頼があることは、互いに伝わっていたから―― 重い扉を潜り抜ければ僅かに照明を落とした店内に、小さなジャズの音が聴こえる。外の世界との隔絶。清潔で落ち着いたL字のカウンターテーブルには若い女性客の姿も見えた。なるほどそういう場所らしい。 二人の少女がどこか所在なさげに席に着く。対面席があっても良かったが、予約出来たのはL字の角席との事だった。小さな店であれば致し方ないことでもある。 「こういうお店、初めてなのよね」 リードしていた糾華だが、どこか不安げでもある。きょろきょろと辺りを見回すエスターテに気がついたのか、店員がゆったりとした足取りと近づいてきた。 「こちらメニューになります。お先にお飲み物をお伺い致しましょうか?」 店員が愛想良く、されど静かに語りかけてくる。純白のエプロンには油の臭い一つしない。硬すぎず優しげな様子が心を落ち着ける。 二人が頼んだのは『おまかせ』コース。旬の食材を一品一品棒揚げと呼ばれる手法で揚げてある。衣は薄く、あくまで素材の旨みを引き出す為の調理法である。 期待をそそる小鉢の中身。一品目はぱりぱりの苦瓜と甘み際立つミニトマトの和え物。ほろ苦い大人の味わいは少女達の舌にどんな思い出を残したろうか。 小さな透き通ったゼリーの箱庭に浮かぶ野菜や魚介を、糾華は興味深げにつつく。見た目にも涼しげで、どこか儚げに美しいから、なんだか似合っている。 ゼリー寄せに気を取られて三品目は聞き逃してしまったが、ソースの中にレンコンのような歯ごたえがするものは何だったのだろう。 だけど気にすることはなかった。それは少女達がこれから知って行けば良いことなのかもしれないから―― ● サラダをつまみ終え、才巻海老の頭揚げを前に糾華が静寂を破る。 「今更ながら、改めて自己紹介」 クールな面持ちに、ほんの僅かにはにかんだ笑顔を隠して。これまで互いに読んでいたのは資料。直接の会話は仕事の話ばかりだったから。 「はい」 「斬風糾華、13歳。中二よ。ふふ、何歳だと思ってた?」 「一つ、上なのかなと。あ。エスターテ・ダ・レオンフォルテ、です」 ぺこりと頭を下げようとして、エスターテのひじが湯飲みに当たる。少々あわてた様子だが、幸い倒れていない。 「えっと、見ての通りのジーニアスのナイトクリーク。ヴァンパイアによく勘違いされるのよね。何故かしら?」 「え、と。白い、から?」 糾華が微笑む。 「こちら車海老です」 小ぶりのこいつを才巻海老と呼ぶらしい。 「ふふ、おいしい」 海老を口に含めばぷりぷりと甘みが舌に広がる。食感はレアに近いが熱はしっかりと通って熱々だ。絶妙な揚げ加減である。 「こちらイカを大葉で包んで揚げてあります」 柔らかな歯ごたえと旨み、大葉の爽やかな香が舌を包み込む。横に並べられたインゲンは新鮮でコリコリと美味しい。 一息つけば、ほんのりとゴマの香り。数種類の油を混ぜることで、強すぎる香りを軽やかに抑えてあるのだ。 「こちら。ア・ス・パ・ラです」 職人の律動が伴うイントネーションに、少女二人がくすりと笑う。アスパラが強調されているような気がしたから。そんな己に少しあわてて見上げると、ベビーフェイスの店主が目を細めて微笑んだ。 青くほくほくとしたアスパラを飲み込んで、再び糾華が口を開く。 「好きな事はゲームと小物集め。モチーフとしては蝶と猫が好き。このあたり有名かしら?」 「はい」 資料から、そして普段の様子からも知ってはいた。それは実感ではなく知識としてエスターテに蓄えられていたものだったが。 「私は――」 エスターテは、はたと己があまり遊んでいないことに気がついた。 「――こういう所に来るのが」 「いいもの食べてるのね」 エスターテの口をついてしまった言葉に、糾華が微笑む。 レンコンの歯ごたえ、きすの味わい。ほんの少量ずつ皿に乗せられる品々を見て、ああ、これが天麩羅なのかと思う。普段見かけるものとは、ずいぶん違うような気がして少し興味深い。 ゆったりと時間が流れていく。 「トウモロコシをかきあげ風に揚げて、バターをそえてあります。おしょうゆをたらすと、おいしいですよ」 店主が微笑む。そういう食べ方もあるらしい。トウモロコシはとても甘くて、どこかスナックみたいで親しみのある味だった。 「エスターテさん、いつもお世話になっているわね」 唐突な呼びかけに少女は答えない。ただじっと視線を合わせた。 「貴女達の奮闘がなければ、私たちは戦う相手と同じ土俵に立つことも敵わない」 私は――私達は。まだ弱いから。 消えいりそうな雪の囁き。 「いくら戦う力があってもまだ、全然……だから。貴女達の戦いも、その過酷さも私が知っている。アークの皆も知っている」 言葉を切る。エスターテは答えない。まだ言葉が残っていると思ったから。 「だから無理に戦場に立つとか言わないで」 じわりと広がる胸の痛みを、冷たいジンジャーエールが乱暴に撫で付ける。 先のバイデン達との戦いの中で、糾華は総大将の軍勢と直接刃を交えていた。その目と鼻の先。戦場に出撃したフォーチュナ達を守る戦いでは、失われたリベリスタも居たのだ。 「私達の刃は、貴方達の刃なのだから、一緒に戦ってるから」 エスターテの視界が揺れた。零れ落ちる――涙。 「友達を失くすのは嫌なのよ」 「……はい」 この日、二人は知人から友人になったのだという。 支払いは皿洗いのおじ様へ。斬風糾華より愛を込めて。 |