
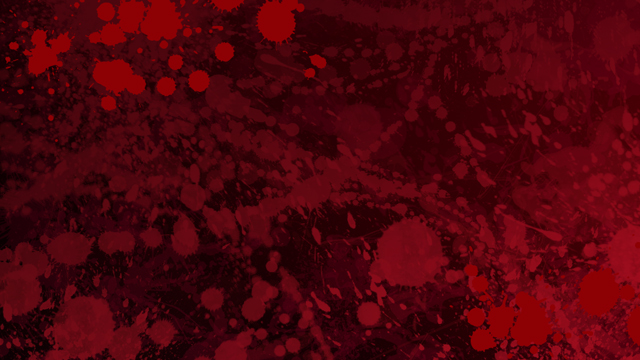
新潟県新潟市―― 「やりぃ♪」 重い雪の吹雪くこの街を『選んだ』男は――『幸運の音色』フェリチャーノ・ビトーントは『何時も通りの絶好調』に思わず声を弾ませていた。 氷点下まで下がろうかという外気は外に居る人間には中々に手厳しいもので、暖かい室内に早くエスケープしたくなる気持ちが生まれない訳ではないのだが、彼の奏でたメロディはその二つ名の通り彼の思う通りの――思った以上の結果を今回の動きにもたらしていた。 「いやぁ、焦った焦った。でも結果オーライね」 含み笑う彼が魔力揺らめくバイオリンを一鳴らしすれば転がっていた死体達が起き上がり、主人への忠誠に頭を垂れた。偶発的に起きた『日本のマフィア』との遭遇戦は予想以上の激戦にはなったが、それも勝った上でならば又良い手駒を増やせた……という事でもある。 「リクドーって言ったっけ。ま、中々だけど……俺等には及ばないわな」 フェリチャーノは鳥が鳴くような声を立てこの後の事を考えた。用意してきた兵隊は消耗したが新しく得た戦力は減らした数を補って余りある。偉大なる指揮者の望む『混沌組曲・破』はこれからが本番なのだ。嵐の中を行く船を孤立させ、絶望に包み、その無力さを思い知らせ、やがて沈める……プロセスは半ばだが、ここまでの予定に大きな問題は感じられなかった。 「やっぱり俺ってラッキーね!」 特別な才覚を持ち得て生まれ落ちた事が。ケイオスという男に仕える身である事が。こうして『いい現場』を引き当てた事が。フェリチャーノに言わせれば自分がどれ程運命の寵愛を得ているのかという証明のようにも感じられるのだった。 「さて――」 「――成る程、主が『楽団』か」 バイオリニストの意志に応え、死者が行軍を始めようとしたのと低く重い声が吹雪を裂いて辺りを揺らしたのはほぼ同時の出来事だった。 「うん? まだ居たのか」 フェリチャーノが声の方に視線を向ければそこには濃い藍色の道着に身を包んだ筋骨隆々なる男が佇んでいた。雪深い中にも足は素足。真っ向から吹き付ける冷たい風にも角刈りの厳しい顔立ちは微動だにしていない。 「日本人――ああ、こいつ等の仲間か!」 「道を究めんとせし者をそう呼ぶならば間違ってはおらぬ」 「おお! じゃあ、ジャパニーズ・オトシマエってヤツですか!」 フェリチャーノは破顔して『今更現れたリクドーの仲間』の行動原理を精神論にあると結論付けた。始まった時よりも自分の戦力は増えている。実に八名からなるリクドーを飲み込んだ自分に『たった一人』が立ち向かおうとするのは『そうとしか思えなかった』。 「否」 だが、道着の男はそれをあっさりと否定した。 「それ等は己が力で主に挑むと云った。六道に属する者、例えそれが途絶える道であろうとも己が道を歪める事なぞ無い。同様に己が道の後始末を誰ぞに委ねようと思う者も無い。なればこそ、道と道がぶつかり合い、主が上回ったと言うならば賞賛こそすれ憎む道理なぞ無かろう」 「……へぇ? じゃあ、何で」 「我は我の道を行くに過ぎぬ。主が望む通り――主の先に我が居るのと同じように。 道を譲らぬ者同士なら、何れか絶えるのも又必然なればこそ」 「……?」 高揚するフェリチャーノは小首を傾げ――この時点で気付くべきだった。『目の前の何を言っているか分からない東洋人』が時にバロックナイツに、時にリベリスタに、時に社会の闇の何処かに潜む『逸脱』を抱いている事に。彼が自分の力で挑むと言った仲間を見送った意味に。吹き付ける北国の風がその風情を変えている事に。 「良く分からないけど――こっちも暇じゃないんでね」 フェリチャーノの調べに乗って死体が踊る。 何度、何十度、何百度――それ以上も繰り返された『楽団』必殺のルーティーンは素晴らしい演奏技術のままに唯の一人に多角的な攻撃を繰り出した。死体が強力な革醒者のものなら尚上々。 「バラバラに――」 ――二閃。 光が瞬いたかのような足刀が前に出た死体を二つ叩き斬る。 「言うだけあるじゃん」 「……」 「ホント、すごい。すごい」 答えぬ男にフェリチャーノは笑みを深めた。 これ程の力の持ち主を自分の軍門に加えたならば、これは幸運を通り越してチャンスである。ケイオスは兎も角として同じバイオリンならバレットの下に甘んじ続けるのは余り面白くもないのだ。死体等、幾ら壊された所で痛くも痒くもない。『この戦力差』の初撃が単体を破壊する程度ならば敵は自分に多数を相手にする術が無いと告白しているようなものである。『この戦力差』なのだ。出し惜しみする意味は無い。故にこの戦いは『当然ながら』自分が負けるものでは有り得ない! 「天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道―― 我、六道を征く者、羅刹。見せて貰うぞ、主が道」 男が声を発したのと同時に吹雪が間合いに吹き付けた。 びゅうびゅうと鳴る冷たい空の吐息にフェリチャーノはその声を聞き取る事が出来なかった。名にしおう悪鬼羅刹のその顔を見る事は叶わなかった。煙る雪に遮られた戦場が視界を酷く狭めていたから。『幸運の音色』はだからまだ気付いていない。何にも、気付いていない。 「何処まで頑張れるかな!?」 男に殺到せんとした死体が全て一撃で破壊されている事に。 群がった兵隊の攻撃が男の肌はおろか道着さえも掠めていない事に。 男が――『技らしい技すら出していない』そんな単純な事実にも! |







