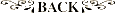●シンヤのアジト●


|
●承前 浮遊した精神が不意に滑落する。 一瞬で靄が掛かっていた思考が覚めた。どんな環境にあっても、疲れた身体と心は睡眠を要求するものらしい。 上半身を起こし、『シスター』カルナ・ラレンティーナ(BNE000562)は、改めて周囲を確認する。調光された間接照明がぼんやりと壁を照らす部屋。かすかに聞こえるのは、換気ダクトの音だろうか。 部屋の中には、自分が横たわる寝台と、テーブルとソファーの応接セット。テレビはないものの、どこかのシティホテルのような部屋だった。よくある備え付けの聖書の代わりに、カルナの古びた聖書がナイトテーブルに置いてあるところを見るに、シンヤ達自身もそのイメージを狙っているのかもしれない。 ただ一つ、普通のホテルと決定的に違うのは、この部屋には窓がない、ということだった。それに気がついて、ここはやはり彼らのアジトなのだろう、と実感する。 ドアは二つ。小振りな一つは、洗面やバスなどの水廻りへと通じていた。もう片方は、シンヤが出て行った扉。 ノブを回す――鍵は掛かっていない。 息を呑む。僅かな、しかし永久にも思えるような時間。だが、カルナはノブを静かに戻し、手を離した。音がしないように、ゆっくりと。 彼女はシンヤの力を――ジャックと出会う以前のものであっても――知っている。そして何より、彼が見せた余裕を知っている。一対一ではまともな相手にもなるまい。この部屋を出たとしても、見つかればそこまでだ。おそらく、鍵が掛かっていないということすら、そういう意思表示なのだろう。 諦めて踵を返し、壁面に設けられたクローゼットを確認する。中は殆ど空で、バスローブが一着、吊り下げられていただけだった。 その時、薄暗い部屋に差し込む光。ドアが開く音こそしなかったが、カルナは誰が入ってきたのか理解していた。もしも部屋を出ていたらどうなっただろう――背筋に寒いものが走る。 「おはようございます、お嬢さん」 振り返れば、逆光に浮かぶ細身のシルエット。その影が、先ほどは気がつかなかった照明のスイッチを押した。部屋に人工の光が満ちる。 「いえ、カルナさん、でしたかね。アークの皆さんから呼ばれていた名前は」 アーク。 その響きが蘇らせるのは、ただ不安だけでしかない。自らの身を気にしているのではなかった。仲間達は生きているのか、生きていたとして、自分を救い出すために無謀な戦いを挑まないだろうか――。 「まあ、お座りなさい。ああ、この部屋ではわかりませんね――今は真夜中ですが、私もベッドに潜り込む気分ではありません」 ナイトテーブルの聖書を手に取り、ソファに身体を沈めたシンヤは、貴方もそうでしょう? と対面のソファを示した。今は従うしかないと、カルナもまた彼に倣い、腰を下ろす。 「どこまで話しましたか……そう、創世の七日間の話はしましたね」 ぺら、と聖書をめくった男は、旧約聖書ですね、と頷く。 「その割にイザヤ書やエレミア書が無いのは不思議ですが……まあいいでしょう。曰く、始めに神は世界を作った。そして光あれ、と命じた。神は光を昼、そしてヤミを夜と名付けた。夕となり、朝となった。これが最初の一日目だった」 歌うように唱えたシンヤは、私達にとっては先ほどのスイッチが『光あれ』の言葉でしたね、とおどけてみせる。 「さて、七日の後、神はエデンを創り、そして最初にアダムを、そしてイヴを生み出しました。これが最初の男女というわけです」 聖書を閉じ、テーブルの上に置くシンヤ。眼鏡越しの視線が再びカルナを射る。 「『破門』に選ばれたお嬢さん。貴女なら、この歪んだ夜のイヴにもなれる。七日の間に貴女が心を決めたならば、ささやかで大それた、新たな創世を始められる気がするのですよ」 唇が吊りあがる。熱に浮かされたようなその口調とは裏腹に、見据える目は蛇のように冷ややかで。 「どうです、カルナさん。私の下に来ませんか――」 ● 「私が『はい』と応えると思っての問いかけとは思えませんが……」 折角の機会ですし、良ければ少しお話ししませんか、と返すカルナ。シンヤの意図が那辺にあるのか、まだ彼女は把握し切れていない。そのためには、少しでも時間を引き伸ばす必要があったのだ。 「そういえば自己紹介もしていませんでしたね。アークのカルナ・ラレンティーナと申します。……貴方がどのような道を歩んで来たのか、何故今の道を選んだのか。お伺いしたいと思っていました」 その言葉は必ずしも嘘ではない。人を殺す、それを愉しみとさえする殺人者と席を同じくして会話するなど、彼女の経験の埒外であった。アークの、と自らの立場を示しながら、カルナは問いかける。 「フ、まあいいでしょう。互いを知る時間というものも必要です」 とはいえ、語ることなどあまりありませんがね。大げさに肩を竦めるシンヤは、やはりどこか芝居がかっていた。 「気がつけば一人で生きてきた、というだけですよ。ホストだった時期もあります。力を得て、フィクサード有力七派が一つ『剣林』に拾われ――後は貴方も知っている通りでしょう。だが私はあの方に出会った。あの圧倒的な暴力に出会ってしまった!」 彼の声は徐々に熱を帯びていく。垣間見えるのは、ジャック・ザ・リッパーへの心底からの陶酔。 「もしも私の『道』などというものがあるならば、それはこの出会いから始まったに違いありません。血と臓物に彩られた道ですがね。フフフ。ぜひ貴女にも、この景色を見せて差し上げたい」 貴女はどうなのです、と水を向けるシンヤ。少女は一瞬の逡巡を見せながらも、凛と男を見据え、ゆっくりと語り始める。 「そうですね……。私は、これまでずっと、多くの命を手に掛け続けて来ました。それが直接ではないとしても」 ただ純粋に護りたいという想いをもったモノを。運命に愛されなかった方を。必要とあらば、元同胞ですら。 「私の『道』は、既に血に染まっています。仰いましたよね、私はいい人殺しになれる、と。ですが私は――」 もうとっくに、堕ちる先の決まっている人殺しなのですよ、と。それでも必死に表情を殺し、少女は言い切った。どろどろとした感情は、決して殺しきれるものではなかったけれど。 「十字教徒は嘘をつけないといいますが、なるほど、見事な告白でした」 にぃ、と男は厭らしい笑みを浮かべる。 「ええ、私も同じ人殺しです。今も昔も、騙して、犯して、嬲って、殺してきただけですよ」 貴女と同じです。 敵手の思いを踏みにじり、よってたかって荒事を仕掛け、完膚なきまでに殺し尽くす。 ほら、ね。 吐く言葉は何処までも毒。蛇の牙から滴った、魂を汚す猛毒。 「貴女も判っているのでしょう? 自分の本質が、どうしようもないモノであることを。『救い』を与えた気になって盛大に酔っ払う、私達『悪』よりよほど救いがたいものであることを!」 立ち上がったシンヤは、身振り手振りも大きく、見下ろすカルナへと語りかける。かと思えば、突然しおらしげに目を伏せ、静かに手を組んだ。まるで、祈りを捧げるかのように。 「ごめんなさい。でも、必要な犠牲でした。どうか安らかにお眠りください。……く、くくっ、それは、他人を殺して生き残った者にとっては、なんとも甘美なる痛みなのですから!」 「……そうですね。仰る通りだと思います。ですが、私──いえ、私達が力を振るう裏には必ず救われる方がいます。それが見えているか居ないかはその時々ですが」 だからこそ私達は、それが正しいと信じ、進むのです。自らの欲望のまま暴虐の限りを尽くす貴方がたとは、そこが違う。 いつしかカルナは、怒りのままにこの長広舌の男を睨みつけていた。それに気付いたのは、ああ、そんなに怖い顔をしないで、というシンヤの声が、彼女に冷や水を浴びせたからだ。 「私も貴女の望みを叶えてあげたいと思っているのです。人を救う聖女となることで、貴女が満足するならば。いずれ、また、そのお話をすることにしましょう」 ● 結局のところ、小鳥をいたぶり自ら羽根を差し出させることだけが、この男の望み。 そう彼女が悟るまでに、時間は必要なかった。ふらりとやってきては、気ままに演説して帰っていくシンヤ。その内容はといえば、いかに『愉しく』殺したかという自慢話と、そして、『神様』の否定。 窓のない部屋。時間感覚が狂っていく中で、いつしか浅い眠りに逃げ込むことだけが、彼女の休息となっていた。それが、熟睡することのないまどろみでしかなくとも。 「そうそう、望みを叶えてあげたいという話でしたね」 男がそう切り出したのは、カルナが連れ去られて三日目のことだった。 「私は貴女の神に成り代わるといいました。ですから、『人の命を救い続ける』という崇高な、貴女が果たそうとして果たせなかった願いも、叶えてあげられます」 もちろん、神というのは本来貪欲ですから、供物を要求するのですけれどもね、とシンヤは付け加える。ああ、それは余りにも邪な、悪魔の囁き。けれど、カルナは訊かざるを得なかった。囚われの自分が、何かを出来るというのならば。 「何をしてくれるというのですか。そして、何をすればいいのでしょう」 「簡単ですよ、毎日私に『愛している』と囁いてごらんなさい。十字教徒は嘘をつけないと言いますから、なんなら心から」 私の傍に侍って、小鳥が囀るように、毎日愛を囁くだけでいい。そうすれば、私はその日殺そうと思った最初の一人を助けましょう。そう、シンヤは頬を歪める。 「別に、神の教えを破った上辺だけの言葉でも、一向に構いません。貴女一人すら救えない神などに、興味はありませんよ」 「……ご提案自体は魅力的ではありますが」 それでも、彼女は言い澱んでしまった。信仰が、嫌悪が、プライドが。何より胸の底に残る希望が、邪魔をしてしまったから。 「私には貴方の心を読む術がありません。それに、貴方も上辺だけの言葉でも構わないというのなら、お互いに意味があるとは思えません」 否定の言葉を言い募る、そこに何の意味があるだろう? 冷静であれば気付くはずの思考を曇らせたのは、疲労と――あるいは罪悪感。 「私に『嘘』を言わせた貴方が、私が嘘はつけないと仰るとは思いませんでした。それに、私は嘘は何度もついていますよ。アークに来てからは特に。神秘を隠すためにも幾度と無く。それにより救われる者が居ると思えば、私は嘘をつくことを憚りません」 私は私が信じる主のもと、私の信じる救いを行うのみです。久方ぶりに頬に赤みを差し、ほとんどまくし立てるに近いカルナの言葉を、シンヤはただ薄い笑みを浮かべて聴いていた。 「ふふ、頑固なお嬢さんですね。しかし宜しい――貴女は今ひとつの選択をした」 ――また一つ、殺人鬼への道を歩むという選択を。 背筋が、思考が一瞬で冷える。実に喜ばしいことです、と上機嫌のシンヤに、カルナは自分が出口のない罠にかかったことを知った。どちらでも良かったのだ、この男にとっては。屈服させることが出来ればそれでよし、成らずとも、カルナの精神をヤスリのように削る武器となる。 「そ、そうでした。バスルームで、汗を、汗を流させて欲しいのですが」 「別段シャワー如き、私の目の前で浴びてくださっても構いませんが……貴女が一人で浴びたいというのなら、席を外しましょう」 その間、わが主に倣って、狩りを楽しんでくることにしますよ。時間を稼ごうとしたカルナを嘲笑い、殺人鬼は立ち上がる。 「くく、貴方の選択で、一人余計に命を奪われるのです。そうだ、お祝いに今度は、これまで以上に有意義なお話をすることにしましょう。そう、例えば貴女の『運命』についての提案をね」 意味ありげに手の中で弄ぶのは黒い十字架。だが、押し潰されそうな少女の視界には入らない。 「待っ……、……っ、いえ……、それでは少し御時間を頂きますね。……また後程」 背を向けたシンヤを、一度は追い出そうとした彼を引き止めようとして、それすらも果たせない。バスルームに飛び込んで、シャワーを全開にする。その水音に混じって、小さく嗚咽が響いた。 「アークが小うるさいと思うと狩りにも身が入りませんでね。それでも、貴女の為に一人だけ殺してきました。ちょうど、貴女と同じくらいの、高校生の男の子でしたよ」 シンヤが戻ってきたのは、それから数時間も経ってからのことだった。 彼女の名前でしょうか、ゆうこ、なんて名前を呼びながら死んでいきました、と。見知らぬ少年が、男の気まぐれによって――自身の選択によって無残に解体されていく様を、強制的に流しこまれるカルナ。耳を塞ぐことすら、少女には許されない。 「ええ、ええ、『貴女』と私が、一緒に殺したんです」 こうして、また一つ『罪』が増えていく。 ● 時間にして四日が経っていた。 無辜の命を奪った。『私』が奪ったのだ。その声は、間断なくカルナを責め苛む。どこまで行っても行き止まりの状況に、自決、という言葉すら頭に浮かべて――首を振る。あの男は、自分の死体すら『有効に、愉快に』使ってみせるだろう。 「私は、どうすれば……」 目に留まったのは、ベッドサイドに置きっぱなしの聖書。市中に出回っているそれとは大きく内容を異にするものの、彼女にとっては慣れ親しんだもの。手にとって聖句を追い――ふと、もう一人の登場人物を失念していたことに気付く。 「『視ている』方が居た方が、まだ望みがあるのかもしれませんね。もし、今もご覧になっているのなら――少しだけ、少しだけ一縷の望みに縋らせては頂けませんか」 「……カルナ様も中々勘の良い方ですねぇ」 閉ざされていた扉が開く。顔を出したのは、肌も露な衣装に身を包み、常に黒い手袋をはめた女。直接会ったことはないけれど、その名前は知っている。 「初めまして、カルナ様。私、アシュレイっていいます。皆さんには『塔の魔女』で顔も名前も知れていると思いますけど」 帽子を取って一礼。バロックナイツ歪夜十三使徒が第十三位は、柔らかな態度を崩さずに語りかけた。 「いや、今回は大変でしたね。此方は此方で――随分と予想外の展開にもなったのですけれど」 はじめまして、お呼び立てをして申し訳ございません、挨拶するカルナは、予想外という言葉に引っ掛かりを覚える。だがそれよりも、彼女には訊かなければならないことがあった。 「いきなり勝手なお願いで恐縮ですが、今回シンヤさんと戦った、私の仲間達の安否は……」 「……そうですね。貴女様ならば、まず御身より仲間達を気にするのも当たり前と言えば当たり前でしょうか。無傷とは言いませんが犠牲が出た……という事は無いようです」 アーク全体を言うなら……お気の毒ですが、お一人、ジャック様に。そう告げるアシュレイに、カルナは顔を歪ませる。 「犠牲は避けられないのでしょうが……仲間が喪われる事はやはり辛い。けれど、身勝手な私をそれでも護ると言って下さった皆様が、誰一人欠ける事が無く戻って下さった事を喜んでいる私は、やはり罪深いのでしょうね」 溜息と共に流れ出たそれには敢えて口を挟むことなく、私がここに来たことはシンヤ様にはナイショにしといて下さいね、と『塔の魔女』は付け加える。 「私がここに来たのは、用という程の用ではないのですよ。単にシンヤ様に捕まった『聖女様』が見てみたかった――と申しましょうか」 琥珀の瞳が、すう、と細まる。 「その『聖女様』が何故そんなに愚直に形無き信仰を貫けるのか、心底疑問に思ったから話を聞きたいと思っただけなのです」 形無き信仰、と鸚鵡返しにするカルナに一つ頷いて、年経た魔女は先を続けた。 「御幼少の頃に家族を失い――貴女は此の世の造りを理解している筈です。なのに何故、貴女は神を信じ得ますか? 父なる主が何一つしてくれないのは良く御存知でしょうに」 それは意外にも鋭い舌鋒。もしカルナが以前にこの魔女と相対したことがあったなら、雰囲気の違いに気がついたかもしれない。普段纏う緩さをどこかに置き忘れたように、根源へと至る問いを彼女は放つ。 「たかだか十六年の生。穢れすら知らない貴女様は、どうして我が身に絶望とその先を受け入れられるのでしょう? 単に無知なだけですか? 『知らないからこそ』肯定出来るのでしょうか。清らかなる『聖女様』はたがを失った男の欲望をご存知でない。世の中には信仰で避け得ない暴力と悪徳が蔓延っていることをご存知でない。いえ、理屈で理解していないとは申しませんが、『実地』で理解するには経験が余りに些少でございましょうね」 切れ目なく問いを発したアシュレイは、我に返ったかのように、意地の悪い物言いをしまして申し訳ありません、と頭を下げる。 「……しかし、生贄の羊を望んだ十字は、神の声は、『無知を罪』とも定める筈です。カルナ様は最悪を御存知ない。カルナ様は確かな信仰をお持ちでも、神の姿を御存知ない。それを知るには余りにも貴女の時間は短過ぎる」 ――しかし、カルナ様は同時に、『それでも父の声に疑いを持つ事は無い』。 「何故ですか? 『破門』の審判さえ避け得るご自身の運命に自信を持っているから? それとも『死を越える最悪』でさえ受け入れられるという『甘い覚悟』をお持ちだからですか?」 ……あはは。また少し意地悪しちゃいましたね。でも良ければ答えて頂ければ、アシュレイちゃん嬉しいです。最後の一言だけはとぼけた風情で、アシュレイはそれきり黙りこむ。 沈黙が落ちる。魔女は答えを促さない。だが、薄暗がりで輝くその瞳は、韜晦を許さないと告げていて。 「ええと、ですね……」 だから、カルナに出来た最善は、自分を謀らずに、偽らずに答えることだった。少なくとも、彼女はそう信じた。一度心を決めれば、言葉は氷が溶けるように紡がれる。 「深く考えたことは無いのですが……。多分、私にとって、主を信ずる事は呼吸をするのと変わらないのでしょう。そうする事が当然であるからそうする。主の下に集った方々が私をここまで生かして下さったのですから、私は主によって生かされたも同じです。もし、育った環境が異なれば別の考え方を持ったのかもしれません。ですが、私は教会で育ったのです。優しい方々に包まれながら」 彼女の脳裏をよぎるのは、この場にはいない紅いナイフの殺人鬼。彼が身を寄せた先が『剣林』でなかったら、あるいは――。 だが、それは優し過ぎる祈りだということを、他の誰でもなく彼女自身が理解していた。 「無論、主は私達を見守るのみ。ですから、実際に人を救うのは人なのだと思います。私を生かして下さったのが、主の下に集った人々であったように。故に、私は人を救う力を得、運命に愛されたことに感謝しています。……もっとも、それは全てを救えると思った傲慢で、それでも止まることはできなかったのですが」 傲慢。その言葉を率直なる自己批判と呼んでいいものだろうか。むしろ誇り高くあるカルナを、『塔の魔女』は冴え冴えとした瞳で見つめている。 「正直なところ、黒い十字が出す答自体はどうでも良かったのです。人を救うのが人であるように、人を裁くのもまた人。魔女狩りは神の意思の下に行われたとは思いません。であれば、彼の十字は人が人の信仰を試す物でしかなく、他の方から見ても私の信仰は肯定されうる物であった、それだけの話だと」 考え考え、途切れ途切れに、自分の内にある『信仰』を言葉にしていくカルナ。 「アシュレイさんが言う『死を超える最悪』と、私が思う『最悪』は異なるのかもしれません。ですが、少なくとも、私の思う最悪となった際には、私の仲間が必ず『それ』を『止めて』下さると信じています。皆とても強く、とても優しい仲間達ですから。だから、私は恐れることはなかったのです。主を信じるように、私はアークで得た素晴らしい仲間も信じています」 そこまで言って、ご興味にお応えできないようなつまらない話になってしまった気がしますが、と申し訳なさそうにする少女。 「……」 だが、魔女は何も返さない。言葉を発しない。ただ、琥珀の瞳で冷ややかにカルナを射抜くのみ。 永遠とも思える数瞬。やがて、アシュレイは大きく溜息をついた。 「……うん。何となく『そういう』答を予想して訊いた私は、それが聞きたかったのか。それを聞きたくは無かったのか。人間っていうのは難しいものですねぇ。どれだけ納得し難くても、時に納得し難い答こそを聞きたがるのですから」 うん、分かりました。カルナ様はとてもお強い方なのですね! その口調から、彼女の考え全てを読み取ることは難しい。簡単に考えを面に出すほどアシュレイは青くはなかったし、カルナもまた、奇しくも魔女が指摘したように、機微に通じるほどの年輪を重ねてはいなかった。 けれど、あえて一つを挙げるとするならば――侮蔑、だろう。 「面白い面白くないという意味では『とても面白かったです』から御心配なく。唯、少しお話が長くなってしまいましたね。シンヤ様がお戻りになる前に私はお暇しなくては」 そう言うと、『塔の魔女』は再び帽子を取って一礼する。 「では、カルナ様。『色々あるとは思いますが』それでも主が貴女と共にあらん事を。失礼しまっす」 魔女が去った後、再び鳥籠に沈黙が落ちる。 一縷の望み、カルナを助ける手は、もう伸ばされる事はないのだと――理由なく、彼女は理解していた。理解せざるを得なかった。 ● 「ところで貴女、まさか七日の後に、自分が『死ねる』なんて――『殺してもらえる』なんて、思っていませんよね?」 もう何日経ったかも判らない。気配に跳ね起きる浅い眠りの連続は、彼女から生活リズムを完全に奪っていた。今も、開かれたドアから雪崩れ込む蛍光灯の光に叩き起こされたところだ。だがシンヤは頓着せず、鳴かない小鳥に会話を強いる。 「そこのところを勘違いしていないかと、それだけが心配でしたよ。創世の七日の後に待っているのは、楽園追放です。そして原罪が故に、人は永遠に苦しまねばなりません。そう、『永遠に』」 それはそれで楽しみではありますが、と酷薄な笑みを見せる暴君。その声に籠もる、じっとりとした熱。 「清らかなる貴女が、嬲られ、穢され、這いつくばって汚濁をすする。そうした後に、貴女がなお『聖女』でいられるか――想像するだけで昂ってくるものがありますね。ええ、ですが私は貴女に、方舟に乗る機会を与えましょう」 「方舟、ですか。既に異なる方舟(アーク)を選んでいる私を、何故そこまで乗せ換えたがるのか、理解に苦しみますが……」 胡乱な目で見るカルナに、シンヤはいえいえと首を振って右手を差し出す。その手に握られているのは、あの黒十字の鎖。 「なにも現状維持というだけではありません。私は、貴女の『運命』を返してあげることすらできる。この十字架を、まさか見忘れたりはしないですよね? そう、Anathema。運命の力そのものを消し去るアーティファクトです」 これ見よがしに振り子を揺らし、あの工場で彼女を縛り付けた十字架を見せ付けるシンヤ。しかし、少女は悔しげな表情すら見せることなく、ただ彼の独演会を聴いている。 「しかし、おかしいとは思いませんでしたか? 倒れた身体に再び立ち上がる力を与え、時にはこの世の法則すら捻じ曲げることもある『運命』。その力が、たかだかアーティファクトによって、何の作用もなく『消滅』すると? 呪いと引き換えに絶大なる能力を与えるならまだしも、このAnathemaが?」 眼鏡越しに、力のないカルナの目を覗き込む。後一押し、そう判断したか、男の声に力が入った。 「そうです。そんなはずはない。『減少』することと『消滅』することはイコールではないのです! 塔の魔女によれば、この十字架の持つ能力は『収奪』。奪った『運命』を溜め込むタンクでもあるのです。そして今、このちっぽけな十字架に、貴女の運命が封じられています」 その時、少女の瞳に輝きが戻ったことに、シンヤは気がつかなかった。彼女を屈服させる切り札として用意した、カルナ自身の『運命』。 ――それがあれば、あるいは。 「もう判ったでしょう。貴女が私の傍に侍ることを望むなら、これを破壊し、貴女の『運命』をお返ししても構わない。そう私は思っています。もちろん、貴女が裏切ることの出来ないような仕掛けは、させてもらいますけれどもね」 いかがです? もう一度お伺いしますが、まさか、あっさりと楽に死ねるなどと――思ってはいないのでしょう? 正確には判らないまでも、自分に残された時間は残り少ない、とカルナは察していた。そして、Anathemaに蓄えられた『運命』は、おそらくシンヤの最後の手札なのだろう、ということも。 彼女は選ばねばならなかった。拒むか受け入れるか。彼の言う永遠の苦しみに囚われるのか、それともシンヤの傍で、フィクサードとしての道を歩むのか。 (考えてみれば、正解なんてありはしないのですね。最初から、不正解の選択肢しか私には無かったのですから) チップが私だというのは助かりますね、と一人ごちる。その響きはシンヤまでは届かなかったらしく、悩む少女を、薄い笑みを浮かべながら見守るのみ。 そして程無く、一つの結論が導かれる。 「こんな状況であれば貴方の好きなように出来る筈ですのに、大分譲歩して下さるのですね。──そうですね、その黒い十字架、Anathemaを私に下さいませんか。破壊して『運命』を返して下さるのであれば、それ自体を譲って頂いても構わないでしょう?」 ほう、と眉を上げ、続きを促すシンヤ。意を決したように――逃げ出さないように、彼を見据え、カルナは交渉の言葉を紡ぐ。 「その十字架には『興味』があります。それを頂けるなら、私は貴方の下に付きましょう。それが許されないのであれば──どうぞ私をご自由に」 主の言葉に背いたことが原罪であれば、幾多の罪を重ねた私に永遠の罰が下されるというのも、仕方の無い事でしょうから。そう続けようとしたカルナの言葉を、素晴らしい! と叫ぶ声が掻き消す。 「ようこそ『こちら側』へ、闇夜の聖女、新しき創世のイヴ! その決断を歓迎しますよ、カルナさん。では、早速ですが、私はテストの素材でも捕えてきましょう。なに、どんな人間にも最初はあるものですからね」 喜色を浮かべるシンヤ。だが、その台詞は彼女にとって聞き逃せないものだった。――テスト? 素材? 「貴女はまず、自らの手で肉を裂き臓腑を抉り、温かい血を浴びて芳醇なる香りを堪能する、その経験を得なければなりません」 その戸惑いを知らず、今にも踊り出すかのような勢いで、彼は滔々と続けた。 「そうすれば、晴れて貴女は方舟へのチケットを得ることができる。フフ、羽化の時ですよ。清らかなる聖女が、血塗れた真の殺人鬼に生まれ変わるのです! 無力に這いずるしか出来ない無様な芋虫が、大空を舞う美しい蝶へと!」 サッ、と血が引く音。カルナの顔が一瞬にして蒼白に変わる。またしても。またしても自分は、この男の悪意を甘く見積もりすぎていた。チップが自分だけだなどと、誰が決めたのというのか。 「実に愉快です。ええ、ええ、望むなら生まれ変わりの記念に、この黒十字を貴女の首に掛けたままにしておくのもいいでしょう。差し上げますよ――私からの、最初のプレゼントです。テストが終わったら、もう一度、私自らが貴女の首に掛けてあげましょう」 声も無い少女を屈服と見たか、シンヤの舞台はクライマックスに向けボルテージを上げる。 「では、準備もありますので、また後程。血の晩餐、我らが祝福の夜にお会いしましょう。く、くくく、フフフフ、あははははははっ! 」 そうして、彼女を一顧だにせず、シンヤは部屋を出て行った。 「そんな……。……それでも……」 扉が、ゆっくりと閉まる。残されたのは、崩れ落ちる身体を手で支えるカルナのみ。――いや、『三人目』もまた『そこにいた』。 「……ううむ。カルナ様。どうも、こう。かなり時間を争う展開になりそうなので、唐突に再度のお邪魔を失礼します。大体の状況は此方も把握していますけど……一つ質問をさせて下さい」 ● 振り向けば、予想通り肌も露なアシュレイの姿。確かに扉は閉まっていた。まるで『突然その場に湧いて出た』ように。おそらくそれもまた、『塔の魔女』が扱う非常識の類なのだろう。 だが今の彼女を包むのは、何かに戸惑っているような、持て余しているような――そんな雰囲気で。 「おや、アシュレイさんいらっしゃいませ。……こうしてまたいらっしゃったということは、あまりに予想外の展開となった、ということでしょうか」 疲れた様子で、それでも笑みを浮かべるカルナ。だがそれには答えず、アシュレイは直戴な問いを投げかける。 「カルナ様はシンヤ様の用意する『テスト』を本当に受け入れられるのですか? 貴女が『それ』を選べると云うならば、私の出る幕はありませんけれど……」 「……出来る出来ないと問われれば、正直わかりません」 弱々しい声。笑みを浮かべさせるのは、自嘲、それとも逃げ場の無い諦念だろうか。 「でも、私は出来るような気がします。私は嘘をつくのが案外上手いみたいですから。そこに理由を見出せれば、自分も簡単に騙せる位には」 うーん。その、そうですね。ええい、何とも……。ごにょごにょ、と歯切れ悪く呟く魔女は、しかし意を決したか、勢いをつけて次の言葉を紡ぎ出す。 「そうです! 私は私の目的の為に、カルナさんを救う選択肢を持っています! 貴女が選ぶ結末によっては私は貴女に手を貸す事が出来る。私の『24、The World』はその選択を肯定しています」 決まり悪げに続けるアシュレイ。『24、The World』の意味をカルナは知らないが、問い返しはしなかった。 「正直を言えば、かなり悩みました。『理性的にどうするのが一番自分に得か』を考えれば、この決断は前回に下されるべきものだったんです。しかして、貴女は余りにもこう……いえ、それは貴女の問題ではありません。全て私の極々個人的な感情の問題なのですが。どうあれ、貴女には私の決断を鈍らせ、結論を遅らせる理由があった。ですから、この期に及んでしまったのは確かですけど――」 回りくどい言い方を続けるアシュレイ。だが、突然に空気が変わる。緩い、あるいは戸惑った雰囲気は掻き消えて、『塔の魔女』に最初に会ったときの鋭さが舞い降りていた。 「――最後の機会と思って聞いて下さいね。貴女は『罪無き羊の生き血を啜り彼と魔道を行きますか?』それとも、『この虎口から逃れたい』と今も思いますか? 罪の楔と強制魔術(ギアス)はやがて聖女さえ汚すでしょう。どんな高潔な魂を持とうと、どれ程何かに抗おうと、内から何かを為そうとしても。他ならぬこの私の魔術は貴女に安直な偽りを許さないでしょう。私はそれが本意では無い。しかし、貴女の決断を押し切ってまで貴女の鳥籠を破ろうとは思いません。ですから、もう一つ私から選択を提示しましょう。後宮シンヤの問いならぬ、アシュレイ・ヘーゼル・ブラックモアの問いをここに」 『貴女は、もう一度訪れ得る朝を望みますか? それとも望みませんか?』 「お答え下さい。シンヤ様がやがて戻る――この短い時間の間に、黒い十字を背負った運命さえ委ねて」 アシュレイは長尺の台詞を一息に吐き出すと、猫のような金色の瞳をすぅと細め、囚われた聖女の瞳を覗き込んだ。 しばしの沈黙。 「……安直な偽りを許さない、ですか……」 ぽつり、と吐き出した声は、か細く、震えていた。 「……私の考えは、酷く見当違いだということなのでしょうね。そこに意味が無いのであれば、本当に私は、何をしているのでしょう……」 「現実を結論のみで語るならば、貴女の考えている事は叶わないでしょう。無為とも呼べるのかも知れません。貴女はシンヤ様に対して、ジャック様に対して、私に対しても酷く無力だ。力ある誰かが略取を望むこの世界に、清らかなだけの想いなんて通用しませんから」 カルナの願い。 制約の内容によっては、シンヤやジャックの傍にあって、少しでもアークの為に役立つ道を探ること。そして、Anathemaをアークに渡し、運命に愛されなかった存在にもそれを分け与える術を研究してもらうこと。 自分は、もうアークに戻ることは出来ない。夢現の中で、愛しい人々には別れを告げた。覚悟を決めた、そのつもりだった。 それでも。 「本当は、最初の時に逃げたかった。でも、できなかった。望まれた気がしたから……! 本当は『聖女』なんて呼ばれたくありません。私は、私は『聖女』なんかじゃない。そんな大それた存在ではないのです……!」 絞り出すような声。今にも泣き伏してしまいそうなカルナ。対するアシュレイもまた、再び唇に感情を乗せ始める。 「ですがね。この場に『私を引きずり出した』のは貴女のその危うい弱さであり強さなのですよ。青く未熟で無為を無為と知らない。いえ、無為を無為と知りながらもきっとそれでも怯まない。己が羽が嵐を飛び抜けるたくましさを持たない事を理解しながらも、荒れ狂う空に飛び立たんとするその瑞々しさ! 何て綺麗なんでしょう。何て、美しいのでしょう。貴女には私が選び得なかった可能性が幾らでもあるようです。そんなもの、この私とて甘い幻想と知らない筈が無いのに」 「……こんな、どうしようもない私でも、救いを望んでも良いのでしょうか。それでも、それでも、もし許されるのであれば……」 私は再び朝を……、朝を望みます……。崩れ落ち、魔女を仰ぎ見る少女の目に、いまにも溢れそうな涙が溜まっていく。 「……貴女は貴女の運命に続きがある事を誇るべきです。時に力を積み重ね、遠い先に可能性を紡げる事を誇って下さい」 羨望と嫉妬、憧憬と憐憫。『塔の魔女』の口上に籠められた色は、万華鏡が織り成す複雑な色彩の様相を見せていた。 「ハッキリ言えば、私は『聖女』なんて呼ばれる類の女が大嫌いなんです。そんな私が貴女を救おうというのは、貴女がこの時間で見せた『人間らしさ』の為なのですから! 『揺れ動き、惑い、無力を知り、可能性を探し、訪れた救いに涙さえ見せそうなそんな顔をする』。無様な――とても『聖女様』とは思えない。私は、そんな顔が見たかった。安心したかった、と言い換えても構いませんね!」 そこまで熱弁し、自分が感情のままに喋り続けたことに漸く気がついたか、アシュレイは一つ咳払いをする。 「……コホン、失礼しました。お約束通り、カルナ様は私が助けましょう」 「それでは、アシュレイさんのお立場が……。いえ、今私が考えるべきはその事では無いのでしょうね。それに、シンヤさんが後ほど連れて来るであろう方は……」 唇を噛むカルナ。無力な自分を責める彼女に、お願いしたいことがあるんです、と魔女は囁く。 「私の立場はご心配なく。ただ、アークの皆さんにも宜しく、と。ついでに、貴女様が欲しているであろう情報もお渡しします。貴女様の運命を取り戻すにどうすれば良いかはもう知れているとして……例えば『私達の目的』とか」 安堵で力が抜けていた少女の身体が強張る。ジャック・ザ・リッパーという頂点の一角に襲来されたアーク、いや日本という国にとって、それは重要過ぎる情報だった。 「私達はね――穴を開くんです。百年に一度の特異点(にほん)――千載一遇の好機と特別の儀式をもって、世界に風穴を開けるんです。塞げない大穴を、此の世を混沌に作り変える狂いに狂った大穴を。誘蛾のように神秘を引き寄せる大穴を」 「神秘を引き寄せる、大穴──」 カルナに頷いて、『塔の魔女』は説明を続ける。ジャック様はこの地に『王国』を作る心算なのかもしれません、と。 「ただ、それは私には関係の無い事ですけれど。想像がついてきましたか? バロックナイツがバロックナイトを引き起こす――字面にすれば冗談ですが、本懐であるとも言えるでしょうね。儀式の時は近く、私は『とある理由』からその訪れを邪魔させる心算は無い。しかしですね、穴の開いた後――私の目的の一つは皆さんとも共有出来るものなのですよ。ジャック様とは、違ってです」 「率直な感想は……控えます。ですが、お話は承知いたしました。アークに伝えさせて頂きますね。そして、それに対する判断は、おそらく本部が」 皆さんとも共有できる、という意味を少女はほぼ正確に察していた。この情報をアークに伝えるメッセンジャー。そして、現時点でも格段の敵意は無く、将来的には手を組む用意がある、という生きた意思表示。 「……うん、まぁ。今はお話はこの位にしておきましょうか。唯でさえ――これは本当に不本意だったのですが、皆さんのお仲間を死なせる事になってしまった。魔女には不似合いかも知れませんが、カルナ様を逃すのも、余計なお喋りをしたのも、贖罪と受け止って下さっても結構です」 「ご恩は必ず。何かあった際には是非お声がけ下さい。例えアークとしては動けなくとも、私個人で動ける範囲であれば、それでも。今の私ではお返しできるものは持っておりませんが、いずれお返し出来る程になれるよう努力致します──その時は、良ければ貴方のお話も伺わせて下さいね」 最後に付け足した希望に、アシュレイは少し笑う。そうなればいいと彼女が思ったか否かは、やはりカルナにはわからなかったけれど――。 「では、カルナ様……」 少女の手を取る魔女。琥珀と翡翠の視線が交錯する。 「それでは。どうか貴方に主のご加護がありますよう」 「……やっぱり、私は貴女のことが嫌いです」 次の瞬間、眩い光がカルナの視界を灼き、その意識を刈り取った。 <リプレイ:弓月可染> |