
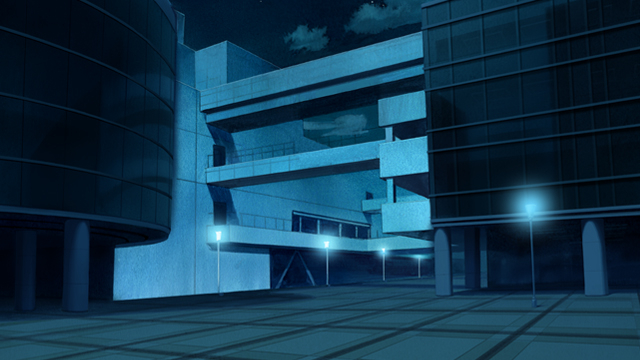

もしかしたら、いつかのお話

|
●もしも、あの時 4月。 「私は世界を愛しています!」 朗々と、少女の子は響き渡った。 思わず顔を上げて、少年は路地を見回した。この雑踏の中で、高らかに謳い上げた声。 少年が人間では無い事など、その道に通じた者しか知りはしないだろう。その頃にはまだ、彼にはフローという名前があった。 「私は世界を愛しています。この世界を、この国を!」 歌うような声だった。物好きだな、と、そんな呟きがフローの唇から零れる。 有り触れたタイル敷きの公園の、有り触れた小さな噴水の前で、黒髪の少女は微笑んでいた。 きっと彼女の目には、通り過ぎる人々の好奇の視線は見えていないのだろう。それどころか自分の声がどれほど通っているのかも気付いていないに違いない。まるで独り言のような態度だった。 艶やかな髪が、彼女がステップを踏むように歩む動きに沿って広がる。揺れる。 魅入るように、少年の瞳は少女の動きを追い掛ける。 ――もしもこの時、フローが彼女の姿を探さなかったなら、一体どうなっていたのだろう。 ●その、約束を 演劇部に所属していた事があるという少女の名は希代子といった。 未だ未来は明るく輝いて、光と優しさと希望に満ち溢れているのだと疑わない年頃。四月に降り注ぐ薄紅色の花びらは、そんな少女の夢を打ち砕くつもりさえ無いようだった。 「私ね、王子様を待ってるの」 「へえ。迎えにでも来てもらいたいの?」 うっとりと夢見がちな瞳で、希代子は青い空を見上げた。立ち上がった拍子に少し捲れたスカートの裾から視線を剥がし、オープンテラスの喫茶店の椅子に腰掛けたまま、フローはコーヒーを啜る。 「そう。それでね、いつかお姫様になりたいのよ!」 とても17にもなった少女の発言では無い。 だが生憎と、異世界出身の少年に、そんな事が分かる筈も無かった。 「ねぇ、フロー。王子様、いると思う?」 カップを持ってテーブルに頬杖をつき、少年はじっと希代子を見上げる。 「…………いるんじゃない?」 「あ、どうでもよさそう!」 不満げに頬を膨らませた希代子に、フローは薄く微笑んだ。 「あはは。行き遅れたら、ボクがお姫様にしてあげるよ?」 「……本当?」 どうやって、とは、希代子は聞かなかった。 疑り深い瞳でフローを見下ろして、その癖酷く期待した顔もして、彼の返答を待つ。 そんな様子にからかいたくもなったが、少年はくすくすと笑い声を立てた。 「本当に」 「約束だからね。その時はフローが小さな王子様って所かしら?」 「うわあ……」 「また嫌そうな顔して!」 ――もしもその約束を交わさなかったら、一体どうなっていたのだろう。 ●また、いつか 時間は随分と流れた。相手がほんの数度会っただけの自分の事など、覚えていないだろう事も承知していた。 かつて夢に満ちていた少女が、果たして未だその夢を抱いているかも分からなかった。――分からなかったが、それでも、フローは彼女の前に姿を現した。 夜も深まりゆく刻限、公園のベンチに腰掛けた女と、その向かいに立つ黒いローブを纏った少年。 仕事帰りの疲れた身体を少し休めていた女は、呆然と、驚いたように死霊案内人を見上げていた。 その何処か懐かしい瞳を、フローもまた、静かに見返す。 その会話をしたのも随分前の事だ。何度目かに顔を合わせた時、希代子の語る夢物語の一つにそれはあった。 「素敵でしょう?」 「そうかい?」 「死んでしまったら一人じゃない。生きていたって幽霊が見えないのに、死んだら他の幽霊が見られる保証もないし」 角砂糖を三つも入れた紅茶を口にしながら、希代子は楽しげに微笑む。 「だから、迷子にだってなると思うのよ。そんな時に、迷子にならないように道案内してくれる人が居たら素敵でしょう?」 「…………。それが?」 フローにとってそれは素敵だとも退屈だとも思わない、いわばどうでも良い事柄ではあったが、楽しげな少女の様子を見るのは心地好かった。 興味の無さを隠した質問に、希代子は益々にっこりと笑う。 「死霊案内人! 顔が隠れるくらい大きなフードが付いた黒いローブを着て、長い杖を持ってるの。杖の先にはカンテラが付いてて、がらんがらーんって音がするのよ」 「何なの、その趣味。死神みたいな格好だね」 「でも、目立つと思わない?」 どうかなとまた呟いて、フローはひょいと肩を竦めた。ただ、その言葉が彼の指針になった事だけは確かだ。 ――もしも彼女がその言葉を口にしなければ、もしもその空想上の職業を覚えていなかったら、一体どうなっていたのだろう。 そんな事は分からないまま、想像すら出来ないままでフローは――死霊案内人は、女へとそっと片手を差し出した。 ねえ、知っていたかい、希代子。 死霊案内人は、死霊を案内しなければならないんだ。その為に、死霊は必要なんだよ。 だから、ボクは。 その言葉を呑み込んで、フローは静かに杖を握り直す。がらぁん、と、不思議な音でカンテラが鳴った。地面を照らす柔らかな光の生む影が、不可思議に蠢いて揺れる。人のようなシルエットだ。 「君の知らない場所で、君の為に物語を演じる物好きが居るとしたら、君は信じる?」 「……どうかしら。理由にもよると思うわ」 不意に眼前に現れた姿へ戸惑いながらも答える彼女に、少年は、アザーバイドは穏やかに微笑んだ。 ねえ、覚えてるかい、希代子。 君の願いを叶えたら、君は共に来てくれるって。そう言っていたんだよ。 あの遠い遠い“いつか”、君がまだ、それを過去とは呼ばなかった頃に。 「ボクは、君の願いを叶えられたと思うかい?」 「……分からないわ……」 呆然と呟く彼女にかつてのように微笑んで、さあ、と促す。 女の白い指が、自身の手のひらに伸ばされるのを見ながら、フローの唇は綻んだ。 全て全て、彼女の為だった。 彼女の為にフローは居た。気紛れに降り立ったボトムで、最初に言葉を交わすようになってから。 ボトムで初めて受け入れてくれた彼女の為に、死霊案内人は生まれ、フローという名を捨て去った。 娘の他愛無い夢を叶え、見守り、夢物語の一場面を演じて見せた。 今となっては気紛れ以外の理由を見出す事は出来なくなってしまったけれど、それも漸く、終わる。 だがしかし、それでも彼は死霊案内人だった。死霊を導く者だった。 物語の終わった先。導ける場所は、一つしかない。 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:猫弥七 | ||||
| ■難易度:NORMAL | ■ ノーマルシナリオ 通常タイプ | |||
| ■参加人数制限: 8人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2015年09月29日(火)20:54 |
||
|
||||
|
||||
| ■メイン参加者 4人■ | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
● 差し伸べた手に女の手が重なるより早く、『死霊案内人』は密やかな溜息を吐き出した。 「何かを忘れるという事には、相応の理由がある」 独り言のような声量だ。深夜の公園へ、ひっそりとしたその声が響く。 「例えば、覚えていたくない事だったり。もしくは覚えるだけの価値が無い事だったり……要は、そういう事だと思ってるんだ」 少しの落胆と、呆れたような溜息を一つ零してアザーバイドは振り返る。 杖を握り直し、尖る先端を地面に軽く打ち付ける。現実味に欠けた鐘のような音で、ガラァン、と杖が音を立てた。 「ご機嫌麗しゅう、ブギーブギー」 振り向いたアザーバイドへと、『覇界闘士<アンブレイカブル>』御厨・夏栖斗(BNE000004)は芝居掛かって一礼を向ける。 黒衣の少年姿もおどけたように肩を竦めて、手のひらを軽く胸へと添えた。 「そう呼ぶのも今じゃ君くらいだろうね」 今のボクは『死霊案内人』だから。 淡とした口調で微笑んで、アザーバイドは首を傾げる。 「な、何がどうなってるの……?」 手を差し出してきた少年と、新たに表れた集団。次々と増える役者に、舞台の袖に一人置いていかれた希代子が小さく呟く。 動揺し切りの彼女の前で足を止めて向き直り、『亡霊』小島 ヒロ子(BNE004871)は柔らかに微笑んだ。 「こんばんは、お姫様……っても、覚えてないよね。初めましてでいいかな」 「……あなたは?」 動揺と警戒を隠せていない希代子を見下ろして、ヒロ子は「そうねぇ」と考え込むように顎に指を当てて、すぐににっこりと微笑む。 「私は……『魔女』ってコトにしとくわ。アルコールで動く、鉄と破れた夢でできた魔女」 「……それじゃロボットだわ、まるで」 冗談めかした自己紹介にぽかんとして、希代子は噴き出すようにくすくすと笑い出した。 その様子を眺めて、彼女の正面で足を止めた『百の獣』朱鷺島・雷音(BNE000003)が淡く微笑む。 「君に思い出してほしいことがあるんだ。……ずっと遠い昔、雑踏で声を上げたときに“自分”をみつけてくれた男の子の事を」 きょとんとしたように瞬く希代子の顔を覗き込んで、雷音は微かに瞼を伏せた。 「きっと、その男の子は君を見守って、君がさみしい時に来てくれた。大切な人だと思う。――そう思いたいだけなのかもしれないけれど」 希望的観測という自覚は、あった。ひっそりとした声で付け足して、揺らぎ掛けた視線を女へと戻す。 「死霊案内人さん、お久し振り……からの、ストップ!」 一見にこやかに手を振り掛けたヒロ子が、その手のひらを案内人へと突き付けた。 「状況は分かってる。けど、本当にそれがあなたのしたいコト?」 「…………」 視線は真剣であり、剣呑でもあった。人の瞳と機械の瞳が一対となって、強くアザーバイドを睨み付ける。一方で杖を握る小柄な姿は、少しだけ口角を下げたまま彼女を見返した。 「彼女があなたに語った物語は、死者の魂を奪う存在じゃない。死神っぽいのは見た目だけ、迷子の魂に寄り添う存在でしょう?」 「きっと、その男の子は君を見守って、君が寂しい時に来てくれた、大切な人だと思う。そう思いたいだけなのかもしれないけれど」 ヒロ子の言葉に重ねるようにして、雷音もまたアザーバイドへと視線を移す。 「……待って、ねえ、さっきから何か勘違いしてないかい? ボクが此処で言う『男の子』だって、何で言い切れるんだい」 少々戸惑ったように静止を掛けた案内人の言葉に、ヒロ子はきょとんと瞬いた。 「違うの?」 小首を傾げるようにして、フードに隠されたアザーバイドの顔を窺おうとしながら尋ねる。 それに対してアザーバイドは、おどけた素振りでひょいと肩を竦め、そっぽを向いた。口角を持ち上げて皮肉めいた笑みを浮かべる。 「さあね。少なくとも、ボクが最初から『ボク』だったのは確かだよ」 「それじゃ違うとは言い切れないじゃない」 「正解とも言い切れないけどね」 惚ける小柄な黒衣姿とヒロ子が暫し、睨み合う。 「良いわ、ともかく! 私の中では男の子なの!」 「あ、開き直られた」 軽口の応酬を切り上げたヒロ子へと、アザーバイドは少々不満げにぼやいた。 それを聞き流して彼女は希代子の手を取り、こっち、と少し離れたベンチまで導く。戸惑い顔の女は元より、アザーバイドもその様子を眺めるだけで、口を挟む事はしなかった。 賑やかな遭遇から一転、束の間広がった沈黙を裂くように、靴音がカツンと夜空に響く。 「さて――死霊案内人だからあの女を連れて行く?」 少し距離を置いた希代子を一瞥し、その視線をアザーバイドに移しながら『神堕とし』遠野 結唯(BNE003604)は目を細めた。 黒い装束の腰元で、鎖が擦れ合い、チャリチャリと鳴りながら月明かりを返して揺れる。 「たわけ、死んどらん生者を連れて行こうとするな。この馬鹿者が」 サングラスのブリッジを指で上げ、低く吐き捨てる。紺色をした双眸が鋭く胡乱に、アザーバイドを睨め付けた。 「お門違いもいい所だ。連れて行くのはあくまで死者の魂、間違っても生者ではない」 「それをしがない『アザーバイド』であるボクに言うのかい?」 鋭い視線を一身に受け、案内人は楽しげに声を揺らがせた。 大仰な身振りで両腕を広げ、子供のような素振りで首を傾げる。 「……何が何でも連れて行く気か」 「さあ、どっちだろう。試してご覧よ?」 アザーバイドは不敵に笑い、剣呑な視線が交差した。 ● アザーバイドの動きは、戦うというよりもまるで逃げ回るそれだった。 甘い香りを漂わせて杖を振るっても、それらの技は一つとしてリベリスタに掠めもしない。悪戯に地面を汚しては凹凸を生じさせるだけだ。それをすぐに見て取って、夏栖斗は視線をアザーバイドへと向ける。 「君は死霊案内人として、直接的に人を殺した事はないだろ?」 夏栖斗が足を止める。それに気付いて合わせるように、アザーバイドも足を止めた。フードの下の視線が彼に向く。 「だったら、なんで、今、そんなに焦ってるんだよ。自分で『死霊』を作らざるを得ないようになるまでなんで焦ってんだ?」 「なんでかって? ボクのありようは最初から“こう”なんだよ」 死霊案内人がからりと笑った。両腕を広げた拍子に杖が揺れ、ガラァン、と低い鐘の音のような音を響かせる。 「直接的に殺した事が無いというけど、ボクが剣を振りかざして相手の首を落とした事があるかっていう意味なら、そりゃあやった事は無いね」 だけど、と。 広げた腕を下ろし、黒衣は杖を構え直して首を傾げる。 「その足元に崖があると知りながら、気付かれないように唆して転落させるのも立派な殺人だと思わないかい?」 惚けた仕草で足元の地面を指差しながら、笑う。 「それがお前のなしてきた事、か」 低い声で結唯が呟く。くゆらせる煙草の紫煙を髪に纏わせ、フィルターに歯を立てて目を細める。 アザーバイドは肯定も否定もせず、取り出した板チョコレートに歯を立てた。パキン、と軽い音を立ててこげ茶色の板が割れ、甘い匂いを仄かに漂わせて案内人の口に消える。 「風見さん、思い出して。誰かに語ったことはない?」 希代子の傍らでライフルを構えながら、ヒロ子が機械化された右目を女に向けた。 「王子様を待ってるコト、迷子の魂を導く存在のコト……それを聞いていたあなたの友達のコト」 「え……」 戸惑っているのは彼女の構える銃器の所為か、それとも現状そのものに対してか。たじろいだように向けられた瞳を見返して、ヒロ子は朗らかに微笑んだ。 「もし彼が『死霊案内人』っていう定められた物語の中で雁字搦めになっているなら、それを打ち破る新しい物語を、彼に与えてあげて」 視線を前方へと戻しながら穏やかに言う。 「風見さんなら出来るって私は信じてるよ。……夢をずっと引き摺ったまま大人になって、とうとう引き返せないところまで来ちゃった、私と同じあなたなら、きっと」 「私――」 口を開いた希代子が何を言おうとしたにせよ、結局その先の言葉が紡がれる事は無かった。 焦げ茶色の腕のようなものが地面からぞろりと生えるように持ち上がり、ベンチの端だけを叩いて飛び散る。 「お喋りは終わったかい」 二人の方を向いた案内人が先程までの、陽気な声では無かった。不機嫌な子供が発するような、少し拗ねたような口調だ。 「余計な事はしないでほしいなぁ。ボクはね、現状特別な不満は無いんだ」 「君……」 「それなのにさっきから、誰も彼もが知ったようにボクの道を決めたがる」 しかし当の“敵”は、自身に銃口が向いている事など気にした様子もなく忌々しげに口角を下げていた。端から問題にしていないのか、それともリベリスタが引き金を引き切る事など無いと信じてでもいるように。 「ブギーさ。……物語を終えたあと、お前はまた一人だ」 何かを物思うような口調で、ふと夏栖斗が口を開いた。 「多分さ、誰かの願いを叶えて、その笑顔をみて。そういうの、嬉しかったんだろ」 アザーバイドの視線は、夏栖斗には向かない。ただ、握り直された杖が再び低く転がるような音を響かせる。 「まだ、終わらせる必要なんてないんだよ」 「……ふん。ボクの内心を推し量って、何か答えが得られるのかい、君は」 「お前なあ!」 子供が意地を張るような、けれどそれともまた違う気配を含んで案内人は顎を上げた。 夏栖斗が声を荒げ、大股で踏み出すとローブ姿の元へと歩き出す。 何を考えているのか、アザーバイドは動かなかった。近付いてくる“敵”に攻撃する素振りも無く、ただ口角だけを下げて彼に向き直る。少年の手が伸ばされて漸く杖を握り直した、が。 「うわっ!?」 放たれたのはアザーバイドの攻撃の一手でも、リベリスタの翳す一閃でも無かった。小柄な黒衣のフードを乱暴に引っぺがして襟足ごと引っ掴まえ、夏栖斗が大股に歩き出す。 「ちょっと、君……!」 「良いから来い!」 悲鳴を上げたアザーバイドがズルズルと引き摺られながら声を荒げたが、それもお構いなしだ。 希代子の座るベンチの前で漸く足を止めると、掴んだままの襟首を突き出すようにして『死霊案内人』の顔を彼女の前に晒す。 「なあ希代子さん、この顔、思い出せない?」 逃げようとしたアザーバイドのフードを掴み直して無理矢理その場に留める少年を、異界の住人は忌々しげに睨んだ。 希代子を一瞥した案内人がプイとそっぽを向く。しかしそれには構わずに、夏栖斗は彼女を見下ろした。 「意外と王子様、本当にいるのかもしれないでしょ? だから思い出してよ。希代子さん、君だけの王子様を」 「王子様……」 けれど、希代子の表情は芳しくない。突き付けられたアザーバイドの顔をしげしげと見詰めるが、心当たりが無いというように。 記憶というものは得てしてままならないものではあるけれど、その理由を良く知るのは案内人の方だった。溜息を吐き、肩を落として投げやりに口を開く。 「ボクが希代子と過ごしたのは精々数日なんだよ? 対して希代子はざっくり三十年だか生きてるんだし。三十年の内の数日! こんなの覚えてないのが普通でしょ」 「たった三十年位なら思い出せるかもしれないだろ!?」 「それじゃ君が三十年前に数回会っただけの人の名前を言ってみなよ。ねえほら、今すぐ!」 「三十年前は流石に生まれて無いな、俺まだ二十だし」 「あぁそうかい、それじゃ三十年後に聞きに行ってあげるよ」 「ねえちょっと、あんまり三十三十って連呼しないでくれないかしら……」 リベリスタとアザーバイドの奇妙な遣り取りよりも、そちらの方が希代子の胸を抉ったようだった。両手で顔を覆って地の底を舐めるような重たい溜息を吐く。 「だ、大丈夫か? ハンカチあるぞ……?」 雷音がそっと差し出したハンカチを受け取って目元を拭う彼女を見下ろして、死霊案内人は酷く面倒臭そうに空を仰いだ。 「もう、良い。分かった! ここはボクが引くよ、それで良いでしょ」 「まだ何も解決してないだろ!?」 「これ以上何を期待してるんだい君は!」 匙を投げるように言ってのけたアザーバイドに夏栖斗が噛み付き、異界の住人が口角を下げる。 そんな光景を見回して。 「……ま、良いか。送り返すまでが仕事だ」 ひっそりと溜息を吐き出して、結唯は構えた武器を下ろした。 すっかりと物騒さの欠如した深夜の公園を見渡して、新たな煙草を一本取り出し唇に銜えて火を点す。 空から降りてきた白雲のように、紫煙が音も無く棚引いていた。 ● どうにか話を切り上げて、急いでフードを被り直した死霊案内人が溜息と共に肩を落とす。諦めたようにも疲れ果てたようにも見える態度で身を翻すと、黒衣がはためいて広がった。 「そうだ、希代子」 ふと、アザーバイドが足を止めて振り返った。 目の前で展開された光景に平静を取り戻せないでいる女を見詰め、死霊案内人は首を傾ぐ。 「『死霊案内人』は、“これから”どうしていくんだろう」 「え……?」 虚を衝かれたように目を見開いて、希代子は少しだけ口籠ってから案内人を見返した。 「それってあなたの事じゃないの? ……それに何だか、水先案内人みたいな呼び方ね」 「そうだね。良いから教えて」 促されてまた口を噤んだ女が、少しの間考え込む。 「そう、ね。きっと……きっと、仕事を続けるんだと思う。死者が迷子にならないように、時々お休みしながら、それでもずっと」 「ふうん。――だってさ、リベリスタ」 フードの下の視線を希代子からリベリスタ達へと移し、アザーバイドは惚けたように口角を下げた。握り直した杖を肩に軽く押し当て、首を竦める。 「つまり『死霊案内人』に終わりは無いって訳。ここは引くけど……」 一度言葉を途切れさせて、アザーバイドは月を見上げた。何事か物思うような僅かな沈黙を挟み、振り返る。 「君達は甘い。いつかその内、此処でボクを殺しておくべきだったと後悔するかもしれないね」 アザーバイドの視線が真っ直ぐに結唯へと向かった。自身を殺さない事を選択したのが彼女だと、そう決定付けるように。 「だってボクは、死霊案内人だから」 その言葉に、結唯は苦々しく眉を寄せる。 「……言っただろう。それならば連れて行くのは死者の魂だと」 「ボクの定義じゃそうなっていないのさ」 だってボクはアザーバイドだから。歌うようにそう言いながら、幼さを感じさせる手が杖を地へと下ろした。 「“そこ”の常識がボトムと合致するとは限らないじゃないか」 軽々しい程の口調で冗談めかした笑い声を転がすようにして夜の公園に響かせる。 「郷に入っては郷に従え、だ」 「郷、ねぇ」 結唯の言葉を聞きながら、小柄な黒衣は答える代わりに杖の先端をとん、と地面に軽く叩き付ける。 「ボクはボトムに居座るよ、これからだって。だからまた、どこかで会うかもね……あぁそうだ、夏栖斗だっけ。これ、リオに返しておいて」 懐を探ったアザーバイドが、布の塊のような物を引っ張り出して夏栖斗へと放り投げた。 「何だこれ……?」 「そっちの制服。箪笥の肥やしになってたから借りてたんだよ」 本人は気付いて無かったけど、と付け足して笑いながら杖を引き摺ると鈍くゴロゴロという音が響き、カンテラの明かりが揺らぐ。 「今はもう、見なくても再現出来る」 「再現……? ――そういえば前に」 古い記憶を引っ張り出そうとした夏栖斗に、アザーバイドはニィ、と口角を吊り上げた。 身長や体格に相応しいだけの小さな手をひらりと振って、彼らに背を向け歩き出す。 「いつだって、秘密が物語を美味しくするんだ。……永遠に解明されない謎があっても、ボクは気にしないね」 子供に似た高い声で歌うように口ずさみ、死霊案内人は歩き出した。足音は徐々に遠ざかり、ある所でふつっと切れた。さながら魔法で消えたか、最初から存在すらしなかったかのように。 「まったく、傍迷惑な奴だったな。……それにしてもお姫様ねぇ」 振り返った結唯の視線が、値踏みするように希代子の全身を眺める。サングラス越しの視線を受けて少し仰け反る様子は気にも掛けずに、ぽんと夏栖斗の肩を叩いた。 「なら御厨にでも白馬の王子様にでもなってもらうか」 「え。俺!?」 「安心しろ、白馬と衣装は用意してやる。お姫様を口説くセリフは自分で考えろ」 己を指差して声を裏返した夏栖斗に、相変わらずの無表情で結唯が頷く。 「あ、あのう……流石にそれは不味いと思うわ。ほら私、アラサーだしね……?」 おずおずと挙手をした希代子が、結唯と夏栖斗を見比べて次第に目を輝かせた。 「それより二人の方が似合いそうよ、クールビューティな頼れるお姫様と、チャーミングな王子様で。あ、何だかイメージが湧いてきたわ」 元は夢見がちな少女だった所為もあるのだろう。目を輝かせ、希代子が手を合わせる。 その光景に苦笑して、雷音は肩を落とした。 「次はキューピッドでも現れそうだな。無理矢理引っ付けるタイプの」 「あら、その時は私が相手をするわよ! でもどうせなら相手はロボが良いわ」 苦笑の混ざる雷音の呟きを聞き付けて、どこかしら嬉々とした様子でヒロ子が手を上げる。 暗い空に、チョコレートの香りがほのかに漂っていた。 異界の住人がボトムに落とした小さな約束も、その思惑も呑み込んだまま、やがて差し込む朝日によって溶けるように消えて行った。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||











