
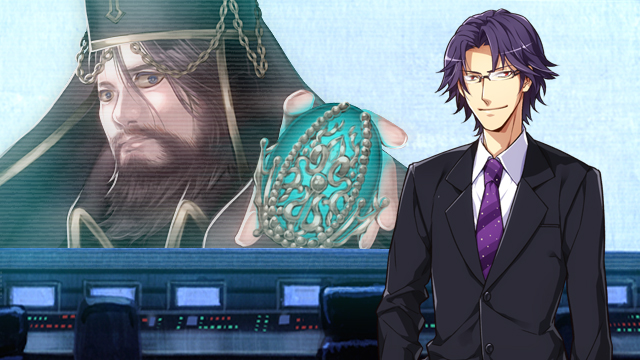

Grigorii Rasputin the Our Mutual Friend

|
●電撃戦 急な話だが、と切り出して、『戦略司令室長』時村 沙織はホールに集まったリベリスタ達をぐるり見回した。 ここには、たまたま三高平近辺に居た、ある程度以上の実力を持つリベリスタが根こそぎ集められていた。無論、たまたま遠出していた者達にも、この場の内容は届けられる手筈になっている。なってはいるものの、これから説明される内容を鑑みれば、まずは彼らが主力となるだろう。ある意味では時間との戦い、なのだ。 そして、そのムードは集められたリベリスタにも伝播していた。ざわめき。戸惑い。熱気。ホールを騒がしいほどに満たしていたそれらは、沙織の第一声を耳にしてぴたりと止まる。 「此処に集まった諸君に、アークから海外旅行をプレゼントしたい。行き先はロシア、首都モスクワだ。新潟でなくて残念な奴も多いと思うが、まずは話を聞いてくれ」 ウィルモフ・ペリーシュの暴虐は、リベリスタ達に否応もなく『敵』を感じさせていた。おそらく、今日集められたのはその対策だと考えていた者も多いだろう。この場で口にされた唯一のジョークは、そんなぴりぴりとした雰囲気を和ませる一定の効果があった。――北の地で待ち受ける危険を考えないようにすれば、だが。 「昨日、ラスプーチン配下の土御門・ソウシから接触があった。手土産はラスプーチンの本拠地と、その狙いだ」 ソウシが『夢魔』の一族であり、奪われた至宝『夢見る紅涙』と『天使の卵』を取り戻すため、ラスプーチンに従っていること。 三高平に残された『夢見る紅涙』に掛けられた封印の解除の鍵は、『研究開発室長』真白・智親(nBNE000501)の死であること。 先の三高平襲撃の真の目的は、全ての戦力を陽動として、市内にいくつもの潜入拠点や結界に護られた非探知区域を確保し、多数のスパイを潜入させることだということ。 このままペリーシュのと決戦に臨めば、間違いなく漁夫の利を狙って動くであろう、ということ。 そして、ラスプーチンの本拠地がモスクワの地下迷宮であり、彼はその最奥にある儀式場に固執し、死守するであろう、ということ。 「知っての通り、ラスプーチン勢力の一翼であるKGBは暗殺と破壊工作のプロフェッショナルだ。こいつを放置してペリーシュとやりあうなんて、とてもじゃないが御免こうむりたい」 故に、機先を制して本拠地たるモスクワを攻め落とす。辿り着いた着いたシンプルな結論を口にして、沙織はグラスの水を含んだ。 「不幸中の幸いか――ペリーシュは動く気配を見せていない。いつ動き出すかは判らないが、こちらとしては片付くまでは待ってくれ、と祈るしかないな」 いずれにせよ、両方を同時に相手取ることは事実上不可能だ。加えて、わざわざ工房である『塔』を攻めるより、出てきたところを迎え撃つほうがまし、という事情もある。ならば、少しでも急ぎ、確率の高い方に賭けるより他にない。 「国内フィクサードも、今は仕掛けては来ないだろう。あいつらはアークとペリーシュが共倒れになることを望んでるんだ、互いに潰しあう前にわざわざ火傷しにこようとは思わないだろうさ」 それに、と続けた沙織のもたらした情報は、集まったリベリスタ達を驚かせた。曰く、海外の有力リベリスタ組織が、次々に日本へと援軍を送り込んでいるのだ、と。 「『オルクス・パラスト』、『ヴァチカン』に加えて、世界のビッグ4の残り二つ、『梁山泊』と『ガンダーラ』も有力な戦力を送ってくれている。本来は対ペリーシュが目的だが、今回は状況を鑑みて、ラスプーチン戦の間の日本の防備も請け負ってくれることになった」 この四組織が一同に会することなど、そう滅多にあるものではない。ありていに言って、大抵の事件や組織相手なら、オーバースペックもいい所である。それは、かの魔導師が世界の『脅威』と目されていることの、端的な証左であった。 「しかも、今回は『スコットランド・ヤード』が気合の入った援軍を申し出てくれた。KGBの本分が暗殺と諜報なら、ヤードの得意技は捜査と監視だ。三高平のスパイ狩りは、彼らに任せて問題ないだろう」 本拠地の護りすら他組織の助けを必要とし、加えて運頼みの色が強い作戦である。誰もが他に道がないかと考えたのは、むしろ当然のことだろう。そして、その誰もが別の道など思い知っていた。 「援軍も含めた総力を挙げても、ペリーシュに届くかは怪しい。そして、ペリーシュと戦いながら、智親を守り抜くなんて芸当は、それ以上に絶望的だ」 そう言い切った沙織の言を否定できる勇者など、どこにも居なかったから。 「綱渡りなのは百も承知だ。けどな、頼むぜ、リベリスタ」 そして、頼むぜ、と言うより他になかった沙織を責められる者など、どこにも居なかったからだった。 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:弓月可染 | ||||
| ■難易度:VERY HARD | ■ イベントシナリオ | |||
| ■参加人数制限: なし | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2014年12月10日(水)22:51 |
||
|
||||
|
||||
|
●大迷宮/1 ずん、と。 振り返ったときには、背後に続いているはずの道はもう消えていた。 「……たまりませんな、これは」 肩を竦める敏伍は、しかし口ほどには疲れた様子を見せてはいなかった。モスクワの地下に広がるのは、刻々と変貌するダンジョン。だが、その変化が全くのランダムであるはずはなかったから。 「なんだかワクワクするなぁ、こういうの」 一方、行動を共にするセイは意外なほど子供じみた感想を漏らす。誰の印象にも残らないように『育てられた』青年は、しかし今、アークの一員としてこの戦場に足を踏み入れることを愉しんでいるかのようにも見えた。 「しかしなんですかね。伝説の中の人物が生きていると、却って凄みを失うものですね」 人の倍の速さで老い朽ちていくだけだった自分と、永遠を求めてあがくラスプーチン。自らの出自に思いをはせながら、敏伍は影の式を作り出し先へと歩ませる。この迷路には何らかの意図、ないしは法則があるはずだ、と。 「まぁ、ぼちぼち始めようか、密偵の仕事を」 独り言をさらりと流し、セイもまた影人を生み出した。彼の下僕に命じられたのは、踏破してきた後方の安全確認。決して大げさではなかった。入り組んだ曲がり角は、容易に敵の姿を隠すだろうから――彼の危険を察知する力をもってしても。 土御門・ソウシの手引きによって、リベリスタ達はクレムリン宮殿の三つの隠し通路から同時に突入していた。彼らが初手から戦力を分散し、幾つもの分岐を総当りで塗り潰すかのように埋めていった大きな理由は、一箇所に戦力を集中し、寡兵で足止めを食らうのを防ぐためである。 「……フン。あの床、怪しいんじゃねぇの」 ウィリアムが二丁拳銃を前方の床に向け、一度ずつ引鉄を引く。跳弾となって甲高い音を立てるかと思われた鉛弾は、しかしウィリアム以外の想像を裏切った。 「幻影、か」 鼻を鳴らす。聞くところによれば、この大迷宮はKGBの縄張りだという。いけ好かないあの連中ならば、こんな小細工も納得できるということか。 「まおが行きます。大丈夫です」 ぺたり、天井に張り付いた影がもぞりと動く。吸い付くように天井と壁を這い回るまおにとっては、床に仕掛けられた落とし穴など何の障害にもなりはしない。 「まおは早く日本に帰りたいです。だからまおは、ロシアでのお仕事をきっちり頑張ります」 穴の向こう側に渡り、ひゅんとコードを伸ばす。壁の突起に絡みついたそれは、即席の手すりとなって仲間達をこちらへと運ぶのだ。 「ありがとよ――ほら、先に渡りな」 下層へと攻め込む役を担う戦友へと、ウィリアムは男臭く笑いかける。儀式場まではエスコートする。先は頼むぜ、と。 「危ねえっ!」 少年が先行する少女の首筋を掴み、乱暴に引き倒す。次の瞬間、ぱららら、という軽い音と共に、銃弾が彼らの頭上を引き裂いていった。間一髪で同僚を救った福松は、短く口笛を鳴らす。 「ありがとっす。礼は後でたっぷりと!」 だが助けられたアイカは振り向きもせず、全身の発条を利かせて飛び起き――いや、そのまま一足飛びに敵への距離を走り抜けた。フィクサードが正しく状況を把握した時には、もう彼女は目の前だ。小柄な少年に引き倒されるほど細い身体。そのどこにそんな力が眠っていたのか、アイカの拳が男の腹に勢い良く叩き込まれた。 「覚悟はいいっすか。ぶちのめしてやりますよ」 教えてあげる。平気で他人を踏み躙る奴が安穏に生きていられる程、現実は優しくないのだと。気合迸る背中。それを眼で追った福松は、しかし気配を尖らせる。 「舐めるなよ、オレにペテンが通用すると思うな」 愛銃を向けるのは、一件何もなさそうな壁。少年らしからぬ修羅場を潜り抜けた眼光が放つ鉛玉よりも鋭い殺気。と、張り詰めた空気に臆したか、『隠れていた』男が壁の中から飛び出して。 「別にドラマは求めちゃいねぇ。だがな――啖呵くらい切らせろや」 振り下ろされた刃を、福松は黄金の銃身で受け止めるのだ。 「幸蓮ねー、まいと一緒に行くですよ!」 その二人をかすめるように、嵐が戦場を駆け抜ける。がりがりと鳴る刃の鎖が縦横無尽に振るわれ、不運なる男に鮫の牙を突き立てた。食い破る貪欲な歯が、血の色に染まる。 「ふふふ、お任せあれですよ! ねーのことはまいが守るのです!」 「ああ、頼りにしている。妹、前は頼んだぞ」 テンションの高い妹に苦笑するように、しかし心からの信頼を籠めて幸蓮は頷いた。 無論、自分も妹も、並み居る強敵に伍しきれるとは思ってはいない。だが、蓄えた魔術の知識を用いて迷宮の探索に加わり、仲間達を支えチャンスを作る。戦闘支援に特化した彼女にとって、それこそが戦場であったのだ。 「アークの逆襲とアシュレイ女史の呪い、どちらも受けて貰うぞ」 黄金の左目に力が宿る。周囲の仲間達に伝えられるのは、この場の全てを掌握し、最適な防御を導き出す戦闘官僚の技術。再び放たれた敵のマシンガンは、此度も空しく宙を穿つ。 「この一戦にアークの未来有り! 皆の者、恐れるでないぞ!」 震源の時代かかった口調は、生まれ変わりと称する武将を意識してのものか。手にした符を四方に飛ばし、喝、と気合を入れた。瞬間、符に囲まれた空間にどろりとした気配が忍び込み、フィクサード達の手足を絡め取る。 「後ろにはワシがおる。皆存分に戦うがいいっ! わーっはっはっは!」 「えっと、でも、無理はしないでくださいね?」 正しく戦場の気分に浸る震源の大声に、困ったように笑う辜月。柔らかな雰囲気を保つ彼が告げた言葉は、仲間達へというよりも、半ば行動を共にする凛へと向けられていた。 「難儀な事だらけだな。まぁ、ぼやいても始まらないが」 その凛は、ここまで辜月や他の後衛陣の『盾』として振舞っていた。一度ならず負傷しては辜月に癒され、心配げな視線を向けられるのだが――それが彼の矜持であり自負であるのだから退く事はない。 「俺は護るべきものを護るだけだ。無いよりマシ程度だがな」 全てを救う、という理想論に興味はない。常に目の前のものを護り続けるだけだ――そして、だからこそ彼は歯噛みするのだ。己の力不足に。自分に、まだ伸び代があるということに。 「頼りにしてますけど……、てせも、無茶は禁物ですよ。先は長いですし」 再び辜月が祈りを捧げれば、涼やかな風が戦場を吹き抜け、凛の傷を癒していく。魔道書を胸に抱いて、鬼謀神算の少年は微笑んでみせるのだ。 「吹っかけてくれた喧嘩はきっちり買うよ。ついでに落とし前もつけさせる!」 狭い通路では少人数の殴り合いになるだけに、後方支援が勝負を分けがちだ。前衛同士は拮抗。されど、援護射撃や回復は圧倒的にリベリスタの側が厚く、そうして綻びた敵陣を黒き風車が蹂躙するのだ。 「立ちはだかるなら叩き潰すまでよ」 命を刈る黒き風車とは、フランシスカの握る骨の剣か、それとも漆黒の六枚翼か。告死天使より溢れ出る昏き瘴気が、惧れを知らぬ戦士の剣気を伴って、通路を塞ぐフィクサードどもを呑み込んだ。 「KGBだかなんだか知らないけれど、道を空けないなら等しく粉砕するわ!」 「ハロウィンで一緒に歩いた迷路とは大違いだなぁ……」 あの夜待っていた桜の花弁は、今は少女の髪に光るのみ。南瓜迷路とはあまりにも違う、悪意の迷宮。ただ涼と共に歩いている、というそれだけが共通点だったから、アリステアはそっと溜息をついた。 「やるしかない、と言うのが因果なところだな」 色気の欠片も無いが、と涼がおどけて見せたのは、彼女の内に芽生えた恐怖を敏感に感じ取ったからだろう。自分が傍にいるからこそ頑張っていられるアリステアの思いを逆手に取っているようで、内心舌を打つ。 「アリステアがいてくれて助かっている……んだがなっ!」 せめても、と告げかけた、平凡でけれど心からの台詞。だが、言い終えるより早く、涼はセメントの床を蹴っていた。向かう先には、奇襲を仕掛けるべく姿を現したフィクサード。 「確実に数は減らさせて貰わないとな」 袖口には透明の狂気、マントには漆黒の殺意。我は正義なりと傲慢なる断罪を掲げ、涼は駆ける。不可視に等しい一撃が敵の先手を取り、無数の斬撃を叩き込んだ。 「後ろ! 通路が消えていくよ、傍迷惑な……!」 そんな彼にかけられるアリステアの声。敵の反撃が涼を襲うと予期して詠唱準備に入っていた彼女は分断の可能性に思い至り、恋人の背後へと身を寄せた。 「仕掛けのある迷路ですか……面倒ですねぇ」 後続のイスタルテが眉を顰めた。涼が暴いた幻影は、壁という不変の安全地帯すら最早トラップになり得るということの証左である。つまり、注意を払わねばならない警戒範囲が、一気に前方向に広がってしまったということだ。 「注意して進みましょうね」 治癒はアリステアに任せて良いと判断し、イスタルテは翼を大きく羽ばたかせた。凍て付いた風が魔力を放つ渦を成し、前方に現われた敵増援へと殺到する。 「こんだけわらわら来てるんやもん、下への道はもうそろそろや」 夕奈が細めた目をす、と開ければ、目つきの悪い三白眼が現われる。割烹着が醸し出していた親しみやすい雰囲気はどこかに消し飛んで、この場を生き抜くという決意と、今の自分を保護するアークを延命させるという本心が顔を出す。 「せいぜいここで目立とかな。目立ってたくさん誘き寄せられれば万々歳やもんな」 にぃ、と浮かんだ酷薄な笑みは戦場を支配する差し手のそれ。自らの持つ戦術を惜しげもなく分け与え、夕奈は手にした紛い物の玩具を弄ぶ。 「わたいらの仕事は、儀式場に行く人らがここを素通りできる様にする事――しっかり気張るっすよ」 「言われなくてもなっ! オラッ、邪魔だどきやがれっ!」 後衛からの援護を受け、突貫する一悟。出し惜しみはしない、と決めていた。そんなことが出来るほど敵は弱くはなく、そんな余裕を許すほどこの大迷宮は甘くはない。 「どかねぇってんなら……ぶち抜いてやる!」 全力で突進し、拳を振り抜いた。高速移動によるソニックブームを纏ったその一撃は、防御の隙すら与えず敵の鳩尾を捉え、勢いのままに吹き飛ばす。 「行け行け、どんどん先に行けーっ! オレ達の分までぶっ飛ばして来い!」 自らの役目は下層攻略部隊の露払い。そう言い切った彼は、しかし大舞台で喧嘩する楽しみを取られまいとするかのように、嬉々とした表情を浮かべていた。 ●工場区画/1 「待たせたな悪党ども! あたしが来た!」 どこぞのアメコミヒーローばりに比翼子が叫べば、全身から放たれた強い光が眩く周囲を照らす。私を見ろ、とばかりの目立ちっぷりは、占星団の騎士達にとっては大いなる侮辱。敵中に突っ込んだ彼女に、たちまちの内に剣と槍とが殺到する。 アシュレイがおいてったナントカがほしいから三高平滅ぼしたりする、というざっくりとした理解すら三歩で忘れた彼女は、もはや自分が誰と戦っているのかも良く判っていないのだが――まあともかく、足で掴んだ二本のナイフで受け流すにも限界があった。 「喰らえ我が奥――痛い痛い串焼きはやめてっ」 「もう少し我慢なさいな。面制圧といきましょう、骨禍珂珂禍!」 亜婆羅の胸に在って全てを見通す一ツ目が、骨と月の加護を受けて怪しく輝いた。無造作に弓弦を引き放てば、魔力の矢が弾幕となって騎士とゴーレムどもに降り注ぐ。 (悪くないわねぇ……熱くって素敵よ) 唯一素肌を見せている唇を、にぃ、と吊り上げる。ここまで仲間に送り届けられ、そして仲間を送り届ける礎となる、それはどんなに甘美な喜びであろうか。 「あたしの世界の彩りに加わりなさい。さあ骨にしてあげる!」 「……、なんかアークって本当に凄い事になってるよね……」 見かけよりはずっと常識人なのだが、それはそれとして外見はインパクトのあり過ぎる亜婆羅。やや離れた場所から彼女を横目に呟いたシンシアは、自分が異世界からの来訪者であることを完全に棚に上げていた。 「でも、今まで乗り越えてきたピンチは、そんなことよりもっと凄かったから」 引き下がる訳にもいかないから全力でやるよ、と気持ちを切り替えるシンシア。そんな彼女に、遥けき世界の境界を越えて世界樹エクスィスが加護を齎す。 「結果として、ここまでアークは人気を得たわけだ」 押し掛けられる事は多々あるが、逆に押し掛けても歓迎されるとは、と皮肉げに言い放つ結唯。彼女にしては珍しい軽口ではあったが、ストイックなまでの無表情はいつもの通りである。 「なら、せいぜい盛大に歓迎してもらおうか」 「できれば戦いたくないけど、ね」 彼女の長い指の先、蓋の開いた黒き銃口より五月雨のように銃弾が吐き出され、術士を、あるいは山羊頭のゴーレムを喰らう。シンシアの希った刃への加護は結唯にも与えられていたから、術士を優先して狙うのは当然の判断であった。 「数が多いな。そこを退け!」 焦れたように疾風が前に出る。全身を覆うスーツ、その肩からは既に輝けるオーラが噴出していた。マフラーのように鮮やかな紅い光の表すものは、唯一つ純然たる闘志。 「この不毛な戦いに終止符を打つ! さあ、正義の使徒達よ、運命に抗えッ!」 光放つ刃をぶん、と一振り。衝撃波と共に放たれるのは、敵するもの全てを穿つ意思の弾丸。あの三高平での戦いと同じくゴーレムによって為された城壁が、がらがらと崩れていく。 「さっきの迷路もえぐかったけど、ここもシュールだねっ」 実に軽く言ってのけた終が、瓦解しつつある『壁』に喰らいつく。笑むように細められた隻眼が、これ以上はないほどの瞬間を捉えていた。疾風の壁崩しの直後、他のリベリスタに先駆けて切り込む事が出来るタイミングを。 「さ、張り切っていこう! まだまだ儀式場までは遠いからさ」 二振りのナイフが生み出すのは、時をも凍らせるほどの神速の斬撃。巻き込まれたゴーレムに為す術はなく、ただ氷の欠片となって散るだけである。 「一回くらいで終わるだなんで思っちゃやーよ?」 そして追撃。壁を突き崩す破城槌の様に城壁を貫く終の後を、一人では行かせぬと仲間達が続く。 「たまには外に出ないと体がなまるからな。運動を兼ねて、ボクはボクのできることをやるとしようか」 小太刀二刀流を引っさげて、美しい黄金の九尾が跳ねる。緊張感を見せない秋火。もちろん、その大言に見合うだけの腕を持っているからこその自身であることは言うまでもない。 「まあ、色々不憫だったなと言う他にないが――ボク達もそんなに暇じゃないんだ。そんなわけでね」 燃え上がる紅の瞳。秋火が二刀を振るうたび、取り囲む山羊人間達が動きを止め、崩れ落ちていった。先行した僚友に劣らぬ超高速の刃が、無慈悲に敵を蹂躙する。 「ボク達もそんなに暇じゃないんだ。凍てつきそして刻まれて滅びろ!」 「ふにゃ、こっちのは何に使う装置なのかなぁ?」 「あまり触ったら危ないですよ、シーヴ」 この階層が魔法技術の粋を集めた工場プラントであるということは知っている。だから、不用意にぺたぺたと触って回るシーヴがどうにも危なっかしくて、メリッサはまた眉根を寄せた。 「気を引き締めていきましょう。何があるか判らないのですから――こんな風に」 突如物陰から現われたゴーレムを、彼女の細剣が貫き通す。 突然の遭遇にも慌てず、流れるように構え、衝く。ただそれだけ、けれど何千何万と繰り返したその動きが、この時、彼女の真の剣であった。 「今宵の二丁拳銃は血に餓えているのですっ」 物騒な台詞を甘ったるく言ってのけ、シーヴもまた両手の拳銃、その引鉄を引く。既にメリッサによって致命傷を受けていたゴーレムは、その銃弾に耐えられず、崩れ落ち溶けていった。 「えへへ、メリッサおねーさんとなら百人力なのですっ」 「私も、シーヴと一緒なら心強いです」 抜群のコンビネーションを見せる二人を始めとして、広いこの区画を何人ものリベリスタが捜索していた。モヨタとナユタ、まだあどけなさを残した兄弟もそのうちの一組である。 「最悪の置き土産だよな。だからあいつは信用ならないつったろ、ナユタ?」 「だって、あんなキレイな人がこんな酷い事をするなんて思わなかったもん……」 少し得意げに言ってみせるのは大人になりかけの幼さ故か。肩を落とす弟を従えて、兄のモヨタがコンテナの立ち並ぶ一帯へと足を踏み入れる。動くものなき視界に、ここも行き止まりか、と踵を返しかける二人。その時。 バタン、と何かが倒れる音がした。 振り返った二人の視界には、口を開いたコンテナ。そして、その中から次々と姿を現したフィクサード達。山羊人間の姿はない――ということは、あの一人一人が自分と対等以上の実力を持っているという事だ。 「コンテナ置き場だ。応援頼む!」 アクセス・ファンタズムに一声叫び、しかしモヨタは次の行動に迷う。増援が来るまで耐えることができるか? 背後の弟を考えれば、逃げるべきじゃないのか? だが。 「にーちゃん見てて! オレの方が役に立つから!」 妙なところで意地を張ったナユタが、そう言うなり周囲のマナをかき集めていた。兄が止める間もなく撃ち出されたそれは、火炎の雨となってフィクサード達を先制する。 「ああもう……ナユタ、兄ちゃんの剣さばきをよーく見てろよ!」 逃げる機会を失った、と理解して兄は頭を抱え――しかし悩むのを一瞬で終わらせる。いずれにせよ逃げられないならば、いっそ切り抜けて見せるまでだ。 「言ったな!」 戦意を全身に巡らせ耳のパーツから光を吹き上げて、モヨタは敵の騎士へと斬りかかる。無論、フィクサードも無抵抗ではなく、彼は二つ三つの傷を負うことになるのだが――。 「お待たせしました!」 近場に居た別チームが駆けつける。やや甲高い少年の声が聞こえると同時に、二人を取り囲むフィクサード達の脳裏に強烈なノイズが走った。 「ボクには護るべき仲間がいるんですっ!」 かつて拒絶だけを供に生きて来た三郎太は、アークで仲間という存在を得た。だからこそ、アークの存在を危うくする存在に対して容赦はしない。 集中などさせはしない、と放ち続けられる思念波は、彼の覚悟の現われである。そして、頭を抱える敵の只中へと涼子が割って入るのだ。 (頭のいいひとは大変ね。いつまでも生きるとか、それを助けるとか) アンティークの拳銃を二丁。それだけを携えて、彼女は死地へと赴いた。やろうと思えば距離を取った射撃戦に持ち込むことも出来たろうが、現実、彼女と敵との距離はゼロである。 「今は、気にくわない何もかもをぶっ飛ばして進む、だけ」 彼女のスタイルも装備も、全てが攻撃に特化したものである。忙しく動き回り、むしろ自分を囮にするような振る舞いを繰り返す彼女は、まさしく捨て身といってよかった。 「わたしみたいのは、ひとつのことしか考えられない。……ふたつ考えたら、覚えてるつもりで忘れてくのさ」 色彩のない声で言い放ち、引鉄を引く。放たれたのは弾丸ではなく黒きオーラ。敵を喰らい自らも喰らう大蛇が、フィクサード達を飲み込み顎にかけた。 戦いが戦いを呼び、戦場を生み出す。双方の戦力が集結した結果、この広いプラントルームは第二層有数の激戦地となっていた。 詰みあがった機械類やコンテナは、防衛線を敷く絶好の拠点である。そこに拠って遠距離攻撃の火線を築くフィクサード達。この段階に至っては、攻め手たるリベリスタ側も射手や魔道師が主攻を担うことになる。 「入り組んだ地形と多数の防衛戦力。やっかいですね」 呟いた修一が、同じくコンテナの陰に身を隠す修二へと頷いた。上よりはマシだがこっちも面倒な作りになってやがる、と毒づく双子の弟は、機械化した左手にエネルギーを集中させる。 「ペリーシュのヤツが陣取ってやがる以上、日本を長く空けるわけにはいかねえしな」 「効率的に敵を排除し、日本に戻らせていただきますよ!」 修一の右手もまた、既にオーバーロードで赤熱しかけていた。彼の声を聞いた修二は大きく前方に掌を広げ、鋼の指より無数の気糸を走らせる。一拍遅れて、修一も気糸の束を放つ。 「あのお方の悲願の為に! 命を押しまず防げ!」 「悲願…ですか」 だが、畳み掛けられる攻撃を必死に受け止めながらも、『我らの友』占星団は未だ高い士気を誇っている。応、と唱和する声。それを聞いて、ミリィは殊更に表情を消していた。 「それに、どれだけの価値があると言うのでしょうね」 ぽつりと添える彼女は、しかしその振る舞いからは想像もできないほどの思考の奔流に精神を委ねていた。レイザータクトの本領たる攻防に渡る戦術補助。既にその展開を終え、あとはこの場の敵を無力化するばかり。だが、それが相当に困難なことだと、彼女自身も良く判っている。 「……、私は私の役目を果たす。今はただ、それだけです」 ならば、と。彼女は一人のリベリスタに戻り、フィクサードを叩くことを決めていた。アイボリーのタクトを小さく振れば、神の恩寵、白き閃光が彼女の元へと強い光を齎した。仇為す者の肌を灼く聖別の光が敵に降り注ぎ、少なからず彼らの動きを鈍らせる。 「此度の戦いも負けられぬものなのは確かだ」 セッツァーはよく通る声を響かせ、その音律に魔力を乗せる。いや、響き渡る声が引鉄となり、周囲のマナをほとんど力づくで励起させるのだ。 「ならばこそ、か。私は『声』(うた)の力を信じているのだよ」 声の質が変わる。朗々たる音程はいまや圧縮された高速詠唱となり、ボルジアの秘術を体現する災いとなってフィクサードに猛毒を撒き散らした。 「さあ、箱舟の仲間達よ。私の『声』が道を開く」 しかし、その時。 騒々しいプラント内を、リベリスタ達のよく知る声が朗々として駆け抜ける。 「騒がしいと思って来てみれば、随分と気張っておるのう」 姿を現したのは、鋼の鎧を着込み大剣を手にした、菫の髪の女騎士。 「儂も参るとしようかの。撃ち合いばかりも退屈じゃろう?」 エイミル・マクレガーが、獰猛なる笑みを浮かべていた。 ●精神と時の儀式場/1 「こっちから積極的に攻勢に出るというのも、珍しいですねえ」 戦場の中にあって思考を巡らすのは、暗殺者として培った余裕か。そう一人ごちた黎子は、横合いから振り下ろされた棍棒を紙一重で避けたかと思うと、とん、と床を蹴った。 次の瞬間、彼女の姿が幾重にもぶれてぼやけ、まるで分身したかのように何人もの姿を象る。その正体は超高速のステップによる残像だが、しかしただの幻でもない。驚くべきことに質量を得たそれらが、紅と黒の双頭鎌で敵を薙ぎ払う。 「……いや、出ざるを得ない、言うべきですか」 そんなに長生きしたいものでしょうかね、というのは彼女の率直な感想だ。魂が磨り減って消えるまで生きて、何がしたいのだろう。 「種族という仕組みは、淘汰と多様性を根幹にする……それに個体の死は不可欠よ」 一方、ティオの言い分は、黎子と似ているようで意を異にする。群体思想とも呼ぶべき彼女の価値観は、ラスプーチンの在り様を非合理と片付けていた。 「誰も死を否定してはいけない。友の死が我らを進化させる――人類の為に彼は淘汰され、その悠久の礎となるわ」 上層で見た錬金設備しかり、ここ第三階層の儀式場手前から仕掛けられている多数の魔力増幅術式しかり。魔術知識に造詣の深い彼女にとって、この場所は宝の山である。神秘が詰まった大いなる財産だわ、と目を輝かせる彼女は、この成果を引き継ぐ為にラスプーチンを殺すことを改めて決意していた。 「殺しても死なない、って有名な話だけど」 せめて観光の時間くらいあれば、と口を尖らせるのはご愛嬌。あどけない少女の姿をした離為は、しかしその外見ほどに柔らかな存在ではなかった。 憎悪が形を成し、黒い鎖を創り出す。じゃらりとフィクサードに捲きついたそれは、一切の容赦なく彼の首を締め上げた。程なく、じたばたともがく動きは止まり、だらりと垂れ下がる。 「残念だけど、引き摺り下ろすのは得意だ」 あるいは背に負った劫火の翼すら、他人を拒む象徴なのか。部屋を護る最後の敵を仕留めた彼女は、行きましょう、と閉ざされた扉を指で示す。 一際大きな扉。この先に待つものを予感させるそれを、何人かの前衛が押し開けた。ぎぃ、という蝶番の音。そして、開いた隙間から流れ出す、圧倒的な魔力。 「ついに、此処まで来ましたか」 そこは、ただっ広いホールであった。足を踏み入れた者を驚かせるのは、床に壁に空間にと張り巡らされた、青い光線による魔法陣。積層型立体魔法陣と呼ばれるそれは、大規模儀式を行う際に欠かせないものである。魔術の知識を修めた者は、ほぼ全員がこの陣の精緻さ、流れる魔力の膨大さに唖然としていた。 「アークの皆さん。こうなってしまった事は全くもって不幸としか言いようがありませんが――」 何重もの護りの向こう、グレゴリー・ラスプーチンという人物の異才を改めて示すばかりの高難易度魔法陣。それが明滅したかと思うと、次の瞬間、リベリスタ達は一様に『何かが変わった』感覚を受けていた。例えば、それぞれが持つ『運』を吸い取られたような。 「――断言しようではありませんか。最後に生き残るのは、私達『我らの友』占星団であると」 「それはこっちの台詞だ!」 スコープで照準を合わせもせずに、木蓮が無造作に小銃を撃つ。幾度も放たれた弾丸は弾幕を形成し、護りを固めるラスプーチン配下へと吸い込まれていった。 「精神的に死ぬってことは、人間としての欲求も楽しみも何もなくなるってことだよな。それは確かに嫌だ。けどな」 なおも吐き出される弾丸。ネックレストップ代わりの指輪が反動で飛び跳ね、木蓮の肌を叩く。 「だが理解は出来ても許容は出来ない。せめて人間として死のうぜ、グレゴリー・ラスプーチン!」 「黙れ不埒者!」 ラスプーチンその人が何かを口にするより早く、その配下がいきり立つ。思えばこの台詞こそが、戦いを開始する号砲であったのだ。 「やっぱりモスクワまで来ると少し寒いねえ。これが終わったら、何か暖かい物でも食べに行こうかね」 金色の鎧に身を包んだ付喪が、暢気な台詞を吐いていた。いや、これはむしろ諧謔の域か。兜の眼の部分より覗く眼光は、決して緩んではいないのだから。 「さて、反撃の時間だよ二人とも。……借りは必ず返す。人間関係の基本だからね」 よーく覚えておきな、と念押しした声に、あれは他人の気がしないのですよ、と九十九が混ぜっ返す。いつもの通り球体の仮面を被る彼は、そう言ったかと思うと、まるで散歩するように平然としてその身を敵の只中へと投じた。手近な一人を打ち据えたのは、この世全ての呪いを煮詰めてみせたような呪詛の苦痛。 「まあ死ぬのが怖いと言う気持ちはよく分かります。私だって怖いですしのう」 いささかすっとぼけた物言いを続ける九十九。と、次の瞬間、苦痛に顔を歪めていた敵騎士が、今度こそ苦痛のあまりに叫び声を上げた。 「楽しいなあ、もっと絶望した顔を見せてください、ね?」 那由他・エカテリーナこと珍粘が、どこか虚ろな瞳に嗜虐の色を映していた。既に石化した身体で逃げることも出来なくなっている騎士は、流れ込む無限の苦痛に耐えかねて遂に精神のブレーカーを遮断する。 「あの髭の方はいまいち好みじゃないんです。これくらいは役得ですよね」 「若いのが頑張ってるのはいいが、あんたはもうちょっと大人しくしな」 苦笑いの付喪は、手にした魔道書を媒介に詠唱を開始する。もっとも、圧縮詠唱を極めた彼女にとっては、詠唱というよりは呼吸の間ほどの時間のこと。 次々に身に喰らいつく魔力の棘の反発に飄々と耐えながら、彼女は天空より星を落とした。とはいえここは地下、虚空を通って隕石をこの場に喚ぶのだが。 「奴への道を切り開くのは任せな。全部吹っ飛ばしてやるよ」 自信満々に言い放った付喪。彼女に続き、血気盛んなリベリスタ達が突撃を開始する。 「なぁ、あんたらに直接恨みや憎しみがあるわけじゃないんだ」 ただ一振りの剣を道連れに、風斗は多くの敵を――つまりは神秘を、人々を苛む理不尽を斬ってきた。その彼からすれば、一度は講和を求めた相手と剣を交えるのはどうにも座りが悪い。 だが。 「けどな、俺の街を、友達を傷つける理由があんたの不老不死ってのは、どう考えても釣り合い取れないんだ」 輝ける大剣に導かれるように、彼は限界を超えた身体能力を引き出していた。彼を押さえ込んでいた迷いも、微塵に砕けたかつての矜持も、とうに吹っ切っている。 今は、ただ一振りの剣。 「あんたの生き足掻きに、他人を巻き込むな!」 振るう剛刃が、掲げられた盾ごと騎士を断ち、手酷い傷を負わせる。なれど、周囲からも復讐とばかりに次々と得物が突き入れられるのだ。彼独りで戦線を維持するなど、夢見事である。 「どうせ、風斗さんは猪突猛進に突っ込むと思っていました」 いや。 彼は独りではない。向けられた敵意を身軽なアクロバットでいなしつつ、うさぎがぴったりと横についていた。 「すまん、これにケリ付いたら飯奢る!」 「期待しないで待ってます」 手には輪だけのタンバリン。鈴とシンバルの代わりに波打つ刃を備えたそれは、いまやうさぎの代名詞となったユニークな武器である。けれど、人殺しの暗器としか考えられないそれは、決して無制限に振るわれてきたわけではない。 「実の所、あの御仁に忠誠を捧げている理由を知りませんが……なるほど、忠誠心は本物と見えます」 ならばこそ、うさぎは見定める。自分が請けるのは汚れ仕事。誰かがしなければならぬことだと信じられる仕事。 そういうことだと言い訳が出来る仕事だけなのだ。 「よろしい――では、諸共に死んで下さいな」 手近なフィクサードに握り込んだ刃で斬りつけ、怯んだ隙に距離を詰める。とん、と左手で胸を突けば、それで一丁上がりである。練りに練った不可視の爆弾は、宿主に気づかれる間もなく派手な音を鳴らして散るのだ。 「ラスプーチン殿は娘御がいらしたと聞いている。無論、その子も、またその子もだ」 美しい翡翠の髪の下、血の様に紅い瞳の中で、瞳孔が大きく縦に裂けていた。その主であるターシャは、ラスプーチンの子孫を命を全うした証と呼んだ。 「何故ここまでして、命を伸ばそうとするのか分からないよ」 ヴィルデフラウの末姫が突き出した掌から迸る、真空の刃。不可視の凶器は空間を渡り、蛇神の眼が睨む先、ローブの術者へと牙を剥いた。 「争わない道もあったはずですが……こうなってしまってはどうにもなりませんね」 ラスプーチンその人を巡っての戦いだけあって、攻防共に気合の入り方が違っている。早くも出始めた重傷者を横目に、セラフィーナは闇断つ業物を正眼に構えた。 「全力で倒しに行きます。貴方達に勝ち目はありません、投降しなさい!」 翼を一杯に広げ突っ込んだセラフィーナ。魔法陣を構成する光が瞬く中、彼女は周囲の空間を『斬った』。時間すら切り刻む一閃が氷の刃を生み、周囲の敵へと襲い掛かる。 だが、そのことごとくは敵の肉へと到達する前に儚く溶けて消える。魔法陣の青い光がフィクサード達を包み、降り注ぐ魔術的な攻撃を退けているのだ。 「ならば、これならっ! さあ、私と踊りましょう!」 無論、彼女もそれで引き下がりはしない。魔術的な防護であれば、物理的に刺せば良いだけのこと。敵に攻撃の間を与えることなく、今度は光の速さすら越えた神速の突きを繰り出してみせるのだ。 「別な道があったかと言われれば難しい。貴様らに信を置けたかというのもあるしな」 結局のところ、手を結ぶのは難しかったと惟は思っている。何よりも、『夢見る紅涙』に呪詛を施すことをアシュレイに許した時点で協力体制が瓦解するのだ。今にして思えば、という部分もあれど、賭けに出るには危うすぎる。 「それにしても、朽ちる事のない精神、それを得て何を為したかったのだ?」 単に生きることそのものが目的ということに思い至らないのは、『理想の騎士』たらんとすればだろうか。そんな疑問を胸に抱きながらも、黒銀の剣を大きく振るう惟。溢れ出る黒いオーラは彼女の得物が帯びていたものか、それとも暗黒の瘴気が形を成したのか――。 「我らが主をお守りせよ! 儀式を邪魔させるな!」 攻勢に出るリベリスタ。だがもちろん、ラスプーチン一党の反撃も苛烈である。術士団が詠唱を終えれば、炎の矢や隕石の槌が次々に降り注ぐのだ。そして、足が止まってしまったその時を狙い、騎士達が逆撃をかける。 「俺達に立ち止まっている時間は無いんだ。それがたとえあの怪僧だとしても」 それら騎士の重突撃を身一つで受け止める快。常より防御のプロフェッショナルと目されている彼だが、それにしても今日の気迫は目を見張るものがあった。 「押し通らなきゃ、その先の未来は掴めない。なら、堂々押し通ってみせるさ」 その理由が背後に立つ一人の少女であることに、もはや疑う余地はあるまい。快にもまた気概があり、意地がある。甘いヒロイズムが男を強くするのは、全く当然のことなのだ。 「人呼んで――守護神。罷り通る!」 ならばこそ、以前は気恥ずかしくも感じたその称号を、今は自分のものとして名乗れるのだ。愛する者を、そして仲間を守り抜く力、その自負があるが故に。 (土御門・ソウシ。君に聞きたいことがある) 一方、極技とすら称される智謀で戦場をコントロールし、仲間達を有機的に連結することに雷音は腐心していた。快によって完璧に守護された彼女は、まさに難攻不落の司令塔。そんな彼女は、一人リベリスタに混じって攻撃を仕掛けるソウシへと思念を寄せる。 (夢魔とは上位世界から因子をうけた少数種族なのか? もう、アークに敵対することはないのか?) (……余裕だな、あんたは) 返ってきたのは苦笑の波動。なるほど、戦いの帰趨を握る鉄火場で今するには、あまりにも唐突過ぎる――或いは場違いな質問である。 (君は神出鬼没だからな。訊ける時に訊かなければ機会がない) (なるほどな。まあしかし、詰まらん答えしかないけどな。夢魔はあんた達フライエンジェと同じ意味で一つの種族だし、敵対するかどうか、答えは判りきっているだろう?) はぐらかされたかとも感じたが、いや、と雷音は思い直す。この期に及んで、アークをだます意味も、裏切る利益も存在しないのだ。 (もうひとつ、君のスキルを学ばせていただきたい。この先を見据えて) (ああ、いいぜ。見合う対価が払えるんならな) 人を食った答えに棒を飲み込んだような表情を見せる雷音。なるほどその通りだろう。彼ら夢魔とアークとはある条件について取引しただけで、『この先を見据える』ような同盟関係にはない。 (……もっとも、アレは夢魔だけの秘儀だがな) そして、付け加えられた一言に、彼女は自分が乗せられたと知るのだ。 「もっと平和的にいければよかったんだけどね……」 小夜香は一身に祈りを捧げていた。既に疲労は激しかったが、まだ余裕は残っている。何より、この戦場が短期決戦で終わるであろうことを彼女は十分に承知していた。 「慈愛よ、あれ」 それは神降ろしの秘儀にも似ていた。陳腐な表現だが、『奇跡』が起こったのだと周囲の誰もが理解するほどの荘厳なる空気が戦場を支配する。 高位存在の顕現。 祈りという名の召喚に応じてこの世界に現われたそれは、そこに在るただそれだけで凄まじいまでの影響を齎した。瞬く間に癒されていく傷。もちろん、戦場の趨勢を支配するほどのインパクトがある術式であるが故に、小夜香に与える負荷も並ではないのだが。 「男の嫉妬は見苦しいと言うやつでしょうか?」 というより元々向いてなかったのでは、と敵将を揶揄し、七海は革紐を巻きつけた翼で大きく弓弦を引いた。もし弦打ちをしたならば、きっと素晴らしく響く鳴弦となったであろう。だが今は、彼自身の羽根より作られた矢が番えられている。 「まああれです。落とし前はつけないといけません」 魔法陣がまた明滅しているのを確認し、解き放つ。びぃん、と鳴る音は空打ちよりも力強く、まさしく邪を射抜く雷鳴の風格。一射が無数の稲光と化して何人もの敵を貫いた。 「この弓鳴りからは、決して逃れられませんよ」 そう言い切った七海の支援を受け、一人の男が突貫する。血に塗れた深い真紅。血を吸った巨大なる得物。破壊を体現するパワーファイター――ランディが、一対の双斧を縦横に振るい、嵐となって征くのだ。 「結局その辺の凡俗と一緒で、テメェが死ぬのが怖ぇだけだろうが」 これほどの力を持っていて、やっている事は結局自己保身の延命に過ぎない。せせら笑えば良いと判っている。だが、彼の内側を満たすのは怒り。彼を荒れ狂わせるのは――。 「いや、そんな偉そうなモンじゃねぇな」 ――どうにもこうにも癇に障る。 それでいい。赤い戦鬼が戦う理由は、それだけでいい。 鎖で繋がれた双斧が、鎧甲冑に身を纏った騎士の壁を食い破る。或いはゼロからの決闘であったならば、決着はまだ遠かったろう。だが、七海をはじめとした後衛陣の援護は既に敵陣を崩しており、小夜香をはじめとした回復役の支援は過保護なほどに厚かった。 そして何より、ランディという災厄は、彼が抱く衝動は、一度の襲来で消え去りはしなかったのだから。 「恐れるより挑め、凡愚め。そして戦え!」 再びの烈風が、ついに敵の戦列に埋めきれない穴を開ける。無論、未だ人垣は厚く、求める雄敵への道のりは長い。 けれど、彼の視界には、黒衣の導師がはっきりと捉えられていたのだ。 ●大迷宮/2 「正直、あれと同時に相手というのはぞっとしないわね」 高伝導素材に置き換えられたシナプスと、高い処理能力を備えた義眼。サングラスを外した彩歌の視界は、魔道と機械の大迷宮をサーモグラフィのように映し出す。 既にアークの本隊は第二層以降に侵攻していた。それでも少なからぬ数のリベリスタが未だ探索を続けるのは、後背の安全を確保する、という一点に尽きる。 比較的掃討しやすい第二層と違い、第一層は通過できても制圧する事は難しい。未だにフィクサードの数は多く、そして敵将と想定されるセルゲイ・グレチャニノフも確認されていなかったのだ。 「……、そこ」 小声で囁いて、足を止める彩歌。緑のLEDが明滅する論理演算機甲を抱くようにして、機械の脳との間に膨大な演算を行き交わせる。果たして、その角の向こうには。 「貰った!」 現われたのは都市迷彩に身を包んだ一団であった。狭い道を三人で塞ぐようにして並び、めいめいの得物を手に躊躇うことなく突貫する。前衛も後衛も無く蹂躙しようというその気迫。 「賞賛に値する雄敵よ。だが、指揮するものの居ない香駒の突進に過ぎん」 立ち塞がるは雷慈慟。少人数戦闘の粋を極めた彼は、この地形であの陣形を採るメリットもデメリットも知り尽くしている。つまるところ、それはリベリスタが多くの小隊を分散させたのと同じ理由だった。 「後顧の憂いは前線のもたれ。まずは足場の確保する!」 彼を中心に渦巻く思考の圧力は、横隊の突撃をただ一人で留め、押し返す。そこに被せられる彩歌の精神波。胡乱な意識に苛まれる敵部隊を、更なる火力が迎え撃つ。 「よう、KGB。俺も近接戦闘訓練なんて二十年ぶりだが、ちょっと付き合ってくれや」 本人の言は謙遜か。長らく第一線を離れていたとはいえ、遥平の実力は折り紙つきだった。それでも不満を残す辺り、かつての実力はそれ以上だったのだろう。 「刑事部と公安部らしく、仲悪く行こうじゃねぇか」 長年連れ添った相棒とあってか、古びた銃把は手に良く馴染んでいた。日本の警察に制式採用されたことのない機種ではあるが、それでいい、と彼は思っている。警察は、常にドラマで描かれるような正義の体現者でなくてはならないのだから。 「俺をやらなきゃ止まらんぜ。食いついてこいよ、俺という餌に!」 銃口から放たれるは目も眩むほどの閃光。電撃は竜の如く敵陣を蹂躙し、その悉くを消し炭に変えんと暴れるのだ。 「チコの目の前では誰も傷つけさせないのだー!」 これほどの火力を抜けてくる敵も、チコーリアが居るならば惧るるに足りぬ。未だ幼い彼女を凄惨なる戦いに連れてくることに胸が痛む者もいないわけではなかったが、彼女自身はあっけらかんとしたものだ。 そして何より、その実力は決して馬鹿に出来ないものだったのだ。足手まといと自分を呼ぶ少女が、謙遜を超えて卑下と感じられたように。 「らすぷーさんには同情しますのだ。だけどイヴパパは殺させないのだ!」 それは純粋にして明快なる戦意。自分の大切な人々を護る為、少女は親指の傷の痛みに耐える。流れ出た血が媒介となって、黒鎖となり敵陣へと押し寄せたのだった。 地下第一層の戦いは、概ねアークの優位に推移していた。しかし、少人数による遭遇戦である以上、ある程度の被害は免れない。 とはいえ、未だ無傷の部隊も存在していた。 「にょ、にょー! ぐわーっ!」 喜び勇んで曲がり角の向こうへと突っ込んでいった六花が、痛いのを一発貰って逃げ帰ってくる。その後をぞろぞろと追ってくる、フィクサードの皆さん。 「あの子供が派手に引っかかれば、他の連中の参考にはなるけれど……」 敵を連れてきちゃダメじゃない、と溜息をつく真名。乱と輝く瞳はどこか胡乱な彩を湛えてはいたが、それでも立ち上る魔力は、彼女もまた一角の能力者であることを示していた。 「あらあら、うふふ。あの子供を助けるのは合点がいかないけれど…… 威勢のいい事ね、と爪を一薙ぎ。吹き出す敵の血が、血よりも尚鮮やかな紅玉を汚す。その後ろに駆け込んだ六花を癒す、一陣の涼風。 「ナナシさん、お願い……力を貸して」 胸に抱いた魔道書は、あの時以来依子に答えを返すことはない。それを寂しくも思う彼女だったが、力を注げば増幅する機能は残っている。ならば、いずれ『彼』を元に戻すことも出来るのではないかと――彼女は、そう思うのだ。 「うにょー、ありがとーよりよりー!」 危険な目にあってもめげない六花は、どうやら再び突っ込む気満々らしい。その様子に、依子ははぁ、とため息をつく。 「危険察知しながら進むことも、必要なのよ……」 「小難しい事言ってアタイをけむにまこうとしても無駄なのだ!」 周囲を引きずり回すのが彼女の常だ。紋章の浮き出た拳を振り回し、残念さを醸し出しながらもすーぱーひーろーは突撃する。 「皆の為に頑張ってるアークを攻撃するとか悪いやつなのだー!」 駆け抜けながら発動するのは、火球を放つ大魔術。勢いだけで突っ走る少女は勢いだけで攻撃をぶち当て、ついでに自分まで焼いていた。 「ぐわーやられたー」 「……やられてないから落ち着いてね」 呆然とその様子を見ていた智夫が、気を取り直したようにフォローに入る。紡ぐ詠唱は神聖なる祈り。天上より舞い降りた妙なる音色が、六花の放つ生命の躍動に呼応する。 「さあ、行こう。迷宮はまだ深いから」 智夫の可愛らしさもここに集った猛獣達には興味のないこと。立ち上がろうとするフィクサード達を凸凹三人組がタコ殴りにするのを眺めながら、現実を逃避した眼で呟く二十歳の冬であった。 一方、そんなお気楽なことは言っていられないチームも多い。その筆頭は、敵指揮官セルゲイと交戦した彼らであろう。 「――舐めるなよ」 小雷と共に侵攻していた者達は皆、意識を失い倒れていた。セルゲイに従っていた護衛は維持と気合で排除したものの、セルゲイ自身には大した手傷も与えられていない。 「俺だって、リベリスタの端くれだ」 不意打ちでは無かった。彼の持つ野生の勘はそんな卑劣を受け付けない。だが、そんなことは問題にならなかったというだけだ。認めよう、彼は強い。 だが、それとこれとは話が別だ。このままおめおめと逃げ帰ってなるものか。ぎり、と奥歯を鳴らす。包帯を巻いた拳を、血も流れよと握り締める。 「威勢のいいことです」 ナイフをくるりと回すセルゲイ。軽やかな動きは、次の瞬間に少年を絶命させよう。それだけの技量の差があった。 ――だが。 「見つけた。前回受けた傷のお返しをさせてもらうよ!」 たたたたた、と響く足音は頭上から。壁を蹴り天井を駆けて、アンジェリカはセルゲイへと迫る。蝙蝠の羽を模した刃が薄暗い天井から舞い降りて、幾つもの残像を従えながら敵将へと挑みかかるのだ。 「くっ……ならば、これでどうです」 すぐ傍に迫る少女の目を覗き込む。カッと注ぎ込まれる眼力。それは、彼が長年の諜報生活で身につけた篭絡術であった。不意の揺さぶりをかけてやれば、並みの能力者など思いのままに操れる。 だが。 「それがどうしたの? 絶対逃さないよ!」 ただ一人の面影を追う少女は、まやかしの支配などものともしない。舌打ち一つ、バックステップで交代するセルゲイ。そんな彼の足跡を、白黒二色の十字刃が追いかける。 (怖がらせたくないから……死ぬわけにはいかねぇんだよ) 思考が乱暴になることを自覚する聖。緊急信号に従って駆けつけたものの、よもやセルゲイその人とは思わない。背に隠した少女が震えを隠せないのは、気配で判っていた。 ――終わったら、一緒に珈琲を飲みましょう? ――ええ、とっておきを用意しますよ。 それでも。 あの意地っ張りな少女が、怖いと明かしてくれた。それでも、終わったら、と気丈な姿を見せてくれた。ならば――。 「――これくらいのピンチで、弱音なんて吐けねぇな」 手元に戻った十字剣をもう一度投げつける。天と罰の無骨なる二刀。組み合わせて投擲とは大雑把だが、彼の腕前はそう簡単に逃げることを許さない。 。 「わたしが護りますから、今は前に進むことを考えて」 「ええ、大丈夫よ」 続いて小雷が殴りかかるのを視界に収めながら、シュスタイナは男の背中に微笑んでみせた。あるいは、微笑むように努力した。 黒き翼をはためかせ、魔力の嵐を叩きつける。けれど、自分が攻撃に回るのはこれが最後だろう。次からは癒しの御業をもって支える番だ。 初めて癒しの力に感謝できそう。そんな気持ちを抱いた時、ふ、と自然に笑みが浮かんだ。大丈夫、怖くない。 ――この人は死なせない。絶対に――。 壁に叩きつけられたのは、最後まで抗った黒翼の少女。ようやく意識を失ったか、血のラインを引きながら彼女はずるりと崩れ落ちていった。 「この辺りもようやく打ち止め、ですか」 双方とも、幾度もの増援を磨り潰していた。累々と倒れ伏すリベリスタとフィクサード。存外に私の部下も情けない、と首を振る彼に、ようやく駆けつけてきたKGBエージェントが声をかける。 「このまま掃討に向かわれますか」 「いえ、猊下の指示はアークの数を間引くこと。我々は十分に戦いましたよ。それに――」 もう、ラスプーチンには未来がない。 今回の襲撃を退けたとしても、リベリスタ勢力はアークだけではない。例えばヴァチカンの猟犬は、必ずこの根城へと攻め寄せてこよう。 「――徐々に警戒態勢を落とし、大勢が定まった時点で離脱します。準備しておきなさい」 「……はっ」 その言葉通り、セルゲイ・グレチャニノフはこの戦いで命を落とすことなく、生き残りのエージェントを率いて姿を消した。諜報のプロの本気を見せたか、懸命の追跡にも拘らず、以降の足取りは杳として知れないという。 ●工場区画/2 対ラスプーチン攻撃部隊の第三層への侵攻を受け、第二層に残留したチームは徐々に一つの点に集結しつつあった。その場所こそ、エイミル・マクレガーも参戦する最大の激戦地――『我らの友』占星団の呼び方で言えば第六プラントルームである。 「死に瀕した老人は見苦しい物ですね」 もはや老害が極まったようなものです、と諭はせせら笑う。その彼は後方に座して、常の如く何体もの影人形を量産していた。 「穴蔵に籠もってこそこそと動き回る相手は、さっさと燻り出してしまうのが一番です。さあ、差し入れをしてあげましょう」 その台詞は即ち配下への号令に等しい。居並ぶ影人が次々に火砲を放つ様はまるで千巻の一斉射撃のようである。むろん、その中でも最強の砲塔は、諭の抱える『実物』であることは論を待たないが。 「今際の際に、熱く燃え上がって果てなさい」 「ひゃあ、派手にぶちかますっすねー」 蛙のレインコートを羽織った少女――仕上が、まるで花火を見るかのように言ってのける。剣林弾雨のこの戦場で暢気な台詞を吐けるあたり、流石は剣林の係累といえよう。 「まあ、敵の陣地に殴り込みとか室長殿も十分派手っすけどねー」 無論のこと、その方針も彼女には心地よい。いずれ最強の頂を目指すとするならば、戦いを避けることなど出来ないのだ。 それに。 「何より、此処でケリを着けとかなきゃ、すっきりしないっすよ」 三高平で戦った女騎士がこの場に居るという。ならば殴りこみに行かない理由などありはしまい。 「さあ、仕上ちゃんの為に道を開けるっす!」 何度目かの突撃は、彼女の燃え盛る右腕を幕開けとして始まった。その背後にぴたりとつくのは、仕上とは別の意味で極まったバトルジャンキー――いやさ殺人鬼。 「きゃっほー! ブラックモアちゃんの呪いってやっぱりファンキーでキャッチーでしょ!」 絶対に潰し合わずにはいられない最低最悪の策謀。塔の魔女の呪縛を、だが葬識はちょおクール、の一言で肯定してみせる。 「まさにアークホイホイ! 釣られちゃうの不可避! さっすがー!」 異形かおをほの鋏を振り回しゴーレムを薙ぎ払っていた彼は、自分に向かってくる騎士の姿を目にして顔を綻ばせた。 「やっぱりナマモノ優先だよね! 俺様ちゃん働き者!」 騎士の槍を掻い潜り、ハンドルを握った鋏の長刀を一閃。だが手応えは軽く――これは楽しめそうだと舌なめずりをしてみせる。 「坊ちゃま、あの様に若づくりし囀る女を好ましいとは思ってはいけません」 美しいメイド姿の少女、葵が遠くで哄笑を上げるエイミルを指差し言い聞かせるように告げる。 「清廉潔白素敵な女性を愛せるまでは、わたくしが誠心誠意お仕えさせていただきます」 「清廉潔白……ねぇ、此処に来てまで何を言ってんのか、葵さんは」 一方、説教を受ける駿河は困り顔である。好む好まないの問題ではなく、敵とあらば慈悲無くぶった斬る。それだけの話のつもりであった。 「ええ。ですから、この様な所で死んではなりません」 「ま、それはお互い様だ。生きる為に今を足掻こうぜ!」 一つ年上の従者に照れたような笑みを見せ、駿河はその場から姿を消す。いや、目にも留まらぬほどの加速でフィクサードへと突進し、身に纏った衝撃波で騎士を弾き飛ばしたのだ。 「主を護る事こそが従者の本懐だというのに……」 そして葵もまた彼を追って駆け、行く手を遮る大男を瞬間の加速で翻弄するのだ。一方で、後方からの攻撃が途切れることはない。火箭飛び交い癒しの秘術が惜しげもなく放たれる中で、一際光っていたのはシエナの援護であった。 「これも、生への執着の……形?」 彼女が求めしは『生きる意味』。それを探す為に死の充満する鉄火場に赴くのはある種皮肉ではあったが、いや、だからこそ得られる真実もあるのかもしれない。 「なら、知りたいって、目に焼きつけておきたいって思う……よ」 いずれにせよ、ここは戦場で、彼女は戦わねばならなかった。だから、彼女は今必要であろう術式を、ぽつり、詠唱する。 「――構成展開、型式、稚者の煽情――composition」 空間に僅かな違和感が満ちる。それは、精神をささくれ立たせ正常なる判断にほんの少しの志向性を与える、それだけのものだった。 もっとも、彼女自身の技量は最精鋭に比べれば一歩を譲る。故に、敵フィクサードの殆どは何らの影響をも受けなかった。より強く働いたのは――。 「集めていく……ね、できるだけ」 山羊頭のゴーレムが、彼女目掛けてひしめき合う。もちろん、彼女はかなり後方に位置していたから、その奔流を受け止めるのはラインを築く前衛であったが。 「なるほどっ、今度はこっちを一網打尽にしようって事だねっ?」 周囲から投げ入れられる手榴弾。次々爆ぜる閃光に得心したらしきルナが、ゴーレム溜まりに幾つもの火弾を投げ入れる。フィクサードに混じり壁を作っていた山羊頭が、加護を剥がれ炎に包まれてみるみる溶けていった。 「皆にはまだまだ頑張って貰わないといけないもの。こんな奴らは私達に任せて!」 ウィルモフ・ペリーシュとの戦いが控えている以上、ラスプーチン戦は被害なしの完全勝利でなければ割に合わない。何時までも不安の種を抱えている訳にはいかない、と彼女はまた詠唱を始めるのだ。 「隠れたり潜入したりするのは、向こうの人の方が何枚も上手だったみたい」 それは、正面衝突に持ち込めればアークに分があるということの裏返しに他ならない。そんなことを考えながら、このように戦いの中に身を投じて冷静で居られるようになったこともまた『変化』なのかもしれないとアルシェイラは気づく。 「永遠の、命」 少なくとも、彼女は未だ、かつてのラ・ル・カーナのように永遠なもの、完全なものを見つけ出してはいない。おそらく、どこにもそんな物はないのだろうと気づいている。 「きと、そう認められることが、強さだから」 だから、永遠を求め続ける事は歪みしか生まないのだと――火球を降らせながら、アルシェイラはそう思うのだ。 「泥臭いまでの執念には感服する。だが、こっちも面倒が控えてるんでな」 墓標の如き巨大なる銃を鈍器代わりに振り回し、剥き出しになった術士に狙いをつける喜平。コンテナを垂直に上り、安全圏だと油断しているフィクサードを一足の射程に捉えて。 「雑魚には雑魚の勝ち筋がある。わざわざ強い相手に立ち向かう必要もないんでな」 非常に珍しいことに、彼は愛銃を本来の用途で用いた。即ち、近距離で敵を狙い銃弾で穿つために。 「其の夢……粉砕させてもらおうか」 轟音と共に放たれた銃弾が、術士のどてっぱらに風穴を空ける。二発、三発。続け様に銃声が響くたび、男の肉体は引き裂かれ、そして糸が切れた人形のようにぱたりと倒れるのだった。 「ハッ! ゴミだけあって良く燃えらぁ!」 両腕に宿るは決して消えぬ劫火。火車の殴打をまともに食らったフィクサード騎士が、全身に回った炎を消さんと地面に転がった。 「そびえ立つクソみてぇだな。行きがけの駄賃にしてもセコくて笑っちまうぜ!」 その鋭い視線の先には、大剣を縦横に振るう女騎士、エイミル・マクレガーの姿があった。 「お前も大差ないだろうがよ。みっともなく帰っても、飼い主が強くしてくれんだから世話ねぇな!」 「ハハッ、若い者は元気が一番じゃの」 内心はどうであれ、口汚く罵しる声を聞いて、エイミルは実に楽しげに笑った。激闘に継ぐ激闘、周囲を固めていた配下を数を減じ、いまは彼女自身が複数のリベリスタと渡り合っている状況だ。 「ねえさんご機嫌麗しゅう! お互いコウモリには振り回されっぱなしの結果だね」 「なに、土御門の坊主なら、今でなくてもいずれ裏切っておったろうの」 唐竹割りに振り下ろされる大剣を、夏栖斗は二本のトンファーでがっしりと受け止める。だが、上から押さえつけられている状況でリーチの長い蹴りを避ける事は出来ない。エイミルの鉄靴が彼の腹をまともに捉え、手ひどく蹴りつける。 「……っ、落としどころはもう、戦うしかないのかな?」 「無論じゃ坊主。次は殺す気でかかって参れ」 判っていて僅かの希望を乗せた優しい問いは、だがにべも無く返される。判らず屋、と組んで投げを打つも、受身を取られ大したダメージはなさそうだ。 「ああ、ようやく決着をつけられるんだ。とっとと喧嘩を始めようぜ!」 曇ることなき白銀の篭手に氷雪の凍気が宿る。雷の如く荒ぶり炎の如く燃え盛る猛が、今は一本の鍛え上げられよく研がれた一振りの日本刀のように、見るものの視線を奪う武技を披露していた。 「喧嘩はよ、ビビッた奴が負けるんだ」 拳が強かに打ったエイミルの左肩が、音を立てて凍り始める。ちっ、と猛を振り払う女騎士。同時に、義手から有刺鉄線のように伸びた茨が彼の肉を裂き、手ひどいダメージを与えていた。 だが、そんな反撃をものともせず、第二第三の刃が彼女を襲う。 「何度も何度も、攻め込まれてこっちはいい迷惑だ」 凄まじい切れ味を誇る直剣が、飛び散る光の飛沫のような幻影すら生む速さで突き入れられる。もっとも、本来この剣は剣先がない。刺突には向かない剣ではあるのだが――。「いくぜ、決着をつけてやる」 遣い手たる劫は、存在しない剣先で敵を突くほどの強烈な概念をこの剣に与えていた。すなわちそれは、敵対する者は容赦なく討つという強靭なる覚悟の故に。 「日常よ、止まれ――俺は誰よりも君を愛している!」 戦士達に囲まれるエイミル。そんな彼女を、紫月の神弓が僅か数メートルの位置から狙っていた。遥か遠くの的を魔力の矢で射抜く彼女にとって、この距離はもはや零に等しい。 「流石に本拠地というだけあって、厄介で護りの堅い場所でしたが……」 大弓を引く彼女の手には、何らの矢も番えられてはいない。だが、弦が美しく描く半月に輝ける光芒が重なり、一本の光矢が生み出される。それは、限界まで凝縮された彼女の魔術の粋。 「問題ありませんね、突破させていただきます!」 放たれた魔矢は真っ直ぐ飛んで、女騎士の胸を射抜く。鎧の表面で弾け貫くことまでは出来ずとも、それは決して無視できぬ衝撃をエイミルに残すのだ。 「少々数を揃えた所で、俺達の足を止められると思うなよ」 流れるような連続攻撃。そのラストを務めるのは、アーク随一の歴戦の剣士たる拓真だ。右手には正義を左手には栄光を。『不完全』なる二振りを携えて、彼はラスプーチン旗下最強の騎士へと挑む。 「障害は全て斬り拓く! それが我が剣の真髄だ!」 祖父の面影を胸に、拓真は征く。己の正義を貫き、より多くを助けられる道を選ぶ為に――。 「俺は、俺が正しいと思う事を貫き通す。この命、果てるまで!」 全力を超えた全力。はちきれんほどに太くなった腕で振るう双剣が十字の斬撃を見舞う。確かな手応え。取った、と確信する。 だが。 「――Beannach leibh」 眩い光。エイミルを囲む四人を突然に襲う浮遊感。埃っぽい床に叩きつけられ、全身を衝撃と痛みが貫いて、初めて彼らは自らの身体が魔力によって編まれた幻術の茨に縛められていることに気づくのだ。 「く……ここまで儂が追い込まれたのも、久しぶりじゃのう」 無論、エイミル自身も無事で済んでいるわけがない。リベリスタ達の集中攻撃を受け、さしもの女騎士も相当な傷を負っていた。未だに余裕めいた笑みを浮かべることが出来るという方が、いっそ驚くほどである。 「意地と矜持で負けるわけには参りません! 私が傷つけ、私が癒やす!」 五芒星のシールドを展開した凛子が、裂帛の気合と共に強く念じる。詠唱らしい詠唱を伴わず、ただ自身の在り様を示す決まり文句だけで上位存在の首根っこを掴んだ凛子は、一際深いダメージを負っていた猛へと神の恩寵を齎して。 「守るものが相容れない時に争いは起きる……悲しい事ですね」 「それでも、少しくらいの祈りは届くものでしょう?」 いらえを返す海依音。現実は祈りよりももう少しシビアで、故に護る事は出来ても争わないことは難しい。それでも、そんな風に答えることか出来る様になったのは心境の変化故か。 「神様、これはアークの為に戦うのであって、永遠の美貌とか考えてないですよ」 茶目っ気を混ぜながらも曲がりなりにもシスターらしく祈りを捧げ、黒く塗り潰された杖を掲げた。たちまち全身より放たれた光が、断罪の刃となって周囲のフィクサードやゴーレムを舐め、加護を剥がし取る。 それでも、周囲のフィクサード達はエイミルを中心に固まるべく動き出す。しかし、再びの乱戦か、と思われた、まさにその時。 「え……、ええっと、頑張りますよ……!」 彼らの頭上より降り注ぐ火の雨。魔道書を抱えた澪の詠唱が導くままに、全てを燃やし尽くす劫火が暴虐の限りを尽くす。 それは、今もって怯えている少女の姿からは想像もできないほどの威力であった。そして、フィクサードへの牽制を見事に果たした彼女が作った、その弟が駆け抜ける。 「助かる」 「これでも、私おねえちゃんですから……!」 臣はこの時を待っていた。あの時斬れなかった相手。非才なる身が到達した、ただ一つの業だけを磨き上げるという在り方が通じなかったこと。 だが今回は違う。負けるわけには行かない。この超重の剣を、二度と受け止められたりはしない。 蜂須賀示現流、その粋の全てがここにある。馬鹿の一つ覚えと謗られようとも、この一撃こそが才なき彼の意地であり矜持であった。故に、それを粋と表現して何ら差し支えはなかろう。 「チェストォォォオ!」 丹田に力を籠め、一足の元に振り下ろす。一般人には持ち上げることすら適わない大業物は、重力を味方につけて加速し――。 「しゃらくさいのう!」 ガ、と鈍い音を立て、必殺の斬撃はその義手に止められる。臣の顔が無念に歪んだ。ああ、けれど、次に聞こえたのは、ピシ、ピシピシ、という硬いものにひびが入る音。 一瞬の静寂。そして、左腕の義手は粉々に砕け散る。無論、エイミルは腕を砕くや否や次の行動へと移っていた。即ち、臣より距離を取り、体勢を立て直すべく。 「君の覚悟、矜持。まさしく騎士と呼ぶにふさわしい」 だが余裕は与えぬとばかりに斬り込んできた蜂須賀の長姉が、エイミルを容易には下がらせない。 「君のそういう頑固さや無骨さは非常に好ましい。けれど、私も逃がすわけにはいかなくてね」 矜持なき凶戦士だがお相手いただけるか、と朔は告げた。無論、返事を聞くつもりなどなく、妖気立ち上る長刀を一息に振り抜いた。 「儂にも意地がある。そう簡単にはこの首はやれんのう」 だが、身を掠める凶刃に構うことなく、彼女もまた大剣を突き入れる。それは意志の力と身体に備わった膂力との双方を爆発させた、引導の一撃。唯の一撃で朔を両断せんほどの傷を見舞い、エイミルは昂然と朔を下がらせる。 「よぅ、前より調子いいぐらいじゃねーか! 心配して損したぜ!」 勢いを止められた蜂須賀の一党に代わり、乱入するツァイン。剣と盾とを柔軟に用い、格闘術じみたカウンターでエイミルの左腕を落とした男である。 「はっ、小僧が大口を叩いておるのう」 「俺の全力はこの前見せた、今度はアンタの番だ。見せてくれよ、その剣技を!」 一度は見切った斬撃。だが、今のエイミルの剣速はつい先日の戦いを遥かに上回る。互いの得物に神気を纏わせ、激突するスコティッシュとアイリッシュ。そして。 「――お見事」 エイミルも無傷ではないが、力押しでツァインを跳ね除ける。だがそこに、新たなるクロスイージスが殴り込みをかけるのだ。 「片腕を飛ばされても失われない忠義、天晴れだ」 右手には輝ける槌を、左手には代名詞となった盾を。侠気の体現者たる義弘は、全力をもって戦いに挑む。 「意地と侠気にかけては、負けるつもりはないぞ――!」 あらゆる悪を許すまじ。あらゆる魔術を逃すまじ。祝福に満ちたオーラを纏わせたメイスが、限界まで引き出した義弘の腕力を乗せて女騎士の胸甲を打ち砕く。 「――ふん、ここまでかの。まあええ、愉快じゃったわ。……しからば我が君、おさらばじゃ――」 それが致命傷となったか、血を吐いて倒れたエイミルは幾許かを呟いて、動きを止める。愉快げに唇を歪めたまま、眠りにつく彼女。三度アークを相手取り戦い抜いた女騎士の、それが最期であった。 ●精神と時の儀式場/2 「……そうですか。逝きましたか……」 戦いの最中、何事かを感じ取ったのかラスプーチンが天を仰ぐ。それが文字通り階上の方向を向いているのだと理解できる者は、勿論本人を除いてはいなかったのだが。 「こうではない決着があったのかどうか……今更ではありますけれど」 そんな感傷を置き去りにして、戦いはただ只管に加速する。ファウナもまた全てを割り切れず、けれど流れのままにこの場に立っていた。 精鋭の騎士達が装備する対魔装甲すら届かぬ炎獄を生み出し、なれどどこか戸惑った風情を隠せないのは、やはり彼女が完全世界の出身だからか。志願してきたとはいえ、未だ彼女は自らの変化の意味を理解してはいない。 「いずれにしても、今は決着をつける。それだけです」 一方、悠月は現状を完全に『割り切って』いた。それは人という種のならい故か、それともファウナよりも少しばかり長い実戦経験が齎すものか。 「個人的には、こういう結果になったのは非常に残念です」 彼女の圧縮詠唱は、高等魔術すら一瞬の内に成立させる。息をつく間に高まっていく魔力。喧騒に塗れた戦いの中で、奇妙に響き渡る呪詛の音階――。 「他に道が無いならば――貴方の下した死の予言、貴方自身の上に成就させて差し上げます!」 悠月の全身に鋭い痛みが走ると同時に、不協和音が鳴り響く。溢れ出したる死と苦痛と破滅のメロディ。一体が騒然となる中を、戦士達は攻め立てる。 「クレムリンの地下にこんな大がかりな施設を作り上げているとは、灯台下暮しも良い所ですね」 この巨大な迷宮施設に、驚きを隠せないユーディス。彼女と共に戦場を駆ける必中の槍は、既に幾人もの騎士を散らしていた。 術師の集まりかと思いきや、少なからず武人の類も居るものだ、と意外な思いに囚われる彼女である。 「ですが、決して如何にもならない程では無い。申し訳ありませんが、打ち砕かせていただきます」 正義為す破者の輝きをその穂先に掲げ、ユーディスは新たなる敵へと挑みかかる。その隣で戦線を象る、すみれ色の髪の剣士。 (なるほど、土御門・ソウシがそのような目的であったのなら、もはや彼が私達の障害になることはないでしょう) 蒼銀の剣と共に戦場を舞うリセリアは、図らずも『味方』となった男をそう総括してみせる。『天使の卵』を横取りするのではないかという声も一部には聞かれたが、そもそも横取りされたところで対して困らない、というのが彼女の見立てだ。つまろところ、好きにさせておけばいい。 「ならば、迷うことなく私達の敵を討ちましょう。――参ります」 魔力を帯びた刃は、その見かけよりも随分と軽く、神速の剣技を振るう助けとなっていた。だが、リセリアはそれに甘んじない。 より速く。より速く。光を斬る手応えを得られるほどに、速さに速さを重ねられたならば――。 「七之太刀・天雷ッ!」 空間そのものが、一瞬の内に切り裂かれ、薙ぎ払われた。歪み。そして発散。世界そのものを『斬った』代償が凄まじい揺れ戻しとなって、広がる稲妻の如く周囲を食らう。 「――人は死ぬ。星すらもいつかは滅ぶ」 終焉からは誰も逃れられないのです、とアラストールは告げた。人は瞬く間の生涯しか持たず、故に己が生を精一杯生きる。 それこそが人に定められた理であり、捧げられてきた祈りなのだ、と。 「我は祈りに応じるもの。ならばこそ問おう、皇帝の友殿」 貴公は何故に死を厭うのか。 もし果たさねばならぬ目的があるなら、己の生涯で叶わぬならば――。 アラストールもまた祈る。共鳴する思いを護りたいと。理不尽に抗う意思を信じたいと。 導かれるままに剣を振るった。ただだた、攻め寄せる『敵』から、響き合えない存在から仲間達を護る為に剣を振るった。そうして、何人かの騎士を打ち倒した時。 「――それは託すべきものではないのですか?」 厚い壁を乗り越えて。 いつしか、彼女達はグレゴリー・ラスプーチンその人に届こうとしていた。 一方その頃。 「歪夜十三使徒に並ぶ相手だろうが……連中と比較しちゃ、いくらなんでも失礼ってもんだな」 影継はそう嘯いて、儀式場全体に広がる魔法陣を眺めやった。平面でなく、幾つもの光の輪が空間を埋め尽くすように積み重なっている。大規模術式でもここまで大掛かりで精緻な仕掛けはそうそうお目にかかるものではない。 「コレだけのモノを持ってきて、望みが『不老不死』とは幾らなんでも小さ過ぎる。アンタと占星団は、この百年の間何も為しちゃいないだろうに」 深い魔術知識を持つ彼だからこそ理解できてしまうのだ。かの『聖杯』とまではいかずとも、この儀式場自体が強力な願望機と化していることを。にも拘らず、そのアウトプットはあまりにも矮小で卑近でしかないことを。 確かに彼らの研究には必要なのだろう。そして、今まさにラスプーチンに力を与え、リベリスタを苦しめているのもこの魔法陣の力だ。 だが、それが何だというのか。 「手加減無しで踏み潰すぜ――これからを為す者として、傲慢にな」 その言に頷いたのは綺沙羅である。彼女もまた、この立体積層魔法陣の解析に挑み、素直に驚嘆もしてみせた一人だった。 「長生きしてるだけあって、ここの魔法陣は中々だけどね。時間があれば盗み取ってやりたいくらい」 カタタタ、とキーボードの音を鳴らしながら、しかし彼女もまたその表情には侮蔑の色を隠していなかった。もとより綺沙羅には厭人的なところがあったが、むしろこの場合は創り手としての感想に近い。 「何百年も生きてる老害が、未だに死ぬのが怖いとか。笑わせるね、こんな大層なものまで組み上げて」 本格的な解析には至らずとも、彼女もまた魔術論の深奥を得たる者。瞬間記憶がてらに陣の構成をなぞっていけば、力の流れが少しずつ把握できていく。 「やっぱり、この魔法陣を止めるのが先決、かな」 同じく魔法陣の解析に当たっている理央は、しかしそのあまりの高度さに何度も諦めそうになる。陣を敷いた術者は、かのグレゴリー・ラスプーチン。あまりにも力量差がありすぎる相手なのだ。 「でも、諦めないよ。小さな積み重ねが、きっと勝敗を分かつんだ」 アークが今まで格上を倒して来れたのは、まさに積み重ねたが故に、だから。術式の一つ一つ、陣の一つ一つを丁寧に辿れば、きっと全てが見えてくるはず――。 そして。 「――アレだな」 影継が指した先には、複雑な紋様に紛れた二重螺旋の意匠。別の場所に同じ回路を見つけていた綺沙羅と理央も、同意の頷きを返す。 この積層陣の大半は、組み上げた魔力を加速させ濃縮する一種のサーキットである。その魔力の流れをコントロールする管制塔を断ち切ってやれば、いずれこの魔法陣は自壊するに違いない。 「死なない為に他に被害を出すのはたまったもんじゃないよ。それが塔の魔女が仕込んだ結果だとしても、ね」 理央の符が真っ直ぐに飛び、影を纏って二重螺旋の紋様に突き刺さった。それを追って、綺沙羅の放った鴉が爪を突き立て、紋様を削り取る。もう片方の螺旋は、影継の抱えた戦車砲が粉微塵に打ち砕いた。 だが。 「あそこ、もう一つ!」 一際眩く輝き始めた天頂部分の魔法陣、そこに見落としていた螺旋模様がもう一つあったのだ。そして、この立体魔法陣は自己修復効果があることが判っている――。 「あいよ、ヒーローは最後にやってくる、ってな」 覆面越しのくぐもった声。紙巻の安煙草をぴんと弾いて投げ捨て、古めかしい散弾銃を片手で構えてみせる。男の名は晦烏、アークで最も胡散臭い男。 「そんな顔するなよ、おじさんだってこれでも魔法陣を調べてたのさ」 綺沙羅にそう笑いかけ――覆面越しだがどうやらそうらしい――烏は天頂へと銃口を向ける。引き出しから取り出すのは、かの親衛隊中尉の告死の弾丸。 「……タイミングを見計らってたね」 「まあそう言いなさんな」 極度の集中が必要な狙撃準備を『終わらせていた』彼は、躊躇いなく引鉄を引く。牙を剥く魔弾は、狙い過たず最後の回路を射抜き――天井の石材ごと砕いた。 「まあ、あんたもこちらもお互いしてやられたわけだが。何かあの魔女に伝えておく事はあるかい?」 機能を喪失した魔法陣の下、烏はそう静かに笑うのだ。 「オレ、この戦いから無事に帰ったら、ユーヌたんとイチャイチャするんだ……」 「黙れ変態。常識は大事だ。自重しろ非常識どもめ」 立てたフラグを一蹴するユーヌ。あれ、ディスるのはラスプーチンじゃないの、と涙目の竜一は、割り込んできた騎士へと蒼い宝刀を振り下ろす。 「お前らが邪魔するからユーヌたんが冷たいじゃないかそれも気持ち良いけど!」 斬撃以上に凄まじい気迫を前にして思わず退いてしまうフィクサード。ぶっちゃけ八つ当たりなのだが、とりあえず今は横に置いておく。 「別にイチャイチャぐらい何時でもするがな?」 顔を赤くしたり白くしたりさせる恋人を面白げに見やり、しかし向き直ったユーヌの表情は戦う者のそれに戻っていた。 「やれやれ、休みが永遠に続けばいいと願う学生のような願いだな」 懐から束で取り出した符を、そのまま頭上に撒き散らす。呪力を蓄えた符は鴉の大群となって、フィクサードを黒霧に隠した。 「永遠の生命、永遠の精神などと下らない……ああ、意外と普通の俗物なのか」 「死ぬことは怖い。それから逃げようとするのはおかしなことじゃない」 臆病であった悠里だからこそ判る。グレゴリー・ラスプーチンという男は、多分もっと、人間臭い存在だ。 「けど、死なない人生なんて悲しいよ」 ぐん、と加速する。地面が縮まるかのような感覚。ラスプーチンまであと一人。眼にも留まらぬ速度を乗せた凍気の拳が果敢に前に出た術士を捉え、瞬く間に氷の棺の中に閉ざす。 「人はいつか死ぬ。だからみんな一生懸命に生きようとするんだから」 「――あなた方に何が判るというのです」 その男。 グレゴリー・ラスプーチンからは、自らの大望を費えさせようとするアークに対する怒りは然程感じられなかった。あのムービーで、アシュレイへのマグマのような憤りを露にしたのとは対照的である。 あるいは、正面衝突で雌雄を決したことが、彼にある種の諦念を齎したのかもしれない。一世一代を賭けた積層立体魔法陣が機能を停止したことが、彼に結末を予感させたのかもしれない。 だが。 グレゴリー・ラスプーチンはフィクサードである。 如何に『話の判る』部類であっても、自らの欲するものの為に力を振るう、という根源は変わらない。 故に。 人間臭い矮小な願いを叶える為、グレゴリー・ラスプーチンはどこまでもあがく。 「私は殺されます。その暇乞いに参りました。もし、私を殺す者の中に陛下のご一族がおられれば、陛下とご家族は悲惨な最期を遂げる事となりましょう」 それは呪い。 それは予言。 銃弾をもって追われたラスプーチンが、ロシアに残した意趣返し。敵も味方も何もかもを闘争の坩堝に突き落とした、歴史の陰に潜む魔道。 「そしてロシアは、長きに渡り多くの血が流されるでしょう」 次の瞬間、リベリスタ達をありとあらゆる呪詛が飲み込んだ。意志の力など一顧だにせず、神の加護など塗り潰して。 多くの者達が動きを止め、悪寒に苦しみ、胡乱に狂い、そして昏倒した。 これこそが死の予言。これこそが、ラスプーチンの遺す絶望という病。 しかし、リベリスタは挫けない。 「予言は、口にした時点で必ず覆される可能性を孕むんだ」 焦燥院フツ、アークで最も徳高き男は凜として立つ。そして自らのありようで示すのだ。予言は、所詮は予言に過ぎないのだと。 「みんな判ってんだろ? オレ達がその予言、ひっくり返してやろうぜ!」 深緋の槍を床に突き刺し、低く発声。応、と聞こえたその響きと同時に生まれ出でた劫火纏いし鳳が、ラスプーチンへと一直線に突き刺さり、爆ぜる。 「言いたい事は色々とあるんじゃが。とりあえず一言で言うとじゃな――紅涙、紅涙、うるせぇんじゃよ!」 手を撒き散らすは二振りの刃。ラスプーチンへと迫る真珠郎の凶手。何かよこせ、と口癖のように宣うのはいつものこと。一切の逡巡なく死地に飛び込むのもいつものこと。 「ふん。齢数百。其処まで生きてまだ死ぬが怖いか」 八十を数える彼女だからこそ吐ける台詞であろう。犬歯を剥き出しに猛る紅涙の狂乱姫は、血のように紅いドレスを翻し老人へと迫る。 「肝っ玉は小せぇようじゃの――命を惜しむな。刃が曇る」 光の粒子が舞う。いやさ、それは刃の閃き。ラスプーチンを護る魔力の層を貫いて届いた刃は、彼に少なからず血を流すことを強要する。 「ハロー、渋カッコイイおじさま! 人魚と一緒に踊りましょ!」 なかなか味わえるものじゃないよ、と言ってのけるせおりは、その可憐な見かけよりは随分と肉食らしい。 「セイレーンがあなたにヴォルガの舟歌を歌ってあげる!」 ラベンダーの鎧を身に纏い、水仙を染め抜いたマントには深い海の色をした石を留める。海と河を統べる幻想種を身に宿した少女は、両手で構えた太刀に運命とも宿命とも言うべき超常の力を宿して。 「強い雄を殺すのは気が引けるけど、割り切らないとね!」 振り下ろす。衝撃。運命よ捻じ切れよと振るわれた高潔なる一閃は、確かにラスプーチンを追い詰めていく。 「それにしても、本当にめんどくさいことをしてくれますね」 その魔法陣、その魔術、その寿命。一体どれほどの物理を踏みにじって成立するものか――垂涎と言ってもいい神秘の精髄。それを前にして、あばたの中に湧き上がるのは性欲にも似た衝動である。 「ああ、是非知りたい。是非解析し物理に落とし込みたい」 狂おしいまでの昂り。それを抑え込み、あるいは昂るがままに、彼女は銃口を向けた。化け物じみたロングバレルが灼熱し――しかし、齎されるのは無音の福音。 「わたしはあなたの神秘を貶める。わたしの脳に刻み込み、そして静かに殺してみせる――!」 銃声なき魔弾。それは、狙い過たずラスプーチンの胸に紅い花を咲かせるのだ。 「恋に破れ、恋に狂い。破滅へと至る彼は確かに愚かです、が――」 何百年と経っても治らない病なのでしょうね、と。 事此処に至り、ラスプーチンの諦念交じりの姿勢に、そういうことかとリリは首肯する。なぜあの時アシュレイにのみあれほど怒り狂ったのか。それは裏切りによる停滞の恨みつらみだけなのか。 (幸せになるなど、赦されなかったのに――) 今となっては、それを答えられる者はもういない。けれど、そうなのだろうと、なぜか彼女はそう信じていた。 「祈りましょう。皆様と、――の無事と幸せの為に」 二丁拳銃の引鉄を引いた。城門すら崩すという魔弾はラスプーチンを捉え貫く。ああ、その腕前すら呪われた過去に得たものだと思えば、贖罪の念すら滑稽にも感じてしまうけれど。 「大丈夫だよ」 何気なく呟いたロアンの一言が、遊離しかけた妹の意識を繋ぎとめる。ぽん、と軽く頭を叩く手は、どこまでも大きく、暖かくて。 「おいで、嘲笑ってあげる。無様な人生も、何もかもをね」 兄は駆け出した。手には切れ味鋭い鋼糸。命を刈り取る、それだけの為に生まれた暗器を道連れに、彼はごぼり血を吐く男の首を狙う。 血を吸って黒く染まった法衣。その姿がぶれて、いくつもの残像を生み出した。僅かに光る銀の軌跡が幾重にも三日月を描き、全ての護りを剥がれた予言者を斬り刻んで。 「――運命はこの手で捻じ伏せた。後付けの予言なんて、今の僕の敵じゃないよ」 最後の一閃が、ラスプーチンの喉を掻っ切った。それが、止めの一撃。何事かを喋ろうとした彼は、しかしひゅう、という音しか残せずに闇の中へと沈んでいった。 ●再び、三高平へ ラスプーチンを討ち取った――程なくして起こった歓声を聞いて、僅かな生き残りのフィクサードも投降を受け入れた。セルゲイ・グレチャニノフは取り逃がしたものの、『我らの友』占星団はほぼ壊滅し、最早組織的な活動は見込めない。 以上が、モスクワ遠征の顛末、そしてラスプーチン戦役の幕切れである。 かくして。 後顧の憂いを断ったアークは、ついにウィルモフ・ペリーシュとの決戦に挑む――! |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||














































































































