
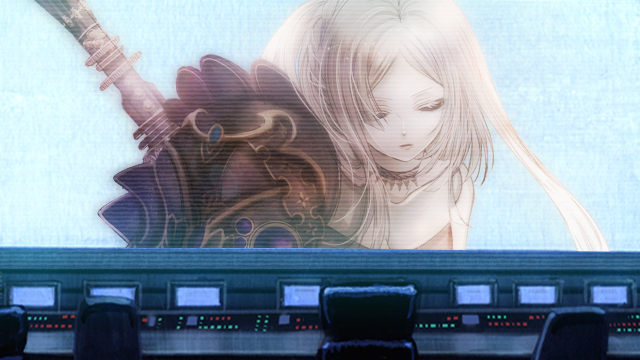

<究極望まば・黄泉ヶ辻>【呪歌の書】誰が駒鳥を殺したの

|
●真っ黒な頁に白インキで記された文字 前書き。 東洋の言葉で『言霊』というものがある。 言葉には霊が宿るというものである。 この呪本は、世界中で唱和されているであろう、ある性質を帯びた歌の力を集め、一種の魔力媒体として完成させる事を目的としている。 ただし、本書を使う為には一定の試練を越えて、権利者とならねばならない事を記す。 ・頁に手を触れて、定められたMagic Wordを唱えれば、本へと侵入できる。 ・本書の中枢を滅ぼした時点で、権利者の決定が行われる。 ・中枢への道は番人に守られている。この番人は、これまで培われた魔力そのものである。 ・番人をより多く屈服させ、中枢を滅ぼした側が、権利者決定に大きく有利となる。 ・本書は二冊ある。権利者が決定された時点で、権利者以外の本は燃えて消える。 ・内部では、神秘の力を拒絶する力が働く。治療といった力には、より強力に働く。 ●3ページ -Who Killed Cock Robin- Who killed Cock Robin? I, said the Sparrow, with my bow and arrow, I killed Cock Robin. 「誰が殺したクックロビン。それは私よとスズメが言った。私の弓で私の矢羽で私が殺した」 真っ白な髪と真っ白な肌の少女が、詩を口ずさみながら切り株に腰を下ろす。自らの腿に頬杖をつく。 場は森である。 木漏れ日が射す所や、日が通らない程深い部分が至る所にある。一部で手を入れかけた様な切り株も点在するが中途半端だ。 この場は、しかし魔力によって作られた呪歌の書の世界である。 少女は深い森の闇へ視線――といっても少女は目を閉じたままだが――を向けた。 「――次はハエでしたっけ?」 「ハエ、魚、カブトムシ、フクロウ、カラス、ヒバリ、ヒワ、ハト、ミソサザイ、ツグミ、牛」 男声で応答が返ってくる。 闇の中から、謝肉祭の仮面をつけたタキシード姿の男がフッと現れる。両脇に動く騎士甲冑を一体伴っている。 突然、木々の向こう側から雀達が矢の様に突進してくるが、この二人に触れる前に、全身から骨という骨を噴出させて落下する。 「この詩は欧州では一般的な民謡なのだが、だからこそ私はこの歌が堪らなく愛おしく思えている」 仮面の男が己の胸に手をあてて、空を眺めるように、かく芝居がかった調子で言った。 無視する様に、少女は絶命した雀の一匹をつまみ上げる。 「また美学についての講釈ですか?」 少女の意図である『聞き飽きた』も皮肉も何もまるで解さない逸脱者が、くつくつと笑って続ける。 「私はこの為の、楽団におけるアンコール担当だったのだと強く感じる。私の命は『楽団』が滅んでから私というものが始まったと言えるだろう! 嗚呼、ジャックザリッパーが逝かなければ、“コンダクター”様は興味を持つこともなかっただろう。『彼ら』が『指揮者』様を殺さなければ、“パフォーマー”様も“シンガー”様も、命を賭す事も無かっただろう。私の素っ首を飛ばす程の情熱的な彼らでなければ、私はまだまだ演奏(や)りたいなどという欲が湧かなかっただろう。今なら“パフォーマー”様のお気持ちがよく分かる! 『倫敦の蜘蛛の巣』の彼がいなければ、今この場に居なかっただろう。君とも合わなかっただろう。次へ次へ連なる楽章の如き様子は『Who Killed Cock Robin』が如く。己の役目を見つけて次へ次へと続く! 私はこの詩がたまらなく愛おしい!」 謝肉祭の男は捲し立てる様に言葉を連ねる。 全てを黙って聞いていただけの少女はため息をついた。 「『風が吹けば桶屋が儲かる』って言葉知ってますか?」 少女は手に持っていた鳥の死体を口に放り込み、ゴリゴリと咀嚼する。ペッと羽を吐く。 「何だね?」 「似たような意味ですよ」 少女は切り株から立ち上がって得物を握る。 向こう側で闇が増えている。無数のハエがぞわぞわと羽音を立てて木漏れ日を埋めていく。 謝肉祭の仮面の男は、先の少女の言葉に首を捻ったが、直ぐに首を正して両手を広げた。 手をピアノの鍵盤にあてがうような形にした途端に、親指に嵌めた指輪から青白い炎を生じる。青白い炎からぼんやりと鍵盤が浮かび上がる。これに指を置き、置いたかと思えば指が滑走する。 たちまち木漏れ日の中で音楽が響き渡る。 「先に口ずさんでいたから、君もこの詩が好きなんだろうね」 「いいえ、大嫌いです」 男が奏でる音楽に乗じる様に、死んでいた雀達が一箇所に固まっていく。肉団子の様になったそれが、ハエの大群につっこんでいき、爆ぜるように小蟲を撃墜していく。 また男の後ろで控えていた騎士甲冑が、ハエの大群に踏み込んでいく。 「果たして、セニョリーナの役割はなんだろうかね」 「今は単なる黄泉ヶ辻の尖兵ですよ。巡様への義理を返し終わった後はわかりません。例えば剣林に元・楽団員の首を手土産にして稽古つけてもらってもいい訳で」 「少し面白い」 くつくつとくぐもった笑いをする、仮面の男の名は、『第四の手』シルベスター・“ピアニシャン”・カストア。 無視するように、騎士へ続く様に踏み込む少女の名は『千の呪詛』斑雲 つづら。 ウィルモフ・ペリーシュと黄泉ヶ辻。其々の悪意の一端である。 Who saw him die? I, said the Fly, with my little eye, I saw him die. Who caught his blood? I, said the Fish, with my little dish, I caught his blood. |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:Celloskii | ||||
| ■難易度:HARD | ■ ノーマルシナリオ EXタイプ | |||
| ■参加人数制限: 10人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2014年10月01日(水)22:18 |
||
|
||||
|
||||
| ■メイン参加者 10人■ | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
●呪歌の書・深層 本に手を置いて、定められたコマンドワードを唱えた瞬間に、視界が閉ざされた。 浮遊感が全身を襲い、暗闇に落下していく。 ただただ落ちていく。どこまでも落ちていく。 やがて、自身の心臓の音を意識する程の静寂と浮遊感の中で、胸に締め付けられる様な苦痛が走った。 鼓動は、耳に響くように大きくなっていく。間隔も短くなっていく。ドクンドクンドクンと短くなる。 一定間隔で来る苦痛は、やがて間隔が無くなる程に連続する。 ドクンドクンと耐え難い境界にまで至り来て、うめき声を漏らしかけたある瞬間、落下も苦痛も悉く止まった。 ●呪本・序 「痛ちちち。二回でも慣れないな。これ」 『覇界闘士<アンブレイカブル>』御厨・夏栖斗(BNE000004)が、うつ伏せから仰向けに裏返った後、足で反動をつけて跳ね起きる。 視界に森が広がっている。 現実の森であれば、不明瞭な視界と足場の悪さに手を焼く所だが、木々は幻の様に存在感がない。 特殊なものを用いらずとも、しかと見通せる。何とも奇妙な感覚であった。 「っと、時間がない! 急ごう!」 夏栖斗の声に、『ガントレット』設楽 悠里(BNE001610)が構えを作る。 「早速来た」 超直観が見据えたる先は、地面を泳ぐようにしてやってくる『魚』達であった。 「1、2、3――3匹ですね」 『現の月』風宮 悠月(BNE001450)が自身に物質を遮断する障壁を施す。 跳ねてきた一匹が悠月へと齧りついたが、ピラニアの様な口は障壁で止まる。『魚』を悠里の拳が打ち落とす。続いて夏栖斗の旋棍で側面を抉り取る。 「徹底粉砕と言いたいところだが、先ずは」 『足らずの』晦 烏(BNE002858)が、木々の間をすり抜けるように飛翔してくる物体を視認した。 雀の死体の塊、ハエの塊。、掃射せんとした右手を止めて神秘の閃光弾を投擲する。同じく直観で捉えた女騎士だ。 「作戦通りにいきます」 『ホリゾン・ブルーの光』綿谷 光介(BNE003658)が視界に捉えたるは、真っ直ぐにこちらへやってくる、かの楽団員の姿であった。 「望まれないアンコールほど、美しくないものもないと思いますけどね」 競り勝つ、という決意と共に、最初に視覚で得た情報を連携する。 「11時方角に“ピアニシャン”、つづらさん。2時方角にジュヌビエーブ。魚の一体は向こう側です。距離は20m程」 直観を持たない者でも、意識を向ければ見える。索敵は完了である。 「鐘は無いかな?」 光介に夏栖斗が問う。 未来視のなかに『牛』の記述がなかった事が、最も気になっていた事である。 「……見当たりません」 光介は見落としは無いかと目を凝らせる。鷹の目はこの空間の端までも見通せる。しかし『以前』と異なって、一向に物理的にも魔力的にも怪しいものは見当たらない。 「私も無縁とは思えません」 アリーサ・ヨハンナ・アハティサーリ(BNE005058)も、自身の考えを付け加える。 「『Who caught his blood?』の答えが、血を吸う魚だったり、『Who'll dig his grave?』の答えが穴を掘るフクロウだったり、敵の能力も元の歌がベースになっています」 三人は同じ結論を出している。 いやさ、この場の多くが予想していた点である。歌の結末は雄牛が鐘を鳴らす事。駒鳥を葬送するのがこの歌の骨子である。故に中枢たりえる。 「――では、行きます」 アリーサは、考えを一旦切って、その場で宙に浮く。 此度、果たさなければならない役割を優先させる。 「お願いします!」 光介の声を背中に受けて、アリーサは木々のすり抜けていった。 「誰が殺したの? それは犯人だけが知っている! さあさ、犯人捜しついでに、フィクサード退治だね!」 『骸』黄桜 魅零(BNE003845)が『六翼天使』フランシスカ・バーナード・ヘリックス(BNE003537)の肩をぺしぺし叩く。 魅零は隻眼を大きく開いて心底嬉しく、楽しく、お気に入りの玩具で遊ぼうという心持ちに近い。そもそも目的はジュヌビエーブである。 「ペリーシュナイトに本はあげらんよ! 全員ここで終わらすよ、さあ、犯人は誰かな!」 「うん、行こう」 フランシスカはふわりと浮く。応じた次に2時方向へと翔ける。 フランシスカは、利害損得など抜きに根本的に戦う事が好きである。 魅零と自分でなければ倒せない存在が敵にいる。仕損じれば総崩れになる。 「……絶対、ぶっ壊してやるわ」 戦う為の理由なんていらないけれど、先行きを委ねられているなら、十分過ぎる。 『デイアフタートゥモロー』新田・快(BNE000439)は、魅零とフランシスカを追う。 「ピアニシャン……楽団のアンコールはもう十分だ。ここで終わらせたいが……」 快はジュヌビエーブの方角から視線を逸らし、“ピアニシャン”の方向を向く。 神秘を拒絶するこの空間が故に、隠蔽魔術を行使していない今が、大きな機会である事は重々承知なのだが。 「今はペリーシュの企みを少しでも防ぐほうが先決だ。悔しいけれど」 「お察しします。まあ、それなりに殺すつもりで鉛球ぶちこんでおきますよ」 快の背中を見送りながら『クオンタムデーモン』鳩目・ラプラース・あばた(BNE004018)が呟いた。 あばたが“ピアニシャン”に抱いている感情は特に深い。 日々の修練、重ねた努力に敬意を持たないどころか嘲笑う。弄ぶ――腕か足か。生かす価値がまるでない。『嫌悪』である。 「しかあし! その前に、文字通りの雑魚を駆除しないとですね」 快や魅零、フランシスカ達の進路に近い『魚』へ鉛球を刺して、自らに注意を寄せるのであった。 ここに、リベリスタ達は大きく3つの役割を分担した形となる。 夏栖斗、悠里、悠月、烏、あばたは、番人の撃破とフィクサードへの対応。 光介が中枢の探し、アリーサは競合するであろう黄泉ヶ辻を抑えるべく動く。 以上のメンバーで撃破が極めて困難なペリーシュナイトに、快、魅零、フランシスカである。 「『神となる研究』なぁ。おじさんは神とて死の定めは免れぬものだと思うがね。ツァラトゥストラはかく語りき」 烏は弾丸を再装填して、安煙草を咥える。紫煙を吐く。 「――で、ネクロマンサーの見地としてはどうだい、シルベスター君」 烏が視線を戻した先。くつくつと、くぐもった様な笑い声がして、一人の男が現れた。 「神は既に死んでいるというのが持論でね。勿論、肯定したい」 「何ともお変わりないもんだ。してその心は?」 「気まぐれなる運命の存在こそ、神の遺志だと常日頃から考えている。凡百の徒の愚考に過ぎないが」 光介が、楽団員の姿を見て奥歯を強く噛む。 「……“ピアニシャン”!」 「少年(ragazzo)よ。再会に何とも歓喜の極みだ」 ちっとも嬉しくないという反論が喉から出かけるが、飲み込んだ。その時間すら惜しいのだ。今は。 あばたの銃が火を噴く。 「神は死んでいる。興味深い話です――だが死ね」 “ピアニシャン”を穿たんとする軌道だったが、雀の死体が弾丸を受け止めた。 「その濁りながらも情熱的な目は、セィィニョリーナ! 今の胸裏、熟成された葡萄酒をグラスに注いだ時の愉しみと形容したい!」 「素っ首飛ばしても死なない虫の類め!」 かく、あばたも鷹の目を心得ている。発砲は一発ではない。横の茂みからやってくる次の番人――大型の『カブトムシ』に先制した。 「見た事のあるネクロマンサーの術とは大分趣が異なりますね」 悠月の視線は、既に解けた雀とハエのフレッシュゴーレムへ向く。 成程。確かにゴーレム。と呟き、早い段階でペリーシュナイトへ、葬操曲・黒で異常を重ねておく。 「『Amor e morte』……上海でのあの男の術、これが元ですか」 かつて『倫敦の蜘蛛の巣』の構成員が上海で起こした事件での事である。 その構成員は、当時アークに敗北した楽団員を利用してデータを得る他、逃亡の手引きをする等の暗躍見せていた。上海の事件に臨むにあたって調べていた事である。 かく、構成員とつながっていた楽団員こそが、幽霊鍵盤を操るソロピアニスト――“ピアニシャン”である事は突き止めている。 “ピアニシャン”と会敵した頭上――空と森林の緑の境においても始まった。 アリーサは、横から飛来した式符の鴉を、閉じた鉄扇で右から左へ受け流す。 「ペリーシュも黄泉ヶ辻も止めたいんですが――私に相手を打ち倒す力はない。回復役としても『中途半端』かもしれません」 アリーサは眦を決する様に、放った術者を見る。 「けれど、足止めぐらいはできますよ?」 「信頼できる仲間がいるとか、そういう話でしょうか?」 真っ白い髪に、白い肌。左腕と左足は球体関節人形という異様な形の少女が、何もない空中を足場の様に蹴って近接してくる。 白子は『魚』の死体を齧った後、残りを捨てて手を翳す。 「極縛陣」 結んだ印が空中に広がる。動きを大きく鈍化させ、不吉な空気が降り注ぐ。 「つづらちゃん」 悠里が見上げる。 「おや。設楽 悠里さん。それから――」 「どーも、ご機嫌麗しゅう。今回も権利者は譲る気ないからね」 夏栖斗の声に、つづらの眉間が微かに歪む。 地上、空中での会敵から、少し距離を隔てた地点でも戦いは始まる。 「さーて、フランちゃんいっくよー!!」 魅零とフランシスカが、得物を大きく振りかぶる。 「いい加減その面も見飽きたわ。ここで壊してやるわよ!」 フランシスカが風車のように縦に一回転しての切り落としが、ペリーシュ・ナイト・ジュヌビエーブの肩へと打ち込まれる。 手応えは硬い。 「ダメか。……それなら、こっちがその鎚でつぶされるのが先か、それともそっちがこっちの刃に潰されるかの勝負よ」 女騎士に黒き剣をつけたまま、一旦着地する。跳躍するように飛ぶ。 「殺人鬼の先輩はいないけれど! 黄桜達でがんばるよ! がんばる!」 魅零は、大業物の切っ先で横一文字を描く。女騎士の装甲はかすり傷も生じなかったが。 「スケフィントーン! どーん!」 綺羅びやかな聖騎士の如きジュヌビエーブを黒き牢獄が包む。 黒き牢獄は、狭まって狭まって女騎士を押しつぶしていく。 「うわっ!?」 黒き牢獄が砕ける。同時に戦鎚が魅零を襲う。 一呼吸にも満たない瞬間に、戦鎚と魅零の間へ割り込んだのは快である。 両手を交差させて受ける。一撃で左腕の前腕部分が拉げた。ぼきりと鈍い音と伝わる痛みから、もう左腕は使えない。 「……立っていられる時間を、少しでも長く」 受け止めて沈んだ上体から、女騎士の顔を睨む。自分に許された時間は少ない。 戦鎚を跳ね除け、幻想殺しの目で、この魔術空間見渡した。 何か無いか。何か無いか。何か無いか――。 まるで見えぬ中枢。飛来する呪本の番人。ウィルモフ・ペリーシュが放った敵、因縁深きフィクサード。 ここに呪本の争奪戦の火蓋が切られるのであった。 ●呪本・破 「(今回は魔力の流れを追うだけじゃ、つづらさんをリードできない……)」 光介は携える本を片手に持ち、もう片手を添える。 風に吹かれたかのようにページは捲れていく。 「術式、迷える羊の博愛!」 顕現させた淡い光は、快を背中から癒やした。防御の上からであるのに威力は恐ろしい。 もっと意識を向けて回復すべきかという気持ちが生まれたが払う。役目はそこではない。 頭を切り替えて中枢を探す。しかし魔力の流れにも違和感が一切ない。何らかのトリガーによって起こるのか。 物語辿るなら番人を『牛』まで倒すのか。 フランシスカは、空色と森林の緑の境目まで飛翔して、急降下の様に全身全霊をぶつける。 「こないだの時の声はあんただったのね、つづら」 『そうですね』 つづらの声は、打ち据えた眼前の女騎士から生じた。つづらと女騎士が携える戦鎚に何かあるのか。 「そういや前にまみえた時に、仕留めたかどうかきっちり確認するの忘れてたわ」 『死にかけて這いずっていた所へ、祭蔵さんの血肉が降ってこなければ死んでいたと思います』 「そういうこと。ペリーシュの野郎にコレ渡すと面倒な事になりそうだしね、邪魔させてもらうわ」 早々にケリをつけるしかない。両足の虚脱感と不吉が中々と厄介で、ジュヌビエーブへの打点を外す可能性が出てきたからだ。 『正直、本の行方なんてどうでも良いんです。私はただアーク戦う事。いいから一発殴らせろって事です』 「人は見た目によらないって、あんたも大概ね。剣林が向いてるんじゃない?」 フランシスカに向かって戦鎚が構えられる。その背後から、魅零が牢獄を放つ。 「手段の為に目的を選ばなーい☆ 最高に感じちゃうシチュエーションだってすごくすごくおもうよ!」 魅零は人差し指を立た形の手を自らの頬に寄せ、隻眼でウインクして可愛く言う。 「感じさせてね☆」 『嫌です』 「えー」 魅零とフランシスカを快が庇う。 「悔しさが身を焦がす痛みに比べれば」 ここで、突如生じた嫌な気配に、快はジュヌビエーブとは別の方向に身構える。 だが、それは意味を為さなかった。体内なら皮膚を突き破ってくる自らの骨。見覚えがあるこの魔法を使う者は一人しかいない。 「“ピアニシャン”……!」 ジュヌビエーブの一撃を受けた後で、防御を素通りする秘術を受け膝を尽きかける。 相手の勝ち筋の一つ――ジュヌビエーブを通す事を優先してきてもおかしくはない。 「追い込まれた、か」 回復を加えたとしてギリギリだ。 フランシスカ、魅零の刃と切り結びながら、女騎士から出る声は快に向いた。 『初めまして、新田快さん。もし覚えていたらで良いのですが、W88の最期を聞いてもいいでしょうか』 「覚えている」 快は口角の血を、生きている右腕で拭う。 軽快なピアノの音色が木々の間に流れゆく。烏が再利用させまいと砕いた肉片であったが、細かく浮かび上がっては団子になる。 団子同士も連なり、混ざり合い、大きな塊へと化していく。 「氷、または燃やさないとダメみたいだね」 悠里は重戦車の様に突進してくる『カブトムシ』を受け止め、氷鎖の拳で『魚』のゴーレム化を阻止する。 「マレウス・ステルラ」 強力な魔術は、この魔術空間の景色を歪め、『カブトムシ』4体とフィクサードを薙ぎ払う。薙ぎ払った側から、また肉団子が辺りに形成される。 「――練度、力量、範囲。あの男とは、天と地程の差がある事は確かですね」 悠月が歯痒さを噛み締めながら独り言つ。呟きをあばたは発砲しながら拾う。 「それがドリスノクというなら、全くもって同意しますね。浅過ぎる。頗るゴミです」 かく、普通の死霊術師が操る動く死体への対処が、まるで対処にならない事が、つくづく死ねばいいと思う点である――もう一つ何かあったような気がしたが、喉から出かかった所で、闇の塊を見る。 「『フクロウ』が来た様です。暗視、地形悪化が来ます」 粛々と『次』を穿つ。 星の鉄槌による番人の瞬殺と、死体の再利用を抑止する適切な対処によって、呪本におけるリードを飾っている。 しかし、中枢はただでは掴めず、ペリーシュナイト側は極めて劣勢に陥った形であるのが今の戦況である。 「見逃された?」 つづらは無表情のまま声で驚愕を表した。悠月の星の鉄槌は、つづらを含めていなかった為だ。 「ますますわかりませんね。どうして見逃されるのか」 つづらの顔はアリーサへと向く。 「悪い人ならやっつけますし、良い人なら話し合ってみます。出来る範囲で最善を尽くす。時には涙を飲んで割り切るしかない」 その時、その時で、最善を尽くすというアリーサの理念、心情、をただ返した。 白子は眉間を寄せる。 「大半が格下。生殺与奪を握っている側は良いものですね。心の置所次第でどうこうできるなんて。強者は」 「世界は優しくないから強くならないといけない。出来る限り誰かには優しくしたい。強く優しく。そうならないといけないと思っています」 強い意志はそのまま、屈託無く返すと、白子は嘲るように口角を上げた。 「一回壊れてみてはどうです?」 「逃げないで下さい」 「逃げてません」 つづらの掌に生じた星占いは、しかしアリーサを避ける様に、『フクロウ』へ放たれた。 烏が放った弾丸と星占いがほぼ同着に、『フクロウ』の一体が墜落する。 口を動かして、落ちる煙草の灰。 「『弱い事が全ての原因』なんかじゃない。弱さを認め、共に補うべく友を、笑い合える仲間を得る事が先へと至る道へと繋がるんだ」 アリーサのいう出来る限り――出来る事を増やすために仲間がいる。これを証明した格好となる。 「『弱い事が全ての原因』ではない――何を言っているんです。そこを否定するんじゃなあない!」 白子は、場に大きく響く程の声量で怒りを露わにする。 「正義感が強かろうと、純真だろうと、夢があろうと、弱ければ塵芥になるだけじゃないですか。貴方達『強者』が教えてくれた事ですよ?」 「甘い事言っているのも理解している――要は、其処でいいのかって所だな」 「どういう意味ですか?」 「弱ければ奪われて良いって理屈を許容するのかって話さな」 悠里は肘を大きく引きながら、二体目の『フクロウ』へと接敵しながらも。つづらへと声を張り上げる。 「最初から強かった訳じゃないし、今だって自分を強いとは思わない」 悠里にとってつづらの言は、自身にも重なる部分にかなり近かった。 「沢山の仲間が死んだんだ。朱子ちゃん、ヴィンセントさん、創太くん……花子さん。何度も傷ついて、失って、その度に藻掻いて、立ち上がって強くなりたいって願ったんだ。誰も彼もを守れるぐらいに」 『フクロウ』が咥えたシャベルを跳ね上げて、凍てつく拳を鉄槌の如く振り下ろす。 闇が消えた所で、再びつづらを見上げる。 「君が僕と似た結論を出したのは、当然かも知れない。僕の守りたいものは、命だけじゃない。人の幸せだ」 「人の幸せ?」 夏栖斗は暗視を用い、飛翔する武技にて三体目の『フクロウ』切り刻む。惜しく撃墜には至らなかったが。 「つづらちゃん、アークにおいでよ。何度でも誘うからね。今回のが終わったあと何処にいくの? どこでもいいならアークでも――」 「『Amor e morte』! その通りだと肯定したい!」 此処で“ピアニシャン”の声である。 次に爆音が域に広がった。重力が狂うような竜巻が生じて、上へと激しく昇っていく。 これは未処理の『カブトムシ』の肉から生じたものだった。『フクロウ』の残り2体と、次に訪れていた『カラス』4体が殲滅される。 「人の幸せの為。ああ、うつくしいものだ。手の取り合いたい。うつくしい。助け合いたい。純粋なる美しさがここにある。だが許されない。おお、何と悲しくもうつくしき。何と悲しきかな」 仮面の男はねっとりとした声色で二の矢を次ぐ。 「彼ら彼女らの言うとおりだ。最善を尽くすべきだ。演奏中に観衆側へ行く演奏家がいるかね? 存じていると思うが、私は“ピアニシャン”だ。The Three-Cornered Worldが一文を引用するならば。うつくしいものを、うつくしからんとすれば、うつくしいものの度は減じるのだ」 「……」 つづらがアリーサに向き直る。手中にある既にゴーレム化した『フクロウ』を解き放つ。 アリーサの視界は、たちまち闇に覆われるものの、暗闇への備えはしてある。 「つづらさん。あの人に言葉は届かないと思います」 あれは逸脱の類。 アリーサは唾を飲み込んで、自らに神の愛を施した。 『フクロウ』のゴーレムが舞って1対2。援護をしてもらう必要が生じる。 あばたは、楽団員の芝居がかった様子を見て、嫌悪と血反吐をペッと吐き捨てる。手で軽く拭う。 「ああそうでした。とんだ失態。肉片でゴーレムを造る事もそうですが、お前の本当の切り札は――」 首を捻転させて“ピアニシャン”は歓喜の顔を浮かべる。 「――『肉爆弾』だった」 「歓喜の極みを伝えたい」 1対2になったアリーサを援護する。その笑いは、いつ見ても吐き気がする。 自衛官の命を奪い、ゴーレムに変え、最後は木っ端微塵に吹き飛ばした奴だ。 コレは何なんだ? 人か? 人どうかも疑わしき怪人だ。 かくして、竜巻で一掃された番人。番人の肉片は、再び混ざりゆく。 “ピアニシャン”の魔術も飛ぶ。防御を突き破って出てくる骨の秘術、呪縛を齎す雑霊弾、そして『肉爆弾』。 ペリーシュナイトも、順調に蓄積が重ねられていたが、一撃一撃が重すぎる。 幸いにして、アリーサはつづらの動きを完全に封じている。 勝敗の天秤が揺れる中、『カラス』の次、『ヒバリ』が到来する。反動を伴う強力な攻撃。特攻機の如く、リベリスタとフィクサードに急降下と上昇を繰り返す。 悠月が、星の鉄槌によって『ヒバリ』4体を粉砕する。反動があった故に脆くもある。しかし倒した番人はフィクサードの手駒に回る。この処理に手を割けば、必然的に次の番人の撃破に遅れを取る。 「ぐっ!」 『ヒバリ』のゴーレムに穿たれ、快が二度目の膝をついた。 光介の回復を貰って尚も厳しい。ここまで、両腕を犠牲に、肩を砕かれ、片足の骨が粉砕されている。 だが、まだだ。 「両脚を砕かれなければ……立っていられる」 頭を砕かれなければ、戦意は燃え続ける。膝を正し、躙り寄ってきた女騎士を見上げる。 『W88を見逃す選択肢はなかったのですか?』 先の問答の続き、つづらの声。ただ、答えなければならない事がある。 「無かった。見過ごせない事をしたからだ」 それでも、もし救える可能性があったなら、最善を尽くそうとしただろう。 『アークにとって見過ごせない任務だから? あの子の為だったとか尊厳を守ったんだとか、任務だから仕方がなかったとか、誰かが用意した理由を言い訳にして逃げている類の人ですか?』 「少なくとも俺は――自分の意志だ。組織も関係ない。そこは絶対に逃げない」 『有難うございます。誤解していたみたいです』 伝えた瞬間に、女騎士から快へ横薙ぎが繰り出される。魅零が代わって受ける。 防御に成功した。したのに一撃で隻眼から血が流れる。痛覚は無いのに、崩れそうになる自らの膝を掴んで、体勢を整える。 「……新田君を早々退場させるわけにはいかないのよ。それにカズトくんの、前で、倒れられるなんて無様、絶対にできない、んだから」 魅零から飄然とした態度は消えていた。息も絶え絶えに、得物を握り直す。 「知を総動員する戦況把握が、ボクのスタイルです」 光介から回復の光が走ってくる。 先に魅零が快を庇った事で、快は二回連続で回復を受けた形になった。一度耐えることができる余裕が出来る。もう一発で戦闘不能だろう。しかし二回盾ができる。 回復は単体に留まっていたものの、誰を回復するかを良く練った事で戦線は維持されている。 ここで光介は、スタイル――と胸中で反芻して、最初に考えた『牛まで倒す』推理を頭から片付けた。 この作者の流儀的に、力一辺倒な事などおそらく無い。 敵方の中枢捜索を担当する筈のつづらに必死さが無い違和感もある。 遠くを見て近くを見て、ひっくり返して探して、盲点に気がつく。漸く『ああここにあったのだ』と認識する様なモノ――そんな気がした。 「つづら。あんた、いい加減ごちゃごちゃうっさい!」 フランシスカは、怒りを上乗せして、黒い剣を女騎士へ振るう。 「ネチネチネチネチ、今直ぐここに降りてこい! ぶん殴ってやるわ」 黒い剣と女騎士の装甲の接触部分から、ぱきりと間抜けな音がした。丹念なる呪殺の蓄積は、ペリーシュナイトの歯車を露出させるに至る。 ペリーシュナイトとの戦いは、程なくして魅零が歯車部分に牢獄をねじ込んだことで決着となる。 聞き覚えがある軋み音。破裂音が鳴り、機械じかけの騎士の動きは大きく崩れ落ちる。 無敵だがそこまで耐久力は無い――高は括られていたのである。 ●呪本・急 光介の戦況分析の結果は、極めてネガティブだった。 この頃になると、リベリスタ達の被害は蓄積している。単体回復にも限界が来ている。 特に恐ろしいのは『肉爆弾』である。倒しに行った瞬間に『域』で爆ぜるのだ。これには悠里や悠月も膝を着きかけ、運命を燃やして立ち上がっている。 そして、己の役割である中枢の捜索。これが果たされていない。焦燥感が首の後ろをちりちりと焼く。 最早、全体への回復を使う時が来たと決して。決した所で手が一寸止まった。 「……まさか」 全体回復、全体回復、全体回復――光介の思索において、完全に頭の外にあった事象が結びついていく。 以前の呪本の争奪において、もう片方の薔薇の花輪の物語に同じ羊仲間が行っていた。 全体回復を使い続けるとどうなるのかも報告書から得ている。時間切れを早めた事で何が起こったか。 もし外れていたら取り返せないけれど、敵がそこそこ余裕に振舞っている理由は、『中枢』に対してはリードしているからではないか? 「――っ! 鐘を見つけました!」 光介は全体回復を躊躇なく使用する。その後も繰り返し使用せんと連続で唱える。 結んだ術式が、デウス・エクス・マキナ――ご都合主義を暗示する名であったのは、呪本の作者への皮肉だったのかもしれない。 見つけた報告と同時に降り注ぎ始めた全体回復。時間が縮まった事を知らせる動悸めいたものが全員に走っていくのだが。 「あ! 『鐘』ある!」 夏栖斗もぽんと掌を打つ。薔薇の花輪の当事者である。 「あるある! 超ギリギリだけど!」 たちまち、“ピアニシャン”へと駆け出す。 一体、どういう事なのだろう。と疑問を浮かべた者もいた。 短き時を且つ短く駆け抜ける戦いは、程なく『ハト』を越え、『ミソサザイ』へ至る。 時間が迫っている事を告げる『鐘』の音色が降り注ぎ、疑問や問い掛けは喉から出る間も無く消え去った。 青空に鐘の音が鳴り響く。 何の鐘の音か――答えは得ている。 鐘が鳴る度に、世界が白黒の写真の様に色を失う。木漏れ日も鬱蒼とした闇も、その瞬間だけは空白となる。 敵も馬鹿ではないと思えば、恐らく同じ解を得ていると予想がついた。 解が外れた時の為か隠蔽魔術は切っていた様だが、先に本へ侵入していた事は揺るぎない。 「諸君等にも聴こえてきたかね? あのうつくしき『鐘』の音が――我々にはたった今『見えた』所だ」 “ピアニシャン”は、雑霊弾を放った。 これは呪縛を齎す。動きを止めることに専念してきたと怪しまれる。 「行かせない!」 夏栖斗がアッパーハートを放って、番人もゴーレムも悉く自分に引き寄せる。『ミソサザイ』が翼を剣のようにして斬りつけていく。 「行かせません!」 頭上でも、つづらが何もないものを見るようにアリーサから顔を逸らした。 察したアリーサが抱きしめる様に動きを止める。つづらが両目を開いている。眼球が無い黒い眼孔である。 「何が貴方達と違うのか。ようやく理解しました」 アリーサに向けられた不吉な呟きと同時に、鬼魅の悪い空気が広がる。 烏が破邪の光を放つ。 「さて、何がくるか」 破邪の光によって、雑霊による拘束から皆を解き放つ。 確かに不吉不運凶運を操る事は脅威だが、純粋な強さですり潰してくる“ピアニシャン”の方がよほど脅威と目していたのだが。 「――大呪封縛鞭」 たちまち万華鏡の予報には、記されていなかった術の名が飛び出した。 本来予備動作を必要とするがそれもない。呪縛を帯びた鞭が前衛に降り注ぐ。“ピアニシャン”の雑霊弾と合わせて、二重の複数人拘束である。 悠里の首に鞭が巻き付く。音の方向へ動かんとした足が止まる。 烏の破邪の光の使用後で、更にはこれまで高い回避能力を用いて抑え続けていたアリーサも鞭に巻き込まれている。 後衛位置によって逃れた悠月が静かに言う。 「『災いの星』の呪い――自身の力として純粋に見るようになれた、という所でしょうか」 「それなりに努力はしてます」 悠月は、この術が『その場に応じた対策』に繋がるものと直ぐに結論づけた。 元々から蝕んでいた不吉等が効果を及ぼさなくなっている事からも、力の管理面を大きく伸ばしたと怪しまれる。 自分達には幻想纏がある。万華鏡による予報もある。アークのリベリスタが意識する事が皆無な部分である。 「弱さを嫌い力を欲すなら、その身体を使いこなすのも確かに一つの道ではありますね」 悠月が葬送の黒き魔曲を放つ。 「――こちらも足止めをさせていただきます」 『その場に応じた対策』。それだけなら非常に地味な秘術だと捨て置いてもいい。問題はそれをインヤンマスターが使っている事である。 かく、アリーサが呪縛を振り払えなければ、つづらを遮る者が居なくなる。中枢へ素通りになるのだから。 東西の魔術が入り交じる中、快がフランシスカと魅零を庇って大呪縛封鞭を受け止めた。 「……済まない。ここまでの様だ」 ここに快が両膝をつき、うつ伏せに倒れ伏す。 しかし予想では一気に沈むと思われていたが、大幅に耐え切った形であった。 「任せて」 「うんうん! 黄桜絶対勝ってくる!」 頼む。とフランシスカと魅零へ託される。 魔曲で死んだ『ミソサザイ』のゴーレム化が始まり、最後の番人『ツグミ』が飛んでくる。 『ツグミ』は被害が大きい順に回復の光を降らせる存在である。最もダメージを受けていた快が倒れた事から、魅零へと行く。 魅零の隻眼とフランシスカの両眼は、“ピアニシャン” 相対する夏栖斗は呪縛を受けている。 二人が森を駆ける。 陽炎の様な茂みを抜けて、先に出たフランシスカが“ピアニシャン”に剣をぶつける。 「いい加減フィナーレを迎えなさい。もうアンコールなど必要ないのよ。死体使いのつまらない技も見飽きたわ」 死体の盾に止まる刃。 目と鼻の先の“ピアニシャン”の顔は、笑顔を崩さずに。捲し立てる様に。饒舌に。 「君の為。君達の為。諸君等アークの為に愛を注ぎ続ける! 終わらない夜を繰り返す存在として在り続ける! 永遠に永遠に永遠にずっとずっとずっとずっとずっと! ああ、私は溢れる喜びを伝えたくてたまらない! 与えたくてたまらない!」 吐き気がした。 指揮者の左右の手“パフォーマー”“シンガー”、見えざる手“インスティゲーター”、使われざる『第四の手』は、指揮者が死して漸く動き出す呪いの様な存在なのだ。 「黄桜、単体しか攻撃できないけどカズトくんのが素敵な攻撃できると思うから!」 魅零は『ミソサザイ』のゴーレムを叩く。死体を盾にするのだから、死体を全て処理すれば盾は消える。 「フラン! みれー! あっち終わったのか!」 夏栖斗が二人へ言う。 「無理しないでね、黄桜の大事なオトコノコ!!」 対“ピアニシャン”最終局面へと移ろう中。あばたはふと空を見た。 「おや。あれですか」 『鐘』だ。 距離にして30、40m程の横。幻が顕に、明滅するように浮かんで消える高さ10m弱の塔。塔の一番上に『鐘』を捕捉する。 足で行けば昇る為に時間を要する。飛行を用いれば直ぐに行けるだろうか。かなり遠くを穿てる者は、少し動けば十分狙える距離でもある。 「天辺に鐘が見えます。どなたかかお願いします」 長い射程を持つ『ロンドン土産』で自ら狙いに行っても良かったが、まだ『塔』は完全に顕れていない。 「さて、この男、“ピアニシャン”のこういう所といいますかね。こいつは絶対に生かしておくべきではないと思うわけでして」 先の講釈を唾棄する。 つくづく、『ロンドン土産』をやらなければならない。 あばたが先ず『ツグミ』を撃墜する。増えた死体だったが、“ピアニシャン”を回復されるよりマシであるからだ。 不安定だった『塔』は、やがて魔術世界に最初から存在した様に聳え立った。上には『鐘』がある。 悠月が先に放った葬送の魔曲の鎖は、つづらを縛り上げていた。 「“ピアニシャン”並に厄介な相手だと認識を改めた方が良さそうですね」 「……っ! ……っ! こんなもの!」 つづらは引き千切ろうと藻掻く。 また、悠里も大呪縛封鞭に首を締めつけられている。見上げて言葉を絞りだす。 「僕の守りたいものは、命、人の幸せ――それなのに」 「いきなり……いきなり何ですか?」 「今目の前にいる少女1人どうすれば救えるのかわからない――やっぱり僕はまだ弱い」 「意地張ってるだけかもしれませんね。よく分からなくなってきました」 悠月は誰宛ともなく、次の行動を促す。 「――今のうちです。行って下さい」 悠月の声と同時に、アリーサが呪縛を振り切る。 振り切ったとして、どうするべきか。そのまま砕きに行くか。しかし自分の攻撃で砕けるか。最善は何か、最善は何か。 見れば、光介がご都合主義の神の詠唱が目に入る。 「私では一回で壊せないかもしれません。抑えを続けます」 その代わり、と翼の加護を唱える。全員が身体に浮遊感を覚える。 光介からご都合主義の神の術式が放たれた。 「これで、動ける筈です!」 番人へは、適切に対処をしてきた為多く倒せている筈だ。中枢を壊せば勝てる。中枢を壊されて逆転される等の失態をしなければ勝てる。 アリーサと光介の行動は『詰み』へと持っていく為の布石である。 悠里の首を縛っていた鞭が消え去った。すぐに『塔』を見る。 「手を伸ばすしかない」 大呪縛封鞭によって最速で動けなかったが、光介の次に一直線に飛翔する。 烏が唸る。 「参ったな。本来なら直接狙えたんだが」 今回持ってきた弾丸では狙えない。烏はそれも仕方がないと、それなら撃てる奴を撃つと頭を切り替える。 「例えば盾が3枚あるって事だが、全て引き剥がしちまえば両方解決な訳だ」 『肉爆弾』を使わせない為にも、別で消費させるべきなのだ。 烏が一枚目『ツグミ』を弾丸によって剥がす。 「よーし、フラン。みれー! お願い!」 夏栖斗が二枚目の『ツグミ』を飛ぶ武技によって切り裂く。再動、三枚目も蹴散らした。 「オッケー」 もう隔てる盾はない。 フランシスカがすれ違う様に“ピアニシャン”を切り捨てる。ダークネスイリュージョンの一刀が肩から腹部までを大きく分かつ。 楽団員が何か喋っているが、どうせ大した事は言っていない。耳が腐る。その怒りも上乗せしている。 「ああん、感じちゃうエクスタシー」 魅零の体内から刃物の如き骨が飛び出した。 「――黄桜は、ほんとはカストアともうちょっと遊びたかったのだけど」 奈落の気を帯びた太刀で、フランシスカが切った逆側を斬り落とす。丁度Vの字になった格好だ。 頭、胸と腹とそれ以外がズルリと落ちる。 仮面の男は、そんな状態になっても笑っている。V型に切り離されたのに、手足が平然と動いて切り離された部分を回収して、再生しようとする。 「ゴホッ――肺が破られましたが。まあ」 あばたにも骨が突き出る秘術は届いていた。 「『ロンドン土産』を差し上げましょう。Amore e morte――死に愛されるがいい!」 死なないかもしれない。だが殺す。 「英国産シングルモルトは十二分残っているがね」 あばたは、内部から突き出てきた痛みを忘却して放つ。サイレント・デス――静かなる死。 音もなく静寂に、“ピアニシャン”の鼻から上は木っ端微塵に弾け飛んだ。 全力での移動から、手を伸ばさんともう一度動く事で、悠里が鐘楼に入り込んだ。 ここには隠れたる『雄牛』と『鐘』が確かに存在した。 彫刻の様に鎮座する不動の雄牛。1.5m程の大きな鐘はひとりでに鳴っている。 時間制限を知らせる鐘の音色はここから来ている。この物語を終える弔鐘は争奪する者の手で鳴らさなければならないのか。 中枢の破壊と記されていた。一撃で終わらせるべく拳を握りこみ、肘を大きく引く。 「終わらせる!」 大きく踏み込み、拳を振りぬいた。 ●呪本・追 権利者の決定は、中枢を壊した時点で行われる。 「上手くいったのでしょうか」 あばたが見上げた空は色を完全に失っていた。 「酷く血生臭い有様でしたが、果たして誰が為に弔鐘が鳴ったのだか」 ゴーン、ゴーンと鐘の音が響き渡り、それは次第に小さく、小さく、小さくなっていく。 空はガラスが割れる様に、ヒビが入って行く。バリバリバリと魔術世界は崩れていく。 見れば、“ピアニシャン”の死体は早々に煙の様に消えていた。 崩れ行く魔術世界の中――ほんの少しだけ話す機会があった。 「また、負けましたか」 放心状態の白子の肩を、夏栖斗がぽんぽんと叩く。 「何です?」 「君はもう『不吉』から解放されてもいいって思う。それから弱い事は決して悪いことじゃない。強くなろうと前向きになれる訳だし」 「――そこは分かってんだよ! 軟派野郎!」 拳が夏栖斗の顔面に刺さる。 「痛った。じゃあ京ちゃんを見た事ある? 強いけどほら、友達がいないし」 ああなりたいの? と言うと、二発目は静止した。 烏が戦後の一服をする。 「行き着く先は黄泉ヶ辻 京介ってな――改めて言うがね、アークに来て治療を受ける気は無いかい? 生きたいと、強く有りたいと願うならば、W00の呪縛が解ければ新たに進むべく道も見えると思うんでね」 つづらは少し俯く。 「……悔しいですね」 白子は呟いて“ピアニシャン”と同様に煙のように消え去る。 悠里が戻ってきたのは、その消えったその時であった。 「つづらちゃん。君はどうしたら笑えるようになるのかな……?」 悠里の呟きを最後にして。魔術世界はガラガラガラと崩れていく。 視界は闇に閉ざされた。 気がつけば、全員がアークのブリーフィングルームに倒れていた。 今回の担当のフォーチュナがあたふたと内線で手当ての為の人員やら何やらを呼んでいく。 「快さん、生きてますか?」 「……何とか」 光介が最初に快へ回復の術式を施していく。 「俺達は勝ったのかな?」 快の問いに、光介がテーブルの上を見て、また快へと向き直る。 「ですね」 テーブルの上には、しかと呪歌の書が鎮座していた。 「疲れた。あの楽団員、どうなったんだろ」 フランシスカが足を引きずってパイプ椅子に座り、テーブルに頬杖をつく。 「殺せたのかな。殺せなかったのかな」 魅零も最後の状況を思い出しながら、うーんうーん考える。 「ま、いいや。カズト君ごろごろー」 「いやはや、不滅の秘術の解除の手応えがどうも要領を得ない」 あばたも、頭を垂れて突っ伏している。殺れたかどうか定かではない。しくじった。あれはもう都市伝説の類になるのではと考えている。 そこへ、フランシスカはガタっと席を立つ。 「あ、殴りそこねてた」 アリーサも意識を取り戻して、癒し手として働く。 もう少しで、手当の職員が来ると思われるが、できることはしておきたかった。 「何か、焦げ臭くありませんか?」 たどると、それは烏から漂っていた。 「――っ!?」 「一体、誰がこの本を作ったのでしょう」 悠月の魔術師としての興味である。呪本をめくっていく。黒い頁が続いていく。 魔術世界の入り口になっている頁は何もない。 秘めた魔力は賢者の石よりも強大に感じる。ならば一人が持つ代物ではない。真白室長や渇望の書行きになると怪しまれる。 日本の言霊という概念を知る者である。ならば限られてくるのではないか。ぺらぺら捲っていく。 そして、その答えは最後の頁に浮かび上がっていた。 1919 Claude A Debussy |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||

















