
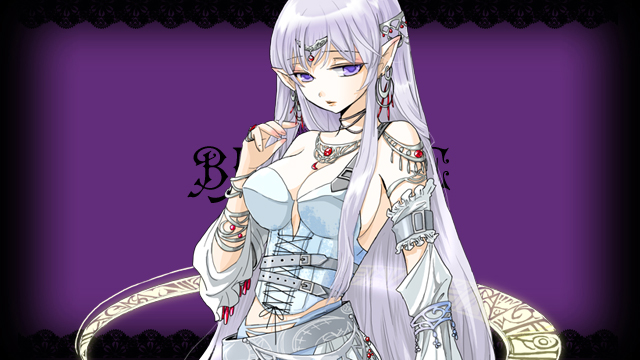

<九月十日>遠く彷徨うカルデアの

|
● カルデアを照らす月の事を、彼女はもう覚えていない。 より正確を期すならば、それが記憶なのか、空想なのか、妄執の一片であるのか。最早定かではないと言った所だろうか。 それでも今宵。このエデンの東の果てに合間見えた月の光は、彼女に何かの感慨をもたらしたには違いない。 古城に満ちる静謐は彼女の好む所であった。 それが例え朽ち果て、自落の末に泡沫と消えうせた廃墟に過ぎなかったとしても。こうして傍らに軍勢を侍らせ戦いの手配を進めることには高揚すら覚える。 グレモリーは月を仰ぎ、笑う。 主より命じられた闘争は、元より純然たる競技であり、命を賭けた遊戯である。 故に彼女はこの地に幻影の陣を構築し、世に数多満ちる民草とは無縁となるように振舞って居た。 望まれようが、望まれまいが、恐らく彼女はそうした事だろう。 人間達の短い生が。つかの間の儚い想いが。姿が。決して嫌いではなかったから。 彼女は遠い記憶の彼方。元より望んで地獄に堕ちた訳ではなかった。 それでも彼女は地獄の掟に忠実である。 夢の彼岸に消えうせた本懐はさておき、数多の大罪に身を委ね、地獄の公爵として軍を率いる事に躊躇いなどありはしない。 当然。その奇妙な生真面目さは幾星霜の彼方に彼女を縛り続けている盟約の履行に対しても同様なのである。 仮にアークが闘争に、この遊戯に応じなければ『応じさせる算段』は出来ていると言うことだ。 それに彼女は人々が闘い。苦しみ。嗚咽し。その想いを命を賭け、熾烈な闘争をする姿を。その儚い生き様を。嫌いではないのだから。 ● ブリーフィングルームに映し出された映像に、現実味はまるでなく。 映像のリアリティだけを追求した出来の悪い映画か、或いはゲームのようにすら感じられる。 「マジで来やがった」 苦笑。過日、三高平に突如現れた『魔神王』キース・ソロモンはこの九月十日という期限を切り、宣戦を布告した。タイムリミットが過ぎたのである。 「キース・ソロモンの配下だな」 分かっていた事態ではあるが、親衛隊との激戦の後、アークの休息はつかの間に過ぎなかったのだった。 「……はい」 故にフォーチュナの少女は、ただの一言で答える。 そもそも配下という言葉自体、適切なのかは兎も角、事実としてあれがキースの命じるがままに活動していることは理解に容易い。 「ここはどこだ?」 「山梨県韮崎市。新府城の跡地です」 「まあ。言われてもわかんねえけど」 キースの噂通り、古文書にも等しい『ゲーティア』が実存するのであれば、グレモリーと呼ばれる魔神は三千年、四千年。あるいはそのもっと昔から存在し、このボトムチャンネルと関わりがあったのだろう。 最早その出自すら明らかでなく―― 机上に散乱する『翠玉公主』エスターテ・ダ・レオンフォルテ(nBNE000218)の資料は、彼女の混乱を物語っていた。 彼女が万華鏡を通じて見たものと、現存するグレモリーの資料――御伽噺にも等しいそれを、戦略、戦術に組み立てるのは、不可能に近い作業だ。 「ゲロ強いフィクサードに使役されるアザーバイドを、ぶちのめしてこいって事だよな」 リベリスタの端的な物言いに、エスターテは微かに微笑んだ。 「能力傾向はどうなんだ?」 戦う以上、何か対策がなければどうにもならない。先読みこそがアークの誇る武器なのだ。 「……分かりません」 「はぁ?」 極めていい加減な回答を吐き捨てながら、眼前の生真面目な少女は視線を落とし、僅かな苛立ちを見せる。 エスターテは大量の資料を広げる。 グレモリーに対する万華鏡の観測結果はぶれ、霞み、矛盾に満ちた記述を多数生み出すに至ったのだと言う。 「分からないということが、能力だってか?」 「はい」 見えてきた。 「おそらく彼女の能力は、未来予知か、それに類する力なのでしょう」 エスターテは、そうとしか考えられないのだと続ける。 そもそも、戦闘可能なフォーチュナは存在しない。 かの塔の魔女――例外中の例外――と接してきたアークのリベリスタ達の感覚は、麻痺している所もないわけではないが、通常そのような存在は交戦相手として想定されていないのである。 「まあ、予習しとけば予想できなくはない事態だろうけどな」 強大な敵であることが容易に予測出来る以上、魔神の能力を万華鏡の観測結果や伝承と照らし合わせ、分析するという作業は随時行ってきてはいるのだろう。 つまりは具体化しづらいというだけとも言える。 「あくまで予測に過ぎませんが……」 エスターテは再びスクリーンに資料を映し出す。 そこには魔神の能力限界予測、グレモリーが持つ道具、軍勢についての予測と考察が並んでいた。 「なるほどね……」 引き出すことの出来る魔神の能力は、配下の質や数まで含め、あくまでキース当人の技量に寄るという事なのだろう。つまるところ制限があるということだ。 まさか異界の魔王七十二人が、軍勢勢ぞろいして狂乱パーティという事態は避けられそうではある。 それがどれほど当てになるかは分からない。それに―― 「やらなきゃ。連中、やらかすんだろ?」 「はい」 だから。 勝って下さい―― 桃色の髪の少女は、静謐を湛えるエメラルドの瞳でリベリスタを見据えた。 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:pipi | ||||
| ■難易度:HARD | ■ ノーマルシナリオ EXタイプ | |||
| ■参加人数制限: 10人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2013年09月27日(金)22:29 |
||
|
||||
|
||||
| ■メイン参加者 10人■ | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
●Lonely Mycroft 『私、死んでも良いわ』 君がそう思えるほどの良い月夜に出来る事を祈って―― 薄紫の一閃を抜き放つ『刃の猫』梶・リュクターン・五月(BNE000267)の脳裏。二葉亭にまつわる一つの逸話がある。真偽は兎も角として多くの人々の得心往くものであるのだろう。 今宵、リベリスタ達が相対する魔神グレモリーは、闘争ではなく、女性の愛をもたらすとされる悪魔だった。 そんな相手に、これほど相応しい言葉はないのではないか。 九月の風は良く冷える。 「ご機嫌麗しゅう、グレモリーちゃん」 昼は未だ残暑冷め遣らぬ盆地の夜ならば、夜露が肌を濡らすように絡みつくのも不思議ではないが―― 七里岩台地に鎮座する新府城跡、藤武稲荷神社に踏み込んだ『覇界闘士<アンブレイカブル>』御厨・夏栖斗(BNE000004)の身体を包み込む圧迫の由来はそれだけではなかろう。おそらく空間が歪んでいる証だ。 「素敵なパーティのご招待ありがと」 まさか悪魔退治をする羽目になるとは思ってもみなかった。 それにしても律儀な相手である。『魔神王』キース・ソロモンといい、この悪魔グレモリーといい。きちんと期日を守り現れたばかりか、何らかの結界を張り巡らし無駄な殺しも厭うとは。 そんな事実に浮かぶのは微かな苦笑。皮肉。そんなのって有り難いにも程がある。第一、倒しても。倒しても。魔神が所詮は現し身なれば、きりがないではないか。 「よくぞ参られた」 頭が痛くなる。微かにハスキーな女の声はまだ若い。その上『日本語』と来たものだ。 そも。相手は魔神。リベリスタ達にとっての分類はアザーバイドなれど、御伽噺の悪魔など、生き物なのか事象なのかの判別も出来る訳がない。 それでもやることなんて決まっている。悪魔を倒せ―― うんざりしても、何も始まりやしない。鉄の心を打ち据えろ。 ――それって物語の勇者みたいじゃん。 だからあえて上を向く。 「ご助力、感謝しようぞ」 照らす月の光から鎔け出るように、女が姿を現した。 白磁の頬にかかる銀糸の髪は美しく。されど彼女が常世の生者ではないことを雄弁に物語っている。 「やったぜ、おっぱいちゃんだ!」 読み通り。彼女は大層悪魔らしい容貌だ。『SHOGO』靖邦・Z・翔護(BNE003820)は嘯く。 叶うならばそうあれかし。パスカルの賭け――決定理論に従うならば、嫌でも見据えなきゃならない相手なんて、そうであるほうがいいに決まっていた。賭けは勝ちだ。後はあべこべになった本音と建前を整理する必要がある。 アーク本部の調査によれば、相手は未来を読むと言う。おそらく戦いにもそれを生かしてくる筈だと言う。 その結論にフォーチュナの少女はかなりの苛立ちを見せていたが、そうと分かっているというのは少なからぬ収穫である筈だ。 予知の力はおそらく――全能ではない。 なぜか。そうでなければ、全能であるならば、そこには戦う意味すらありはしないから。 万能の悪魔が枷を嵌めてまで相対する意義は、未来視に勝る人間の知恵と結束を見たいからなのかもしれない―― そう思っておく。今は信じておく。 大切なのは、読まれても簡単に折られはしない戦いをするということだけなのだ。 で。さ。 「どんなメニューがお好み? 綺麗なおねーさんにはサービスするよ」 もう一度、夏栖斗おどけてみせた。 「そなたらの愛を」 返る言葉もどこか巫山戯て響く。どうやら、この悪魔とやらには皮肉なユーモアも通用するらしい。 「大丈夫? それって結構高いよ」 口調とは裏腹に、リベリスタ達は得物を構え始める。 「値切ろう等とは思わん」 微笑みながら。 「そなたらに恋する我が主への届け物ならば」 リベリスタ達の視線の先に、グレモリーの眷属達が浮かび上がる。 薄絹を纏うしどけない怪異の眼前へ『雪風と共に舞う花』ルア・ホワイト(BNE001372)は舞い降りる。 ベビーブルーアイズに映る夜の精は、華奢な指先をルアへと伸ばし――遮るのは刹那の剣閃――白の領域(L'area bianca)。 舞い踊る氷片は夜と嵐の精、二体を美しい氷像へと変える。 「行くよ!」 奇しくも魔神の名を冠する白杖を掲げる『フェアリーライト』レイチェル・ウィン・スノウフィールド(BNE002411)達、リベリスタ陣営へ向けて。殺到しつつある敵達はなんらかの方法で戦策を共有し、リベリスタ達のこれからの行動へ対策を有する規律を保っているのだろう。 純白の軽鎧に身を包む少女は思案する。予知は万能ではない。その筈だ。少なくとも万能であるならば、僅か数瞬前にルアの攻撃すらも通るはずがないのではないか。ならば付け入る隙とやりようはあるはずなのだ。 今この時。リベリスタ達に給される光の翼は、とりあえず問題なく作用した。 けれど安堵は早いのだろう。 相手は、何をしてくる――? 如何なる時を経ても尚――夜天に輝く銀の円環は悠久不変。 まさか。こうして出会う機会を得られるとは思ってもみなかった。 「――泡沫の現世の月は如何ですか、魔神グレモリー」 月下に問えば、魔神は悪くないと言う。裏を返せば不服なのだろう。 職能を歪め、忌々しくも闘争を強いられるこの状況にか。 そうなのかもしれない。けれど、そうでないのかもしれない。 彼女は状況に忠実である。その力は過去、現在、未来を見通す。見えぬ形なき宝を探し、女性の愛を得る方法をもたらすと言う。女性の愛、形なき宝を暗喩するならば。箱舟との闘争に飢える金色の獣(キース)の為、健気に尽力する姿をして『イケメンの恋を応援するおねえさん』等と呼んでしまえば、あまりに単純、滑稽に過ぎる。けれども存外、魔神の言う通りに事実なのかもしれない。 矢張りごく単純に、ここで見える月が魔のヴェールを通している事へ、か。 興味。栓なき愉悦。故に必然と問いは変わる。 「それはアルダト・リリ(夜の精)。でしょうか」 二天。双月の邂逅。絡み合うのは偶然の符合。数奇な縁だった。 「興味深い御客人。なれどその名は意味を持たぬ」 魔神にとってはそうなのだろう。 問いそのものに意味もない。名に意味を持たせるのは魔術師(にんげん)の領分だ。 グレモリーと呼ばれる魔神の語源を探って行けば、それはゴモリ――ギメル(駱駝)となる。 セフィロト(生命の樹)のギメルはケテル(王冠)とティファレト(美)を結ぶパスである。カバラ数秘術によればタロットの対応は女教皇であり、宮は月を表すという。『星の銀輪』風宮 悠月(BNE001450)は僅かに微笑んだ。他ならぬ彼女自身が西欧起源の魔術師であり、『神秘探求同盟』が第二位・女教皇(The High Priestess)の座に位置する『風宮の悠月』であるのだから。 ルアが斬り付けたのはバビロニアの魔物。バアル妻たるイナンナ。イシュタル。つまりは墜天せしアスタロトに関わる眷属の類とも思われる。 そも。グレモリーが太古の月の女神だとするならば。あの問いへの反応ならば。アスタロトと同郷であっても不思議はない。ならばまさかその真名は創世記に記されたイサクの妻リベカなどと――深淵ヲ覗ク。 「それでは不服か。お若いの?」 「いいえ。ありがとう御座います」 答える悠月は魔術の座学を極めに来たわけではない。駆ける彼女が組み上げたのは魔の盾を纏う大魔術だ。相手が未来を読むのであれば、その上『キースの力量』という枷を――気休めにもならないのだが――持つのであれば。行動はシンプルな力押しに限るのだろう。小細工を弄するのではなく、あえて読まれる前提の定石を打つのだ。 「そっちに!?」 ある種、致し方ないこととして、彼女の反応より僅かに早く、バーニーの壁画に浮かび上がる二匹の歪な梟は、『ぴゅあわんこ』悠木 そあら(BNE000020)に次々と鋭い爪嘴を突き立てた。 「つ――ッ」 梟はグレモリーの側を離れず、行動を共にしてくるものと思われたが、アーク本部の予測からもこれは想定外の事態であった。 よりにもよって一気に最後衛へ。当然それすらも歴戦のリベリスタ達は予見し、彼女を守るように行動していたが僅かに間に合わない。 魔神が用意した特殊な空間の中での戦いである不安に加え、行動が予知されてしまう厄介さの正体とは正にこの事なのだろう。 梟の一撃は突如そあらの精神をかき乱し、燃え上がる怒りはアークの事前予測にはない。不確定の事象だ。 それでも―― 「あたしは、頑張れるです!」 右手の薬指に輝くピンクサファイアが。さおりんが一緒に居るのだから。 戦場に満ちるのは強烈な閃光。邪悪を滅する神聖なる裁きの光はリベリスタ達のシンプルな解答だった。 敵が未来を読むなら。 その答えは? だからどうした。それでもどうにも出来ないようにすればいい。 光を真っ向から身に浴びながら顔色一つ変えぬグレモリーに加え、さすがに梟はすばしこいようだが、側近であろう魔将達は咆哮をあげ、四体の精霊達は確実に動きを鈍らせている。 梟は兎も角、敵による陣形内部への浸透は最小限に抑えられている筈だ。 それに、敵の底が見えてきた。おそらくグレモリーはリベリスタ達の初手の動きを読んだ上で、初手における最も厄介な攻撃を、そあらを倒しきることで防ごうと考えたのだろう。攻防一体の発想ではあるが、リベリスタは甘くない。 続いてそあらへと一気に殺到を始める魔将へ向けて。激突するのは悠月と夏栖斗だ。 魔将が悪魔なら悪魔らしく。コンピュータゲームよろしく遠距離への攻撃も出来るのだろうが、これ以上後衛へ射線は通さない。悠月と夏栖斗へ向けて、敵は蛮刀を纏う闇色の波動を一気に叩き込んでくる。並のリベリスタなら一撃で膝を折るのかもしれない。けれども二人は非凡だった。貫き込まれる蛮刀の一撃は、悠月の眼前。鼻先紙一重で魔陣にせき止められる。眉一つ動かさぬ悠月の、口元だけの微笑みは彼女の魔術が完全な効果を表していることを示していた。 結果として。グレモリーはリベリスタの初手を通してしまったことになる。 それでも未だ、もう一対の精霊達は後衛のそあらへ迫りつつある。 「もずさん――」 人懐こい笑みが『怪人Q』百舌鳥 九十九(BNE001407)に向けられた僅かな刹那。 「どっちに行くか、ジャンケンで決めない?」 キャッシュからの―― 「私に矢面に立てと言いますかな」 意外にも律儀に差し出された怪人の掌に返すのは、パニッシュ☆ 足りない全てを無理矢理補う第一印象のインパクト、それがSHOGOのワンフレーズポリティクス。 ぱーとちょき。怪人と増税。絵面――全身図を見てやってほしい。九十九が左の嵐の精。SHOGOは右の夜の精。 九十九に襲い掛かる赤い毒風(シムーン)。瘴気と雷撃を伴う強烈な砂嵐は九十九の身を切り裂くが――それでも完全な効果は示されない。 「面白い――」 突如レイチェルの頬を撫でる冷たい指先。 全身に走る悪寒。それを打ち消し余りあるどす黒い甘さの源は、そっと持ち上げられる華奢な顎先から。最奥に陣取っていたグレモリーが、なぜここに居るのだ。 精神をかき乱すヴォクス・ルナリウム(月の囁き)は逃れようもなく。 レイチェル自身の意思とは裏腹に心を甘く蝕み―― ●Selenium Eve おそらくグレモリーは、バックアップに入る『Friedhof』シビリズ・ジークベルト(BNE003364)とそあらに早々と見切りをつけ、次手に素速く戦況のカバーリングを行うであろう彼女をターゲットに据えたのだろう。 だが。 「それは――ダメだよ」 レイチェルの全身から放たれる純白。陽光に煌く雪を思わせる聖なる光は、魔性の波動、その顕現を決して赦しはしない。 「連れんのだな」 ほんの一瞬、魔神は眉を曇らせて。円環が煌き、グレモリーは再び掻き消える。 「グレモリーの端末さん御一行様。ようこそ――」 ここが最奥。最下層のどんづまり。歪み詰まれたパンケーキの最後の一枚――ボトムチャンネル。 上位世界とやらの魔神サマ達は招かれざる客には相違ない。 「謀略と恐怖で日本の屋台骨を支える柳生一族の末席におります柳生麗香と申します」 そんな彼女等に対するべきは『おもてなし』の心。 皮肉な挨拶はどこまでも慇懃に。 「指圧の心は母心ともうしますが、わたしは優しくスウィートにデッドオアアライブをぶっ刺す事を心がけております」 粗相なき様、笑ってみせてやる。『うっちゃり系の女』柳生・麗香(BNE004588)はそのまま瞳を細めた。 「ほう……?」 「あなたがたも上位アザーバイトではございますが、弱肉強食が鉄の掟のボトムチャンネルの流儀に従っていただきましょう」 では尋常に勝負ッ!! 抜き放たれた剣、強気の口上も然るもの。されどかくも情報量が少なければ敵の分析も忘れはしない。 それこそ彼女が背負う一族が誇る、太刀以上の武器の一つであるのだから。 必然と浮かび上がる課題。あの円環の力はなにか。 初めの推測では『高く飛ぶ』、或いはグレモリーに呼応して何らかの『遠距離攻撃』を放ってくるものと考えていた。その能力そのものがあるのか、ないのか。それは未だ分からないが、この時点で見えていることもある。 グレモリーは一度目、己が力で。二度目は腰の円環に運ばれて。少なくとも、麗香にはそのように観察出来る。 あの円環は独立して行動している。 とすれば、それは意思を持ち、なんらかの方法でグレモリーの意思に呼応して彼女と行動を共にしているのは確実だ。 そのうえ己が一手。円環の一手を使い、わざわざ近づいたのはグレモリーの万能さを否定するものでもある。 あれがただの道具でないのは分かった。 あるいは麗香等に対して悠月が述べたように魔神ウヴァルそのものであるとでも言うのか。 ともかく、どうであるにせよやることは一つ。敵の手の内が読めてきた以上、予知など考慮にも値しない。後は可能な限り相手の力を読み取り、戦況に反映する――そんな『お・も・て・な・し(裏柳生のやり方)』は如何。 そしてなによりも――麗香が抜き放った剣が鋼の歌声を響き渡らせる。凍りつき、閃光を浴び、動きの鈍った相手など、物の数ではない。 魔神――それが異界の魔王であろうと曲げられぬものはある。 少なくとも五月の目にはそれが確かに映っている。 否。それだけにあらず。 護りの剣は、道理を、人を、心を護る。 揺らめく紫花石の切っ先が氷像となった精霊達を打ち砕く。 「さて、撃つ瞬間や弾道まで読まれてしまうなら。かなりの不利とは言えますな」 仮定というものは、積み重ねれば積み重ねる程、結果は曖昧になって行く。 九十九が銃を構える。 砂塵に覆われるように、蜃気楼のように、薄れ、消えてしまう真実であっても――それでもやるしかない。 波状攻撃であれば避けようもない筈なのだ。 九十九の弾幕と麗香と五月の剣嵐――リベリスタ達の猛攻は二体の精霊を瞬く間のうちに打ち倒した。 これで二体。しかし力の天秤は簡単には動かない。 「ちょっとそういうのは、二人きりになってからにしない?」 夜の精。イドル・リリの魔手がSHOGOの背を越え、遠くそあらの胸を強かに抉った。 彼女は喜悦の表情を浮かべ、その鮮血を、そあらの生気を舐めている。 ――のです―― 強烈な一撃にそあらの意識が遠のく。 「負けないのです――!」 平素ほんわかと見える中。その実、意外にも俊敏なそあらの力をもってしても避けきれぬ精度には一抹の悪寒を禁じえないが。 それでもさおりんを――そして仲間を信じて震える膝を叱咤する。 彼女は深化した。シャンプーだって変えた。 この場に集っているのはアークきってのエース達。強力な布陣だ。負けるわけにはいかない。負けるわけがない。 「やっぱ夜は――あぶないよね」 飄々と態度を崩さぬSHOGOが纏うのは極限の集中だ。 「いくよ――」 夏栖斗の旋棍――炎のアギトは魔将を貫き、勢い衰えぬ闘気はそあらを襲う精霊の背までもズタズタに引き裂く。 月下――闇色の仇花を咲かせる鋭い悲鳴。 「成る程――」 浪々と響く声。 鉄扇を構えるシビリズの瞳が長すぎる十秒の終焉を告げた。 ●Wye + why not. 未来を知るか。 「私はね――」 響き渡るのは神の声。徹底的な殲滅を旨とする闘神の守護がリベリスタ達に強大な力を与える。 「――未来は固定されていると思っているよ」 「ほう――」 グレモリーはさも面白げに首を傾げて見せる。 その未来を誰が決めているのか。神か、悪魔か。いかなる存在であるか等、知ったことではないのだが。 裂帛の闘気を身に纏い、リベリスタ達は更なる刃を振るう。 「未来を知ることの出来る貴様は、およそ大きな優位性を持っているのだろうな」 さりとて。 「ただ一つ、言わせて頂こう……」 「言うてみよ」 貴様がこれから見る未来は、貴様が敗北する未来だ。 さぁ未来を見据えろ。そして死ね! 「不遜――されど愉快な」 ククと耳に響くのは現世ならざる美声の筈なれど、どこか耳障りな魔神の哄笑。 場所は敵陣、逃げ道は無し。 どうせ倒さねば出してもらえないのだろう。 けれど――当然レイチェルは誰1人殺させてあげるつもりなんてありはしない。 これ以上ないくらい満身創痍でもいい―― 「なんだっていいから、生きて帰るんだ!」 俊敏な梟達が更なる攻撃を開始するより早く、Nettare Luccicanteの白金の刀身。Otto Veritaの緑のガーネットが反射する剣先が闇夜を切り裂く。 ルアの双刃は二体の精霊をたちまち氷像に変え、深く傷ついたそあらの傷は、自身の魔力とレイチェルの力がたちまちのうちに癒して往く。 リベリスタ達の立て続けの攻勢は止まらず、グレモリーは早くも夜と嵐の精を全て失いかけている。 敵の予知能力に対して、リベリスタ達が仕掛けたのは純粋なる力比べである。 ともすれば強引に過ぎる手段なのかもしれないが、今のところそれはしっかりと機能していた。 砂漠の駱駝(ギメル)。その背の遠く向こうに浮かび上がる蜃気楼のように、歪む未来への対抗手段としては、この上もなく分かりやすい単純明快なプランで真正面から闘うのみ。 或いはそれすらも『魔神王』キース・ソロモンの望み通りだとでも言うのか。 兎も角。それから幾順かの激闘。剣と剣、牙と牙は魔神とリベリスタ達をシムーン(赤い毒風)色に染め上げる。 後は。 ――願わくば勝利を。 ナイトメアダウンの悲劇以降、リベリスタ無きこの地は極東の空白地帯と揶揄され、強力なフィクサードである主流七派に牛耳られてきた。 そんな中で新進気鋭のリベリスタ組織である箱舟(セイギノミカタ)は、瞬く間のうちに主流の七柱を八柱とするまでに成長し、次々にバロックナイツを下していった。 それを――魔神王は喰おうと謂う。 さぞ喰い甲斐があるに違いない。五月が魔将に剣を突き立て、九十九の弾丸が胸を穿つ。 月の力で戦場をかき乱さんとするグレモリーの戦術は、バッドステータスへの耐性に秀でたリベリスタにはいまいち機能していない。 麗香の目には、読めると云われる未来の限界というものも露呈し始めているのだろう。即ちグレモリーはリベリスタ達それぞれが次手、能動的に何をするかという情報だけを得ているのであり、その結果までは分かっていないと推察出来る。 検証。果たして本当にそうなのか。 力の限界など知れたことではないが、少なくとも今と同様の顕現では、そしてもう一つの条件として戦闘中に限ればこの程度だという事だ。 先のシビリズの言葉を借りれば、『固定された未来の予測』は出来ていない。 「それで、これから何度闘えばいいのかな」 少なくともグレモリーは、この戦いの中でもリベリスタ達の能力に合わせて戦法を変えてきている。 仮に――考えたくも無いが仮にもう一度闘う機会があったとして。グレモリーが予めリベリスタ達に仕掛ける予定の攻撃の、とりあえずの結果まで読み取って挑んでくるのであれば、行動効率は桁違いに上がるはずだ。それはリベリスタ達の布陣と能力まで読み取っているに等しいからである。 殿とばかりに。癒し手のバックアップを続けるシビリズの心とて、聖骸の闘衣により揺るぐ事はなかった。 そんなにも。 「力と力がお望みならば――」 得体の知れない御伽噺の怪異は、白魚の指先を向け示す。 やはり早々に策を変える必要があるのだろう。 「ようこそ――グレモリーちゃん」 グレモリーは夏栖斗と向き合う魔将と入れ替わりに少年の眼前へと舞い降りる。 陣形の混乱はちょっと頂けない。敵とて動くもの。当然の事だ。ならばどうする。 「歓迎、痛み入る」 突如、爆発的に膨らむ魔力。 グレモリーの指の先。中空に咲き誇るエンピレオの砂薔薇が砕け、砂塵を伴う灼熱の業火が五月、ルア、九十九、翔護、麗香に吹き付ける。 予測は出来ていた。 体中が焼け焦げ、悲鳴をあげる中、ルアの胸に突き込まれたのは巨大な魔将の蛮刀だ。 痛みすら感じはしない。 ぬるりと滑る感触に怖気が走る。 「無駄よ」 それじゃ私は――殺せないわ。 鮮血と共に口を滑り落ちた言の葉に、ルア自身が驚いた。 最前線に立ち続ける事が危険であることなど知っている。 怖くない訳ではなかった。ほんの少し前まで戦いに怯えてばかりいた事は、今でも鮮明に思い出せる。 もしかしたら――死ぬかもしれない。そうも思った。 けれど両手に握られた二振り。太陽と花、真実の瞳は大切な人に託された想いの結晶だ。 待っている人達は。弟は、親友は、父は、母は――何よりも大切な恋人は。 彼女が無事に帰る事を望んでいる。 だから―― 視界を歪め、はらりと零れる涙は決意の証。 守るんだ。 みんなの心を。この場に居る仲間達の心を。 だから――――! 絶対に。 「勝つの――ッ!!」 想いから放たれた真空の刃が魔将の胸を貫く。 刹那の霧散は、仮初の命の終焉を告げた。 ●Harsh Mistress しかして未だ戦いは終わらない。 数を減らしつつある魔神の軍勢とリベリスタ達の拮抗は徐々に崩れつつあった。 月の囁きは夏栖斗を、ルアを襲うが、抗いがたい蠱惑の波にも、シビリズの秘技。そしてそあらとレイチェルの癒しが功を奏していた。これまでグレモリーの攻撃は散発的であり、強力な火炎嵐――エンピレオの砂薔薇にそれほど頼る様子は見えない。 それはなぜか。 麗香と悠月の分析があれば、その理由は月下の元に晒される。 グレモリーは配下とする魔神の伝説を持つ。即ち一説にはグレモリーの騎獣たるウヴァル。そして魔界最強の魔獣たるマルコシアスと、その二柱が率いる軍勢達。 それ自体、嘘か真かは分からないのだが。さりとて魔術というものは、そう単純なものでもない。 真偽は常に表裏一体。眼前の事象、魔神達が話す言葉、その姿は抽象化された象徴に過ぎないのかもしれず、また逆に目の前のこれがその本質そのものの生き写しであるかもしれないのだ。 つまり、出そうと思えば出せるとしても不思議ではない訳だ。 ならば尚更。なぜ、この場にその二柱が居ないのか。 推察される見解は幾つかある。一つはこの軍勢が魔神王キースの限界点である事。ここはこの際どうでもいい。どれもこれも手当たり次第に制御すれば、魔神一柱あたりが持てる力が減衰する。あるいはキース自身が満足に闘う力を残す上で、制御の限界がある。どれもこれも曖昧な過程に過ぎないが、その程度だけならば当然の推察に過ぎない。 他にはどうか。愛情を司り、己が社会に忠実ならばこそ、彼女はたとえそれが仮初の肉体であったとしても、己が旧知が傷つくのを嫌うのではないかという点。 故に、味方を巻き込む可能性のある範囲を侵す火炎嵐を闇雲に行使する訳がなかったのだ。 つまりなかなか仕留めきれぬ梟の最後の一体を九十九の弾丸が貫けば、再び状況も変わるという事。 もう一つの戦慄すべき事象。魔神はある程度『自主的に』行動出来るという点だ。 ゼパールやビフロンスがこの世界に姿を現したような、何らかの方法で。グレモリーの窮地に、彼女を慕う魔神が現れでもする可能性はあるのか―― あるいは。キースという男はそれを考慮してグレモリーという魔神を選んだのか。 魔神の持つ傲慢さ、強大さ。何より仮初の存在であることを考えれば、ここで顕現される可能性は薄いのだろう。 それでもここから予想される火炎嵐の乱発にも配慮するならば早々に決着をつけるべきではあるのだ。 出来るのか。 敵の数はずいぶん減った。それでもグレモリー自身と、そして得体の知れない円環は無傷に等しいではないか。 それに反してリベリスタは満身創痍。 誰もが予感した。 ここの先は死線。命と命の壮絶な削りあいになるのだと―― 「SHOGOちょっと、うちのおじいちゃんに似てるトコあって」 この期に及んで軽口を叩く彼とて、次々に迫り来る炎嵐の前には無事な筈も無い。 「暑いの苦手なんだよね」 リベリスタ達は梟と最後の魔将までも倒しきり、残す相手は未だ涼しげな表情を崩さぬグレモリーただ一柱となっていた。 キャッシュからの――パニッシュ☆ SHOGOが極限の集中から叩き込んだ13番目の銃弾は、硬質な円環を穿ち、深い傷を与えている。 「こんな風に出会いたくなかったよね」 出来ればコンパで。年金も心配な世代なら、秘密の宝とやらの在り処を教えてほしいものだった。アシがつかなければ最高だろう。もしかして、勝てば教えてくれたりするのだろうか。 其れはさておき、移動の他に何をしてくるか判らない以上、こうするしかないという部分もないわけではない。 少なくとも今の時点で判明している能力――空間転移それ自体も厄介な上、おめおめと逃げられるのも癪に障る。 「ふむ……実に」 何人が膝を折りかけたのか、最早数えるのも面倒なくらいだ。 「実に宜しい!」 ここが最早力と力がぶつかるだけの単純な戦場なれば。 「未来も! 過去も! 関係無い!!」 ただ闘争を。もっと闘争を。 血反吐を吐き捨て、奥歯を噛み砕き、四肢の全てが潰えるような闘争を。 この刹那を――楽しもうではないか!! 哄笑。劣勢如きに潰えるシビリズの闘志ではない。 むしろ好ましい程だ。今一度、神々の黄昏が戦場を覆う。 「これだけの悪魔を召喚するなんてやっべーな、キース」 けどさ。 あの時、夏栖斗等を送り出した桃色の髪の少女は言ったのだ。 「可愛い女の子に『勝ってください』なんて言われたら男なら――そうするしかないじゃん!」 夏栖斗はグレモリーの懐に飛び込む。対の旋棍を握り締める。目の前の強大な魔神は、意外にも小さく見えた。 この子だってただのオンナノコ――じゃあないよね。そんな事は分かっている。 拳が唸りを上げる。 倒したらさ。 勇者だって褒めてくれたりする? 現世のグレモリーが只の分身に過ぎないとしても。 誰に。目の前の魔神に。それとも――Forget-me-not. どこまでもただ真っ直ぐに。 全身全霊を篭めた裂帛の一閃。咲き誇る虚ロ仇花。 「クックックッ」 ずた布のように成り果てた外套。仮面の奥で笑う九十九は、銃口をグレモリーに向ける。 「ああいった姿ですと、なんとなく撃ち難い気もしますがのう」 「我が身。壊してみせよ」 まあ、なんと言われても撃つのですがな、と。これまた数奇にも、月の女神の加護を纏う九十九の銃弾は、銀光を纏うグレモリーの白い身体に血花を咲かせる。 どうせ少女の姿でも魔神は魔神。夜や嵐の精とて同じだ。 「まさか血が赤いとまでは思いませんでしたがな」 はて。倒せば褒美にカレーの未来でも教えてもらえるのだろうか。 立て続けの火炎嵐にもリベリスタは倒れない。 そこに想いがある限り。 決して負けない。 護るものがある限り。 オレの剣は護りの剣だ―― 君の笑顔がある限り、オレはどこまでも強くなれるよ。 この月夜に君が望む事があるならばオレは矜持を掛けて聴こう。 「さあ、お嬢さん」 願わくば――戦おう。 君が楽しめる夜を与えられるように。 伝承等知らない。 ただありったけの想いで君にぶつかろう。 眼前の魔神に向けて闘気の全てを解き放つ。 生と死を分かつ一閃。 ダメージは確実に与えている筈だ。 それでもグレモリーは倒れない。 続く反撃の炎に麗香の膝が折れるのは二度目となる。ここまでずっと戦況を分析し、戦闘をリードし続けたとて、最早立ち上がる力はない。 最後の時が迫ろうとしていた。 撤退か。撃退か。それとも―― 命を賭けても良いと想えど、犬死にをする云われはない以上、潮時というものも近い。 されど。 矜持は此処に在る。 君が思う今。五月は剣を振るう。戦場を覆う鮮血と炎。 差し違えにも見えた一閃に、されど五月の視界が揺らぐ。 お嬢さん――月はどんな色をしてる? 倒れても、前へ。 二人もの撃墜を赦してしまった。 レイチェルが桜色の唇をかみ締める。鉄の味がする。 追い払えれば上々。倒せるならば最上―― そう思っていた。 けれど。強力な眷族とすら比較にならぬほど強大なグレモリーに彼女等は無力なのか。 違う。 こうしてわざわざ敵陣に乗り込んで来たのはお互い様である。 上々止まりじゃ満足なんて出来はしない! こっちだって逃がすつもりなど無いのだ。 「ここで倒させてもらうわ!」 絶対! 戦場に再び満ちる聖なる光はリベリスタに最後の力を与える―― 一瞬の逡巡。そあらは思案した。 恐らく二度の火炎嵐を食らえば終わりだ。ならばここに癒しを重ねたほうがいいのではないかと。 けれど。 僅かなことで戦況が覆るほどの敵の火力である以上、そして既に二人のリベリスタが倒れている以上。 別の手段を選ぶほうが勝利に近づけるのではないか。 「攻撃こそ最大の防御です」 そあらは『とちおとめEX』を天高く掲げる。 どうせ未来を読むなら、あんな金髪の狂犬じゃなくて、己とさおりんの未来を見てほしかったのです。 今一度、裁きの光が戦場に満ちる。 きっと。 やっぱり聞かなくて正解だったのだ。 なぜなら。未来は己が手で切り開くものなのだから。 「負けない――ッ!」 炎の洗礼を浴び、満身創痍のルアが振るうのは二刀の閃光。 真空の衝撃が切り裂き――尚ももう一度。 立て続けの刃は戦場を純白に染め上げる。 なのに…… 「これで最後だ。リベリスタ」 グレモリーが瞳を閉じる。 最後の一撃。 指先が虚空を切り、浮かび上がるエンピレオの砂薔薇が―― ――虚空に掻き消える。 指先が至高天の陣を描けない。 グレモリーは瞳を閉じたまま、皮肉気に笑う。 これまで幾度か浴びせた真空刃のクリーンヒットにも魔神は耐えていた筈だ。 だが磨き上げられた精度が、それを上回ったということか。 「グレモリー」 「名を聞こう――『現の月』」 女教皇が一振りの剣を天高く掲げる。 左手に握られた『月の光の剣』。 「『銀の車輪』の名に懸けて、貴女を祓います――――『古の月』!」 魂を斬り裂く悠月の秘奥技がグレモリーの豊かな双丘に吸い込まれ。 『金の車輪』を伴う古の女教皇はそのまま中空へと溶け消えた。 月が――綺麗ですね。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||

















