
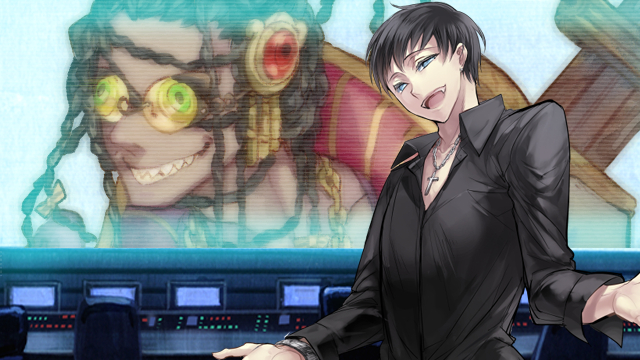

<三ツ池公園大迎撃>球体演技

|
● 「……先日『君の手を借りるのも今回限り』等と大見得を切っていたと記憶していますが、何故我は此処に呼ばれているのでしょうね」 「……その分料金は割り増ししてるんだから見逃してくれないかなぁ……」 「前回までは同属の誼で割り引いてたので正規料金です。――今までで最高の出来だ、と言っていた『其れ』に自信がないので?」 今や異形の博覧会の様相を呈している三ツ池公園で、『オーバーステップ』灯屋諒次に問いながら、等活は傍らの異形を見上げた。 比較的長身の諒次を二人縦に並べたよりもやや高い丈……いや、直径を持つそれは、今まで彼が作った中でもとりわけ異様な風体をしている。 単純に述べれば、球体だ。 だが、透明な表皮には幾つも幾つも顔が浮かんでは消えて行く。 苦悶の顔。老若男女を問わず、透明な表皮に肌色の顔が現れては埋もれて消えてまた現れた。無数に浮かび上がる泡が、水面で弾けて消えていくのと、よく似ている。 視線を下げれば、子供の様なサイズの青色の球体が付き従っていた。 「いいやぁ……本来ならば、この『オーナメント・オーナメント』たちと私たちで充分なはずだったんだよねぇ……けどさぁ……」 視線が動く。その先にいたのは、複数の男。六道研究者ではなく、ましてや等活の部下でもない。 諒次の顔に浮かんだのは、不快。 六道紫杏への忠誠と、研究への貪欲さ以外の感情が薄く物事に頓着しない彼にとっては珍しい表情だった。 「……紫杏様はこの『メインディッシュ』にあたり援軍を呼ばれた。それはまあいいんだけどさぁ……私らの所にも更に割り振られそうになったからさぁ……」 「姫君の命が気に食わないので?」 「違うよ……、……合理的に考えれば受け入れても問題ないけれどねぇ……ただ、あの連中は『紫杏様』の為に動いてるんじゃない。それが気に食わないだけだよ……」 一歩、二歩、進んで下がって元通り。諒次の言葉は主観的な感情論に因ったものであったが、確かに即席のあの『援軍』は奇妙であった。等活とて六道構成員全てを把握している訳では当然ないが、大半は見た覚えもない。幾ら紫杏の言葉であったとしても、戦力の一翼を任せる信頼に値するかと言われれば――否なのだろう。 無論、等活も『六道紫杏』の為に動いている訳ではないが、金で雇われある程度状況や人柄を把握している分まだマシ、という事か。 「――まあ、何せよ地獄の沙汰も金次第。我らは金払いの良い客は歓迎します」 歩みに合わせて異形も進む。小さな青い球体は素直にころころと転がっていたが、大きな球体はその下部に生えた無数の腕と指を使い前進している。さながら、不恰好なクラゲの様でもあった。透明の触手が生えて肌色の腕となり岩を越えて指で地を掻き線を描いてはまた球体の中に飲み込まれる。浮かんでは消え、消えては浮かび。 肌色の顔が消えた一瞬、透明な表皮の内部が窺えた。 浮かんでいたのは、また無数の球体。赤い球体。真っ赤な球体。 『オーナメント・オーナメント』に取り込まれ、肉団子と化した人であったもの。 バルーンアートを等活は思い出した。透明な風船の中に、小さく赤い風船を幾つも浮かべたのに、似ている。骨を砕き肉を刻みながら『餌』を内部に取り込む異形を愛しげに撫でて、諒次は笑った。 「君は金の為に。私は紫杏様の為に。そして我らが全ては、紫杏様の享楽の為に――」 ● 「……さて皆さん、既にもう知らせ自体は届いているかと思われますが、六道によって三ツ池公園が襲撃されました。皆さんのお口の恋人断頭台ギロチンがご説明しますので、よく聞いて下さいね。面倒ですからよく聞いて下さいね」 繰り返し、『スピーカー内臓』断頭台・ギロチン(nBNE000215)は息を吐いた。 「今回の襲撃は『キマイラ』による事件を多数発生させている『六道の兇姫』こと六道紫杏とその取り巻きによるものです」 とは言え、このタイミングで襲撃を仕掛けてきた理由は不明だ、とフォーチュナは告げる。 公園は先日、ケイオス・"コンダクター"・カントーリオ率いる楽団の構成員による襲撃を受けて警備体制を強化したばかりだ。決して手薄であった訳ではない。 「ただ、理由としてはアシュレイさんによる推察がされています。紫杏と何らかの関係を持つバロックナイツの『モリアーティ教授』が彼女に援軍を派遣したからではないか、と。故に紫杏は警備強化を振り切って襲撃へと打って出たのかも知れません」 紫杏の狙いは、公園に開いた『閉じない穴』であろう。 彼女は研究の為であれば手段を選ばない。穴を使い更なる崩界を招く事で、研究を進めようというのだろうが――それこそ先日の楽団員の襲撃が、紫杏を焦らせたのかも知れない。 「ですが当然、ぼくらとしては見逃す訳には行きません。紫杏側も今回は本気で戦力を編成し攻め込んで来る様子ですので、アークとしても少数による対応は不可能と判断しました。よって大規模部隊による防衛作戦を展開します」 広げられた三ツ池公園の地図。 これを見るのは、幾度目だろうか。その一つ、水の広場と呼ばれる付近にギロチンは丸を付けた。 「皆さんに向かって頂くのはこちらになります。迎撃して頂くキマイラは『オーナメント・オーナメント』と名付けられたものです。革醒者を幾人も取り込み、その能力を底上げしている様子です。小型のものもいますが、それは製作者である研究員を庇うための要員です」 更に、とギロチンは資料を広げる。 「六道の研究員が四名、護衛が四名。加えて援軍が四名。……つまり総計二体と十二名。今回は彼らも戦闘に参加します。研究員は戦力的に護衛四名よりは劣りますが、侮っていい程の相手ではありません。特にリーダー格の『灯屋諒次』はそれなりの実力を有する覇界闘士です」 ひょろりとした頼りなさげな男の手足には、装甲。 「で、護衛は『地獄一派』を名乗る集団の一人『等活』と彼が率いる部下です。先程の研究員は紫杏の命を達成しようと粘るでしょうが、こちらは金で雇われている側ですのでうまく使えば退却へと追い込めるかも知れません」 ですが、とギロチンは溜息を吐いた。 地図から目を離し、端末を操作する。現れたのは、一人の男。 「重大な懸念がもう一つ。バレット・"パフォーマー"・バレンティーノ……ケイオスの私兵集団『楽団』の実力者です。彼もこの公園内にいます」 ぶつかり合うのは、アークと六道。共に強力な革醒者を有する集団。 死者を操る楽団において、これほど渡りに船な状況もない。 死の香りを嗅ぎ付けた彼らは、ハゲタカの如くその死を掠め取ろうと公園へと現れた。 「公園内を移動する彼のルートは万華鏡でも把握し得ない。……先頃の動きを見る限り、表立って派手に動くつもりはまだない様子ですが、それでも存在自体が脅威である事に違いはない」 頭痛がする、とでも言いたげに、ギロチンは目を瞑る。 「六道を殺すな、とは言いません。そんな手加減ができる相手ではありませんから。けれど――死者を操る楽団が、公園内に潜伏している、という事実だけは気に留めておいて下さい」 何より。 「……皆さんは、決して、死なないように。お願いします」 ● 十二月の酷く冷たい風に混じるのは、血の匂いであり濃密な死の匂いだ。 聞こえてくるのは生と死の交錯。 確かに、『The Living Mystery』ジャック・ザ・リッパーが散ったというこの公園には、彼が引き連れてきた『死』が蟠っているのだろう。 それだけならば、余り興味は惹かない。けれど今は、より好ましい音が響いている。 バレットは、軽く首を回して唇を笑みに歪めた。 「やっぱ音楽ってのは生が一番だろ。昔の再生音じゃ興奮が足りねぇ」 モーゼス・“インスティゲーター”・マカライネンが誇っていた通り、この場の残滓は、なるほど強力であった事だろう。だけれども、好みからは少し外れた。 生身の肉同士が千切れ骨が砕かれ内蔵が踏みしだかれる音が、生者と死者がどちらも等しく血に塗れ命であったものの欠片を散らす音が、何よりも好ましい。 その点で言えば――現状、この公園はよりバレットの『好み』に近付いていたと言えよう。 それに。 バレット・"パフォーマー"・バレンティーノ。 『楽団』第一弦楽器。 介入を確認――。 「……さて」 茂みの向こうの囁き声。一つ残さず聞き取って、男は笑う。 誰だかは知らない。が、少なくとも聖櫃や、騒ぎを引き起こしたマフィアとは異なる連中に違いない。 「小難しい観客も増えてるみてーだし、カデンツァをもう少々、ってな」 |
| ■シナリオの詳細■ | ||||
| ■ストーリーテラー:黒歌鳥 | ||||
| ■難易度:HARD | ■ ノーマルシナリオ EXタイプ | |||
| ■参加人数制限: 10人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |
■シナリオ終了日時 2012年12月30日(日)23:54 |
||
|
||||
|
||||
| ■メイン参加者 10人■ | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
● あの日は紅の月だった。 嘗て歪夜の使徒によって傷付けられた三ツ池公園は、一年の歳月を経て傷口を蹂躙されようとしている。 抉るナイフを手にしたのは、六道の系譜に連なる姫君、紫杏。生まれながらにして『探求』という狂気に染まった彼女は、掛け合わせの生物、異種の神秘を組み上げた『キマイラ』の更なる発展を、『完璧』を求め、下層世界に入った皹へと手を伸ばした。 それを持ち上げるのは、探求に取り憑かれた六道研究者。 彼らは紫杏の為、己の探求欲求の為、異形を引き連れこの公園へ現れた。 「けれど、全く厄介ねぇ。楽団がいるだけで作戦が立て難いったらないわ」 愛銃を手にした『ヴァイオレット・クラウン』烏頭森・ハガル・エーデルワイス(BNE002939)が、帽子のつばに隠れた空を仰ぐ。 そう。アークがこの場で警戒すべきは、狂気の姫君と取り巻きだけではなかった。 バロックナイツ第十位『福音の指揮者』ケイオス・“コンダクター”・カントーリオ率いる『楽団』が潜んでいる。ネクロマンサー、命を失った存在を操る彼らは、猛獣のお零れを掠めるハイエナの如くこの戦闘が呼ぶ『死』へと纏わり付いていた。 「早い所対策を確率しないとポーランドの二の舞かしら。でも、その前に」 エーデルワイスは指先で体をなぞり、血の掟を刻み込む。 「血と鉄と炎の加護よ。今宵も生贄を捧げましょう」 そんな姿を前にして、『百の獣』朱鷺島・雷音(BNE000003)は目を伏せた。 彼の楽団員が一人、バレット・"パフォーマー"・バレンティーノも、この公園にいるという。雷音にエーデルワイス、『九番目は風の客人』クルト・ノイン(BNE003299)、『K2』小雪・綺沙羅(BNE003284)は彼とつい先日見えたばかりだ。 バレットに奪われた命――十を超える裏野部の構成員と、『junkie』威岐路・死祢。楽団の戦力増強を防ぐ為に死者から守るはずであった彼らの命は、容易く彼らの指の隙間から零れて行った。 死自体を嘆く訳ではない。死祢も他の連中も、普段ならば救いがたい連中だ。けれど、楽団はそれよりも厄介な出来事をこの国に撒き散らす。死者はその一端となってしまう。 「漁夫の利狙いとかマジ勘弁。二度も美味しい思いをさせてやる義理はないよ」 綺沙羅が首を振った。あくまで『六道紫杏』と『アーク』の戦い。この場で痛む事のない楽団の腹を膨れさせてやる必要はない。 「ねぇ、もし」 不安の色を隠さずに、『いつか出会う、大切な人の為に』アリステア・ショーゼット(BNE000313)が呟いた。唯一の専業回復手として厚い回復の力を小さな身に詰め込んだ彼女は、戦闘や力に溺れるでもなく、一人の心優しき少女だった。 「もし、私が死んじゃったら、体は木っ端微塵にしてくれるかなぁ……」 けれど、その覚悟は決してただの少女に非ず。 死体を操る楽団という存在に対し、己の体を好きに使われるというのならば、その身を壊してくれと、宵色の目に確たる決意を込め、仲間に願う。 回復手を狙うのは、アークも使う常道。故に、後方にいようが決して安心はできない。 「大丈夫だ。生きて帰るんだからな」 アリステアの肩を、振り向いた『てるてる坊主』焦燥院 フツ(BNE001054)が叩いた。少女の姿は彼の背に隠されて、敵からは見えにくくなるだろう。例えそれが微々たる効果しかないとしても、フツはそこを譲ってやる気などない。 「それに、やたらと数が多いが、俺らのやる事はキマイラの撃破だ」 『リベリスタ見習い』高橋 禅次郎(BNE003527)の言葉通り、彼らに課された使命は、『オーナメント・オーナメント』と『ブルーオーナメント』の撃破。 必要以上に留まる必要もなければ、敵を全滅させる必要もない。 或いはそれは、『それ以上の成果は困難』とアークが判断したからかも知れないが――最低限、撃破が叶えば後は楽団が訪れようが撤退するだけである。求められているのは、殲滅ではない。 ああ。影が差す。 人ではありえないフォルムに、無数の顔を貼り付けた異形が、やってくる。 その姿に唇を噛んだ『紅蓮の意思』焔 優希(BNE002561)は、すぐに頭を振って冷気を身に染み渡らせた。 例えどれだけその行為が許せなかろうと、目的を見失ってはならないのだから。 ● リベリスタの想定と違ったのは、ブルーオーナメントを伴った『オーバーステップ』灯屋・諒次が前へと出てきた事だろうか。 並んだのは、黒スーツの男。地獄の第一層、等活。 だが、それは――安全策を用いない、六道の『本気』とも取れた。 戦える者が前へ、アークの防御を打ち破るための陣形。 「さぁて、お出迎えどうもありがとう……」 にたり笑った白衣の男の声が終わるより早く、場は戦闘の渦と化す。 真っ先に駆けたのは、『LowGear』フラウ・リード(BNE003909)。白い吐息をその場に置き去りにして、金の髪を流し巨大な球体へとナイフ片手に跳躍した。 「――我が身が最速である事を今此処に証明する」 速度を求め速度に焦がれ速度に取り憑かれたフラウの刃は、執念の威力を以って球体へと幾度も突き刺さる。麻痺が効かない事などは織り込み済み。狂気の速度を乗せたフラウの刃は、他のどの技よりも高い威力で敵を迎えた。 これ以上の速さなど、並のソードミラージュには求めようがない。 「お話になんないっすね」 大幅に出遅れた刀輪処を見て、フラウは肩を竦める。 その刃を、優希が迎え撃った。 「貴方達、仲良いのね」 少しの呆れと皮肉を滲ませて、『蒙昧主義のケファ』エレオノーラ・カムィシンスキー(BNE002203)が声を掛ける。視線の先には、並ぶ男ら。 「……羨ましいかい?」 「アークのご活躍のお陰でね。護衛依頼が減らないのだよ」 ちらりと視線を投げた諒次に、溜息を吐かんばかりの嫌味を乗せて等活が答える。 「あら、千客万来でしょう? 感謝して欲しいくらいよ」 「それ以上に邪魔されているのでね。感謝はせんさ」 薄く笑った少女の顔はそのままに、後方へ向けて気糸が放たれた。狙うは極苦処、回復手。理性を失わせ己へと攻撃を向けさせる為の糸は惜しくも直撃は叶わなかった様子だが、当たる目は決して低くはない。ダメージを与える事だけが目的ではないのだ。癒し手の意識を攻撃に向けさせれば、その分六道側の継続戦は難しくなる。 だが、それは六道側も理解している事。 「やれ、我は時間の掛かる相手は嫌いなのだが……君は他に任せていては余計に時間が掛かりそうだ」 空を掴むように伸ばされた指先にエレオノーラが飛び退けば、足先を気糸に僅かに引っ掛けられた。 邂逅も四度目。 実際にエレオノーラが等活と交戦したのは一度のみ、諒次に到っては今回が初めてであるが、地獄一派を含めた六道は彼の戦闘データを充分に得ている。 身軽さを生かし最前線で当たらぬ的として立ち回るエレオノーラの厄介さを理解した上で、出し惜しみは必要ないという事だろう。 得たデータに更なる精密な演算を加えた論理戦闘者、優れたプロアデプトである等活の攻撃はエレオノーラをも其の手に捕らえ得る。が――囮として立ちはだかっている以上、攻撃を引き付けるのはエレオノーラにとってもいっそ望む所であった。 「あたしを捕まえる間に老衰で朽ちないでね?」 その背を追いかけるように放たれたのは、フツの声。 「聞け! オレ達はこの戦いに負けるつもりはない。キマイラは破壊する」 挑発か。 それにしては余りに安いそれを研究員が嗤うより早く、彼は言葉を続けた。 「ただし、それ以外の者にトドメは刺さない。――この戦いを見ている連中がいるからだ」 「ほう?」 「お前さん達も聞いた事があるだろう。バロックナイツのケイオスが率いる『楽団』のバレット・"パフォーマー"・バレンティーノ!」 「例えその名は知らずとも、『楽団』の最近の動きくらいは知っているだろう? なぁ、等活」 間をすり抜けたクルトが、拳を握り十二月の冷気よりも尚冷たい一撃を巨大な異形へと叩き付ける。それは唯一、異形の動きを止め得る手段。 止めるまで、何度でも。氷を扱う細身の格闘家が、決して攻撃の手は緩めずにヴィオラの目を等活に向けた。 「裏野部に威岐路・死祢って奴がいた。お前と同じプロアデプトだ」 「……ああ。あの喧しい狂人か」 「実力者『だった』けれどね。バレット率いる楽団に襲撃され、配下二十人と共に交戦したが、今は奴らの手駒だ」 「半径20m毒を大盤振る舞いする厄介な奴だよ」 「ボクらは死祢を助けられなかった。もしこの場に引き連れて来られたならば、簡単にはたおせないだろう」 綺沙羅と雷音が繋げる。ぎゅっと唇を噛んで、届かなかった手に、悔しさを混じらせながら言葉を紡いだ。 「俺達のどちらが倒れても、死体として奴等に利用される。……ここは退け、灯屋!」 目前の男に叫びながら、優希は平時ならば爪が掌に食い込む程の強さで握った拳を振り被る。敵の間を抜ける事をせずにすんだのは、彼にとって大きな幸いであった。 今回の目標の一つであるブルーオーナメントは、諒次と共に在ったのだから。 「奴らの戦力は、自ら集めた死体だ。それも強力な革醒者の死体を求めている」 「まっ、そういう事っすね。うちらが死んでもあんた達が死んでも、連中にとっては結局万々歳」 フツの言葉に続き、フラウが冗談のように溜息を吐く。 「うちらが死んでどの程度のモノが牙を剥くか、今から試してみるっすか?」 ナイフを構えて問う、それは剣呑な挑発。 けれど、そんな言葉が楽に通じる相手ではない。 難なく受け止めたブルーオーナメントの向こうで、諒次が、研究員が嗤う。 「……そんなに言うんだったらさぁ……君たちが退いてくれればいいんじゃないかな……」 「紫杏様が欲しいのはこの公園」 「紫杏様が求めるのは更なる成果」 「君達も『使えそう』だから勿体ないけどねぇ……退いてくれたらそれでもいいよ……。ほら、そうすれば死体なんか出ないだろう? 簡単じゃないか……」 両腕を広げる諒次に、退く気などないのは明白。 そして一斉に口を動かし出したオーナメント・オーナメントの行動が、何より六道の指針を語っている。 いたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいいいいいいいいいいいいいいいい。 無数の唱和、無数の怨嗟。いたい。いたい。放つ単語はそれだけなのに、伴うのは無数の感情。苦しい辛い怖い嫌だ助けて死にたくない嫌だった死にたくなかった助けてくれなかったお前も死ね。絶望に染め上げられた呪詛は、フツにアリステアを庇った影人、禅次郎に身を蝕む呪いを、足を止める呪縛を、凶運を与えた。 耳を塞ぎたくなるようなその言葉に、けれど気丈に顔を上げながら雷音は言葉を変える。 「バレットは、楽団の幹部だ。そして、そこの蜘蛛の巣の親玉、モリアーティ教授の敵だ!」 「そしてモリアーティも、倫敦の援軍もバロックナイツだ」 雷音が指差したのは、優希が睨み付けたのは、武器を構える四人組。 オーナメントを挟んで六道面子とは反対側に陣を組んだ彼らは、その言葉にも黙したままだ。 「モリアーティが楽団の介入を知らない訳がない。君達の姫君はいいように騙されているんじゃないのか?」 疑念を煽る言葉。蜘蛛は動じはしなかったが、四人の内で最も上なのだろう――インバネスコートを纏った男が呆れた様子で口を開いた。 「……知っていたとして、だから何だと? 教授はそれも計算の内で充分な量の援軍をこの場へと派遣した。死体漁りに遅れなど取らない。取るに足らないものを相手にしなかったとして、それが騙した事になるのかい」 「うふふふふ、それは本当かしらねぇ? 本当にそれだけかなぁ?」 エーデルワイスの問い。同時に仕掛けるはハイリーディング。 読み取られる思考に一瞬男はうっとおしげな視線をしたけれども、エーデルワイスが得たのは、紫杏の要請を受けた『教授』が己の部下を寄越した、という既知の事実と、蜘蛛が『楽団』を恐れぬその理由。気難しい指揮者は、己の譜面に従い事を成す。未だ『序』にある旋律で、指揮者が楽団員を派手に動かすはずがないという確信。 それを読んでいるから、蜘蛛の巣は楽団を恐れない。 闇冥処が死の口付けをクルトに見舞った。身を蝕む毒に、彼は僅かに眉を寄せるものの、決して巨大な異形の前から退かず。 「ねぇ。本当に大丈夫? 助力を得てお姫様は意気揚々みたいだけど、幾ら師弟関係とはいえ、相手はロンドンの犯罪王だよ? 利用されてるんじゃない?」 綺沙羅が重ねる問いに、諒次は肩を竦める。 「……紫杏様にその問いをしてみるといいよ。次の瞬間、君は肉塊だろうね。……ま、そんな手間をかけさせる訳にはいかないんだけどさぁ……」 六道紫杏という姫君は、それこそ『教授』か、愛しき愛しき恋人の言葉以外など、気紛れ以外で聞くはずもなく、ましてそれが『教授』を疑うものであったならば、どれだけ己を慕っていようが忠誠を誓っていようが『それ以下』でしかない研究員など廃棄されるまでだ。 故に、彼らは忠告などは行わない。姫君が慕う教授の正体などは二の次だ。 彼女が慕い、信頼しているというその事実だけが真実である。 兇姫の言葉は、『絶対』だから。 「正直に言おう。ボクはアレが怖い。君たちが命を張る覚悟がないのなら、この場は――」 「ああ。分かった」 まみえた者にしか分からない悪寒。 バレットと顔を合わせた時に覚えた恐怖を言葉にしようとする雷音を、諒次は片手で遮った。 「命を張る覚悟がないのは君だろう。……私達の全ては、紫杏様の為に。この頭も、命もね」 浮かぶのは、不快。 彼らはキマイラに自信があるのは無論としても、アークが全力で守る場所に攻め込んで来ているのだ。 その覚悟に、意地に火を点けた少女は――ぎゅっと拳を握って、氷の雨を呼んだ。 「來來氷雨!」 ● 雨が降る。雷音と綺沙羅、フツの呼ぶ氷の雨が、公園の気温を更に下げた。 「……酷い」 影人が消えた後、受けた呪縛から逃れたアリステアが泣きそうな声を上げる。 オーナメント・オーナメントと名付けられたキマイラの表皮に浮かぶのは、無数の顔。顔。顔顔顔顔顔。全て恐怖に怯え、苦痛を刻み、苦悶に歪んでいる。 恐らくは、それが死した時の顔なのだろうと、想像は容易だった。 中に浮かぶ赤い球体。その一つ一つが、今表に浮かんでいる『彼ら』なのだろう。 「どうしてこんな酷いことができるの……」 少女には、六道の狂気が理解できない。したくもない。血塗られた研究道など、知りたくもない。 足元を支える腕には、細く小さいものもあった。重さに耐え切れず潰れるように埋もれては、また現れる。 研究員は、それを哀れと思わないのだろう。 ただ、玩具を見せびらかすように、誇らしげに連れている。 先程受けた呪詛が痛い。悲しみと苦しみと痛みに満ちたそれが、戒めを解いた今も心を締め付けた。 前ではクルトとフラウが、多数の顔に齧り付かれている。 異形へと化した無数の彼らの身を癒す事は叶わないが、味方を癒すと同時にその心が少しでも救われる事を、遥かに高みの存在に、祈る。 禅次郎が吐き出す息も白い。 生命力を黒き瘴気へと変え、後方にいる六道のスターサジタリーごと巻き込んだ。 後衛が放つ氷の雨は、あそこまで届かない。エレオノーラの攻撃も極苦処を引き付けてはいるが――その回復もあり、なかなか撃破に至らなかった。 本来ならば彼もキマイラへ向かうべきだったのかも知れないが、六道側で唯一の回復持ちと思われる極苦処を狙えるチャンスがある以上、その手を緩めはしない。 小地獄、及び研究員が優希に向ける攻撃は苛烈であった。 「その程度の豆鉄砲、効くと思うな!」 脇腹を撃ち抜いた射手の弾丸をそう切り捨てるが、血の止まらない創傷はじくじくと痛む。刀輪処、ナイフを両手に構えたソードミラージュの斬撃の痕は、痒みすらも伴いながら赤い肉を晒していた。 振り上げた拳は、諒次の『盾』であるブルーオーナメントへと吸い込まれる。石を投げ込まれた水面のように表皮に波紋を広げた異形は未だ倒れないが、手応えは充分その掌に伝わっていた。 だが、優希へと向かう攻撃は後衛研究員と小地獄だけではない。 「……いいなぁ君。もう少し強くなってみる気はないかなぁ……。紫杏様がこの公園を手に入れれば、このオーナメント・オーナメントより強いキマイラだって、もっと手軽に作れるようになるはずだからさぁ……」 人差し指で挑発のように手招く顔は笑っている。 いかにもインドアな見た目に不釣合いな金属製の手甲を身に付けた諒次は、その外見に反し実力は優希と同程度、或いは僅かに上だろうか。攻撃は全てブルーオーナメントが肩代わりする故に、完全に自由に動ける諒次の一撃は、未だ一度も止む事なく優希へと向けられていた。 「ふざけるなっ!」 が、その攻撃の威力は高いものの、優希よりも些か狙いが甘い。炎を纏う拳の直撃を避けた優希は、歯噛みして諒次を睨み付けた。 積極的に殺すつもりはない。だが、それも『楽団』という外部要因を警戒するからに過ぎない。 死者を弄ぶ存在は、例えその死者が憎い相手だったとしても許す事はできないが――それは憎い相手を許容する、という事とイコールではない。何れこの手で、と思っていた相手から人性を剥ぎ取り『化け物』に堕とした諒次ら六道も、優希にとっては許しがたい存在である。 それを嘲笑うかのように、諒次は語ってくるのだ。拳を握り、せめてもの皮肉を。 「モリアーティが紫杏を手駒にし、意のままに操っているとなれば、六道はとんだ道化だな」 「……。……道化の踊りに付き合わないといけない君らもねぇ」 一瞬の沈黙。 返された言葉もまた、皮肉だった。 一方、後衛を狙うエレオノーラにはマンツーマンの状態で等活が張り付く。が、超頭脳演算で底上げした命中でも、エレオノーラに直撃させるのは容易い事ではない。 等活の攻撃が単体を狙うものだけではない以上、後衛を含めた攻撃範囲内への波及は防ぎようのないものではあったが、彼は充分に役割を全うしていたと言えるだろう。 アリステアにも向いていた気糸を、フツが受け止めたのを視界の端で確認して、エレオノーラは口を開いた。 「操られるだけの木偶が貴方の言う『死を越えた生』だと思うのなら、自分の身で試してみる?」 「興味はあるがね。君の言う通り木偶でしかないのならば時間の無駄だ」 「八大地獄の一人が死体になって操られるなんて無様な姿、晒してくれるなよ?」 周囲に熱源、つまり生者であれば隠しようのないはずの体温を探しながらのエレオノーラの言葉に首を振る等活に、クルトが付け足す。オーナメント・オーナメントに巻きつかれ噛みつかれ、無数の痣と血痕を散らす彼は、それでも何処か涼しげな顔で等活を見た。 「俺はまだ、お前に美術館での借りを返してないんだ」 「……そういうのは同輩に言ってくれたまえ。彼は君を褒めていたぞ」 過去に出会った場所、クルトが苦汁を舐めた場所の話をすれば、等活は肩を竦めて首を振る。 一見、剣呑ながらも和やかな会話に見えるが――それも真意を表に出さぬ者同士の牽制のし合い。 攻撃には一片の躊躇も思案も、ない。 「全部穿ってあげるわ、あはははっはははは!!」 テンション高くバウンティショット・スペシャル、神速の抜き技を放つエーデルワイスに、蜘蛛の巣が面倒臭そうな顔を向ける。慣れない場所故か、余り協力的でない六道のせいか、どうにも手際が悪い彼らは、先程からエーデルワイスを仕留める一瞬を逃している。 BangBangBang.反した銃でもう一度。血飛沫が舞い、六道の研究者の一人が膝をついた。 が、その相手に再び銃口を向ける事はしない。トリガーハッピー、戦闘を楽しんでも戦闘に溺れはしない。 「さっさとそいつ引き摺って退きなさい♪」 笑う彼女の横合いを、ようやく蜘蛛のクリミナルスタアの放つ有罪の魔弾が撃ち抜いた。 血に塗れても、エーデルワイスは不敵に笑う。刻まれた掟によって引き寄せたドラマ、今宵の出番はまだ終わらない。 「それとも死体になって蜂の巣が好み? リサイクル不可なくらいに粉々よ」 間髪いれずに放たれた、蜘蛛の巣からのマグメッシス。ぞぶりと胸を貫いたそれに血を吐き出し、けれど禅次郎は倒れず運命を燃やす。 「粉々になっても、死んだ後まで利用されるよりはマシだろう?」 禅次郎が放つペインキラー、鎮痛剤の名を持つそれは、彼の痛みを呪いへと変えた。 受けるは極苦処、神秘耐性に優れていても、無視できる程に軽くない。 それはお返しとばかりに極苦処の恩寵をもぎ取って行った。 傾き傾く天秤を、余裕で眺める者は何処か。 戦闘の合間にも、優れた耳を持つリベリスタは微かな音も聞き逃すまいと耳を澄ました。 特別な力はなくとも、後方にいるアリステアも周囲へと注意を払い続ける。 けれど、未だその姿は見えず。 そんな中――響いたのは、水の入った風船が爆ぜるような音。 びちゃり。 優希に、諒次に、青い液体が飛び散った。 「……幾ら優れた防御を持とうが、俺の前には無意味」 集中攻撃により恩寵を削りながらも立ち続けた優希の一撃が、とうとうブルーオーナメントの盾を破ったのだ。 正面に位置する諒次が、小さく舌打ち。 一つ二つ、自分達に傾く戦況。だが、クルトは地に広がるブルーオーナメントへと視線を投げ、僅かに眉を寄せた。 今までのキマイラは命尽きれば蕩けて溶けて崩れ去ってしまったのに、これはまだ残っている。 「今度の死体は自動埋葬じゃないのか?」 冗談のように軽く問いかけるが、実質的な注意喚起。 その意図は六道にも通じたのだろう、余裕を減らした諒次が口を開く。 「……あれは未熟だから起こり得た事さ。より完成に近付いた個体では、自己崩壊の確率は減る。無論ゼロではないけどねぇ……」 「――死んだら自前でお持ち帰り願うよ」 厄介ごとが一つ増えた。けれどもそれならば、より速やかな決着を目指すのみ。 オーナメント・オーナメントはその体力と再生力を持って、未だクルトとフラウの前に存在していた。 ● 「來來氷雨!」 声も枯れんばかりに、雷音は雨を呼び続ける。 少女の体には無数の傷が付き、流れる血が地面を汚していた。 それは彼女だけではなく、エレオノーラとフラウを除く他の者も同じ事。 放たれたのは、等活地獄。 刀剣の藪に投げ込まれた痛みは、雷音と綺沙羅に運命を消費させる程の威力を持っていた。 だが、綺沙羅が生み出していた影人によって庇われていたアリステアは難を逃れ、癒しさえも拒むその地獄を取り払うべく息吹を請う。 「皆で、アークに帰るんだよ……!」 それは願いで決意。 重ねられる氷の雨。氷の拳。 いくら体力が高くとも、再生力に優れようとも、極苦処という回復役を失っては収支が合わない。 風が舞った。 風になったフラウの刃が、オーナメント・オーナメントを貫いた。 一度震えて、表皮に浮かんだ顔があげるのは金切声。 耳を劈くそれに、隣にいる諒次や研究員さえも思わず顔を顰めた。 ゆらり。血を流す頬を拭い、禅次郎が呼びかける。 「……これ以上の戦闘は楽団の利になるだけだ。殺すつもりはない。退け」 血の減った頭でくらりとする感覚を覚えながら、綺沙羅も諒次へと声を掛けた。 「ここで死んで良いの?」 「……死ぬ気はないけ」 「あんた達が死ねば連中が幅を効かせるんだろうね。兇姫に忠誠を誓っても無い連中が」 隣へと向く、紫水晶。視線の先には、倫敦の蜘蛛の巣。 「……君は嫌な子供だねぇ……」 「どうもありがとう、頭の悪い大人」 諒次の溜息を受け流し、綺沙羅は貧血でおぼつかない足で地を踏み締めた。 嫌な緊張。 六道の側は、未だ倒れぬ蜘蛛が四匹、そして諒次と等活、闇冥処と刀輪処。 そしてリベリスタの側は、運命の恩寵こそ消費したが未だ欠けはなし。 数で言えばリベリスタが勝り、尚且つ癒し手を失った六道と違い、アリステアが、雷音がいた。 けれどこのまま六道が戦闘継続を選んだならば、リベリスタには次の懸念が襲い掛かる。 即ち、楽団の介入だ。 自然、この場のリーダーである諒次に視線が集まり――彼は一つ、首を振る。 ぴいん。 「……あ」 だが、その唇から何か言葉が発されるも早く、諒次の目線は半分潰れたオーナメント・オーナメントへ。 全員が嫌な予感を覚えたのと同時、表皮に浮かんだままであった顔が一斉にその目を狂ったように動かし始め、その触手に似た腕が何かを求めるように飛び出した。 「ぐ」「げ」 「――」 響く声の合間に、銃声。 放ったのは蜘蛛。己に伸びてきた腕を、銃で、気糸で弾き返す。今までの手際の悪さが嘘の様に優れた連携であった。蜘蛛の巣の面々は、それから一言も発さずに一斉に退却へと転じ、暗闇へとその身を沈ませる。 が、六道の側はそうは行かない。 倒れた仲間を引き摺って退却しろ、なんてリベリスタの言葉は戦闘中に聞き入れられるはずもなかった。 綺沙羅の影人も、味方を庇う役には立っても、敵の陣を抜けて戦闘不能者を遠くまで運ぶ事は不可能。 となれば、倒れている研究者の未来など決まったも同然。 「っ……!」 諒次の元へ伸びた一本は、辛うじて等活が受けた。 透明の腕に掴まれ、ごぎりと嫌な音を立てた腕を振るい、等活は諒次の身を背後の部下へと投げ渡す。 最早説明は不要だった。 「死体にたかる蝿って、耳元に来てから煩いのよね」 「……ずいぶんと、良いタイミングで来るものだな」 エレオノーラの溜息。掠れた声で、雷音が呟く。 優希が、クルトが、禅次郎が、揺れる茂みの音を聞いた。 「――それとも待ってたんすかね。御機嫌よう、良い夜だ……とでも挨拶すればイイっすか?」 ああ。 いつの間に、これだけ近くにいたというのか。 フラウが振り向いた先に、その男はいた。 「ああ。良い夜だなあ。もっと奏でちゃくれねーのかい。小難しい連中は帰っちまったみてーだけどよ!」 「これで終いですよ。ね、楽団のバレットさんよ」 じり、と距離を取るリベリスタを気にした風もなく――鮮やかで奇妙な眼鏡を空に向け、バレット・"パフォーマー"・バレンティーノは笑う。 第一弦楽器と呼ばれるのだから、手に持っているのはバイオリン……なのだろう。改造を施され原形からは大幅に外れている様だが、それでも弦が張られ、彼が弓を持っている以上、それは『楽器』に違いなかった。 ぴいん、と弾かれた弦、手慰みのようにピッツィカートの音を立てながら、男は木に凭れて動かない。 アリステアが、前に立ちはだかるフツの服を、そっと握る。 「お呼び頂いたのにわりーね。ゾーエが居ないモンで、アンタが誰なのか分かんねぇんだ」 「別に覚えて貰わなくっていいっすよ」 軽口を叩きながら、フラウは仲間に目配せをした。 その視界の端で、白衣の男達が蠢き出すのが見える。バレットの背後に、黒い影が幾つも立ち上がったのも。 退け、と、雷音が口の動きで等活へと呼びかける。 立ち上がった姿に己の部下である極苦処を認めた等活は、一瞬忌々しげな顔を向けたが――諒次を抱えた他の二名と共に、無言で踵を返した。 バレットは追わない。 死者も、その背を追いかけない。 動けない者はいなかった。リベリスタはじりじりと、退却路を確認し合いながらタイミングを計る。 殊更軽く、エレオノーラが声を掛けた。 「貴方の所の歌姫にもっと愛想よくしろって伝えてくれないかしら。美人が台無しよ、あれ」 「へえ。アンタお姫様に会ったか。そりゃ俺も言ってるけどな、大将の言う事じゃなきゃ何も響かねーみたいでね」 同様に軽く返る声には、何も見えない。敵意も悪意も殺意も。 その会話の横で、エーデルワイスが目を細め、心を読もうと試みる。ネクロマンシーの情報を、近い内に必ずアークが相対しなければならないであろうこの男の情報を。 だが、ハイリーディングは脳の中身を全て読み取るような便利なものではない。 結局の所、その時その相手が浮かべている思考を読み取るだけなのだ。 エーデルワイスが読み取ったのは、見えなかった殺意。 音がする。 水っぽい粘っこい内臓を抉るような音が皮膚を骨を突き破る音が髪がぶちぶちと千切れる音が肉が無理やり左右に引き裂かれる音が悲鳴が歯が砕ける音が飛び出た眼球が踏み潰される音が耳が穿たれる音が肉に包まれた骨が衝撃に耐え切れずひび割れ砕ける音が、 「何だ」 はっ、と顔を上げる。 バレットの顔も、エーデルワイスの方を向いていた。 「聴きてーならサービスするぜ。大将に怒られるんでアンコールは無しだけどよ!」 構えられた弓。それが本気ではない男の『悪ふざけ』だとは雰囲気で理解しても、それに乗る余裕はリベリスタにない。 故に、誰かが一歩引いた。踵を返した。 背後から追いかけて来る足音は、聞こえない。 絡んだ意図は、明確な筋道をまだ覆い隠していた。 けれどリベリスタは生き残り、蜘蛛網から零れた獲物を得たシデムシは、地へ潜る。 混迷極める公園で、勝ち星一つ。 リベリスタ側に損害はなく、それはとても――優れた成果と言って、良かったのだろう。 丘の上へ向かった仲間を思い、リベリスタは祈り、願う。 誰一人その手から零れないように、と。 |
| ■シナリオ結果■ | |||
|
|||
| ■あとがき■ | |||
|
|||

















