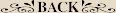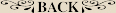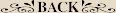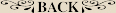「……ですが、何故?」
声を落としたアシュレイの問いはここで訝しむような調子になった。
改めて言えば、アシュレイの握った白刃――ジャック・ザ・リッパーの愛用した『ミストルージュ』は、穏やかな談笑を楽しむディーテリヒの胸から生えていた。蒼い意匠は鮮血に染まり、地面に血の池を作り出している。
相手は『疾く暴く獣』。無論、俄かには信じ難い光景だ。
「『何故、私は成功したんですか?』」
問うたアシュレイの凶行は、追い詰められての暴発に過ぎない。一分の隙も無い最大にして最後の障壁は、幾多の奇跡さえ達成したアークさえ退け、この裏切りの魔女に何の仕事も許さなかった。『最後の審判』に望む彼を止める機会があるとするならば、この瞬間だけだっただろうが――この結果は奇跡と呼ぶにもおこがましかろう。
「我が使徒等の多くを箱舟と共に屠った裏切りの魔女よ。逆十字を呪うイスカリオテのユダよ。卿は己の遂行を疑うのかね?」
「ええ、とっても」
「愚かな魔術師が同盟相手に裏切られた――その結末を疑うと言うのなら……
そうだな。私は一つの嘘も言っていない、と言っておこうではないか」
「嘘を、言っていない?」
「私は、箱舟の勇者達に告げた筈だ」
――『審判』が始まる。方法はどうでも良い――或いは、その勝者さえ――
「それがどういう……」
「つまり、必要なのは『どちらが適格か』という事に他ならぬ。
卿は己が目的と我が目的を『別個』と考え、私を対立者と考えたのだろうが――違うのだ。
私の目的は卿の目的と同道する。その大いなる目的の前に極些細なる違いがあるとするならば、卿は勝たねばならず、私は負けても良いというだけだ」
「……」
「……私は、運命に選ばせたいだけだ。まどろみの時を願うのか、全てを洗うのかを。
公平にして公正なる審判を与えたかったに過ぎない。この世界が崩界を認めるのか、そうでないのかを。神の寵愛を保証した聖書(じだい)になく、この現世に。果たして人間(ひと)がどちらを選び取るのかを!」
つまり、『世界を滅ぼす機会を作る』までは二人は同じ。アシュレイはあくまで達成勝利に執着し、ディーテリヒはそれが阻止されても構わないという事だ。
ディーテリヒは大きく息を吐き出した。
「『絶望』の象徴が卿、そして『希望』の象徴こそ箱舟だ。
私はこの世界を愛している。自然を愛し、芸術を愛し、時には人を愛している。つまる所――足らぬのだよ。私では『最後の審判』はミス・キャストだ。美しくない。相応しくない。
理解出来るかね? 卿は私が見定めた演者。『私の望みを最も正しく遂行する定められた代行者』という事だ。この世界を、世界を構成する全てを憎み、恨んでいる卿ならば……」
本当の意味でディーテリヒの望む、箱舟(アーク)との相克に相応しい。
思えば両騎士にアークを監視させたのも理由は同じだったのだろう。
彼は『絶望』と『希望』、その双方に同じ力を持つ『代行者』を欲っしていたのだ。
アシュレイがアークに『バロックナイツ打倒』を願ったのは半分が隠れ蓑だ。
アシュレイが必要としたのは彼等の持つ『神器級アーティファクト』。そしてもう一つ、最も重要だったのは『ウィルモフ・ペリーシュだけが持つ他者や器物から魔力を吸い上げる最高技術』であった。この二つと臨界を迎える『閉じない穴』が組み合わされれば、『目的』に届き得る。そう考えていた。
事実、『聖杯<ブラック・サン>』は扱えぬも、紛い物とは比べられないペリーシュの技術は拝借出来た。全てを手にした訳では無いが、アークの打倒した使徒達から『燃料』になる幾多の品を手にする事は出来た……
「理解を、したかね。『塔の魔女』」
「最初からその心算で」
アシュレイはそれ以上を言う事が出来なかった。果たして『ヨハネの黙示録』は何処から何処までを読んでいたと言うのだろう。こんな時にも微塵も超越を崩さないディーテリヒの呼吸は浅く速くなっている。恐らくは『敢えて致命傷を受けた』彼は退場する人間に他なるまいに、絶大な敗北感は禁じ得ない。
己が小さな――そして余りにも重大な『復讐』が彼女自身を責め苛んでいた。
唇を噛みしめたアシュレイの眼前で長身の男の身体が傾いだ。
血の海に沈んだ彼はその美しい瞳だけを月下に佇む魔女に向けた。
「――『両者に守護を、願わくば祝福までも』」
掠れた一声が彼の指輪の魔力を増した。
現れた戦乙女達が血濡れた主人に寄り添うように集まっている。
「これは……」
「『ヴァルハラ』は――卿に差し上げる。『ロンギヌス』は――」
戦乙女の一が白き槍を抱いて赤い夜空を駆けていく。
「――多言は蛇足か。良い時間だったとも、卿も、箱舟等も。唯、感謝している」
それはまるで巨人の墜落を意味する流れ星のように光芒の糸を引いていた。
|