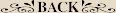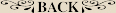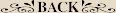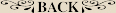この2年間追いかけてきた、宿命の相手ともいうべき「彼」との最終対決。
海音寺政人との決着の時が、刻々と近づいてきたようです。
出発前のこのひと時、なんだか不思議と、穏やかな心持ちの自分がいます。
ここにいたるまで、彼と自分との因縁について、
考えるべきことはすべて考え尽くしてきたという自負があるからかもしれませんね。
さて、あとで読み返すかどうかも、わかりませんが。
せっかくですから、この空き時間を使って、
この戦いについての所感を手記に残しておきたいと思います。
◆モチベーションについての内省◆
戦いそのものについて考える前に、簡単に、
自分がこの戦いにのぞむ動機について内省しておきたいと思います。
いってみれば、以前のボクは、海音寺政人の中に自分と同様の性質を見ていました。
家族を歪め、家族に囚われ、家族にすがり、狂っていく。
進む方向と方法論は違えど、失った家族を理由にして、「探求の道 / 贖いの道」に
それぞれ身を投じていく彼とボクは、あり方がきわめて近しいのではないか。
そんな勝手な共感から、決着が両者に何らかの答えを与えてくれるかもしれないと考え、
彼との戦いに固執している節がありました。
でも、いまは少し、方向性が違ってきています。
狂いゆく彼の人格の形成に、W・Pシリーズの『漣の指輪』の
本当の能力が大きく関わっていると判明してから。
彼とボクの性質そのもの、歪み方そのものを比べるのは、少し違うのかもしれない……
と思い直し、途中からは別の動機で、戦いに身を投じてきた次第です。
指輪の効果だけが彼を歪めたわけではない。
従来の彼の持っていた凶暴性やフィクサード性、
そして従来の彼に備わっていた性質や思いが、指輪の助けを借りて表出しただけである。
指輪がなくたって、いずれはいまの狂いかけた彼に辿り着いていた可能性はある。
ここ最近続けざまに出てきているそんな情報は、ある面、
ボクの前述の理解が不十分であることを示唆するようにも思います。
ただ、実際のところ……ボク自身は、仮定の話にはあまり立ち入らない性格です。
たとえば、ふいに「先立った父さんと姉さんのもとに自分も逝けたら」
という衝動的な思いに駆られることはあっても、
「父さんと姉さんがこの場にいたら。もし生き返ってきてくれたら」
と考えた経験は、ほとんどありません。
そういう意味では変にリアリストなのだと思います。
話を戻せば、確かに指輪がなくても、
彼はいずれ目標・生きがいのバランスをふりきって狂っていたのかもしれない。
家族を捨てたうえで、家族を歪めながら、研究の道に邁進していたのかもしれない。
それは海音寺政人本来の性質であり、やはり、
自分との同質性を問うにふさわしい相手なのかもしれない。
そういう話がある一方で……現実に、「指輪を持たない」彼は存在していません。
実際にいるのは、指輪を手にし、多かれ少なかれ指輪の介入を受けたうえで、
いまの形に辿り着いた彼だけです。
だからボクは、彼の本来のあり方が自分ときわめて近しかったのかどうか、
その命題には立ち返りません。
でも、それで思い入れが軽くなったというわけでもない。
要はまた少し、別の角度から……
彼とボクとの関係性について、ボクが彼と関わって為したいことについて、
考えながら戦っていくつもりです。
じゃあ、いまは何が自己のモチベーションなのか、という話をする前に。
彼の身に何が起こってきたのかは、推測を交えてでも、
少しふり返るべきでありましょう。
それは自分にとっての問題と方針を見定めることでもあり、
少々の疑問点を整理することでもあります。
◆はじまりについての考察◆
まず手始めに、もともとの彼は「研究」と「家族」と
それぞれどう向き合っていたのかを考えてみましょう。
そのヒントは、ごく初期の報告書に記されています。
海音寺が研究を始めた理由は家族を養う為だった。
給料が良ければその分幸せにできる。
心優しい父親であったから。それももう、全ては失われてしまったのだが。
(『<三ツ池公園大迎撃>青の波間』より)
ここから1つわかるのは、彼の研究の動機、彼が研究を還元する先は、
もともとは「家族の幸せ」にあったということです。
おそらくきっかけというだけではなく、あるいち時点まではそうだったのでしょう。
しかし、同時に思い出さなければならないのは、
彼が最初から「六道のフィクサードであった」という点です。
この点において、彼はほぼ間違いなく、
研究そのものに没頭する心性、探求の業も持ち合わせていたはず。
つまり彼は、「生物研究の追求」と「家族の幸せの実現」というファクターを
両方望みながら、両目的のバランスを取りつつ、
「研究」と「家族」にかわるがわる向き合って生きていた、ということになりましょう。
(手記の―2―へ続く)
|