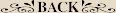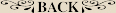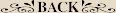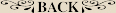それでも、世は並べて事も無し
サンダーの実父実母がやってきました。
曰く、子を返せと。
真崎夕子を返せと。
金で売った自分の子を。
わたしはタッパが低くドスも効かない。加えて向こうは大人二人。
増してここはわたしのヤサです。大声を上げるのははばかられる。
状況はわたしに対してとても不利でした。
娘を出せ。娘を返せ。
始めは、頼むから返してくれと控えめだった口調も次第に荒荒しくなり、しまいには、――――想定しえたことではありますが―――――実の子に逢えないなんておかしいだろ、と抜かし始め。
なまじ理屈が通っているからバカはすがるのです。
「その実の子さえも自分で売ったのだろ」という理屈は都合良く無視して。
わたしはバケモノです。
そしてその自覚がある。
人の世に忍んで生きるためには、謹んで己を律さなければならない。
それでも、湧きあがる心を押さえられないことはあるのです。
わたしは思い切り殴りつけました。
彼らの後ろにあった、マンションの廊下の壁を。
派手な音がして、モルタルの壁に手首までめり込んでいました。
彼らは恐れをなし、それでも減らず口を叩きながら、そそくさと去って行きました。
時間帯が故か奥様連中がちらほらと出てきましたが、わたしは無視して部屋に戻りました。
サンダーは学校に行っていて、部屋にはいませんでしたから、わたしの気持ちがどうあれ彼らにあの場で渡すことなど有り得なかったはずなのに。
己の行動を理不尽だと認めつつ、心の奥底は、最良の行動であったと誇っていたのです。
|