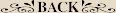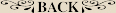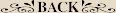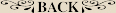「……困ったものですな。こうも再々『研究』の邪魔をされるのは。
小生の『研究』の価値をまさか理解していない皆々様ではありますまい?」
先から芯までチョコレートならぬ嫌味たっぷりなその台詞に漸く重い口を開いたのは『少なくとも彼よりはアークを良く知る』老紳士だった。
「ペリーシュ殿。彼等の動きはフロックではありませんぞ」
ジェームズ・モリアーティは眉を動かしたペリーシュに構わずにその先を続ける。
「奇跡は二度続けば奇跡とは呼ばない。それは必然だ。我々バロックナイツが敗れるとするならば、それは過ぎた自尊心による自負位のものとは思えませんかな。少なくとも過去の二人は純然とした実力で敗退した訳ではない。『より大きな力』に飲み込まれた訳ではなく、力点を正しく作用させる『効率的な力』に撃ち抜かれたのだ。私はそう理解しているのだが――」
モリアーティの視線がちらりと一人の女の方を向いた気がした。視線を受けた当の本人――『塔の魔女』アシュレイは涼しい顔でそこに在る。毒気無く屈託の無い笑みを浮かべたまま、ユダは在る。
極めて『もっとも』であろうモリアーティの発言をしかしペリーシュは鼻で笑う。
「――力の足りぬ者程、色々な言い訳に余念が無い。
油断の次は何を挙げるのやら。隠し玉の存在か。不足の事態(イレギュラー)への無念か。ありとあらゆる事象を全て捻じ伏せ、完璧なまでの勝利を収める事が出来ぬとするならば、それは恥じるべき無力であろうに。諸君等は仮にも小生と『同格』の使徒では無いのかね?」
嘲りを多分に含んだ一言に一人の男が肩を竦めた。
「異論でも?」
「まさか。ニッコロ・マキャベリは君主論で――や、『私に』言った。
支配を被るべき人種に王が取る行動は『頭を撫でるか』、『消してしまうか』
智慧溢るる賢者も、愚かな道化も。等しく卿に前者が出来るとは誰も思いますまいよ」
奇しくも新たなる法王が誕生したばかりのこの日に、『史上最悪』とも称されるそれを父に持つ優男は飄々した調子を崩さずにそうとだけ呟いた。
ケイオス・“コンダクター”・カントーリオの戦死を受け開かれた円卓は『欠席』した二人の欠員、姿を見せぬ『第三位』、『第四位』、『第九位』、断りを入れたリヒャルト――六人もの空席を示している。『第十二位』たる彼が顔を出したのは彼なりの『穴埋め』の心算であろうか。
「何れにせよ。汚らしい死人使い風情が恥を――」
「――ストップ」
饒舌なるペリーシュの悪罵を止めたのは長い足を机の上に放り出し、これまでは彼の達者な嫌味を楽しそうに聞いていた『魔神王』キース・ソロモンだった。
「それ以上言ったら、俺様がこの場で相手になるぜ。どっちか、死ぬまでな」
「そう言えば魔神王殿と彼は『友人』でしたな。これは失敬」
「分かって貰えると助かるぜ、虚言の王」
ペリーシュの言葉の後半にはやはり皮肉が混ざっている。しかして、キースはそれ以上を告げる事は無い。但し彼は有言を必ず実行する男でもある。この場に立つ事が出来ないケイオスにもう一言でもペリーシュが侮辱を向けたならこのベルリンは火の海になるだろう。
「麗しい友情ねぇ」
ペリーシュは人生最大最高と自負する『研究』の途上である。無意味な徒労を嫌ったのか彼は漸く水を『本命』であるディーテリヒに向けた。
「では、『戯言』はここまでに。盟主殿の采配をお聞きしたい所ですな」
「――『ヨハネの黙示録』の示す未来には多くの屍が積み上がっている」
ディーテリヒの言葉はあくまで重く荘厳に黒き円卓の間に透き通った。
「それが卿等のものなのか、箱舟のものなのか。
現時点で私に特定の叶うものでは無い。否、雑多多様なる運命の入り乱れしこの『嵐の夜』は如何な航海士であろうとも読み切るには到るまい」
アーティファクト『ヨハネの黙示録』は森羅万象の理を遠大に書き示す神の書である。詩的な、暗号めいた黙示録の書はアシュレイの占いやアークの目とは別のアプローチで『彼の望む』未来を掠め取るもの。ディーテリヒは『あの』ヴァチカンとこれを争う事で『正逆戦争』なる神秘史の重大エピソードを引き起こした事があるのだが――
「されど、恐れる者は卿等には在るまい。
死の運命を己に自覚する(きづく)者は使徒ではなかろう。
故に卿等に逆十字円卓は提案しよう。此度こそは提案しよう。
かの箱舟を沈めるべし。無慈悲に、容赦なく。私は卿等にその力が備わっているものと確信している。唯の一時疑う余地も無い程に」
ディーテリヒの言葉は『自由』とする前回より敵に対して『積極的』なものに変わっていた。真意を悟らせぬ彼の美しい横顔を見つめながらセシリーは密かに首を傾げ小さくその柳眉を動かしていた。
(……ディーテリヒ様はアークを攻略しろと提案した。
されど、何故懐刀たる我々には命令を変更せずに監視を続けろと仰るのか……)
彼女にとってディーテリヒの言葉は神のそれに等しい。
彼を疑う事は決してない。彼に背く心算は毛頭無い。されど。
(……解せぬ……)
水面に落ちたインクが広がりを見せるように白騎士の心には僅かな靄が掛かっていた。疑うではない。背くでもない。ただ理解(わか)らなければ釈然とはしない。傍らのアルベールは彫像のように表情を変えず、盟主の言葉を騎士達を除く円卓は概ね好意的に了承してはいたのだが……
「これはなかなか。『イスカリオテのユダ』は本当に一人なんでしょーかねー」
……小さくぽつりと漏らしたアシュレイの言葉を聞き咎めた者は居なかった。
|