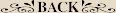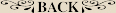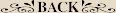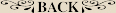(――追放されたのは、むしろフュリエか)
変わるという事は何処までも不完全になる事だというその意味を沙織は改めて思い知っていた。もし『以前のままのフュリエならば、今のバイデンと共存は出来たのかも知れない』。しかし『以前のままのバイデンではフュリエとは共存出来ない』。詰まる所、完全世界の不協和音は定められた範囲を抜けては居ない。
「……止めても、無駄か?」
「私は心より皆様に感謝しております。しかし、私には自分の世界と同胞を守る義務があるのです。皆様がそれを強く願っているのと同じように」
この場合、バイデンを見過ごせという言葉は「ボトム・チャンネルのエリューションを可哀想だから見逃せ」という意味にも等しい。
「つまらん事を言ったな。悪かった」
痛い所を突かれた沙織はそう応えたが――しかしこれも観測気球。確認であり、想定の内だった。元より僅か半年首を突っ込んだ異邦人には分からない事なのだ。『十年以上も罪無き同胞を殺され続けた彼女の痛み』は。それは理屈で分かっている。
「実際にラ・ル・カーナで命を賭けたのはうちの連中だ。俺は俺の一存だけでこれからのアークがどういう進路を取るのか決める程、傲慢じゃない」
「はい」
「その上でお前に確認しておきたい事がある。『もし、バイデンをラ・ル・カーナから排除出来るとするならば、お前は必ずしもその絶滅を求めない』な?」
「……仰る意味が良く」
「つまり、連中をこっちに隔離するっていう選択肢もあるって事だ。世界樹エクスィスを『打倒』したこのボトム・チャンネルはラ・ル・カーナの生物を運命と共に受け入れる事が出来る。少数になったバイデンをボトム・チャンネルに移す事が出来たなら、絶滅は不要だろ?」
「……」
シェルンは唇を引き結んだ。
沙織の提案は論理的解決の提示である。シェルンの中に煮えるのは人間的な復讐心という感情に違いない。しかして、沈黙の時間は長くは続かなかった。
「……受け入れましょう。しかし、予め断っておくならば……我々はバイデンと共に歩む事は不可能です。もし、皆さんが私達に助力を求めるならば私達は『命を賭して』今度はこの世界の為に尽力しましょう。そういう覚悟を持っております。しかし、バイデンがこの世界で皆さんと共に歩むなら、それは――」
「……ああ。分かってる。唯、な。リベリスタの連中もバイデンに情の移った奴等も居る。こればかりは分かってくれよ。所詮、俺達は異邦人だった。お前の気持ちを完全に共有するなんてのは、最初から不可能だったんだ。だから、俺は何とも答えられない。リベリスタの意見を募り、リベリスタ自身に決断を下させる。フュリエと共に歩むのか、バイデンを救うのか。それともラ・ル・カーナを閉じるのかも含めてね。何れの結論が下ったとしても、それは運命だ」
こくり、とシェルンは頷いた。
彼女がボトム・チャンネルの――リベリスタの為に力を貸したいと思っているのは、共に戦いたいと思っているのは本当だろう。
しかし、楽園での時間は終わりを告げたのだ。
失楽園の先に広がる風景は、フュリエの過ごしてきた豊穣の森では無い。むしろ、バイデン達が駆け抜けた憤怒と渇きの大地の如く。
――世界は痛みばかりで出来ていた。
都合のいいハッピー・エンドは三千世界の何処にも無い。
|