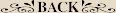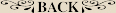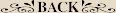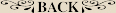『好機足り得ぬ好機』は焦れた彼を真っ直ぐに突き動かしていた。
「ああ、ああ――ああ!」
まるでそれは血の臭いに酔っているかのような声だった。
まさに感極まると言った内心を微塵も隠す事は無く。死する仲間に、戦う宿敵達に、狂った世界樹に歓喜の声を上げたのは黒い巨獣を狩るプリンス・バイデンだった。後方より十分な加速をつけ、動き出したプリンスは――グレイト・バイデンはまさに異形の波を掻き分ける黒い弾丸だった。その背にしがみつくバイデンは最早、二人。堅牢を誇ったバイデンの精鋭もプリンスとイゾルゲを除けば皆死してここにはない。
愚直な猛進は格好の的だった。
向かってくる愚かな獣とその背の馬鹿者にはまさに雨のような集中攻撃が加えられていた。黒獣は痛みに怒りの声を上げ、その背の二人は死力を尽くして抗い、抗う。
それでも、そんなものは気休めに過ぎないのだ。
「楽しいな。楽しいなあ、イゾルゲ!」
彼が居たのは自身の真横。正面から伸びてきた捩れ根に頭を砕かれ、血の線と共に転がり落ちた僚友に、届かない言葉を投げるプリンスはその大きな口を笑みに歪めて声を張った。
運命は無い。命は一つ。それさえ最早、終わりが色濃い。
立ち止まれば二度と走り出せない愛騎と、満身創痍なる戦士である。戦いの『隙を突く事で』辛うじて敵陣を切り分けた一人と一匹は渾身を以って最後の敵に衝突する。
戦場に走った轟音と衝撃はまさに『世界が揺れた音』である。
捩れた根の槍が蠢き、動きを止めた黒獣の全身を滅茶苦茶に突き刺さる。
「おああああああああああああああ――ッ!」
揺らぐ『足場』で絶叫し、乾坤一擲の一打を自身に加えたプリンスさえ何の問題にもしていない。美しかった樹の幹に浮かぶ醜悪な顔が、その口が。よろめいた彼目掛けて、節くれだった触手を無数に吐き出した。
……プリンスだったものが地面に転がれば世界樹はそれを取り込むように触手を伸ばした。殺しても殺しようが無い筈だったそれが死んでも、壊せぬモノは無い筈だった一撃が突き立てられたとしても。後に残されたのはほんの小さなかすり傷。
たかが、虫にさされたかのような――そんな疵。
余りに愚かで、余りに無意味で、余りに小さい。たかが、疵。
だが、時に。強大堅牢な砦さえ、蟻の一穴が崩す事もあろう。
「プリンスを殺すことができたのは、ラ・ル・カーナでは世界樹だけだったか」
遠く――イザーク・フェルノは感に堪えぬように呟いた。
「そうだ。あれこそが『世界』。あれこそが『世界を飲み干す者』。
ああ、あれは、やはり強いのだな――!」
緑色の液体を零しながら『再生』を試みる世界樹をイザークも、リベリスタ達も見逃す事はしない。たかが一瞬の話とは言え、愚かな吶喊に乱れた敵陣を戦士達が駆け抜けた。
「――クェーサーはフュリエの指揮を代行したか。
……ならば、これよりシェルンが来る……!
聞け! 本部の指令だ。今から本隊を二つに分ける!」
霧也の声は動き始めた戦場に新たな意味をもたらすもの。
「半数で『穴』までの道を切り開き、守り抜く!
一隊は誘導し損ねた化け物を頼む。主力は道を拓き、 あの『穴』が塞がるのを食い止める! 突入部隊は消耗しないように下がっていろ!」
いざ、接近を果たせばそこは地獄。
無数とも思えるほどの世界樹の根や枝が、執拗に絡みつき、締め上げ、あるいは鋭く突き刺さんと宙に蠢く。されど、この場に立ちて退く者は無かろう。世界樹に刻まれた小さな疵、小さな疵を押し開き、運命を逆転させるのはこれより来る――リベリスタ達の仕事である。
嬉々として槍を振るうイザークでも無く、恐れを顔に浮かべながらも戦場に立つエウリスでも無く、死したプリンスでも世界樹を憂うシェルンでも無い。
あくまでそれは『リベリスタ達の仕事』なのだ!
――生臭い風を吐き出した世界樹の鳴動に世界が揺れた。
無数の痛みを盾にして、動き出した突入班の目前に『運命』が迫る。
ガラクタじみた迷宮、光呑むその洞に希望は――見えない。
でも、それでも。
→世界を飲み干す者(第一ターン)
|