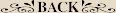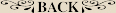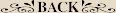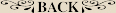http://bne.chocolop.net/img/top_bg/BNE_bg_20120920ex.JPG
<煮沸する血の荒野>
「……プリンス」
血濡れた槍を手に肩で息をするイザーク・フェルノは傷付いていた。彼が口にした――呼んだその名の響きに、幾らか頼るような色が混ざった事はまさに今彼がどういう状況に置かれているかを示していた。
「プリンス、此方は片付いた。しかし、酷い状況だ」
「分かっている。何人死んだ?」
強靭なる巨躯を血に染め、全身に無数の傷を刻み。両足で地面を踏みしめるプリンス・バイデンの目の前には『バイデンだったもの』の残骸が山のように転がっていた。緋色の河は乾いた大地に横たわり、大きな流れを作り出している。噎せ返るような血と死の香りはバイデンがラ・ル・カーナに生まれて以来初めてと言ってもいい程のものであった。
「……分からない。村中で戦いが起きている。沢山死んだ。俺も、何体か殺したが――」
殺したが、味方も殺された。
そんな光景が集落中で起きている。壮絶なまでの『同士討ち』が一体どれ程の被害をもたらしたのか、即座の把握さえ難しい。
イザークは言葉の後半を敢えて口にはしなかったが、唇を噛む彼がそれを快く思っていないのは明白だった。死を恐れるバイデンは居ないが、死に意味を求めたがる者は居る。少なくとも『突然、おかしくなった仲間に不意を打ちで殺される』のはバイデンの望む最期ではない。
「……これは一体どうした事なのだ。何故、突然……!」
「何故?」
「何がおかしい、プリンス!」
イザークは骨の戦斧から血を払ったプリンスに噛み付くように声を荒げた。プリンスはそんな彼の様子にも頓着しない。
「フフ、本当に分からないのか。イザークよ。
我々の目の前にはあれ程に明確な『証明』が存在しているというのに!」
プリンスの見やる彼方には異形と化した『世界樹』が佇んでいる。ソラに浮かぶ『眼球』はバイデンにとっての父なる巨人。失われた世界に根を張るのは母なる狂樹である。傷付きながらも全身に力を漲らせるプリンスは『滅びに直面しようとするバイデン』すらをも厭わずに、大きく肩を揺すって笑った。
「……リベリスタ、フュリエ共との争いに水を差す。
しかし、それが『アレ』であるならば話は別だ。
イザークよ、アレは強いとは思わぬか? アレはこの世界そのものなのだぞ!」
「――――」
イザークの手が強く槍を握り直した。
バイデンの王は静かに冷静に狂っていた。
しかして『無形の巨人』の血を色濃く引くバイデンには最早、世界に弓を引く選択肢の他は残されていない。少なくとも、変異し、理性を失い、異形と化し――荒野を闊歩する『バイデンだったもの』と同じになりたくないならば。
「世界を飲み干す者か。フフ、面白い! 面白いぞ!」
「いいだろう、プリンス。だが、あれを折るのはこの俺だ!」
「囀るな、小僧!」
イザークの見得をプリンスは口よりも好意的に受け止めた。
プリンスにせよ、イザークにせよリミットが近いのは間違いない。
なればこそ、彼等は猛る。世界を飲み干すのだ。飲み干して、越えるのだ。父も母も彼等には関係ない。唯、求むるは滅びの間際まで、血沸き肉踊る闘争のみ――!
|