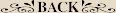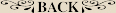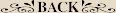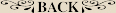元々クェーサー家は『狂犬』としてその名を神秘業界に轟かせている。総ゆる悪性神秘を見逃さず撃滅する原理主義者としてである。フリーの頃のアシュレイを追い詰め、バロックナイツと交戦し、R-typeを押し返して果てた……この数十年ばかりだけを見ても戦果は赫々と輝いているのだが。誰かと馴れ合う事を良しとせず、任務の達成を何よりの至上と位置付ける彼等の戦い方は悲しいかな、一族の短命と衰退を呼んだ。結果として一族は数を減らしやがて絶え、最後に残った夫と妻は『世界最少のリベリスタ組織』と皮肉と揶揄交じりに謳われる事になったのだ。父ハインツと母深雪がナイトメア・ダウンで消失して十三年弱。クェーサー最後の血脈は己が無力にクールな顔の向こう側で青白い感情を燃やしている。
「当主殿の評価は他に任せるとして、どうする」
フォックストロットの言葉に深春は答えない。彼は続ける。
「前金は貰った。仕事はまだだ。俺はまだ付き合うが、現実問題四人で『鬼ノ城』を攻略するのは不可能だし、『温羅』と戦うなんてそんな。こわいこわい。
言っとくがこりゃ青大将もクローセルも一致した意見だぜ」
「分かっている」
深春の言葉に平素は見せない僅かな苛立ちが滲んだ。
クェーサーの家訓は総ゆる悪性神秘を間違い無く撃滅する事。そこにどんな手段を用いても、どんな犠牲を払っても……である。アークに誘われた時彼女がこれを断った理由は簡単だ。そも歴史上においてもクェーサーがクェーサー以外のものと上手くやったという履歴は無い。抱える価値観が違えば不協和音は起きる事は分かり切っている。請われた一時の共闘は良しとしても、本格的に轡を並べるのは――それを考えるのは大いにクェーサー的では無いのだ。若年の少女は幼い頃に亡くした父を、母を。歴史に名を残す先祖の誇りを何よりの意気と感じて生きてきた。生き抜いてきた。その矜持を曲げるのかと、少なからぬ葛藤がある。
「……」
「……………」
長いようで短い沈黙が降りた。
再び目を瞑った深春はこれまでの事を、これからの事を考える。思い知った事は自分は父では無いという事である。母では無いという事である。
深春・クェーサーは無力であるという唯のつまらない現実である。
(ならば、私はどうするか。どうすべきなのか――)
積み重なる迷いに心を惑わす時間は無い。逃げぬのならば道は無い。
鬼道の脅威は現実に差し迫り、アークは自分以上の戦果を挙げ、彼等に対抗する手段を手に入れたのだから。もう迷う時では無いと彼女は自分に言い聞かせる。
「……フォックストロット。青大将とクローセルにも連絡を」
「へいへい」
「クェーサーは媚びない。クェーサーは馴れ合わない。
クェーサーはクェーサーの手のみによって神秘を抹消し続けてきた。しかし……」
「しかし?」
「クェーサーの辞書に敗北は無い。諦める位ならば家訓にも背こう。
深春・クェーサーが頼る矜持は、神秘を撃ち滅ぼす事それのみ!
これより私は――アークに参戦を申し入れる」
所詮一個。所詮一部隊。
少女自身が戦場に与える影響等、たかが知れたものである。無力を感じた彼女がそう結論付けたように最早拠る以外に術が無いのは明白なのだ。
「そうこなくっちゃ――」
しかし、深春の決断を深春の見得を「ヒュウ」と口笛を吹いたフォックストロットは何処か楽しそうに眺めていた。
(頑ななお姫様の心を動かす戦い振り、ね。流石は連中って所か。
しかしまぁ、現代日本で鬼退治ってのも乙なもんだ。
『鬼ヶ島』で暴れる主役はお任せするとして――こりゃ、面白くなるかもな)
|