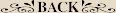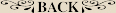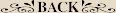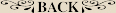http://bne.chocolop.net/img/top_bg/BNE_bg_20111003ex.JPG
<Baroque>
色濃い神秘が満ちる場所。
それは世界すら、運命すら、神の目さえも欺く『塔の魔女』の作り出した『現代の黄昏』とも言うべきBaroqueの根城である。
幾重に神秘の張り巡らされた異界と化したマンションの一室に特別なメンバーが揃っていた。この場の支配者、『The Living Mystery』ジャック・ザ・リッパー。その片腕にして愛人『塔の魔女』アシュレイ・ヘーゼル・ブラックモア。そしてもう一人、『伝説』に魅入られ、『伝説』に認められた殺人者『Ripper's Edge』後宮シンヤの三人である。
「ご存知とは思いますがね。『伝説』の幕開けは上々のようですよ」
シンヤは革張りのソファにどっかと腰掛け、ブランデーを呷るジャックの目の前に新聞と雑誌を放り投げた。日々、紙面をテレビの中を騒がせる猟奇殺人事件の多発はあのジャックの『政見放送』の影響と見るのが正しい。
「あのアークの連中が動き出したみたいですね。まぁ、元々有象無象の連中です。相当数が敗れ鎮圧されたようですが、何。大した問題じゃありません。連中は端役、演出の書き割りです。いい所、単に貴方の伝説を賑やかす枯木の山に過ぎないのでしょうからね」
猟奇事件の発生はアークの活躍もあって小康状態を迎えている。
しかし、件数が減っただけで事件消えた訳ではない。神秘の絡む事件ならば見逃さない万華鏡も日常の中に潜む『唯の狂気』の看破には至らない。街では人が死んでいた。日本は変わらず不安定なまま、不安と恐怖を孕み続けていた。
「それより流石ジャック・ザ・リッパーですねぇ。無軌道な連中の暴発は兎も角として、『伝説』に協力したいという兵隊はどんどん集まっていますよ。後宮シンヤの名前じゃこうはいかない」
答えないジャックに構わずシンヤは饒舌に言って笑った。事件を起こした連中の大半はジャックの部下ではない。ましてやシンヤの部下でもない。場を盛り上げる為に動いたシンヤ一派のフィクサードは大した被害を受けた訳でもない。元よりこの程度で脱落する程度の人間ならば不要と彼は思っている。
自身の力に絶対の自信を持つジャックは本来群れる事を好まない。しかしてシンヤは自分の力と身の程を知っていた。彼の伝説に自分がどう『奉仕』するのが最良なのかを理解しているとも言えた。後宮シンヤはバロックナイツではない。『塔の魔女』の持つ魔術の奥義も、『The Living Mystery』の持つ圧倒的な武力も彼には無い。しかし彼には『伝説』をより確実に遂行する為に出来る事があった。
「……ピーチク囀りやがる。今日は随分とご機嫌じゃねぇか。シンヤ」
クリスタル・グラスを硝子のテーブルの上に置き、シンヤに視線を向けたジャックは漸く短い言葉を返した。
「いい事でもあったか? 余程、楽しい事でもあったように見える」
「ええ、とても。 前々から興味があった面白い獲物を捕まえましてね 」
「……」
シンヤの言葉にアシュレイの眉が小さく動く。
「ほう。リベリスタの連中をからかう心算って――言ってたな。
お前の眼鏡に叶う奴が居たってのかよ」
「ええ。運命とは数奇ですねぇ、胸を焦がす情熱を時に敵にさえ向けさせる。
それより先程の言葉はそのままお返ししますよ。
今日は随分と上機嫌じゃないですか。察するに『貴方から嗅ぎなれない血の臭いがする事』と無関係では無いように思いますが」
シンヤは少し冗句めいて言葉を返した。
彼の鋭敏な嗅覚は、直観はジャックが負った小さな手傷を見逃しては居なかった。そしてその意味がどれだけ重大な事かも『一分のテストで傷を負わせる事は出来なかった』彼だからこそ知っている。
「……ああ、今の俺様は最高に落ち着いてるぜ。
『歪曲運命黙示録(しんなるうんめいのちょうあい)』に遭うとは思わなかったからな 」
シンヤの表情が僅かに歪む。
「成る程、話には聞いていましたが……実際に発動する事もあるものなのですねぇ」
運命に選ばれた存在の中でも何人がその高みに届くだろう。
御伽噺のようなデウス・エクス・マキーナの産物ならば確かに主に手傷を負わせるのも不可能ではなかろうと彼は納得した。
しかし。
「……妬けますねぇ。『伝説』は無傷で居て頂かないと」
「ハ。一方的な狩りじゃ退屈だと思ってた所だぜ」
何処まで本気か分からないシンヤの言葉をジャックは笑い飛ばす。
「挨拶は十分だろ。始まるのさ、凶き紅月のバロックナイトが。
最高へ到る道が! バロックナイツの――ジャック様のこの手によって!
運命も何も捻じ伏せて……だから俺のパーティだろうが!」
ジャックが笑う。シンヤが笑う。
「……」
アシュレイは黙ったまま楽しげな二人の男の様を眺めていた。
暗い金色の瞳は深い沼の底のように黄昏の光を飲み干している。
|